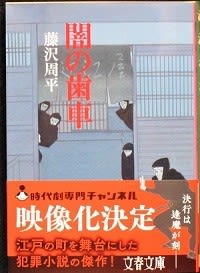
「あらすじ」
「酒亭おかめ」
三 (佐之助はおくみと暮らすことになり、金が欲しくて、奥村の家を訪ねる)
佐之助は今朝あったことを思い出していた。暁のぼんやりした光の中に浮かんだ、女の白い胸が、心をしめつけてくる。妙な成行きになったぜ、と笑い捨てる気になれなかった。震えながら身体をゆだねる女に、哀れみが募る。
土間に倒れたおくみは、その夜から譫言を言うような高い熱を出した。その晩は、夜っぴいて水で額を冷やし、翌朝、佐之助は医者を呼んだ。診たては風邪だったが、医者は楽観していないようだった。眉をひそめて、非難するように佐之助を見た。
「少しこじれているな。なぜもっと早く呼ばなかったかな」
「………」
「薬を飲めば、一日、二日で下がるかもしれんが、そのあとしばらくは動かしてはならん。この家は、あんた一人か」
医者は危ぶむように言った。すぐ薬を調合するという医者について行って、薬をもらうと、高い金をとられた。
薬を飲ませるときだけ、おくみは目ざめたが、飲み終わると、またこんこんと眠った。
………。
医者の診たては正しく、おくみの熱はなかなか取れなかった。高い熱は丸二日ほどでひいたが、今日は気分がいいから、と一刻ほど床の上に起きていると、そのあと必ず熱が出た。粥しか欲しからず、おくみは痩せた。眼が大きくなり、どちらかと言えば可愛い顔立ちが、凄艶な感じになった。
おくみの熱がすっかり治まったのは、昨日になってからである。昨日の夜に入っても熱が出なかった。
淡い気持の動きだったが、おくみに惹かれていた。十日近く病気を看取っている間に、情が移ったようだった。
今朝、佐之助は薄暗いうちに目覚めた。それが、隣の茶の間から聞こえてくる、きれぎれなすすり泣きの声のせいだと気づくまで、しばらく間があった。
「どうしたい ? また、ぐあい悪いかね」
佐之助が顔を覗きこむと、おくみは黙って首を振った。
………。
「及ばずながら力になろうじゃないか。なに、あんたさえよかったら、このままずっとこの家にいてくれてもいいんだ」
「そんなことは出来ません。お世話になった上に、そんな………」
「俺はいてもらいたいんだよ、おくみさん。あんたが病気の間、俺はあんたのことだけ考えていた。………」
「………」
「多分あんたを好きになったのだ、おくみさん。こいつはいけないことかね」
「抱いて」
不意に手をさしのべて、おくみが言った。
「しっかり抱いてください」
佐之助が抱くと、おくみは佐之助の胸や頸に顔をこすりつけた。おくみは震えつづけていた。
小名木川の岸を歩きながら、佐之助はおくみという女とそうなったことを後悔していなかった。そう言えば、はじめから気がかりな女だったのだ、という気もしてくる。それにしても金がいる。
佐之助は少し足を早めた。奥村の家を小路から入っていく。佐之助の気分はもう仕事に踏みこんでいた。
奥村は御家人だったという噂もあった。しかし、奥村がやっていることと言えば、佐之助のような男を使って、人を恐喝したり、無慈悲に貸金を取り立てたり、人を誘って不具にしたり、もっと怖い仕事が含まれているとのことなのだ。
「じつは、仕事がありましたら、分けて頂きたいと思いやして」
「仕事はいつでもあるさ」
少し固くなって口を切った佐之助に、奥村は歯切れのいい江戸弁で答えた。
「どうだ、お前さん。人を殺めたことがあるかね」
「いえ、まだですが」
「一度やってみるかね。手当は十両だ」
「………」
「やってみるかね」
「待ってください。殺しは、あっしの性に合いません」
「………」
ぴたりと奥村は口を噤んだ。
じっと佐之助を見据えている。奥村の視線が、身体を突き刺してくるのがわかった。佐之助は、これまで覚えたことのない恐怖が、心をかすめるのを感じた。
「それでは、ごめんこうむります」
佐之助は漸く言った。
「四」に続く














