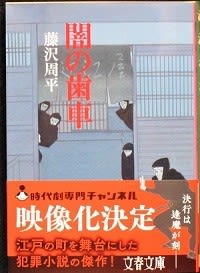
「あらすじ」
「酒亭おかめ」
(佐之助も仲間に入り、おかめの二階で、常連四人に押込みの計画を告知する伊兵衛)
二 (おかめからの帰り、酷い雨の中で逢ったおくめを、佐之助は家に入れ、介助する)
佐之助がおかめに入ると、客はいつもの青白い顔をした浪人一人で気の毒なほどがらんとしていた。
酒を持ってきた親爺から、「今日はいい魚が入らなくて、ひらめの塩焼きですが………」と言われて、いいよと、佐之助は銚子を持った。
親爺は遠慮した口ぶりだったが、しばらくして持ってきたひらめの塩焼きは、うまかった。べつに押し込みみたいな危ないことをしなくとも、こうして酒を飲める、と思った。この前、飯台の向こう側に座って、しつこく押し込みをすすめた男を思い出したのである。
男とは、そのあと二度ほどこの店で顔を合わせている。だが、男は遠くからにこにこ笑いかけただけで、近寄っては来なかった。諦めたのかもしれないな、と佐之助は思った。
「亭主、勘定たのむ」
不意に浪人が言った。
―――珍しいな。
今夜は早いなと佐之助は思って浪人の横顔を眺めた。
すると、その視線を感じとったように、浪人が佐之助を振り向いた。そして、近寄ってきた。
「ちと、ものを尋ねたいが………。癆咳というものは、治らんものかな ? 」
「………」
「いや、身どもの家内が癆咳での。夜も昼も苦しむのだ。何か良い薬でもご存じないかと思っての」
佐之助は、そいつは気の毒だと言いながら、噂の高麗人参の話をする。
………。
「俺もひきあげるぜ。いくらになるね」
佐之助は立ち上がった。
―――降ってきたぜ。
佐之助は足を速めた。だが、雨はそれからいくらも歩かないうちに、凄まじい雨音をともなった土砂降りになった。
―――これじゃ、埒があかねえぜ。
手をやってみると、膝から下は絞るほど濡れている。
空を斬り裂いて稲妻が走り、そのたびに町は昼のように明るくなる。夜道にまごつくこともなく、佐之助は走り続けた。
女に気づいたのは、表通りから裏店に通じる小路に走り込んだときだった。
「おくみさんじゃねえか。どうしたい ? 」
佐之助は女の手を掴んで怒鳴るように言った。
「これじゃどうしょうもねえぜ。家へ来な」
佐之助はまた怒鳴った。
―――とんだ道行きだ。
佐之助は思わず舌打ちした。厄介なものを背負いこんだ予感が、胸をかすめたのである。
家にに入ると、佐之助は上がり框(かまち)に着物を脱ぎ捨て、行燈に灯を入れた。それから大急ぎで女のために着物を探した。
「こっちに上がって着換えなせえ。あ、それからな。着換える前に手拭でごしごしと身体を拭かなきゃだめですぜ。髪もな。手拭は窓のところへつるさがってまさ」
………。
「あんたのご亭主は、やっぱり家の中に入れてはくれなかったのかい ? 」
「いなかったんですよ」
女がぽつりと言った。呟くような声で聴きとれなくて、佐之助は女のほうに耳を傾けた。
「いなかったんですよ。あの人、どっかに引越しちゃったんです」
「え ? そいつは気づかなかったな」
………。
「あたし帰ります」
と言って女が立ち上がった。気がつくと雨がやんでいる。
おくみは、戸を開けてから、なぜかためらうように外の闇を見つめた。それから振り向くと、呟くように言った。
「すみません。さっきは寒かったのに、今度は暑くて………」
「どうしたね。気分でも悪いか」
佐之助が土間に片足をおろしたとき、おくみは入口の柱に縋ったまま、ずるずると土間に崩れ落ちた。抱き起して、額に手を当ててみると、火のように熱かった。
「三」に続く














