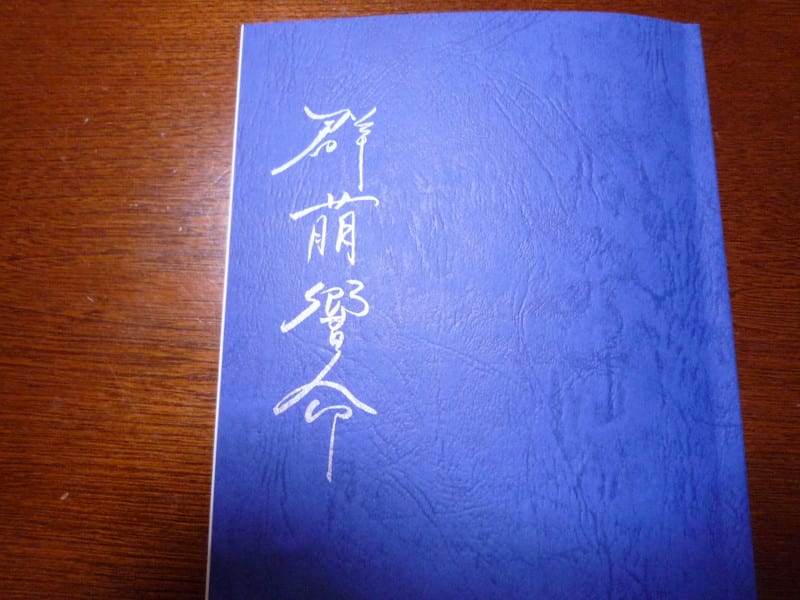
「論。悔眠尋伺至無別翻對 述曰。不定四法。通染不染三種性故。如遍行觸等。等餘四法。別境中欲等。亦等四法。無別翻對。唯惡不通三性法者。方翻之也。此前或有行相相翻。如捨治掉擧。掉擧相高。捨相靜故。亦得通治。以掉擧是貪・癡分故。又説性對治即忘念等三癡分者。是不忘念等正翻是。或有行相體性皆相翻。不忿等是無瞋一分等。如理應思。然八十九大有諸煩惱名字。一一應翻對之數彼多少何分所攝 第二問答廢立。」(『述記』第六本した・三十三右。大正43・440b~c)
(「述して曰く。不定の四法は染と不染との三種の性に通ずるが故に。遍行の触等の如し。余の四法を等す。別境の中の欲等にも亦四法を等す。別に翻対すること無し。唯だ悪にして三性に通ぜざる法は、方に之を翻ぜるなり。此より前は或は行相相い翻ずること有り。(行)捨の掉擧を治するが如し。掉擧の相は高なり。(行)捨の相は静なるが故に、亦通じて治することを得。掉擧は是れ貪・癡の分なるを以ての故に。
又、性の対治を説く。即ち妄念等の三の癡の分なる者是れなり。不妄念等は正しく是れに翻ず。或は行相も体相も皆相い翻ぜる有り。不忿等は是れ無瞋の一分なる等なり。理の如く思うべし。然るに八十九に大いに諸の煩悩の名字有り、一々之に翻対して、彼の多少の何の分に摂せられるかを数うべし。
第二に廃立を問答す。」)
対煩悩・対小随煩悩・対中随煩悩・対大随煩悩について、能対治法→所対治法と其の体を述べてきました。それが実法か仮法かについても説明されてきました。尚、六位五十一の心所は頌では、第九頌から第十四頌に述べられています。ただ、この六位五十一の心所は理世俗に依って説かれていると展開されてきます。
心の構造の分析は、理世俗に依ってのみいわれることで、真勝義には無いんだと。『論』には、「識差別の相は理世俗に依る、真勝義には非ず、真勝義の中には心言絶するが故に。
伽陀に説くが如し。
「「心・意・識との八種は俗の故には相別なること有り、真の故には相別なること無し、相と所相と無きが故にと」(『楞伽経』)
世間世俗・世間勝義は四重二諦によって説明されていますが、世俗諦と勝義諦を世間・道理・証得・勝義の四つに分けてそれぞれの四つがどのように相応するのかを説いたものです。世俗は有我・勝義は無我の立場からの説明ですが、これは二つに分かれているという話ではないのですね。世間の在り方の中に二つの方向性があるということなのです。
ここは大変大事な所でありますので、随分脱線してしまいますが、少し考究してみたいと思います。 (つづく)




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます