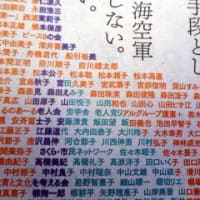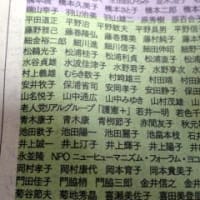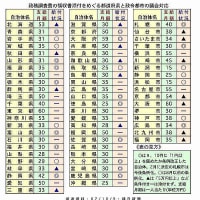先日日経ニュースで、千葉の覚せい剤事件の被告側の弁護人が『「裁判員裁判は違憲」とする控訴趣意書を東京高裁に提出していたことが16日、分かった。裁判員裁判を違憲として控訴したケースは全国初とみられる』と報じていた。
記事によれば、弁護人は控訴趣意書で、『「下級裁判所の裁判官は、最高裁の指名した者の名簿によって内閣が任命する」とする憲法80条と、くじで市民が選ばれる裁判員制度が矛盾すると指摘。「裁判員制度を認める条文はどこにも存在しない」と主張している』とのことである。
これを読むと、弁護人の主張は至極ごもっともなことのように思える。これまで裁判員制度導入にあたっては賛否両論があり、いろいろ議論されてきたが、法律の専門家や行政側は憲法80条との整合性をどのように議論して、クリアしてきたのであろうか。国民には知らされていないように思う。
裁判員制度導入の経緯をウイキペディアで見ると『制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子[1]、次いで意見書[2]がまとめられた。』と説明されている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6
審議会のメンバーには複数の法律学者も弁護士も含まれているからなおさら不可解である。しかしメンバー(ウイキペディア参照)には裁判官は三権分立の立場からか含まれていないようである。仮に裁判官がメンバーに含まれていれば、このような事は事前にそれなりの解釈がなされ、憲法との整合性は計られ、提訴は起こり得なかったのではないかと推察できる。
しかし訴訟が提起された今、素人が憲法80条を広義に解釈すれば、弁護人の主張が正当に思える。しかし狭義に文理解釈すれば、裁判官と裁判員は違い、憲法80条には抵触しないとの解釈も可能であろう。また裁判官も裁判員も実質裁判に携わる以上、同じであるとの広義の立場にたてば、裁判員は最高裁が「指名した者」ではなく、「くじで選ばれた者」であり、憲法に抵触すると解釈ができる。
既に裁判員制度もスタートして10ヶ月である。何れにしろ東京高裁、最高裁には裁判員制度のスタートに関係なく、正当な憲法判断を期待したい。
「護憲+BBS」「裁判・司法行政ウォッチング」より
厚顔の美少年
====
厚顔の美少年さん紹介の下記コメントですが、被告側弁護人の主張はおかしいと思います。裁判員は裁判官ではありません。憲法80条と抵触しません。こういう訴えをする弁護士の法解釈は詭弁です。裁判員という名づけがおかしいので、簡単な法解釈もできないのです。
裁判官は官憲(憲法の)であり、国家の代理人として80条の適用を受けますが、裁判員は陪審同様に三権の埒外にあり、憲法の認める司法の民主化に貢献するものであり、憲法が委任する法制度だと解します。
>控訴趣意書で弁護側は、「下級裁判所の裁判官は、最高裁の指名した者の名簿によって内閣が任命する」とする憲法80条と、「くじで市民が選ばれる裁判員制度が矛盾すると指摘。「裁判員制度を認める条文はどこにも存在しない」と主張している。
「護憲+BBS」「裁判・司法行政ウォッチング」より
名無しの探偵
記事によれば、弁護人は控訴趣意書で、『「下級裁判所の裁判官は、最高裁の指名した者の名簿によって内閣が任命する」とする憲法80条と、くじで市民が選ばれる裁判員制度が矛盾すると指摘。「裁判員制度を認める条文はどこにも存在しない」と主張している』とのことである。
これを読むと、弁護人の主張は至極ごもっともなことのように思える。これまで裁判員制度導入にあたっては賛否両論があり、いろいろ議論されてきたが、法律の専門家や行政側は憲法80条との整合性をどのように議論して、クリアしてきたのであろうか。国民には知らされていないように思う。
裁判員制度導入の経緯をウイキペディアで見ると『制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子[1]、次いで意見書[2]がまとめられた。』と説明されている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6
審議会のメンバーには複数の法律学者も弁護士も含まれているからなおさら不可解である。しかしメンバー(ウイキペディア参照)には裁判官は三権分立の立場からか含まれていないようである。仮に裁判官がメンバーに含まれていれば、このような事は事前にそれなりの解釈がなされ、憲法との整合性は計られ、提訴は起こり得なかったのではないかと推察できる。
しかし訴訟が提起された今、素人が憲法80条を広義に解釈すれば、弁護人の主張が正当に思える。しかし狭義に文理解釈すれば、裁判官と裁判員は違い、憲法80条には抵触しないとの解釈も可能であろう。また裁判官も裁判員も実質裁判に携わる以上、同じであるとの広義の立場にたてば、裁判員は最高裁が「指名した者」ではなく、「くじで選ばれた者」であり、憲法に抵触すると解釈ができる。
既に裁判員制度もスタートして10ヶ月である。何れにしろ東京高裁、最高裁には裁判員制度のスタートに関係なく、正当な憲法判断を期待したい。
「護憲+BBS」「裁判・司法行政ウォッチング」より
厚顔の美少年

====
厚顔の美少年さん紹介の下記コメントですが、被告側弁護人の主張はおかしいと思います。裁判員は裁判官ではありません。憲法80条と抵触しません。こういう訴えをする弁護士の法解釈は詭弁です。裁判員という名づけがおかしいので、簡単な法解釈もできないのです。
裁判官は官憲(憲法の)であり、国家の代理人として80条の適用を受けますが、裁判員は陪審同様に三権の埒外にあり、憲法の認める司法の民主化に貢献するものであり、憲法が委任する法制度だと解します。
>控訴趣意書で弁護側は、「下級裁判所の裁判官は、最高裁の指名した者の名簿によって内閣が任命する」とする憲法80条と、「くじで市民が選ばれる裁判員制度が矛盾すると指摘。「裁判員制度を認める条文はどこにも存在しない」と主張している。
「護憲+BBS」「裁判・司法行政ウォッチング」より
名無しの探偵