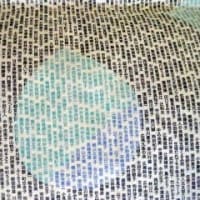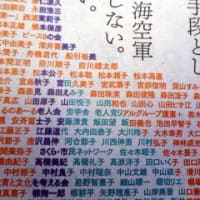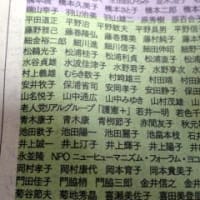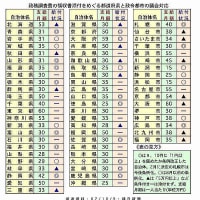もし社会に、何らかの構造的課題が存在しているのであれば、それに対しては是正に繋がる行動が為されてほしいものだ。その課題が国内のものであろうが、国際間にまたがるものであろうが、同様に行動が為されてほしいものである。
ところが、グローバルノースに対してグローバルサウスが存在していると言われていること自体に、両者の間には厳然たる構造的課題が国際間には存在していることは明白である。
例えば、パーム油のプランテ―ション開墾の為の森林伐採の横行や、違法伐採木材すらが流通し横行している状況の放置であり、結果として森林伐採が進行し、ために気候変動事象が更に悪化していくという悪い回転の構造が今もあり、しかも減るどころか拡大していると言われているのである。
そして課題が生じる大きな原因の一つに、格差の存在とその放置の問題があると考える。
ここで伝える話題の論旨は、例えば、先の能登地震の問題を考える際にも通じる興味ある視点が提供されていると思う。日本の国内にも、更に更にと富み栄えていく都市部と共に、更に更にと疲弊が進み消滅さえ懸念される田園部との格差問題があり、この課題の放置は許されないのであり、是正に繋がる行動が大いに論じられ、そして為されてほしいと思う所である。
かかる視点から、このパプアニューギニアの現在の災害状況を伝える記事は、これらの課題を再確認する機会となり意義あるものと思い紹介する次第です。
***
何故にパプアニューギニアで多くの死者の発生を伴う地滑り・土砂崩れが多いのか?どのような協力が我々にできるのだろうか?
(原題:Why does Papua New Guinea experience so many fatal landslides---and what can be done?
ABC news Australia アンドリュー・ソールペ氏記す )
この金曜、パプアニューギニア・エンガ州のカオカラムという辺境の村で、100人を超す人命が奪われたと見られる大規模な地滑り・土砂崩れが発生した。
パプアニューギニアでは、ここ数カ月間、地滑り・土砂崩れ被害が続いている。例えば4月にはシンブ州で14人が生き埋めになっており、3月中旬には3件の地滑り・土砂崩れが発生し少なくとも21人が亡くなっている。
人命が奪われる地すべり・土砂崩れ被害の発生は、パプアニューギニアでは今に始まったことではなく、しかも悲しいことに、地すべり・土砂崩れが定期的に発生し、多くの人命がこの地で奪われるものの、それらの報道が海外に流されることは余りないのである。
パプアニューギニアにおいて地すべり・土砂崩れが何故頻繁に発生するのか、しかも多数の人命が奪われ続けるのか、そして世界の国々がこの状況の打開にどう協力できるか、を考えてみたい。
科学雑誌「Eos」で「地滑り・土砂崩れブログ」を運営している、著名な地滑り・土砂崩れ事象専門家である英国のハル大学副学長のデイブ・ぺトレイ氏は、パプアニューギニアで頻発する地滑り・土砂崩れには多くの要因が絡んでおり、その中の主な要因としてパプアニューギニアの山岳地帯特有の気象環境と熱帯特有の天候とが深く影響している、と語る。
激しい風雨や嵐により地盤の浸食が進行していき、洪水や高潮といった全ての事象が危険な岩石落下の発生率を高める働きをする、とぺトレイ氏は指摘する。
それに加えて、パプアニューギニアは太平洋の2つのプレートの境界に沿って活火山が走り、そして地震活動の活発な環太平洋火山帯に位置しており、地滑り・土砂崩れが起こりやすい環境が整っている、としている。
「常時起こる地震自体が地滑り・土砂崩れを誘発することがあり、地震によって岩盤の斜面構造が弱体化されるということも起こる。いわば、これらの地域全体が構造的に非常に活動的な場所となっている」とぺトレイ氏は指摘する。
パプアニューギニアで頻発する地滑り・土砂崩れは確かに問題ではあるが、パプアニューギニアに限ったものではないのであり、例えばアメリカ・日本・イタリア・オーストリアやスイスのような世界の各地の丘陵・山岳地域で、厳しい気象条件が重なれば地滑り・土砂崩れは同様に発生しやすくなるのである。
それでは、人命を奪うような地滑り・土砂崩れが、ことにパプアニューギニアで頻発しているのは何故なのだろうか?
研究者らは、地震やその他の通常起こる自然災害の場合と同じく、地滑り・土砂崩れによる死亡者数とその地域の経済状況との間に存在する関係性に長年にわたり着目している。
全ての条件が同じであれば、国が貧しいほど、死亡者数は多くなる、と言われている。
この説明に対する理由は数多くある。インフラ構築物が貧弱な点・緊急時対応が有効に働かない点・医療体制が低水準である点や早期警戒警報システムがない点などが主な理由である。
別の理由として、その地域の人々の居住場所が、地域の開発状況によって決まってしまうという点を指摘する研究者がいる(Joshua West,The Conversation,January22,2018)。
パプアニューギニアは世界で最も田園地帯特有の社会が残っている地域の一つである。
公式発表の人口は、1050万人だが、実際はもっと多いと見られ、国連の調査結果によると1700万人程になるだろうと見られている。この違いの発生は、基礎的統計資料の運用上の不備が原因とされている。
いずれにしても、パプアニューギニアの都市部に居住する人の数は、全体の20%以下で、大半の人々は自給自足型農業に依存して暮らす農耕民であり、彼らは農耕のためある程度の土地を必要としている。そして人口が増大する傾向のなか、丘陵地が主体の地域で暮らさざるを得ない彼らは、必然的に地滑り・土砂崩れの危険性があり、緊急時の支援活動が期待できない地域に居住せざるを得ない状況に置かれているのである。
地形的な条件や気象条件の問題に加えて、パプアニューギニアの地滑り・土砂崩れ頻発の原因として、ペトリイ氏は人間の生産活動がもう一つ別の大きな要因となっていると指摘する。
パプアニューギニアの森林地域には、小さな規模の村々及び彼らの耕作地域が展開されている以外に、大規模産業の数多くの工場もまた展開されており、金・銀・銅・コバルトの採掘や液化天然ガス(LNG)も採掘が行われており、過去に人命を奪った地滑りが引き起こされていたのである。
規模の大きい違法伐採の問題もパプアニューギニアには存在しており、またパプアニューギニアは世界で5番目に多くヤシ油を輸出しており、ヤシ油のプランテ―ションには大規模な森林伐採がついて廻るのである。
ぺトレイ氏は、「地形的には、植林化・森林化が強く求められるのであるが、パプアニューギニアの森は伐採され続けている」と指摘する。
パプアニューギニアの森林伐採の問題は、衛星写真で確認する限り改善の兆しはない。パプアニューギニアは地滑り・土砂崩れの危険性の除去や低減に役立つインフラ作りに苦闘している最中である。
一方で、森林伐採も原因して気候変動は高進していき、海面上昇による高潮被害も課題となってきている。海岸沿いの村レセ・カヴォラの住民は、巨大高潮により農作地や飲み水が被害を受けたことから、この3月村全体の移動の検討を始めている。
気候変動は、地域の地形が対処できる能力を超える突然の気象状況を発生させることから、特に地滑りに大きな影響を与える、とぺトレイ氏は指摘する。
「短時間に、多大な降雨量を伴う雨に対して、崖という斜面は特に脆弱だ」としている。
「地形というものは、それが従来経験してきた最も大きな衝撃には耐える構造ではあるが、もしも新たな衝撃が従来経験した以上の大規模な場合、その地形は、新たな衝撃に応じて変形していくのであり、即ち地滑り・土砂崩れということが必然的なものになるのである」とぺトレイ氏は指摘する。
山岳地帯での地滑り・土砂崩れは、ある程度は避けられないものである。しかしながら、死亡者数や対応策という両面において地滑り・土砂崩れの被害を軽減することは出来る、と専門家らは指摘する。
ヤシ油のプランテ―ションやLNG開発の様な大規模プロジェクトを推進するのではなく、規模の小さい地元経済の後押しが、パプアニューギニアが進めるべき正しい方向の対策であろう。
ぺトレイ氏は、過去に数百人の人命が地滑り被害で失われていたヒマラヤ地域が植林活動・森林化促進活動により成功を収めてきているネパールの事例を取り上げている。「森林再生に積極的だった地域では、地滑り・土砂崩れはかなり減少しているのである」と指摘している。
パプアニューギニア以外の国々の人々は、例えばヤシ油への必要量を抑えることとか違法伐採の木材の利用をやめるといった形でパプアニューギニアの森林伐採スピードを遅らせる形での協力は可能である。
「希少金属等の資源の採掘の運用上の規制を強めることも又、我々には必要なことである」とぺトレイ氏は指摘している。
「護憲+BBS」「新聞記事などの紹介」より
yo-chan
ところが、グローバルノースに対してグローバルサウスが存在していると言われていること自体に、両者の間には厳然たる構造的課題が国際間には存在していることは明白である。
例えば、パーム油のプランテ―ション開墾の為の森林伐採の横行や、違法伐採木材すらが流通し横行している状況の放置であり、結果として森林伐採が進行し、ために気候変動事象が更に悪化していくという悪い回転の構造が今もあり、しかも減るどころか拡大していると言われているのである。
そして課題が生じる大きな原因の一つに、格差の存在とその放置の問題があると考える。
ここで伝える話題の論旨は、例えば、先の能登地震の問題を考える際にも通じる興味ある視点が提供されていると思う。日本の国内にも、更に更にと富み栄えていく都市部と共に、更に更にと疲弊が進み消滅さえ懸念される田園部との格差問題があり、この課題の放置は許されないのであり、是正に繋がる行動が大いに論じられ、そして為されてほしいと思う所である。
かかる視点から、このパプアニューギニアの現在の災害状況を伝える記事は、これらの課題を再確認する機会となり意義あるものと思い紹介する次第です。
***
何故にパプアニューギニアで多くの死者の発生を伴う地滑り・土砂崩れが多いのか?どのような協力が我々にできるのだろうか?
(原題:Why does Papua New Guinea experience so many fatal landslides---and what can be done?
ABC news Australia アンドリュー・ソールペ氏記す )
この金曜、パプアニューギニア・エンガ州のカオカラムという辺境の村で、100人を超す人命が奪われたと見られる大規模な地滑り・土砂崩れが発生した。
パプアニューギニアでは、ここ数カ月間、地滑り・土砂崩れ被害が続いている。例えば4月にはシンブ州で14人が生き埋めになっており、3月中旬には3件の地滑り・土砂崩れが発生し少なくとも21人が亡くなっている。
人命が奪われる地すべり・土砂崩れ被害の発生は、パプアニューギニアでは今に始まったことではなく、しかも悲しいことに、地すべり・土砂崩れが定期的に発生し、多くの人命がこの地で奪われるものの、それらの報道が海外に流されることは余りないのである。
パプアニューギニアにおいて地すべり・土砂崩れが何故頻繁に発生するのか、しかも多数の人命が奪われ続けるのか、そして世界の国々がこの状況の打開にどう協力できるか、を考えてみたい。
科学雑誌「Eos」で「地滑り・土砂崩れブログ」を運営している、著名な地滑り・土砂崩れ事象専門家である英国のハル大学副学長のデイブ・ぺトレイ氏は、パプアニューギニアで頻発する地滑り・土砂崩れには多くの要因が絡んでおり、その中の主な要因としてパプアニューギニアの山岳地帯特有の気象環境と熱帯特有の天候とが深く影響している、と語る。
激しい風雨や嵐により地盤の浸食が進行していき、洪水や高潮といった全ての事象が危険な岩石落下の発生率を高める働きをする、とぺトレイ氏は指摘する。
それに加えて、パプアニューギニアは太平洋の2つのプレートの境界に沿って活火山が走り、そして地震活動の活発な環太平洋火山帯に位置しており、地滑り・土砂崩れが起こりやすい環境が整っている、としている。
「常時起こる地震自体が地滑り・土砂崩れを誘発することがあり、地震によって岩盤の斜面構造が弱体化されるということも起こる。いわば、これらの地域全体が構造的に非常に活動的な場所となっている」とぺトレイ氏は指摘する。
パプアニューギニアで頻発する地滑り・土砂崩れは確かに問題ではあるが、パプアニューギニアに限ったものではないのであり、例えばアメリカ・日本・イタリア・オーストリアやスイスのような世界の各地の丘陵・山岳地域で、厳しい気象条件が重なれば地滑り・土砂崩れは同様に発生しやすくなるのである。
それでは、人命を奪うような地滑り・土砂崩れが、ことにパプアニューギニアで頻発しているのは何故なのだろうか?
研究者らは、地震やその他の通常起こる自然災害の場合と同じく、地滑り・土砂崩れによる死亡者数とその地域の経済状況との間に存在する関係性に長年にわたり着目している。
全ての条件が同じであれば、国が貧しいほど、死亡者数は多くなる、と言われている。
この説明に対する理由は数多くある。インフラ構築物が貧弱な点・緊急時対応が有効に働かない点・医療体制が低水準である点や早期警戒警報システムがない点などが主な理由である。
別の理由として、その地域の人々の居住場所が、地域の開発状況によって決まってしまうという点を指摘する研究者がいる(Joshua West,The Conversation,January22,2018)。
パプアニューギニアは世界で最も田園地帯特有の社会が残っている地域の一つである。
公式発表の人口は、1050万人だが、実際はもっと多いと見られ、国連の調査結果によると1700万人程になるだろうと見られている。この違いの発生は、基礎的統計資料の運用上の不備が原因とされている。
いずれにしても、パプアニューギニアの都市部に居住する人の数は、全体の20%以下で、大半の人々は自給自足型農業に依存して暮らす農耕民であり、彼らは農耕のためある程度の土地を必要としている。そして人口が増大する傾向のなか、丘陵地が主体の地域で暮らさざるを得ない彼らは、必然的に地滑り・土砂崩れの危険性があり、緊急時の支援活動が期待できない地域に居住せざるを得ない状況に置かれているのである。
地形的な条件や気象条件の問題に加えて、パプアニューギニアの地滑り・土砂崩れ頻発の原因として、ペトリイ氏は人間の生産活動がもう一つ別の大きな要因となっていると指摘する。
パプアニューギニアの森林地域には、小さな規模の村々及び彼らの耕作地域が展開されている以外に、大規模産業の数多くの工場もまた展開されており、金・銀・銅・コバルトの採掘や液化天然ガス(LNG)も採掘が行われており、過去に人命を奪った地滑りが引き起こされていたのである。
規模の大きい違法伐採の問題もパプアニューギニアには存在しており、またパプアニューギニアは世界で5番目に多くヤシ油を輸出しており、ヤシ油のプランテ―ションには大規模な森林伐採がついて廻るのである。
ぺトレイ氏は、「地形的には、植林化・森林化が強く求められるのであるが、パプアニューギニアの森は伐採され続けている」と指摘する。
パプアニューギニアの森林伐採の問題は、衛星写真で確認する限り改善の兆しはない。パプアニューギニアは地滑り・土砂崩れの危険性の除去や低減に役立つインフラ作りに苦闘している最中である。
一方で、森林伐採も原因して気候変動は高進していき、海面上昇による高潮被害も課題となってきている。海岸沿いの村レセ・カヴォラの住民は、巨大高潮により農作地や飲み水が被害を受けたことから、この3月村全体の移動の検討を始めている。
気候変動は、地域の地形が対処できる能力を超える突然の気象状況を発生させることから、特に地滑りに大きな影響を与える、とぺトレイ氏は指摘する。
「短時間に、多大な降雨量を伴う雨に対して、崖という斜面は特に脆弱だ」としている。
「地形というものは、それが従来経験してきた最も大きな衝撃には耐える構造ではあるが、もしも新たな衝撃が従来経験した以上の大規模な場合、その地形は、新たな衝撃に応じて変形していくのであり、即ち地滑り・土砂崩れということが必然的なものになるのである」とぺトレイ氏は指摘する。
山岳地帯での地滑り・土砂崩れは、ある程度は避けられないものである。しかしながら、死亡者数や対応策という両面において地滑り・土砂崩れの被害を軽減することは出来る、と専門家らは指摘する。
ヤシ油のプランテ―ションやLNG開発の様な大規模プロジェクトを推進するのではなく、規模の小さい地元経済の後押しが、パプアニューギニアが進めるべき正しい方向の対策であろう。
ぺトレイ氏は、過去に数百人の人命が地滑り被害で失われていたヒマラヤ地域が植林活動・森林化促進活動により成功を収めてきているネパールの事例を取り上げている。「森林再生に積極的だった地域では、地滑り・土砂崩れはかなり減少しているのである」と指摘している。
パプアニューギニア以外の国々の人々は、例えばヤシ油への必要量を抑えることとか違法伐採の木材の利用をやめるといった形でパプアニューギニアの森林伐採スピードを遅らせる形での協力は可能である。
「希少金属等の資源の採掘の運用上の規制を強めることも又、我々には必要なことである」とぺトレイ氏は指摘している。
「護憲+BBS」「新聞記事などの紹介」より
yo-chan