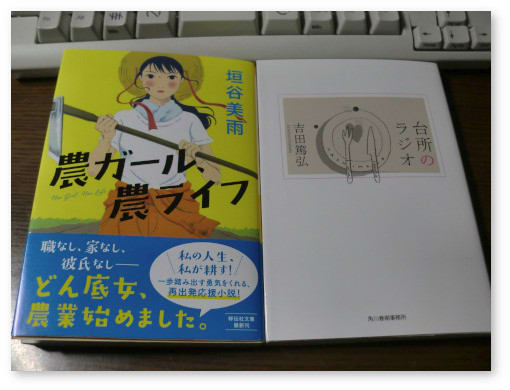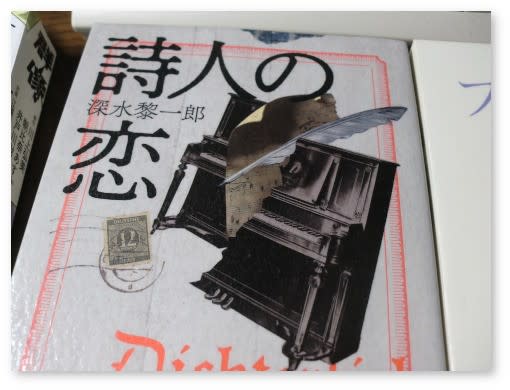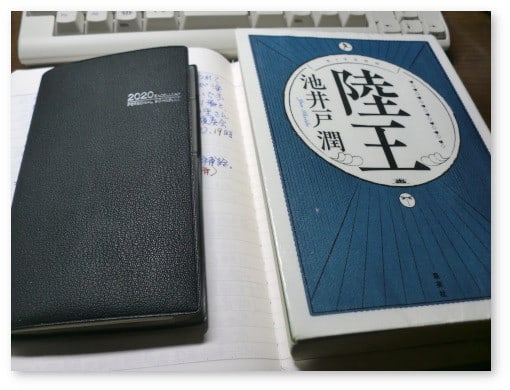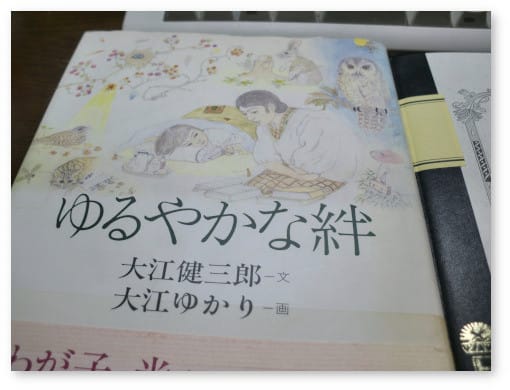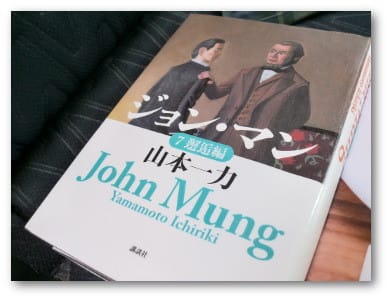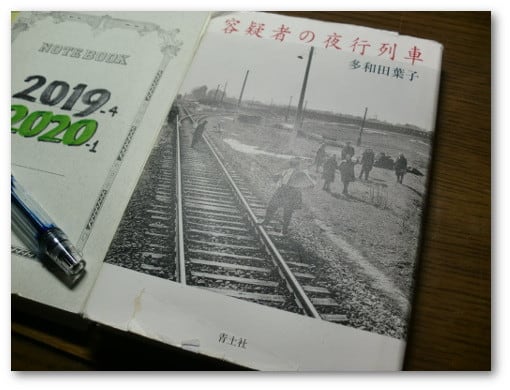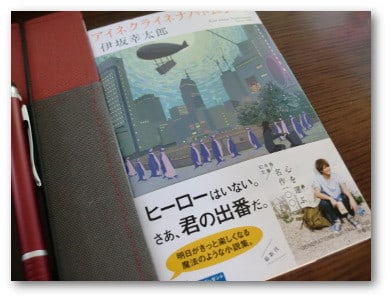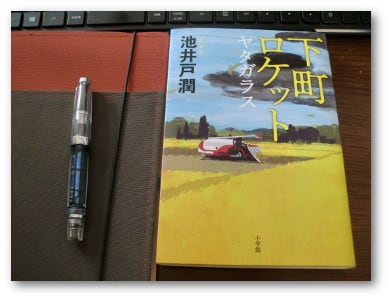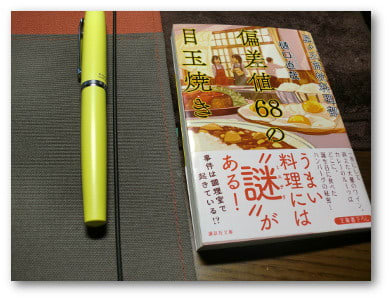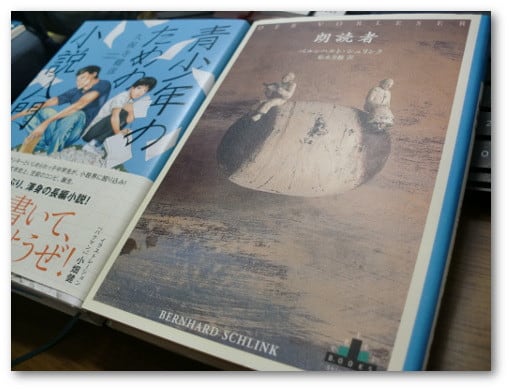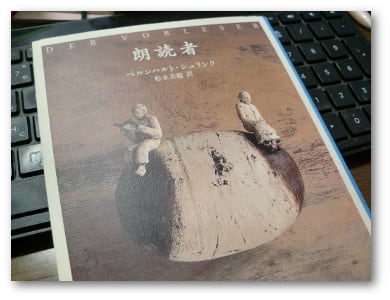角川のハルキ文庫で、吉田篤弘著『台所のラジオ』を読みました。2017年刊行で単行本は前年に出ているようです。今年の真冬に購入したのは2020年5月発行の第4刷ですから、ある程度、安定して読まれているのでしょう。本書カバー裏の内容紹介には
とありました。短編集の中身は、
というもので、著者のあとがきによれば女性と男性の主人公が交互に登場する配列にしたのだそうです。『台所のラジオ』という題名のとおり、また以前読んだ『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(*1)と同様に、何かしら食べものや料理が登場するのですが、今回はそれらがどれも「ひねている」というか、登場人物が力説するほど美味しそうには思えない。どこかフワフワした物語はいつのまにか終わっている、というようなタイプのお話が並びます。
うーむ、やっぱりこれは、もっと若い頃に都会の空気の中で読むには良かったのかもしれないけれど、もうすぐ古希の爺さんが果樹園の草刈りの一服で読むような本ではなかったなあ。まあ、夢に出てくるような強烈さは皆無なので、寝床で一話ずつ読み進めるのには良かったけれど。一緒に購入した『農ガール、農ライフ』は、すぐに面白く読んだ(*2)のでしたが、こちらは読みかけては中断、また読みかけては中断と、だいぶ時間がかかりました。
(*1): 吉田篤弘『それからはスープのことばかり考えて暮らした』を読む〜「電網郊外散歩道」2013年7月
(*2): 垣谷美雨『農ガール、農ライフ』を読む〜「電網郊外散歩道」2021年2月
それなりの時間を過ごしてくると、人生には妙なことが起きるものだ―。昔なじみのミルク・コーヒー、江戸の宵闇でいただくきつねうどん、思い出のビフテキ、静かな夜のお茶漬け。いつの間にか消えてしまったものと、変わらずそこにあるものとをつなぐ、美味しい記憶。台所のラジオから聴こえてくる声に耳を傾ける、十二人の物語。滋味深くやさしい温もりを灯す短篇集。
とありました。短編集の中身は、
- 紙カツと黒ソース
- 目薬と棒パン
- さくらと海苔巻き
- 油揚げと架空旅行
- 明日、世界が終わるとしたら
- マリオ・コーヒー年代記
- 毛玉姫
- 夜間押しボタン式信号機
- <十時軒>のアリス
- いつか、宙返りするまで
- シュロの休息
- 最終回の彼女
というもので、著者のあとがきによれば女性と男性の主人公が交互に登場する配列にしたのだそうです。『台所のラジオ』という題名のとおり、また以前読んだ『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(*1)と同様に、何かしら食べものや料理が登場するのですが、今回はそれらがどれも「ひねている」というか、登場人物が力説するほど美味しそうには思えない。どこかフワフワした物語はいつのまにか終わっている、というようなタイプのお話が並びます。
うーむ、やっぱりこれは、もっと若い頃に都会の空気の中で読むには良かったのかもしれないけれど、もうすぐ古希の爺さんが果樹園の草刈りの一服で読むような本ではなかったなあ。まあ、夢に出てくるような強烈さは皆無なので、寝床で一話ずつ読み進めるのには良かったけれど。一緒に購入した『農ガール、農ライフ』は、すぐに面白く読んだ(*2)のでしたが、こちらは読みかけては中断、また読みかけては中断と、だいぶ時間がかかりました。
(*1): 吉田篤弘『それからはスープのことばかり考えて暮らした』を読む〜「電網郊外散歩道」2013年7月
(*2): 垣谷美雨『農ガール、農ライフ』を読む〜「電網郊外散歩道」2021年2月