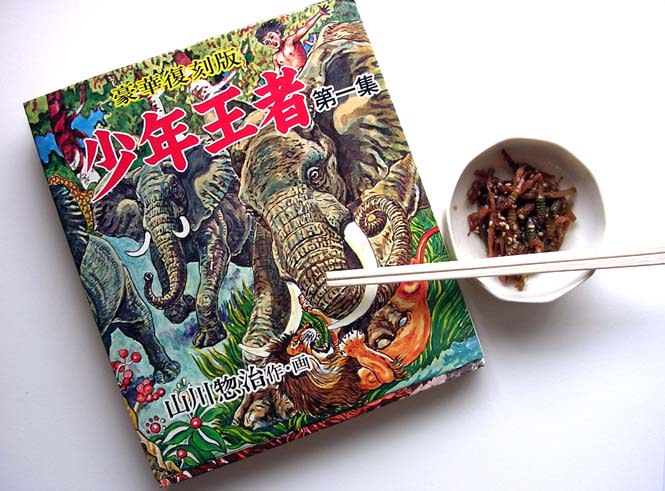30歳代の前半までの私の生活は半夜行性で、昼前に起き出し午前2時頃から始まる「深夜劇場」という古い洋画を放映するTV番組があり、それが始まるまで仕事をして観終わって眠りにつく生活をしていた。
子どもが眠い目をこすりながら学校へ行くのに、親父はまだ寝ていたのでは示しつかないから、息子の入学を機に昼型の生活にあらためた。
その深夜劇場の中で邦題で「缶けり」という短編の洋画があり原題も「CAN KICK」となっていて、 私たちが子どもの頃に遊んだ缶けりとまったく同じ遊びで、缶けりは日本の昔の遊びかと思っていたが、缶詰めと同時に輸入された遊びだとそのときに知った。
映画の内容は深夜の老人ホームの一室で、一人の老人がむっくりと起きだし、それに合わせるかのように次々と他の部屋からも老人たちがホームの中庭に抜け出して来て、月明かりを頼りに缶けりに興じはじめた。
遊んでいるうちに老人たちは次第に子どもの姿に変わり、ひとしきり遊んだ子どもたちがベッドに戻り再度の眠りにつくと、子どもたちの顔はまた元の老人に戻っていった・・・・・。
そんな古い映画を思い出したのは、先日のクラス会の夜だった。
熱海駅に到着した16名のクラスメート(級友で旧友)たちは修学旅行の一行のように笑顔に満ちていた。
夕食中も話の切れ目がなかったが、食事後の深夜の歓談も50年前の話で盛り上がっていて、そのとき私は「CAN KICK」を思い出し、今カメラのシャッターを押せばきっとあの頃の18歳の姿が写るはずだと思って何枚かの写真を撮った。
しかし、デジカメの液晶画面には視覚的に大きな変化は見られなかったが、家に帰って写真を拡大してみると16人の瞳は確かに18歳のときの輝きをしていた。

帰りの小田原の 新幹線の改札はしばしの夢から実年齢に戻るゲートだった。
孫たちへのお土産を手に名古屋に向かう旧友たち
子どもが眠い目をこすりながら学校へ行くのに、親父はまだ寝ていたのでは示しつかないから、息子の入学を機に昼型の生活にあらためた。
その深夜劇場の中で邦題で「缶けり」という短編の洋画があり原題も「CAN KICK」となっていて、 私たちが子どもの頃に遊んだ缶けりとまったく同じ遊びで、缶けりは日本の昔の遊びかと思っていたが、缶詰めと同時に輸入された遊びだとそのときに知った。
映画の内容は深夜の老人ホームの一室で、一人の老人がむっくりと起きだし、それに合わせるかのように次々と他の部屋からも老人たちがホームの中庭に抜け出して来て、月明かりを頼りに缶けりに興じはじめた。
遊んでいるうちに老人たちは次第に子どもの姿に変わり、ひとしきり遊んだ子どもたちがベッドに戻り再度の眠りにつくと、子どもたちの顔はまた元の老人に戻っていった・・・・・。
そんな古い映画を思い出したのは、先日のクラス会の夜だった。
熱海駅に到着した16名のクラスメート(級友で旧友)たちは修学旅行の一行のように笑顔に満ちていた。
夕食中も話の切れ目がなかったが、食事後の深夜の歓談も50年前の話で盛り上がっていて、そのとき私は「CAN KICK」を思い出し、今カメラのシャッターを押せばきっとあの頃の18歳の姿が写るはずだと思って何枚かの写真を撮った。
しかし、デジカメの液晶画面には視覚的に大きな変化は見られなかったが、家に帰って写真を拡大してみると16人の瞳は確かに18歳のときの輝きをしていた。

帰りの小田原の 新幹線の改札はしばしの夢から実年齢に戻るゲートだった。
孫たちへのお土産を手に名古屋に向かう旧友たち