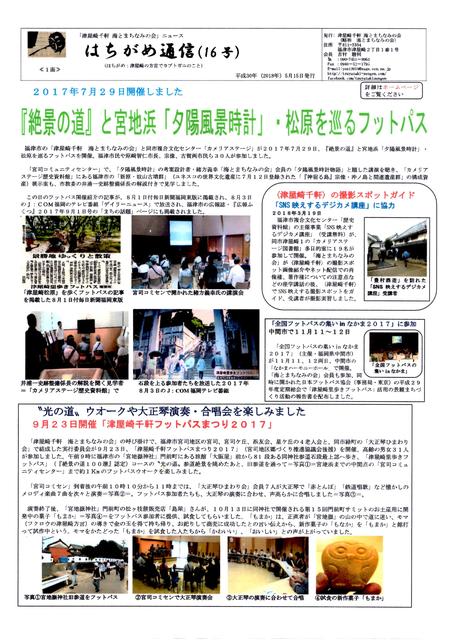写真①:『旅をするチョウ アサギマダラに会いに行こう!-ポイント案内1-』の表紙
=左上の写真は「津屋崎浜」でスナビキソウの花の蜜を吸うアサギマダラ(2015年5月20日、吉村勝利撮影)
アサギマダラに会える日本と台湾15ポイントのガイドブック電子版を発行
「津屋崎浜」〈「絶景の道」のスナビキソウとアサギマダラ〉も掲載
アサギマダラの移動の謎を調べている全国の同好者約140人で組織している「アサギマダラの会」(中西元男会長、事務局・大阪)編集委員会が8月1日、アサギマダラに会えるポイント解説のガイドブック・『旅をするチョウ アサギマダラに会いに行こう!-ポイント案内1-』=写真①=を電子書籍Kindle版(114ページ、価格400円でAmazon.co.jpで販売中)で発行。日本と台湾の計15ポイントの解説記事がカラー写真と地図付きで紹介されており、私が所属している福岡県福津市のまちづくりボランティア団体・「津屋崎千軒 海とまちなみの会」が2016年から海浜植物・スナビキソウの花の蜜を吸いに飛来するアサギマダラのマーキング調査を続けている同市・「津屋崎浜」も〈「絶景の道」のスナビキソウとアサギマダラ〉のサブタイトル付きで、九州本土でただ1か所、掲載されました。「絶景の道100選」認定・「津屋崎里歩きフットパス」コースにあるポイントと紹介されたことは、津屋崎が全国的に注目されると喜んでいます。
執筆者は、医師でアサギマダラ研究家の栗田昌裕・群馬パース大学(群馬県高崎市)学長=ポイント「福島県デコ平」の解説執筆=や、「アサギマダラの会」 副会長の金澤至・大阪市立自然史博物館外来研究員=ポイント「鹿児島県喜界島」、「高知県室戸岬」などの解説執筆=ら16人。「津屋崎浜」はアサギマダラに会えるポイントの2番目に掲載され=写真②=金澤副会長から「スナビキソウがそれほど話題になっていない2000年頃に(福津市)勝浦在住の花田氏ご夫婦が5~6月にアサギマダラのマーキングを行っておられた情報を元にアサギマダラの会が2003年6月に調査に入り、アサギマダラの北上期の重要な吸蜜源であることが確認された歴史的なポイント。その後、本格的な調査は行われなかった」として執筆を依頼された「海とまちなみの会」の吉村が記事、写真などを寄稿しました。

写真②:15ポイントの2番目に掲載された「福岡県 津屋崎浜」の記事画面
「津屋崎浜」の解説記事では、成虫が見られる季節は主に5月初旬~6月中旬とし、ポイントの概要として〈福津市の玄界灘に面した「津屋崎海水浴場」周辺である。スナビキソウは「津屋崎浜」の白い砂浜に群生し、このポイントは2014年に開設された「津屋崎里歩きフットパス」というコースの津屋崎1丁目にあたる。津屋崎里歩きフットパスは、「絶景の道100選」(新日本歩く道紀行推進機構)に2015年に認定された〉と説明、同市の里山・宮地岳(標高182㍍)自然歩道から津屋崎の街と津屋崎浜へ寄せる荒波を遮る岬「渡半島」を俯瞰した展望パノラマ写真や、「渡半島」・大峰山(標高114㍍)頂上の東郷公園から見た津屋崎浜と背後のクロマツ林が東西に帯状に伸びる津屋崎松原の写真を添えています。東郷公園からは、ユネスコの世界遺産に登録された「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産である玄界灘沖に浮かぶ「沖ノ島」も、天気に恵まれれば遠望できることも紹介。
さらに、調査経過として〈2013年6月6日に津屋崎浜にスナビキソウに群生地を見つけ、飛来した(アサギマダラ〉10頭(羽)を確認。2015年5月27日には(「海とまちなみの会」主催の)「津屋崎里歩きフットパス」ウオークで1頭が飛来し、取材した各系列テレビ局のニュースで放送された。2016年3月7日に(「海とまちなみの会」)会員2人が福津市本木(もとぎ)の山中でアサギマダラの幼虫が、つる性の植物・キジョランの葉の裏にいるのを見つけ、会員6人で現地調査した結果、幼虫を多数確認し、同月16日付読売新聞に掲載された。本木で生まれた幼虫がサナギから羽化して「津屋崎浜」へ飛来の可能性も否定できないとみて、継続調査を進めている〉と掲載。
また、春季に北方へ渡るアサギマダラの「津屋崎浜」での再捕獲例では、〈(近くに住む)宗俊頼子氏が2013年6月3日に捕獲したメスに「MG 上五島 5/11」の標識があり、野下広人氏が5月長崎県五島列島上五島の林道でマークし、東北東に154kmを23日間で移動したことがわかった〉などと紹介、「津屋崎浜」までの鉄道や車でのアクセス、宿泊出来る民宿の情報で結んでいます=写真③=。

写真③:Amazon.co.jpのホームページにアップされた『旅をするチョウ アサギマダラに会いに行こう!-ポイント案内1-』Kindle版紹介画面