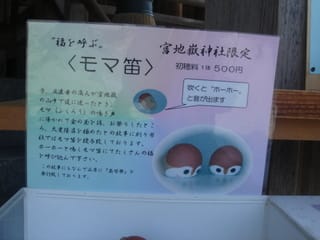=2010年1月26日、福津市天神町で撮影
・連載エッセー『一木一草』
第16回:2010.01.26
路地から海が見えるまちなみ
〈津屋崎千軒〉のまちなみの特徴について、「路地から海が見えるようになっていますね」と、津屋崎の外に住む人から教えられ、思わずうなずいたことがあります=写真①=。この特徴を指摘されたのは、福津市企画政策課が市まちおこしセンター「津屋崎千軒なごみ」の建設前に、センターの基本計画を検討したいと08年に開催したワークショップの折、アシスタント役をつとめた席で話された㈱醇建築まちづくり研究所(福岡市)所長の牧敦司さんです。
〈津屋崎千軒〉で江戸後期から戦前までに建てられた125軒の家(九州大学大学院芸術工学研究院・田上研究室発行『津屋崎千軒のマチとイエ』)の造りで目立つ特徴は、敷地の奥行きの長さのほか、隣の家とのすき間・「スアイ」=写真②=や、中庭=写真③=、土間の設置などが挙げられます。これらの特徴は、博多の町家と似か寄った点もありますが、「スアイ」の「路地から海が見えるようになっている」点が大きく異なります。まさに「海に拓けた港町」・〈津屋崎千軒〉を象徴する特徴と言えるでしょう。
 ">
">写真②:隣の家とのすき間・「スアイ」。家の壁は隣家との延焼を防ぐため、トタン張りが多い。
=福津市古小路で、2007年6月7日撮影
 ">
">写真③:床の間の奥側にある町家の坪庭
=福津市天神町の「上田製菓」で、2009年4月21日撮影
〈津屋崎千軒〉のまちなみは、江戸後期から明治初期にかけて完成したとみられています。「津屋崎漁港」東側の北の一区・北の二区は漁師町として、その東の新町区は漁師町から後に商人町として、天神町は職人町、その北の岡の二区と岡の三区は農民の町として発達。昭和42年に県道「渡(わたり)・津屋崎線」(海岸通り)が建設されて、海岸沿いに住宅が建ち、平成13年の「しおさい通り」建設でまちなみは二分されました。
また、〈津屋崎千軒〉の建物の高さでは、1階建て、2階建ての低層住宅がほとんどで、海岸沿いに3階建て以上の建物があります。建物の建設年代別では、明治から昭和初期に建てられた古い住宅が「しおさい通り」より西側の〈千軒通り〉沿いに多く見られます。
さて、“A Quaint Town”という〈古風な趣のある町〉を印象づけているのは、何でしょう? それは、「しおさい通り」より西側の〈千軒通り〉沿いに残る町家の古風な魅力に加え、「海が見える路地」があるまちなみの造りが、住んでいる人、訪れる人にも開放感を与えてくれているからではないでしょうか。
“A Quaint Town Tsuyazaki-Senngen”(古風な趣のある町 〈津屋崎千軒〉)
という〈まちなみ散策地図『津屋崎千軒そうつこう』英語・日本語併記版〉表面に載せたキャッチコピーが、歴史的なまちなみの良さをアピールできる名フレーズに思えてきました。












 ">
"> ">
">
 ">
">