
そんなわけで、下田市のはずれのホテルに泊まって昨夜はゆっくりと体をいたわりました。
朝一番で下田市の中心部へと向かい、まずは道の駅「開国下田みなと」に立ち寄って、ここで黒船仕立ての遊覧船で湾内クルーズ。
海の上から見ると、下田の港が地形の防波堤に囲まれて天然の良港であることがよくわかります。
また江戸時代は、江戸との交易をおこなう廻船の江戸往復に対して「入り鉄砲」、「出女等」のチェックため「船改番所」を置き、「陸の関所 箱根」に対して「海の関所 下田」と言われたのだとか。
米一つとっても、陸路を牛や馬で運ぶことを考えると、船による海上物流はずっと効率的で、なくてはならない輸送手段となっていたことがよくわかります。
続いては下田開国博物館へ行き、開国に関する情報や資料を見学してきました。

開国と言うと、ペリーによる黒船来航という記述からアメリカとの開国ばかりが話題になりますが、実はアメリカと日米和親条約を結んだすぐ翌年に、プチャーチンの働きによって日露和親条約が結ばれています。
しかも日米和親条約の条文のほとんどは、実はプチャーチンがかなり前から日本と条約締結に向けてやり取りをしていたものがそのまま使われているのだそうで、当時のロシアが日本との通商条約締結などになみなみならぬ意欲を持っていたことがうかがえます。
また、この日露和親条約には第二条において双方の領土のことが、「今より後、日本国と露西亜国との境、エトロフ島とウルップ島との間にあるべし。(中略)カラフト島に至りては、日本国と露西亜国の間において、界を分たず是迄仕来りの通りたるべし。」と初めて定められています。
今の(新暦の1855年)2月7日(旧暦では前年の安政元年12月21日)が「北方領土の日」とされているのは、この国境条項を含む条約が平和裏に調印された日として定められたのだそうです。関心を持ってみていると色々なことが分かってくるものです。
◆
しかし、この日露和親条約締結作業のさなかに、旧暦の嘉永7(1854)年11月4日の安政の大地震による津波が下田を襲い、下田は壊滅。停泊していたロシアの船ディアナ号も甚大な被害を受け航行不能になってしまいます。
修理のために西伊豆の戸田(へだ)へ移動中に、ディアナ号はあえなく沈没してしまいましたが、プチャーチンは代船の建造を幕府に願い出て幕府もこれを許可。
修理をするはずだった戸田の港に近在の船大工が集められて、日露共同で日本初の洋船の建造が行われました。
ここで貴重な経験を積んだ船大工は、後に同じ船を六艘建造したほか、長崎造船所や石川島造船所などで洋艦の造船に力を尽くし、その後の日本海軍の礎になっていったのです。
旅のお土産って、饅頭やお酒も良いけれど、こんなエピソードが生き生きと身近に感じられるのが良いと思うのです。
博物館を出たところに売っていたちょっとした冊子をやっぱり買ってしまうのですが、これが案外良い本で嬉しくなりました。

北海道民は忘れちゃならないロシアとの北方外交史にも下田は重要な役割を果たしています。
歴史の知識も良い旅の土産となりました。
「下田なんて何があるんですか?」と言われたけれど、旅は知らないことを知るところに宝があるのです。

【ペリー上陸の地】


















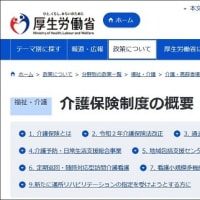







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます