「バカの壁」でお馴染みの、解剖学者にして昆虫学者であられる養老孟司さんですが、医療健康雑誌のロハス・メディカルという雑誌に教え子の医師中川恵一さんとの対談が載っていました。
日本人の宗教観、死生観、現代社会の潔癖性への違和感などについて縦横に論じられていて興味深い内容になっています。全文は長いので最後の部分をご紹介します。
---------- 【以下引用】 ----------
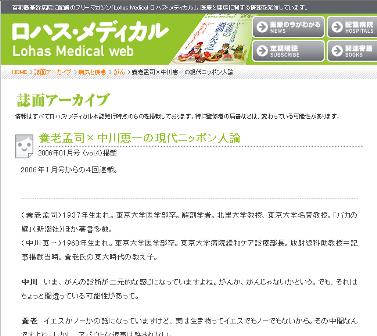
養老孟司×中川恵一の現代ニッポン人論
ロハスメディカル2006年01月号 (vol.4)掲載
http://lohasmedical.jp/archives/2006/01/post-35.php?page=all
・・・【前半省略】・・・
中川 僕らは患者さんと毎日話すんですが、いま、みなさんが心の問題に戻ってきているような感じがするんです。"諸行無常"の感覚は、日本人の集団的無意識には残っているんでしょうか。
養老 僕は当然あると思いますよ。早い話、「バカの壁」が売れたのも、あれの基礎にあるのが仏教ですからね。仏教思想は日本人に強い影響を与えたんですけども、日本人って面白くてね、それを本当に自分のものにしちゃうと、逆に仏教思想だとは思わないんですよ。
中川 なるほど、そうですね。
養老 平和と民主主義とか、個人とか、そういうものは要するに建前として置いておく。諸行無常は、日本人にとって実は当然のものなんです。日本人がよく「自分は無宗教です」って言うけれど、あれは典型的な「無の思想」ですよ。般若心経の二百何十字の中に、「無」って言う字がいくつあるか以前数えたことあるんですが、21ありました。一割が「無」ですよ(笑)。自分が「無宗教です」って言っているときに、実は仏教思想を根本においているって言うことに気づいてない。
中川 無宗教ではなく、無思想。
養老 そう。たとえば、イスラム教徒は豚を意識的に食わないでしょう。日本人は蛇を出されると、人間の食うものじゃないって言う。宗旨として蛇を食わないことにしているから、っていう風には言わないんですよ。だって、食おうと思ったら食えるんですから。そこが有思想と無思想の大きな違いで、それが理解されないのは私は当然だなという気がする。なぜなら、世界の大部分は有思想なんですから。
中川 もうひとつ、患者さんと接していて思うんですが、いまの日本人は「自分は死なない」と本当に考えていますね。でも、意識から死を排除している患者さんに対してがんの治療をするのは、実は非常に難しいんです。がんの場合、初回の治療がかなり大きなウエートを占めていて、おそらく95%以上がそこで決まります。でも、根治、非根治っていうのはしょせん相対的なものでしかないんですよね。
養老 人間の死亡率は100%なわけだから。
中川 そうなんです。ところが、そのことになかなか患者さんも医師も思い至らないので、亡くなる直前まで根治を目指すという不幸なことが行われているんですね。その根底には、やはり死生観というか、"そもそも俺は死ぬんだ"って思うことが欠けている気がするんです。特にゲーム世代なんかは、画面の中でしか死を見たことがないですよね。
養老 リセットだもんね。
中川 いま、人は病院でしか死にませんでしょ? そうすると、若い子は病院に来たがらない。場合によっては、自分が死ぬまで死体を見る機会が一度もないっていうことだって。
養老 病院は死ぬ人が行くところだっていうことになってしまう。そこに極めて新しい差別が生まれていると、僕は思っています。
養老 解剖をやっていてしみじみ思うのは、人間の体は、全体がぼろぼろになっていくのがいいんです。車だって、ガタガタになっているのに立派で強力なエンジンをつけたら全部分解しちゃうでしょう。
中川 がん治療もそうなんです。ぼろぼろになりつつある体なんだけれども、がんについては「取りたい、なくしたい」というアンバランスな部分があって。
養老 それは、いまの人の潔癖性と結びついているんですよね。
中川 ええ、そう思います。
養老 "正しくありたい"っていう気持ちは人間には必ずあるんですけど、正義っていうことを振りかざすと、必ずまずいことが起こってくる。悪に対する潔癖性がアメリカにはありますけど、あれが極めて迷惑でしょう。それと同じで、がん細胞があったらとにかく気に食わない。
中川 医者にいくら「放射線治療いいですよ、もっとやりましょう」と言っても全然変わりません。本当に変わりません。
養老 おっしゃる通りで(笑)。
中川 緩和医療もそうです。患者さんが痛くてつらそうだからモルヒネを飲んでもらいましょうと言っても、俺はいやだ、あんたが説得しろ、と言われてしまう。でも、モルヒネで痛みをとると、長生きできるのですけどね。実際には、患者さんは、モルヒネを飲むと寿命が縮むといやがります。ですから、患者さん側がやっぱり変わっていかないと。
養老 僕も全くそう思います。世の中の人の考えを変えなきゃ、学問は変わらない。
中川 潔癖で、体になんの問題も作りたくないという気持ちはわかるんですが、そうやって治療法を間違って選んだり、結局は不幸になるんですよね。でも、それを我々が説得しても、その人は無意識にその生き方を選んでしまっているわけで。集団的無意識というか、ムードっていうものを変えていくために、「人間は必ず死ぬんだ」ということをわかってもらうにはどうしたらいいんでしょうか。
養老 実は僕、それで人体の展示をやったんです。僕が「日本人って捨てたもんじゃないな」っていつも思うのは、ああいう展示をやると、世界に類を見ないほど人が入って、しかも黙って見ているんです。あれを外国でやると、コントラバーシャル(物議を醸すもの)だって言いますよね。でも、日本だとあまりそうはならない。
中川 死体に、個性や本人性を見ないということでしょうか。
養老 日本人が自然に親しむというのは、まさにそういうことだと僕は思っています。これだけ文明化しても、土に還るとか、自分が自然の一部であるということを、暗黙のうちに引きずってきた人たちじゃないかという気がする。つまり、あるところまでは田舎者だった。ところが、今は危ないなと思っています。それこそ、もっと白黒はっきりさせる、潔癖性を出す、と考える人が必ず出て来るなと思っておりますから。 (おわり)
---------- 【引用ここまで】 ----------
自分が死ぬということを想像して、自分を律した生活をする・・・。簡単に書けますが実践は難しそうです。
患者を個人ではなく、社会の一員として見る立場になると一人一人の生に対する執着が強すぎるように見えるのでしょうね。私としてはお迎えが来そうになったときには、若ければ運命に抵抗して、一定の年齢に達したらあまりじたばたしたくないものだ、と思うのですが・・・。
「人間は必ず死ぬ」ということは、突然理解や納得するようなことではなくて、長い時間をかけて少しずつ諦観、あきらめる気持ちを醸成することなのではないでしょうか。
そのために、社会的な装置として、仏壇や神棚、お寺や神社があり、それらに日々手を合わせたり畏敬を年を育てるということで心の中に安らぎが積み重なってゆくのではないかと思うのです。
経済的合理性や効率性では語れない、時間だけが育める大切な思いに心を寄せられるでしょうか。
今はこちらから家族みんなで一緒に見ているお仏壇は、いつか自分もそこからこちら側を見る窓なんですね。
日本人の宗教観、死生観、現代社会の潔癖性への違和感などについて縦横に論じられていて興味深い内容になっています。全文は長いので最後の部分をご紹介します。
---------- 【以下引用】 ----------
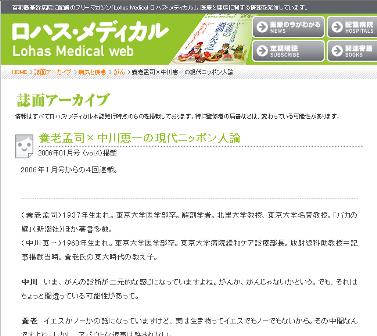
養老孟司×中川恵一の現代ニッポン人論
ロハスメディカル2006年01月号 (vol.4)掲載
http://lohasmedical.jp/archives/2006/01/post-35.php?page=all
・・・【前半省略】・・・
中川 僕らは患者さんと毎日話すんですが、いま、みなさんが心の問題に戻ってきているような感じがするんです。"諸行無常"の感覚は、日本人の集団的無意識には残っているんでしょうか。
養老 僕は当然あると思いますよ。早い話、「バカの壁」が売れたのも、あれの基礎にあるのが仏教ですからね。仏教思想は日本人に強い影響を与えたんですけども、日本人って面白くてね、それを本当に自分のものにしちゃうと、逆に仏教思想だとは思わないんですよ。
中川 なるほど、そうですね。
養老 平和と民主主義とか、個人とか、そういうものは要するに建前として置いておく。諸行無常は、日本人にとって実は当然のものなんです。日本人がよく「自分は無宗教です」って言うけれど、あれは典型的な「無の思想」ですよ。般若心経の二百何十字の中に、「無」って言う字がいくつあるか以前数えたことあるんですが、21ありました。一割が「無」ですよ(笑)。自分が「無宗教です」って言っているときに、実は仏教思想を根本においているって言うことに気づいてない。
中川 無宗教ではなく、無思想。
養老 そう。たとえば、イスラム教徒は豚を意識的に食わないでしょう。日本人は蛇を出されると、人間の食うものじゃないって言う。宗旨として蛇を食わないことにしているから、っていう風には言わないんですよ。だって、食おうと思ったら食えるんですから。そこが有思想と無思想の大きな違いで、それが理解されないのは私は当然だなという気がする。なぜなら、世界の大部分は有思想なんですから。
中川 もうひとつ、患者さんと接していて思うんですが、いまの日本人は「自分は死なない」と本当に考えていますね。でも、意識から死を排除している患者さんに対してがんの治療をするのは、実は非常に難しいんです。がんの場合、初回の治療がかなり大きなウエートを占めていて、おそらく95%以上がそこで決まります。でも、根治、非根治っていうのはしょせん相対的なものでしかないんですよね。
養老 人間の死亡率は100%なわけだから。
中川 そうなんです。ところが、そのことになかなか患者さんも医師も思い至らないので、亡くなる直前まで根治を目指すという不幸なことが行われているんですね。その根底には、やはり死生観というか、"そもそも俺は死ぬんだ"って思うことが欠けている気がするんです。特にゲーム世代なんかは、画面の中でしか死を見たことがないですよね。
養老 リセットだもんね。
中川 いま、人は病院でしか死にませんでしょ? そうすると、若い子は病院に来たがらない。場合によっては、自分が死ぬまで死体を見る機会が一度もないっていうことだって。
養老 病院は死ぬ人が行くところだっていうことになってしまう。そこに極めて新しい差別が生まれていると、僕は思っています。
養老 解剖をやっていてしみじみ思うのは、人間の体は、全体がぼろぼろになっていくのがいいんです。車だって、ガタガタになっているのに立派で強力なエンジンをつけたら全部分解しちゃうでしょう。
中川 がん治療もそうなんです。ぼろぼろになりつつある体なんだけれども、がんについては「取りたい、なくしたい」というアンバランスな部分があって。
養老 それは、いまの人の潔癖性と結びついているんですよね。
中川 ええ、そう思います。
養老 "正しくありたい"っていう気持ちは人間には必ずあるんですけど、正義っていうことを振りかざすと、必ずまずいことが起こってくる。悪に対する潔癖性がアメリカにはありますけど、あれが極めて迷惑でしょう。それと同じで、がん細胞があったらとにかく気に食わない。
中川 医者にいくら「放射線治療いいですよ、もっとやりましょう」と言っても全然変わりません。本当に変わりません。
養老 おっしゃる通りで(笑)。
中川 緩和医療もそうです。患者さんが痛くてつらそうだからモルヒネを飲んでもらいましょうと言っても、俺はいやだ、あんたが説得しろ、と言われてしまう。でも、モルヒネで痛みをとると、長生きできるのですけどね。実際には、患者さんは、モルヒネを飲むと寿命が縮むといやがります。ですから、患者さん側がやっぱり変わっていかないと。
養老 僕も全くそう思います。世の中の人の考えを変えなきゃ、学問は変わらない。
中川 潔癖で、体になんの問題も作りたくないという気持ちはわかるんですが、そうやって治療法を間違って選んだり、結局は不幸になるんですよね。でも、それを我々が説得しても、その人は無意識にその生き方を選んでしまっているわけで。集団的無意識というか、ムードっていうものを変えていくために、「人間は必ず死ぬんだ」ということをわかってもらうにはどうしたらいいんでしょうか。
養老 実は僕、それで人体の展示をやったんです。僕が「日本人って捨てたもんじゃないな」っていつも思うのは、ああいう展示をやると、世界に類を見ないほど人が入って、しかも黙って見ているんです。あれを外国でやると、コントラバーシャル(物議を醸すもの)だって言いますよね。でも、日本だとあまりそうはならない。
中川 死体に、個性や本人性を見ないということでしょうか。
養老 日本人が自然に親しむというのは、まさにそういうことだと僕は思っています。これだけ文明化しても、土に還るとか、自分が自然の一部であるということを、暗黙のうちに引きずってきた人たちじゃないかという気がする。つまり、あるところまでは田舎者だった。ところが、今は危ないなと思っています。それこそ、もっと白黒はっきりさせる、潔癖性を出す、と考える人が必ず出て来るなと思っておりますから。 (おわり)
---------- 【引用ここまで】 ----------
自分が死ぬということを想像して、自分を律した生活をする・・・。簡単に書けますが実践は難しそうです。
患者を個人ではなく、社会の一員として見る立場になると一人一人の生に対する執着が強すぎるように見えるのでしょうね。私としてはお迎えが来そうになったときには、若ければ運命に抵抗して、一定の年齢に達したらあまりじたばたしたくないものだ、と思うのですが・・・。
「人間は必ず死ぬ」ということは、突然理解や納得するようなことではなくて、長い時間をかけて少しずつ諦観、あきらめる気持ちを醸成することなのではないでしょうか。
そのために、社会的な装置として、仏壇や神棚、お寺や神社があり、それらに日々手を合わせたり畏敬を年を育てるということで心の中に安らぎが積み重なってゆくのではないかと思うのです。
経済的合理性や効率性では語れない、時間だけが育める大切な思いに心を寄せられるでしょうか。
今はこちらから家族みんなで一緒に見ているお仏壇は、いつか自分もそこからこちら側を見る窓なんですね。















