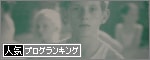作品情報⇒https://movie.walkerplus.com/mv12146/







以下、TSUTAYAのHPよりあらすじのコピペです。
=====ここから。
外界と遮断される孤島の古城に、再婚した若い妻・テレサと住んでいた初老男・ジョージ。ある日、島に強盗をしくじって負傷したふたり組の悪党・リチャードとアルバートが逃げて来て…。
=====ここまで。
初老男・ジョージをドナルド・プレザンス、若い妻・テレサをフランソワーズ・ドルレアック、悪党・リチャードをライオネル・スタンダーと個性派がズラリ、しかも監督はポランスキー。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆
不覚にも、ドナルド・プレザンスがポランスキーの映画に出ていたとは知りませんでした。しかもドルレアックと夫婦役とな?? とにかく、ドナルド・プレザンス+フランソワーズ・ドルレアック+ポランスキーの映画なんて見ないわけにはいかんでしょう、、、と、見てみました。
◆アンバランスな夫婦と闖入者
冒頭から、なんかもう色々とヘンで、一体何が起きるのやら、、、、と興味津々になる。
ゼンゼン雰囲気も展開も違うけれども、見ていてハネケの『ファニーゲーム』を思い出してしまっていた。いや、ジャンルとしては同じでしょ。突然、見ず知らずの怪しい男たちに侵入されて生活をメチャメチャにされる、、、っていう。ただ、本作は、ゲームではなくて、あくまでもリアルという話で。しかも、本作はサスペンスにカテゴライズされているけど、見終わってみれば、ブラックコメディでしょ、これ。
プレザンスとドルレアックという、実に巧みな配役で、このカップリングの違和感が十分出ているのがミソ。実際、ドルレアック演ずるテレサは、近所の青年とヨロシクやっている。そしてまた、夫であるジョージにも破天荒な妻そのまんまで、ジョージにネグリジェ(死語?)を着せた上に口紅まで塗るというおふざけをして、さらにその異様な姿になった夫を見てゲラゲラ笑っている。これだけで、この夫婦の関係性が何となく分かってしまう。
そこへ闖入してきたのがリチャードという、これまたアクの強いキャラ。乱暴者なんだか、意外に物わかりが良いのか、イマイチよく分からん。
勝手に人んチの電話を使って首領にSOSの連絡をした後、電話線をぶった切ったかと思うと、テレサの浮気現場をバッチリ目撃していたにもかかわらず、夫に薄笑いを浮かべながらも「お前の女房、浮気してるゼ」などという野暮なことはチクったりしない。
かと思うと、大怪我して動かせないからってんで相棒を車に残したまま、夫婦の城にある鶏小屋で堂々と昼寝なんぞしてしまう。その間に、車を置いてあった所は潮が満ちてきて、相棒が溺れそうになるとか、もう訳分からん展開、、、。その後、思い出したリチャードが、夫婦を引き連れて助けに行くんだけどサ。
ドヌーヴ主演の『反撥』でもそうだけど、こういう訳分からん不穏な感じで話がどんどん進んでいくっていうの、ポランスキーは天才的に上手いなぁ~と改めて感動。まあ、本作の方が『反撥』よりは大分笑えるけど。
結局、救出した相棒は死んでしまうし、死んだら死んだで、リチャードは夫に墓穴を掘らせるとか。首領が差し向けた助っ人が来たかと、白い車がこちらへ向かってくるのを見てぬか喜びするリチャードだが、それは助っ人ではなく夫の友人家族だったとか。とにかく、あれやこれやと話が進む。
で、結局どうなるか、、、。まぁ、それは敢えてココには書かないけれど、ただでさえ危うい夫婦が、ただで済むとは到底思えないわけで、その通りの展開になるのであります。
◆ポランスキーの映画
この映画が制作されたのは1966年。ポランスキーは、この前年に『反撥』を撮っている。コメディタッチとシリアスとで、映画としての趣は違うけれど、この2作に限らず初期~中期のポランスキーの映画って不条理モノが多い気がする。
『反撥』にしても、(モノクロだからかも知れないが)不条理モノのポランスキー映画は、何というか、、、何かに追われているような、不安げである。
本作も、テレサの視点から見ればそうでもないが、夫・ジョージから見れば不安だらけだ。終盤に明らかになるが、ジョージはテレサが近所の若者と浮気していることは知っていて、それだけでなく、途中でやって来た友人家族と一緒に居た中年の色男とやたら親しげにするなど、ジョージにしてみれば、テレサは一番痛いところを突いてくる。この古城を全財産はたいて手に入れたのと同じくらい、この若くて美しい妻はシンボリックな存在なはず。しかも、実はジョージは前妻に逃げられているということも判明し、また同じ轍を踏むことになるのではないかという不安が、ジョージには常にある。
そして、それがポランスキー映画に通底するものであるということ。この人は、常に不安を描いているのだ。『ローズマリーの赤ちゃん』だってそう。『水の中のナイフ』だって、夫婦のバカンスに突然若い男が闖入してくる話で、夫婦のバランスが崩れていく。夫にとっては不安でしかない。
こういう作風を、彼の生い立ちに見出す評者も多い。確かに、それはあるだろうなぁ、、、と思う。でも、それを確実に映像化してしまうことができる、ってのが凄いなぁ、、、と感心させられる。しかも、前面に押し出すのではなく、何となく不安げ、、、という極めて曖昧だけれども確実にじわりと感じる、、、という演出。不安と笑いってのは、実は相性が良いのだと、本作などを見るとよく分かる。
◆その他もろもろ
とにかく、ドナルド・プレザンスが素晴らしい。やっぱり、この人はすごい俳優だ。情けない男を、実に巧みに演じている。その風貌から、どうしたって、ヒーローではないが、一筋縄ではいかない悪役や、ジョージみたいなワケありの劣等感に苛まれた男は、実にハマる。
ドルレアックは、やはり美しい。この翌年に亡くなるのかと思うと、見ていて複雑な気分になる。ぶっ飛んだ若妻を、奔放に演じているように見えるが、きっとポランスキーの計算された演出なんだろう。
闖入者のリチャードを演じたライオネル・スタンダーも実にイイ味出している。声がもの凄いハスキーで、それがイイ。夫の友人家族がやって来たときは、夫婦の下男をやむなく演じることになるのだが、およそ下男とは思えない風貌と粗野な言動で、実に笑える。
ラストシーン、プレザンス演ずるジョージが、しょんぼりと膝を抱えて体育座りしている図が、何とも寂しく哀しい。しかも、ここで口にする女性の名前は、テレサではないのだ。嗚呼、、、。
ポランスキーの人間不信が現れた映画かも。