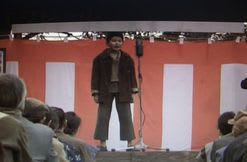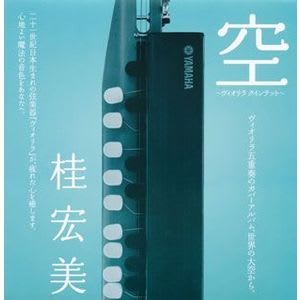今夜もまもなく10時から児童養護施設を舞台にしたテレビドラマ『明日、ママがいない』が始まります。かなり反対意見が強くスポンサーが次々に降板して、“明日、スポンサーがいない”状態だといいます。
私のところにも、放送中止を求める署名依頼のメールが届いています。
1話、2話を見ました。結論は放送中止にするほどのものではないと感じました。したがって中止を求める署名には賛同しません。
物語はフィクションです。
養子縁組を前にした子供たちをペットショップの犬にたとえ口汚くののしる場面がありますが、それに対して子供たちは反発しているし時に逆襲の態度をとることもあります。なんと言う酷い会話だろうとあきれ、そこで見るのを止める人もいるでしょう。しかし最後まで追っていくと作者の想いが伝わってきます。施設職員のセリフは、たしかにきわどい。かつて似た感じのドラマ『家なき子』の中で「同情するなら金をくれ!」というセリフを思い起こします。実際、現実はきれいごとばかりではないわけですし「金」も必要なわけです。現実の汚さをこうして表現する自由はあって良いと思います。
福祉施設で真剣に業務に励まれている職員の方々には、誤解を招くようで腹立たしいものを感じるかもしれません。しかし子を捨てる親が後を絶たない、それに対して福祉予算は少なく職員の待遇も環境も十分でないことも事実です。日本テレビは『ダンダリン』では日頃話題にならない労基署を取り上げました。『明日、ママがいない』では児童養護施設にスポットです。日本テレビにはスポンサーが離れても最終話まで、自信を持って放送されることを願います。
 |
子どもが語る施設の暮らし |
| 『子どもが語る施設の暮らし』編集委員会 | |
| 明石書店 |