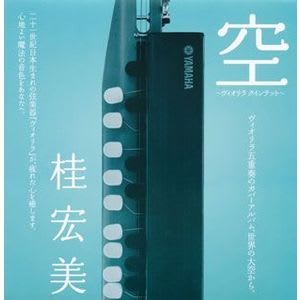作品の一つひとつがまず、大きのに驚きました。描かれた絵は、その大きさが表すように見る者に強い衝撃を与えました。
サラリーマンから画家に
会社退職後から画家に転身した面高春海さん。8月30日31日に群馬県大泉町・文化むらで「面高春海 作品展&トーク」を開きました。会場には面高さんが講師を勤めた「東京三洋女子高等学院」のOGの方々をはじめ旧東京三洋電機の関係者も多数訪れました。
ソ連軍の侵攻で悪夢が
面高さんは小学校3年まで満州国(現中国東北部)がふるさと。五族協和(日、朝、漢、満、蒙人の王道楽土をめざした満州国建国理念)のもと満州の地で平和に過ごしていましたが、ソ連軍が中立条約を破って侵攻してからすべてが一変した。面高少年は満州北部から命からがらに逃走してきた悲惨な日本人開拓団の人たち(黒い集団)がやってきたのを見て驚いた。作品の一つにこの時の様子がしっかり描かれている=写真下。

整然としていた日本人避難民
面高家は食堂を営んでいた。お母さんが黒い集団の人たちが差し出す空き缶にご飯やおかずを入れてあげた。「頑張って。元気を出してね」とお母さんも黒い集団の人たちも、ともに泣きながら。。
「北満州からの黒い集団は、日本人の整然とした態度が海外から高評価を受けた3.11東日本被災者と同じように、いがみ合ったり物を奪い合うようなことはなかった」(面高さん談)。
いつの時代も民衆は国策に翻弄され
危機的事態が迫っていることを知る関東軍(日本軍)が血相を変えて「ここから早く逃げろ!」といって食料品の入った袋を面高少年に投げて寄こした。これを聞いた時、福島の飯館村付近で、異常に高い放射汚染を知る白い防護服集団が、まだ事態の深刻さを理解していない住民達に対して「早くここから離れろ!」と言ったこととダブってしまった。「原発」も「移民」も国策。その国策が破綻した時は常に犠牲となるのは民衆、民間人・・
シベリア行逃れたご来場者
本文最上の写真の絵は2009年作『世界のどこかで(生きる)』。赤い矢印(白シャツ姿)の座っている子供が作者、面高少年。路上でお菓子を売っていたが、おつりの用意がなく叱られたという。絵の上側には列車が走っている。貨車に日本兵を詰め込みシベリアに連行するソ連の軍用車両だ。大泉町文化むらでの展示初日、見学者のご老人が、この絵を見て「自分はシベリア行きのこの汽車から軍服のまま命がけで逃げて乗らなかった」と話されたといいます。
トークタイムでは、説明される面高さんが、悲しい過酷な想いに堪え切れずおもわず言葉が詰まることが・・・。
面高さんはこの展示会を「8月」に開催することの意義を強調されている。終戦・敗戦の8月の内に。当広場も8月の意義に合わせてアップしました。
にほんブログ村 雑感
【面高春海(おもだか はるみ】(昭和11年(1936)- )満州国大連生まれ。東京三洋電機入社、同社を57歳で退職。以後画家の道に。独立美術協会 所属