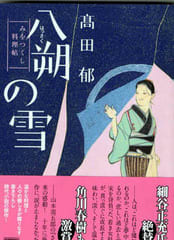主人公の与平は、薬種屋「仁寿堂」十代目の主。店は今や、三人の息子たちに譲って、晴れて隠居の身。これまで働き詰めに働いたのだ、これからは悠々自適に・・・・いくはずが、俳句の会も物見遊山もいまひとつ楽しめぬ。
与平はそこでただ引きこもってはいなかった。ある妙案が思いつくのである。
世の中には、自分の話を誰かに聞いてもらいたい人が山とある。話せば気が楽になることもあろう、だったら自分がその役を買って出ればいいじゃないか。
彼は早速、両国広小路の仁寿堂裏手に机を出す。看板の「お話、聞きます」の文字に、通りを行く人はいぶかしげな目を向ける。
宇江佐真理著「聞き屋与平 江戸夜咄草」集英社文庫
昨今、人の話を聞かない人が多い(自分を含めて・・・)。そのあたりひたすら人の話を聞く与平という人物の懐の深さに感心する。が、与平は聖人ではない。家族のことに腐心し、暗い過去を背負って生きている普通の人間。腹も立てるし、話の内容に愛想尽かしもする。
それだけに臨場感がある。与平のそばで一緒になって心配したり喜んだりしている気分になる。自分の悩みや悲しみは、結局、人には分かってもらえない。だからと言ってひがんだりしてはいけませんよ。誰でもが、重い過去を引きずって生きているんですから。
江戸の四季、折々の行事を取り混ぜて描く著者の手腕はたいしたものだ。
この本の巻末で、木内 昇氏は「聞き屋与平」をうまく解説している。
家族遠く離れ、江戸で一人働く少年にとって、与平の言葉はどれほど支えになったろう。
「他人をねたんで大人になったとしたら、ろくな男にならない。
その前に、少しだけ情を掛けてやれば、とげとげした心は和むだろう」
かつての日本人はきっと、こんな風に謙虚で、相手を慮(おもんばか)ることが得意な人たちだったのだ、と改めて気付かされる。いや「かつて」なんて言葉で切り離してはいけない。現代に生きる私だってやっぱり、悩みを抱かえたときには、機微を心得た与平の「何でもお聞きいたします」と言うひとことを聞きたい。「あなたなら大丈夫!頑張って、夢はきっと叶う!」と畳み掛けられるより、遥かに。