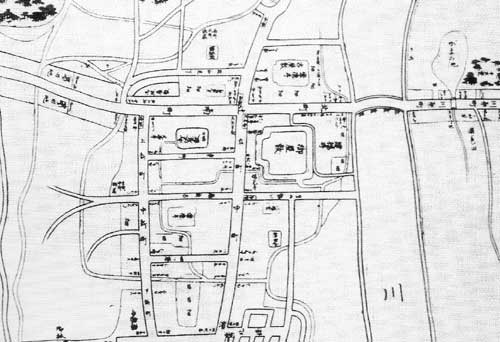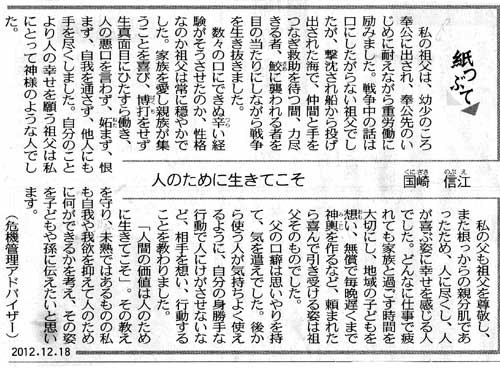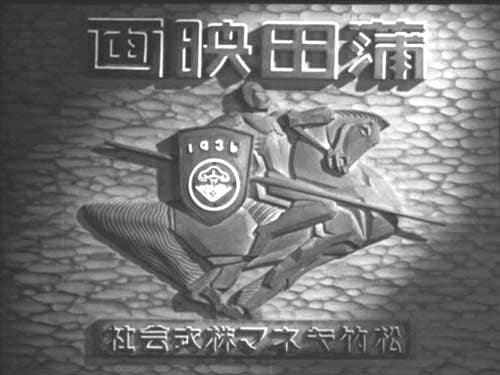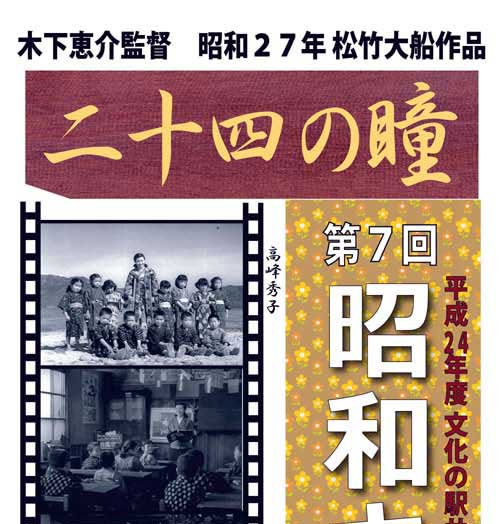清水宏監督の“有りがたうさん”は、昭和11年に公開されました。今から76年前です。昭和11年は、2・26や阿部定事件が起きた年でもあり、昭和不況の中、太平洋戦争が影を落とし始めたころです。
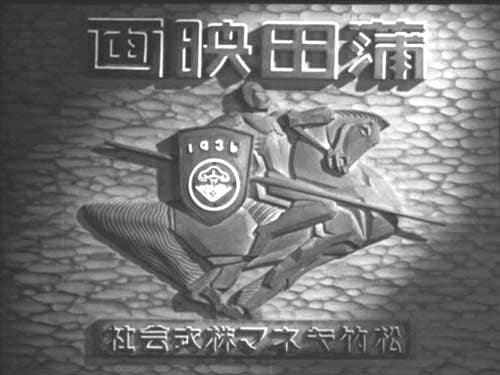

伊豆半島の下田と三島間の山道を路線バスが砂埃を上げて行きます。清水監督は、2年ほど前に公開のアメリカ映画、フランク・キャプラ監督による「或る夜の出来事」にヒントを得たといわれています。クラーク・ゲーブルとクローデット・コルベールによるコミカルでテンポの良い映画でした。
清水宏は日本の自然を大切にする監督で、この映画はオールロケーションで作られました。当時としては画期的なロードムービーだったと言えます。
自然の中に俳優をなじませることを流儀としていた監督は、役者に熱演は求めなかった。工夫された演技はむしろ不自然だと。そのため脚本はあまり綿密に書かれず、現場で即興的な演出をしていたそうです。
ある女優が自分の演じる役柄について研究し数パターンの感情表現を用意して、現場で清水宏に見せたそうです。すると清水宏は「よく勉強してきたね」と言って、「じゃあこのシーンは気持ちナシで」と言い放った。いかにも清水宏らしいエピソードです。
道をよけてくれる人々(時にニワトリにまでに!)に、「ありがとう~、ありがとう~」とイケメンの運転手(上原謙)が声をかける。だからその運転手のことを人々は親しみと尊敬をこめて「有がたうさん」と呼びました。個性豊かな乗客たちが次々と乗っては降り、とんでもなくゆったりとした口調でセリフのやり取りがなされていきます。どうやらこの言い回しは、作為的だったようです。


女郎屋へ身売りする少女と母親に投げかけられる言葉。「男の子なら乞食になるかもしれないが、女の子なら身売りしてお金になるから幸せだよ」しかし、そこに悲壮感は漂わない。私たちはその場から距離をおいて見ていられるからでしょうか。


道行くチマチョゴリ風の衣装を着た大勢の男女をバスが追い抜いて行きます。その中の一人の女性が、休憩しているバスに近づき、ありがとうさんに声をかける。どうやら馴染みらしい彼女は道路工事に従事しており、ここの工事が終わると、信州の方の現場に移動すると、別れを告げます。「自分たちは、道路が完成しても、そこを通ることはない。一度は日本の着物を着て、ありがとうさんのバスに乗ってみたかった」と話します。

そして今日も、ひとびとの「暮らし」と「こころ」を縫うようにして走るボンネットバス。“ありがとうさん”は永遠に当事者になれない傍観者です。不思議と彼だけ生活感が漂わないのはそのせいでしょうか。あくまでも風景の一部としてすれ違っていく人々。この作品を観ながら、想像をたくましくして「お幸せに」とひとりごちたとき、ふとどこかで「ありがとぉ~う」の声が聞こえた気がしました。
昭和11年公開 清水宏監督作品「有りがたうさん」 貴重なフィルムに映し出される 明治・大正・昭和の風景と人情!ご期待ください!