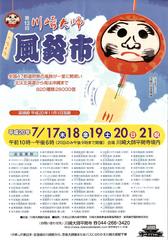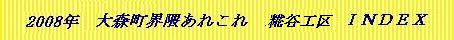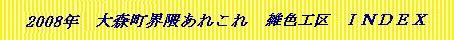kan-haru blog 2008
< 総合INDEX へ
雑色駅付近の高架化工事は3か所に分担して工事が行われており、その1つは駅より北方にある京急蒲田第9踏切から南へ(地図再掲参照)と1・2号(北)工事機により高架橋建設が進められ、その2は駅より南方にある雑色第4踏切南側から北へ(地図再掲参照)と1・2号(南)工事機により高架橋架設が進められ、3か所目は同第4踏切南側から南の六郷土手駅までの傾斜高架橋部の高架化の工事であり、それぞれの進捗状況を7月29日に見てきました。
1号(北)工事機の基礎杭打設工事
1号(北)工事機による雑色駅ホーム上の基礎杭打設は、前回の雑色駅付近(第5回)の記述時からは工事機が南方に移設して工事が行われていました。工事機の移動は、工事機の下りホーム側の南脚柱傍の仮ホーム屋根の棒状柱が、移動前の3本柱から1本柱に減った位置(右拡大写真参照)まで移設されました。

移設の1号(北)工事機(左:下りホーム上から見た移設工事機、中:京急蒲田第12踏切見た移設工事機、右:上りホーム上から見た移設工事機)
基礎杭打設工事は、工事機の南側窓から行われホーム上には工事囲いシート(左・中写真参照)で覆ってあります。また、上りホーム地下通路階段は、第4回で掲載の2期工事により川崎側の階段が閉鎖され、京急蒲田側階段の通路幅が狭められていました。

上りホームの基礎杭打設工事(左:工事囲いシートで覆って行われている基礎杭打設、中:基礎杭打設工事囲いと地下通路階段、右:幅が狭められた地下通路階段)
2号(北)工事機の高架橋築造
2号(北)工事機は、京急蒲田第12踏切直前まで移動して高架橋の建設が進められていました。

高架橋建設の2号(北)工事機(左・中:京急蒲田第12踏切直前まで移動の2号工事機、右:築造中の高架橋)
1号(南)工事機の基礎杭打設工事
雑色駅から南方の1号(南)工事機は、雑色駅付近(第5回)の記述時からは雑色第2踏切北側にある献血供給事業団 大田出張所ビルの北壁まで移動して基礎杭打設工事を行っていました。

献血供給事業団横で基礎杭工事の1号(南)工事機(右:雑色第2踏切から見る工事機)
2号(南)工事機の高架橋築造
2号(南)工事機は、雑色第2踏切南に建築中のビル南まで移設して高架橋の築造を行っていました。

雑色第2踏切に近ずいて高架橋建設中の2号(南)工事機(左・中:雑色第2踏切から見た工事機、右:築造中の高架橋)
六郷土手駅傾斜高架橋部の高架化工事
雑色第4踏切南に接して建てられている高架橋は平地部の最南端にあり、それより南側の第1京浜国道が参道の寶珠院付近から、京急本線の線路が傾斜高架橋を上り六郷土手駅へ達します。この傾斜高架橋を高架化工事を行うためには、大森町第2工区平和島の傾斜高架橋と同様に、上り線の仮線路を設ける工事を最初に行う必要があります。雑色第4踏切付近の南端高架橋には、この仮線の分岐部が設けてあります。

雑色第4踏南の仮線分岐部のある高架橋(左・中:平地最南端の高架橋、右:交通止めにしての高架化工事)
これより南側の線路西側の道路を交通止にして、傾斜高架橋部高架化の仮線路敷設準備の工事が進められていました。

傾斜高架橋部高架化の仮線路敷設準備の工事(右写真拡大)
< 総合INDEX へ
・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(7月分掲載Indexへ)
・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次 2008年後期版、2008年前期版、2006・2007年版 へ
・サブ・カテゴリー別Index 京浜急行の高架化 大森町付近工区、梅屋敷付近工区、京急蒲田付近工区、雑色付近工区、糀谷付近工区 へ
<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 京急蒲田駅付近(11回) へ
次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 大森町駅付近(第21回その1-1) へ>
< 総合INDEX へ
雑色駅付近の高架化工事は3か所に分担して工事が行われており、その1つは駅より北方にある京急蒲田第9踏切から南へ(地図再掲参照)と1・2号(北)工事機により高架橋建設が進められ、その2は駅より南方にある雑色第4踏切南側から北へ(地図再掲参照)と1・2号(南)工事機により高架橋架設が進められ、3か所目は同第4踏切南側から南の六郷土手駅までの傾斜高架橋部の高架化の工事であり、それぞれの進捗状況を7月29日に見てきました。
1号(北)工事機の基礎杭打設工事
1号(北)工事機による雑色駅ホーム上の基礎杭打設は、前回の雑色駅付近(第5回)の記述時からは工事機が南方に移設して工事が行われていました。工事機の移動は、工事機の下りホーム側の南脚柱傍の仮ホーム屋根の棒状柱が、移動前の3本柱から1本柱に減った位置(右拡大写真参照)まで移設されました。

移設の1号(北)工事機(左:下りホーム上から見た移設工事機、中:京急蒲田第12踏切見た移設工事機、右:上りホーム上から見た移設工事機)
基礎杭打設工事は、工事機の南側窓から行われホーム上には工事囲いシート(左・中写真参照)で覆ってあります。また、上りホーム地下通路階段は、第4回で掲載の2期工事により川崎側の階段が閉鎖され、京急蒲田側階段の通路幅が狭められていました。

上りホームの基礎杭打設工事(左:工事囲いシートで覆って行われている基礎杭打設、中:基礎杭打設工事囲いと地下通路階段、右:幅が狭められた地下通路階段)
2号(北)工事機の高架橋築造
2号(北)工事機は、京急蒲田第12踏切直前まで移動して高架橋の建設が進められていました。

高架橋建設の2号(北)工事機(左・中:京急蒲田第12踏切直前まで移動の2号工事機、右:築造中の高架橋)
1号(南)工事機の基礎杭打設工事
雑色駅から南方の1号(南)工事機は、雑色駅付近(第5回)の記述時からは雑色第2踏切北側にある献血供給事業団 大田出張所ビルの北壁まで移動して基礎杭打設工事を行っていました。

献血供給事業団横で基礎杭工事の1号(南)工事機(右:雑色第2踏切から見る工事機)
2号(南)工事機の高架橋築造
2号(南)工事機は、雑色第2踏切南に建築中のビル南まで移設して高架橋の築造を行っていました。

雑色第2踏切に近ずいて高架橋建設中の2号(南)工事機(左・中:雑色第2踏切から見た工事機、右:築造中の高架橋)
六郷土手駅傾斜高架橋部の高架化工事
雑色第4踏切南に接して建てられている高架橋は平地部の最南端にあり、それより南側の第1京浜国道が参道の寶珠院付近から、京急本線の線路が傾斜高架橋を上り六郷土手駅へ達します。この傾斜高架橋を高架化工事を行うためには、大森町第2工区平和島の傾斜高架橋と同様に、上り線の仮線路を設ける工事を最初に行う必要があります。雑色第4踏切付近の南端高架橋には、この仮線の分岐部が設けてあります。

雑色第4踏南の仮線分岐部のある高架橋(左・中:平地最南端の高架橋、右:交通止めにしての高架化工事)
これより南側の線路西側の道路を交通止にして、傾斜高架橋部高架化の仮線路敷設準備の工事が進められていました。

傾斜高架橋部高架化の仮線路敷設準備の工事(右写真拡大)
< 総合INDEX へ
・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(7月分掲載Indexへ)
・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次 2008年後期版、2008年前期版、2006・2007年版 へ
・サブ・カテゴリー別Index 京浜急行の高架化 大森町付近工区、梅屋敷付近工区、京急蒲田付近工区、雑色付近工区、糀谷付近工区 へ
<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 京急蒲田駅付近(11回) へ
次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 大森町駅付近(第21回その1-1) へ>