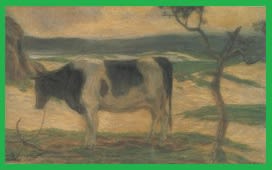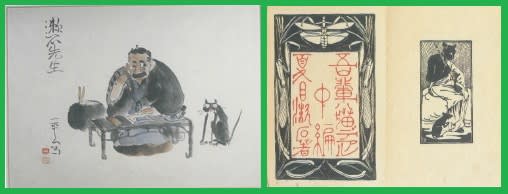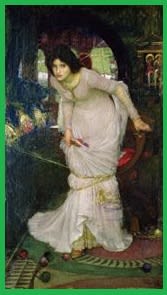< 総合INDEX へ
昔を追い上野の山の散策
東京藝術大学大学美術館で、夏目漱石の文化と美術に関する展示会を観賞したので、往時の寛永寺跡の面影を忍んで、上野の山を散策し130周年を迎えた上野駅を見て帰宅しました。
かっての寛永寺は約30万5千坪の寺地を有しており、寛永時代に現東京国立博物館敷地に寛永寺本坊が建立され、元禄時代に今の上野公園大噴水のあるあたりに本堂の根本中堂が完成し、清水観音堂、不忍池辯天堂、 五重塔、開山堂、大仏殿などの伽藍が競い立っていました。上野の山は、幕末の慶応4年に彰義隊の戦の戦場となり、根本中堂をはじめ主要な堂宇は焼失し寛永寺は、明治政府によって境内地が没収されました(その1参照)。


上野戦争(左:上野戦跡 平凡社「鹿鳴館秘蔵写真帖」よりWikipedia Link、右:上野戦争の図(本能寺合戦之図) 歌川芳盛 明治2年Wikipedia Link)
・上野恩賜公園の変遷
明治政府によって没収され寛永寺の境内地の変遷を追うと、1873年(明治6年)に太政官布達で、上野の山一帯を日本最初の公園に指定され、1876年(明治9年)に東京府から内務省博物局に移管され、1882年(明治15年)には上野動物園が開園しました。1890年(明治23年)にはうえの公園が宮内庁に移管され、1923年(大正13年) 東京市に下賜され上野恩賜公園となりました。

上野恩賜公園散策地図
・上野の森を歩く
東京藝術大学大学美術館を後に、都道452号を東京国立博物館正門前に戻ると、平成24年に道路南側に接した竹の台広場には、東京都が新名所の噴水を完成させました。竹の台の名前は、噴水のあるあたりに寛永寺の根本中堂が建立されており、正面の両側には、竹の台(うてな)が配置されていたことにより竹の台と称しています。

上野恩賜公園噴水(㈱ウォーターデザインLink)
噴水のところで右折し上野の森を縦断して進むと、右側に花園稲荷神社(台東区上野公園4-17)の鳥居が見えてきます。創祀の年月は不祥で、1654年(承応3年)に天海大僧正の弟子、本覺院の住僧、晃海僧正が廃絶していたお社を再建し上野の山の守護神とし倉稲魂命を祀られています。幕末には彰義隊の戦では激戦地となり、1873年(明治6年)に再興され、花園稲荷と改名し社殿も南面にて造営され神苑も一新されました。花園稲荷神社に接して五條天神社があり、創建は伝景行天皇朝の時期で、幾度か社地を転々とした後、1928年(昭和3年)に現在地に遷座され、祭神は大己貴命、少彦名命、菅原道真公が祀られています。(「風景・風物詩 初詣風物詩 上野五條天神社、不忍池弁天堂と飯田橋東京大神宮」参照)

花園稲荷神社と五條天神社(左:花園稲荷神社0823、右:五條天神社20090104)
神社を後に進むと、左方に天海僧正毛髪塔が見えてきます。天海大僧正は、1643年(寛永20年)10月2日に百八歳で示寂(じじゃく)され、諡号(しごう)は慈眼大師と称します。墓所は日光山輪王寺に造られ、寛永寺には弟子の晃海(こうかい)が供養塔を建立し、後に伝来していた毛髪を納めた宝塔を建立され、都指定旧跡です。

天海僧正毛髪塔(0823)
宝塔を先に進むと、博士王仁碑が二基建立されています。王仁博士は「古事記」によると、古墳時代の前半に渡来して、「論語」・「千字文」を伝えた学者であり、後に帰化したとされており、その子孫は文筆をもって朝廷に仕えたといわれます。「博士王仁碑」の二基は、1940年(昭和15年)と1941年(昭和16年)に建立されました。

博士王仁碑(0823)
・清水観音堂
天海僧正は上野の山に寛永寺を建立時に、天台宗の最高権威だった比叡山延暦寺をモデルとしました。
清水観音堂(国指定重要文化財)は、1631 年(寛永8年)に上野の山の中ほどの摺鉢山(東京文化会館西側の岡)に、京都の清水観音堂がモデルにして建てられた寛永寺の伽藍の一つです。本堂正面を舞台づくりとし、不忍池の景色を眺められるようにしました。

舞台づくりの清水観音堂(0823)
その後の1694 年(元禄7年)に清水観音堂は、上野忍ケ岡にあった幕府学問所の焼失跡の現在地に移り、上野の山に現存する創建年次の明確な最古の建造物です。本尊は、比叡山の恵心僧都の作といわれる千手観音菩薩(国指定重要文化財)が祀られています。本堂は、安永年間に改築されたが、上野の戦争、大正大震災などいく度かの災火の難をまぬがれて残された、歴史をかいくぐった貴重な建物です。

清水観音堂(左:花園稲荷神社方から見た観音堂、右:観音堂正面0823)
本堂内右手前には、座布団の上に「びんずる尊者」が御安置されており、昔からおびんずる様の体を触って、その手で自分の体を撫でると、病気が治って頭も良くなり、節々の痛みも軽くなるといわれ、深く信仰されています。また、堂内に掲げてある絵馬や額も寛政、天明期の古いもので、平家物語にちなんだ「盛久危難の図」「千手観音」などがあり、明治期の画家五姓田芳柳の描いた「上野戦争図」も人目をひきます。
清水観音堂の舞台の前には、江戸時代の浮世絵師、歌川広重が描いた名所江戸百景「上野清水堂不忍池」と「上野山内月の松」が、約150年振りに復活しました。

歌川広重 名所江戸百景(左:上野清水堂不忍池1856年(安政3年)、右:上野山内月の松1857年(安政4年))
「月の松」は、明治初期の台風で消失したままとなっていたが、2013年1月17日に除幕式が行われ、3月には公園整備事業の一環として月の松の下にある桜を移設して、月の松から不忍池弁天堂が見えるように整えられました。

清水観音堂と「月の松」(0823)
しかし、名所江戸百景の「上野山内月の松」の絵は、不忍池の中島弁財天に下りる石段の直線上にこの松があり、月の松の円形中に遠く本郷台の町並みを覗かせるという構図をとり、中島弁財天は右下に見えます。

約150年振りに復活した「月の松」(0823)
なお、清水観音堂では、毎年9月25日は人形供養大法要が行われます。人形供養は、本堂右壇に御安置する「子育観音」に、人々が心願成就のお礼としてお子様の身代わりを奉納し御供養したことが始まりで、今日では心の安らぎを得たり愛情を注いできた人形を、報恩供養するようになったのが人形供養大法要で、人形を回向し供養の碑(Top写真参照)が建てられました。

人形供養大法要施行の看板(0823)
< 総合INDEX へ
毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)
・カテゴリー別Index イベント総目次 2013年版、2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ
<前回 イベント 東京藝術大学大学美術館 鶯谷から上野まで古寺・古建築を巡り夏目漱石の美術世界展を見るその4 へ
次回 イベント 東京藝術大学大学美術館 鶯谷から上野まで古寺・古建築を巡り夏目漱石の美術世界展を見るその6