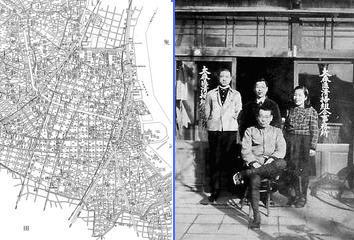kan-haru blog 2008
< 総合INDEX へ
京急蒲田駅構内の高架化工事
京急蒲田駅構内では、4組のジョイントベンチャーが分担して第3~5、7工区の高架化工事を行っており、広大なエリアに2階部分の高架橋から建設を進めておりますが、最終完成時には本線と空港線の上下線に分けて3階建ての高架駅となります。
京急蒲田駅構内の高架化工事の広大で複雑な高架駅橋の構造は、俯瞰的に全体的を見渡せることができません。したがって、高架駅橋の工事進捗の様子を見るのは、京急蒲田駅上下線ホームからと、駅周辺の道路からの観察となります。今回は、8月23、27と28日に見てきました。

京急蒲田駅南部の高架駅橋構造(高架橋駅構造模型拡大図)
・京急蒲田駅北端部の高架橋工事
京急蒲田駅北端の梅屋敷第4踏切道(補助36号線)の北端に接してクリーム色の、まだ2階部分のみの高架橋が建てられています(高架化 京急蒲田駅付近(第10回)参照)。この高架橋は、その北側に第2工区担当が建設済みのグレー色3階建ての高架橋と接続します。
また、このクリーム色の高架橋は、同第4踏切道南の第3工区担当の高架駅橋と補助36号線を跨ぐ鉄橋で接続されます。

梅屋敷第4踏切道付近の上り線路部の高架橋(左:踏切道北側の2階部の高架橋、中・右:踏切道から見た京急蒲田高架駅橋)
補助36号線道路から見る2階部の京急蒲田駅橋は、丸鋼管脚柱を中心として左右の突起部が上り線路の踏切を跨ぐ鉄橋を架ける位置で、右側が本線上り線路で、左側が空港線上り線路の様です。踏切端で建設中の高架橋上の本線上り線路の位置は、現在の地上運航の本線上りホームより西側の外部に位置しており、駅ホーム中心となる丸鋼管脚柱の位置は現在の上りホーム付近の上空にあたたり、空港線上り線路は現在運航の本線上下線の上空位置にあります。

高架橋建設中の上り本線高架橋(左・中・右拡大)
京急蒲田駅ホーム外部からホーム北端部付近までの、2階部本線上り線の高架橋の外観が駅西口道路の呑川付近から見られる様になり、最終が3階建て高架駅橋ですので丈夫にがっちりとした骨格で構築されています。

京急蒲田西口道路から見た上り高架橋(左・中・右拡大)
一方、空港線の上り線路部の高架橋は、高架化 京急蒲田駅付近(第11回)で、ホームから見た写真を記載していますが、この部分の高架橋は橋上が塞がれているため構造が良く分かりません。

ホームから見た京急蒲田駅北部高架橋(左・中・右拡大)
・京急蒲田駅中央部の高架橋工事
京急蒲田駅ホーム中央部から見た工事状況は、同じように高架駅橋が橋上で塞がれているため築造が見えず、進捗している筈の工事が高架化 京急蒲田駅付近(第11回)で掲示のものとは変化がありませんが、今回は視野角度を変えて写真を撮ってみました。

京急蒲田駅ホーム中央部から見た高架橋(左・中・右拡大)
・京急蒲田駅南部の高架橋工事
第4工区の京急蒲田駅ホーム南部から見た工事状況は、高架橋の工事が進行中で、骨格の一部が露出状態であるため、高架橋上の線路走行のコースが見えました。

京急蒲田駅ホーム南部から見た高架橋1(左・中・右拡大)
現行路線の上空を通る空港線線路は、左にカーブして第1京浜国道上を渡り、羽田空港方向へ東進して進みますが、横浜方面との乗り入れのため上り本線へも分岐交差をします。
駅南部の高架橋の梁桁の骨格は、緩やかに左に折れた形状で築造されているのが見え、また横浜方面への進行ルートも構築されています。

京急蒲田駅ホーム南部から見た高架橋2(左・中・右拡大)
< 総合INDEX へ
・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲載Indexへ)
・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次 2008年後期版、2008年前期版、2006・2007年版 へ
・サブ・カテゴリー別Index 京浜急行の高架化 大森町付近工区、梅屋敷付近工区、京急蒲田付近工区、雑色付近工区、糀谷付近工区 へ
<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 梅屋敷駅付近(第11回) へ
次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 京急蒲田駅付近(第12回その2) へ>
< 総合INDEX へ
京急蒲田駅構内の高架化工事
京急蒲田駅構内では、4組のジョイントベンチャーが分担して第3~5、7工区の高架化工事を行っており、広大なエリアに2階部分の高架橋から建設を進めておりますが、最終完成時には本線と空港線の上下線に分けて3階建ての高架駅となります。
京急蒲田駅構内の高架化工事の広大で複雑な高架駅橋の構造は、俯瞰的に全体的を見渡せることができません。したがって、高架駅橋の工事進捗の様子を見るのは、京急蒲田駅上下線ホームからと、駅周辺の道路からの観察となります。今回は、8月23、27と28日に見てきました。

京急蒲田駅南部の高架駅橋構造(高架橋駅構造模型拡大図)
・京急蒲田駅北端部の高架橋工事
京急蒲田駅北端の梅屋敷第4踏切道(補助36号線)の北端に接してクリーム色の、まだ2階部分のみの高架橋が建てられています(高架化 京急蒲田駅付近(第10回)参照)。この高架橋は、その北側に第2工区担当が建設済みのグレー色3階建ての高架橋と接続します。
また、このクリーム色の高架橋は、同第4踏切道南の第3工区担当の高架駅橋と補助36号線を跨ぐ鉄橋で接続されます。

梅屋敷第4踏切道付近の上り線路部の高架橋(左:踏切道北側の2階部の高架橋、中・右:踏切道から見た京急蒲田高架駅橋)
補助36号線道路から見る2階部の京急蒲田駅橋は、丸鋼管脚柱を中心として左右の突起部が上り線路の踏切を跨ぐ鉄橋を架ける位置で、右側が本線上り線路で、左側が空港線上り線路の様です。踏切端で建設中の高架橋上の本線上り線路の位置は、現在の地上運航の本線上りホームより西側の外部に位置しており、駅ホーム中心となる丸鋼管脚柱の位置は現在の上りホーム付近の上空にあたたり、空港線上り線路は現在運航の本線上下線の上空位置にあります。

高架橋建設中の上り本線高架橋(左・中・右拡大)
京急蒲田駅ホーム外部からホーム北端部付近までの、2階部本線上り線の高架橋の外観が駅西口道路の呑川付近から見られる様になり、最終が3階建て高架駅橋ですので丈夫にがっちりとした骨格で構築されています。

京急蒲田西口道路から見た上り高架橋(左・中・右拡大)
一方、空港線の上り線路部の高架橋は、高架化 京急蒲田駅付近(第11回)で、ホームから見た写真を記載していますが、この部分の高架橋は橋上が塞がれているため構造が良く分かりません。

ホームから見た京急蒲田駅北部高架橋(左・中・右拡大)
・京急蒲田駅中央部の高架橋工事
京急蒲田駅ホーム中央部から見た工事状況は、同じように高架駅橋が橋上で塞がれているため築造が見えず、進捗している筈の工事が高架化 京急蒲田駅付近(第11回)で掲示のものとは変化がありませんが、今回は視野角度を変えて写真を撮ってみました。

京急蒲田駅ホーム中央部から見た高架橋(左・中・右拡大)
・京急蒲田駅南部の高架橋工事
第4工区の京急蒲田駅ホーム南部から見た工事状況は、高架橋の工事が進行中で、骨格の一部が露出状態であるため、高架橋上の線路走行のコースが見えました。

京急蒲田駅ホーム南部から見た高架橋1(左・中・右拡大)
現行路線の上空を通る空港線線路は、左にカーブして第1京浜国道上を渡り、羽田空港方向へ東進して進みますが、横浜方面との乗り入れのため上り本線へも分岐交差をします。
駅南部の高架橋の梁桁の骨格は、緩やかに左に折れた形状で築造されているのが見え、また横浜方面への進行ルートも構築されています。

京急蒲田駅ホーム南部から見た高架橋2(左・中・右拡大)
< 総合INDEX へ
・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲載Indexへ)
・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次 2008年後期版、2008年前期版、2006・2007年版 へ
・サブ・カテゴリー別Index 京浜急行の高架化 大森町付近工区、梅屋敷付近工区、京急蒲田付近工区、雑色付近工区、糀谷付近工区 へ
<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 梅屋敷駅付近(第11回) へ
次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 京急蒲田駅付近(第12回その2) へ>