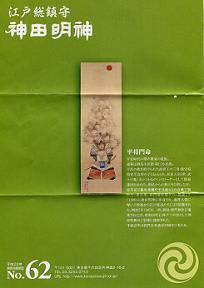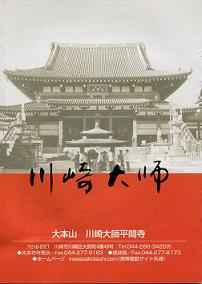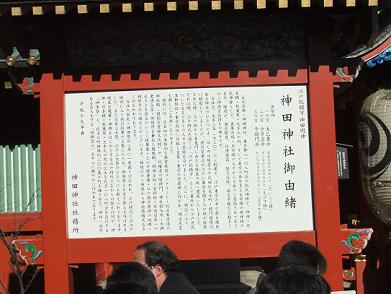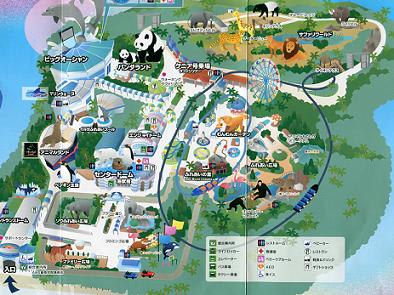kan-haru blog 2010 糀谷高架駅舎棟の壁面
< 総合INDEX へ
今回は、全工区統合編(第12回その2)以後の蒲田高架化工事の続報と、第8工区の糀谷高架化工事および第2~5工区電力線・電気設備工事の速報を掲載しました。
蒲田高架化工事続報
・第3工区高架駅舎棟築造
1月29日に見ると第3工区の高架駅舎棟は、第4工区境界側から築造の駅舎棟と多摩堤通り側から築造の駅舎棟の骨組みがドッキングしていました。また、多摩堤通りガード上の高架駅舎棟は、第1京浜国道側ではガード北端から高架橋の1橋長分の養生シートが外されていました。

第3工区高架駅舎棟の築造が進む1(左:第3工区高架駅舎棟の全体が結ばれる、中・右:多摩堤通りガード上の高架駅舎棟東壁面が初お目見え0129)
また、JR蒲田駅側のガード上でも高架橋の3橋長分の駅舎棟壁面が初お目見えし、呑み川南岸では2橋長分の高架駅舎棟壁面が養生シートを外されていました。

第3工区高架駅舎棟の築造が進む2(左:多摩堤通りガード上の高架駅舎棟西壁面が初お目見え、中・右:呑み側南岸駅舎棟西側壁面の養生シートが外される0129)
・第4工区高架駅舎棟築
同29日には、京急蒲田西口改札口南方の高架駅舎棟中央部の養生シートが外され、2階から3階までの全面高窓枠と左右に模様のついたデザインのスマートな壁面が公開されました。

西口改札口南方の高架駅舎棟中央部のスマートな壁面(左・中・右写真拡大0129)
第8工区糀谷高架化工事
糀谷高架駅舎棟の工事は1月20日に見ると、駅舎棟北面の京急蒲田(空)第4踏切側の養生シートが高架橋の4橋長分外されて、2橋長分はまだ足場が残っていました。

糀谷高架駅舎棟北面の西方で養生シートが外れる(左・中・右写真拡大0120)
また、上り線用の2階仮ホーム(「全工区統合編(第7回)」参照)への接続の階段は旧跨線橋用の階段を転用するもので、1月20日には2階ホーム部への結合通路部分の工事が完了していました。

転用階段による仮2階ホーム部への結合通路(左:旧跨線橋で使用した階段転用091018、中・右:転用階段による仮2階ホーム部への結合通路0120)
同29日には糀谷高架駅舎棟北面の壁面は、駅ホーム東端近くまで外壁が現われており、外壁工事作業用の道板が撤去されていました。

大部分が姿を見せた高架駅舎棟の北側壁面(左・中・右写真拡大0129)
なお、駅舎棟南面の外壁も、糀谷第1踏切側で高架橋の2橋長分の養生シートが外されていました。糀谷高架駅ホームのPC台板は、はっきり見えませんが取付けられているようです。また、上り線の単線高架橋用の電力線電柱の建立はすでに完了していました。

糀谷高架駅舎棟の築造が進む(左・中:駅舎棟南面の外壁も一部養生シートが外れる、右:高架駅ホーム台枠にPCホーム板が見える0129)
第2~5工区電力線・電気設備工事
1月29日に見ると、第2~5工区の上り線の電力線の架設は、梅屋敷第3踏切付近から、京急蒲田第8踏切南の蒲田消防署の先までトロリー線の架線が完了しています。
2階上り高架橋を梅屋敷第3踏切から南に進むと3階の下り高架橋の下を通り、電力線の架線は高架橋の下に付けられた懸垂碍子に架線されています。京急蒲田第6踏切を南に進むと、片張鋼製の電力電柱にトロリー線が架設されています。

梅屋敷第3踏切から京急蒲田第6踏切間のトロリー架線(左上・中上:梅屋敷第3踏切付近のトロリー架線、右上:京急蒲田第2踏切のトロリー架線、左下:同第4踏切のトロリー架線、中下:同第5踏切のトロリー架線、右下:同第6踏切付近のトロリー架線)
電力線の敷設工事は、29日現在同蒲田消防署の先まで進んでいます。

第5工区の電力線の架線が進む(左:京急蒲田第6踏切付近のトロリー架線、中:同第8踏切南の消防署裏のトロリー架線、右:消防署南方の電柱まで電力線架線工事済)
< 総合INDEX へ
・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(1月分掲Indexへ)
・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次2010年前期版、2009年後期版、2009年中Ⅱ期版、2009年中期版、2009年前期版、2008年後期版、2008年中期版、2008年前期版、2006・2007年版 へ
・サブ・カテゴリー別Index 高架化全工区統合編、大森町付近工区2009年版、大森町付近工区2008年版、大森町付近工区2006・2007年版、梅屋敷付近工区、京急蒲田付近工区2009年版、京急蒲田付近工区2006~2008年版、雑色付近工区、糀谷付近工区 へ
<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合編(第13回その1) へ
次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合編(第14回その1) へ
< 総合INDEX へ
今回は、全工区統合編(第12回その2)以後の蒲田高架化工事の続報と、第8工区の糀谷高架化工事および第2~5工区電力線・電気設備工事の速報を掲載しました。
蒲田高架化工事続報
・第3工区高架駅舎棟築造
1月29日に見ると第3工区の高架駅舎棟は、第4工区境界側から築造の駅舎棟と多摩堤通り側から築造の駅舎棟の骨組みがドッキングしていました。また、多摩堤通りガード上の高架駅舎棟は、第1京浜国道側ではガード北端から高架橋の1橋長分の養生シートが外されていました。

第3工区高架駅舎棟の築造が進む1(左:第3工区高架駅舎棟の全体が結ばれる、中・右:多摩堤通りガード上の高架駅舎棟東壁面が初お目見え0129)
また、JR蒲田駅側のガード上でも高架橋の3橋長分の駅舎棟壁面が初お目見えし、呑み川南岸では2橋長分の高架駅舎棟壁面が養生シートを外されていました。

第3工区高架駅舎棟の築造が進む2(左:多摩堤通りガード上の高架駅舎棟西壁面が初お目見え、中・右:呑み側南岸駅舎棟西側壁面の養生シートが外される0129)
・第4工区高架駅舎棟築
同29日には、京急蒲田西口改札口南方の高架駅舎棟中央部の養生シートが外され、2階から3階までの全面高窓枠と左右に模様のついたデザインのスマートな壁面が公開されました。

西口改札口南方の高架駅舎棟中央部のスマートな壁面(左・中・右写真拡大0129)
第8工区糀谷高架化工事
糀谷高架駅舎棟の工事は1月20日に見ると、駅舎棟北面の京急蒲田(空)第4踏切側の養生シートが高架橋の4橋長分外されて、2橋長分はまだ足場が残っていました。

糀谷高架駅舎棟北面の西方で養生シートが外れる(左・中・右写真拡大0120)
また、上り線用の2階仮ホーム(「全工区統合編(第7回)」参照)への接続の階段は旧跨線橋用の階段を転用するもので、1月20日には2階ホーム部への結合通路部分の工事が完了していました。

転用階段による仮2階ホーム部への結合通路(左:旧跨線橋で使用した階段転用091018、中・右:転用階段による仮2階ホーム部への結合通路0120)
同29日には糀谷高架駅舎棟北面の壁面は、駅ホーム東端近くまで外壁が現われており、外壁工事作業用の道板が撤去されていました。

大部分が姿を見せた高架駅舎棟の北側壁面(左・中・右写真拡大0129)
なお、駅舎棟南面の外壁も、糀谷第1踏切側で高架橋の2橋長分の養生シートが外されていました。糀谷高架駅ホームのPC台板は、はっきり見えませんが取付けられているようです。また、上り線の単線高架橋用の電力線電柱の建立はすでに完了していました。

糀谷高架駅舎棟の築造が進む(左・中:駅舎棟南面の外壁も一部養生シートが外れる、右:高架駅ホーム台枠にPCホーム板が見える0129)
第2~5工区電力線・電気設備工事
1月29日に見ると、第2~5工区の上り線の電力線の架設は、梅屋敷第3踏切付近から、京急蒲田第8踏切南の蒲田消防署の先までトロリー線の架線が完了しています。
2階上り高架橋を梅屋敷第3踏切から南に進むと3階の下り高架橋の下を通り、電力線の架線は高架橋の下に付けられた懸垂碍子に架線されています。京急蒲田第6踏切を南に進むと、片張鋼製の電力電柱にトロリー線が架設されています。

梅屋敷第3踏切から京急蒲田第6踏切間のトロリー架線(左上・中上:梅屋敷第3踏切付近のトロリー架線、右上:京急蒲田第2踏切のトロリー架線、左下:同第4踏切のトロリー架線、中下:同第5踏切のトロリー架線、右下:同第6踏切付近のトロリー架線)
電力線の敷設工事は、29日現在同蒲田消防署の先まで進んでいます。

第5工区の電力線の架線が進む(左:京急蒲田第6踏切付近のトロリー架線、中:同第8踏切南の消防署裏のトロリー架線、右:消防署南方の電柱まで電力線架線工事済)
< 総合INDEX へ
・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(1月分掲Indexへ)
・カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次2010年前期版、2009年後期版、2009年中Ⅱ期版、2009年中期版、2009年前期版、2008年後期版、2008年中期版、2008年前期版、2006・2007年版 へ
・サブ・カテゴリー別Index 高架化全工区統合編、大森町付近工区2009年版、大森町付近工区2008年版、大森町付近工区2006・2007年版、梅屋敷付近工区、京急蒲田付近工区2009年版、京急蒲田付近工区2006~2008年版、雑色付近工区、糀谷付近工区 へ
<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合編(第13回その1) へ
次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 全工区統合編(第14回その1) へ