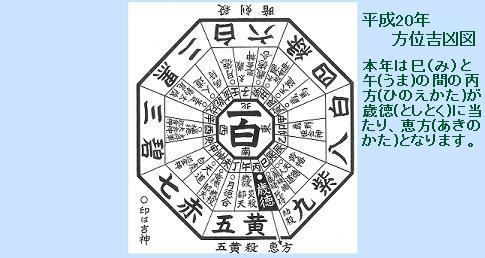kan-haru blog 2008
< 総合INDEX へ
第1工区高架化工事の特徴
大森町駅付近の高架化工事の分担は、第1工区で京急・大豊・西松・鉄建建設JVの担当で、平和島駅南の環七通り鉄橋から高架を下り内川橋梁を超えて、平和島第5踏切で地上となり、これより大森町駅を過ぎて現在閉鎖中の元大森第2踏切付近までの工区です。
この工区は、平和島第5踏切を堺にして、北方の平和島高架駅までの上り坂部と大森町駅を挟んだ平坦部とでは異なる工事法での高架化工事となるのが特徴工区です。
大森町駅付近高架橋工事の進捗
平和島第5踏切以南の高架橋は、年末までには第1高架橋(8本柱脚)と第2高架橋(10本柱脚)と高架橋間の連絡橋が完成してましたが、年が明けてから工事が急ピッチで進行し、その後の進行模様を見てきました。

年末までに完了した高架橋部分
工事機械の設置位置は、大森町駅ホーム上の先行工程分担の2号工事機械は年初から、1月16日には約10m程南方に移動し、同じく架橋構築工事の1号工事機械は約数10m程移動して第3高架橋の橋脚の構築が始まりました。

工事機械設置位置(2008.1.7拡大) (2008.1.16拡大) (2008.1.22拡大)
先ず、第3高架橋部の一部となる橋脚4本が、1月22日には建てられていました。

第3高架橋部となる橋脚4本
1月26日には、4本の橋脚間に縦と横に4つの橋桁が取り付けられていました。

橋脚間に縦横の橋桁が取り付け
この第3高架橋は、縦に2本の補強梁が1月28には取り付け完了という、急ピッチな高架橋建設の行程で進捗していました。

橋脚間に補強梁を取付(拡大) (拡大) (拡大)
第3高架橋は、大森町駅ホーム北端部に掛かる8本柱脚で、2号工事機械設置脇の大森町駅「上りホーム専用臨時改札口」(「大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 大森町駅付近(第6回)」参照)の北方のゑびす市場跡空地(「大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 大森町駅付近(第1回その1)」参照)では、連日トラックミキサ車がセメントを搬入して高架橋橋脚の基礎工事が進められています。

連日トラックミキサ車がセメントを搬入
また、大森町第1踏切南方でも高架橋建設の準備工事が行われております。

第1踏切南方の高架橋準備工事
駅設備関係では、大森町西口の券売機設備の移動(「大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 大森町駅付近(第11回その1)」参照)により、改札口への通路が拡幅されましたが、さらに3機の改札機の並びが、一列に揃えて設置して整理されました。
< 総合INDEX へ
毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(1月分掲載Indexへ)
カテゴリー別Index 京浜急行関連総目次 へ
<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 蒲田駅付近(第5回) へ
次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 大森町駅付近(第13回) へ>
< 総合INDEX へ
第1工区高架化工事の特徴
大森町駅付近の高架化工事の分担は、第1工区で京急・大豊・西松・鉄建建設JVの担当で、平和島駅南の環七通り鉄橋から高架を下り内川橋梁を超えて、平和島第5踏切で地上となり、これより大森町駅を過ぎて現在閉鎖中の元大森第2踏切付近までの工区です。
この工区は、平和島第5踏切を堺にして、北方の平和島高架駅までの上り坂部と大森町駅を挟んだ平坦部とでは異なる工事法での高架化工事となるのが特徴工区です。
大森町駅付近高架橋工事の進捗
平和島第5踏切以南の高架橋は、年末までには第1高架橋(8本柱脚)と第2高架橋(10本柱脚)と高架橋間の連絡橋が完成してましたが、年が明けてから工事が急ピッチで進行し、その後の進行模様を見てきました。

年末までに完了した高架橋部分
工事機械の設置位置は、大森町駅ホーム上の先行工程分担の2号工事機械は年初から、1月16日には約10m程南方に移動し、同じく架橋構築工事の1号工事機械は約数10m程移動して第3高架橋の橋脚の構築が始まりました。

工事機械設置位置(2008.1.7拡大) (2008.1.16拡大) (2008.1.22拡大)
先ず、第3高架橋部の一部となる橋脚4本が、1月22日には建てられていました。

第3高架橋部となる橋脚4本
1月26日には、4本の橋脚間に縦と横に4つの橋桁が取り付けられていました。

橋脚間に縦横の橋桁が取り付け
この第3高架橋は、縦に2本の補強梁が1月28には取り付け完了という、急ピッチな高架橋建設の行程で進捗していました。

橋脚間に補強梁を取付(拡大) (拡大) (拡大)
第3高架橋は、大森町駅ホーム北端部に掛かる8本柱脚で、2号工事機械設置脇の大森町駅「上りホーム専用臨時改札口」(「大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 大森町駅付近(第6回)」参照)の北方のゑびす市場跡空地(「大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 大森町駅付近(第1回その1)」参照)では、連日トラックミキサ車がセメントを搬入して高架橋橋脚の基礎工事が進められています。

連日トラックミキサ車がセメントを搬入
また、大森町第1踏切南方でも高架橋建設の準備工事が行われております。

第1踏切南方の高架橋準備工事
駅設備関係では、大森町西口の券売機設備の移動(「大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 大森町駅付近(第11回その1)」参照)により、改札口への通路が拡幅されましたが、さらに3機の改札機の並びが、一列に揃えて設置して整理されました。
< 総合INDEX へ
毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(1月分掲載Indexへ)
カテゴリー別Index 京浜急行関連総目次 へ
<前回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 蒲田駅付近(第5回) へ
次回 大森町界隈あれこれ 京浜急行の高架化 大森町駅付近(第13回) へ>