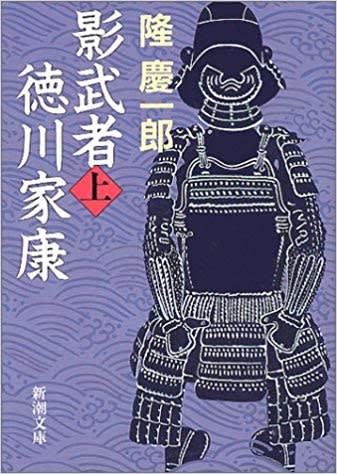
『影武者徳川家康(上・中・下)』 隆慶一郎 ☆☆☆☆☆
隆慶一郎の代表作と言われる『影武者徳川家康』を読了。文庫本にして全三巻、なかなかのボリュームである。
徳川家康は実は関ヶ原の戦いで死に、その後に天下を取ったのは実はニセモノ、つまり家康の影武者だったという物語である。まあ、ぱっと聞いただけだとトンデモ時代劇と言われても当然のアイデアだ。ところがこれが実は単なる荒唐無稽な思いつきではない、というから驚きである。作者の隆慶一郎はもともと家康に興味を持っていたが、特に関ヶ原の戦い以降の人が変わったような家康の言動に矛盾を感じ、その謎めいた人物像に惹かれていたという。それがある時誰かの本で家康の身代わり説というものを読み、これで史実の謎が解ける、とひらめいてこの小説を書いた。つまりこれは作者なりの史実解釈、真実探求の書なのである。
従って、これは単に面白おかしく筋を転がしていくだけの小説ではない。エピソードごとに史実が参照され、当時の記録からの文章が引用され、注釈がつけられ、この「身代わり説」によっていかに合理的に史実の謎が説明されるか、を作者が懇切丁寧に説明していく。いやー驚いた。この小説の主眼はそこにあり、チャンバラでも忍法合戦ではない。なんとも知的なエンターテインメントである。
さて、主人公はもちろん家康の影武者その人なのだが、この影武者・二郎三郎のキャラ造形が非常に魅力的だ。もともと野武士上がりのツワモノで、筋金入りの「いくさ人」、加えて影武者として家康の思考法をほぼ完璧に身に着けたレプリカント。ただの、周囲の傀儡ではない。もちろんそうでなければ話が面白くならないが、といっても何の権力もない影武者がただ天下を思いのままにできるはずはないので、「まだ家康が生きていることにしておかないとまずい」という徳川秀忠や側近や大名たちの思惑が、彼をそういう立場に追いやっていくことになる。が、いったんそうなってからは、傀儡として使われ用済みになったら殺されるのは嫌だ、と考え、二郎三郎は天下統一なったばかりのきわめて微妙なパワーバランスを読み、豊臣家と徳川家の間で巧みに動くことで状況を自分の思う方向へもっていく。
この政治的駆け引きこそが本書の読みどころである。二郎三郎に味方するのは豊臣側の島左近、その配下の忍者・六郎、そして六郎が味方につけた風魔一族。島左近と六郎は、二郎三郎が豊臣家を滅ぼすのではなく延命させようとしていることを知り、皮肉にも家康の身代わりである二郎三郎を支援することになる。
もちろん島左近は史実では関ヶ原の戦いで死んだことになっているが、実は生きていた、という設定である。『赤い影法師』のレビューにも書いたが、歴史上死んだことになっている人物が実は生きていた! という設定は伝奇小説には欠かせない。こういうのが出てくると途端にワクワクしてしまうのは、私の悪い癖である。
そして二郎三郎の敵は、徳川秀忠とその配下の柳生宗矩。秀忠はしばらく家康が生きていることにして徳川家の支配体制を固め、豊臣家も滅ぼし、その後なるべくはやく家康(の身代わり)から征夷大将軍を譲り受けて自分が天下人になろうともくろんでいる。もちろん、用済みになった二郎三郎はすぐ殺すつもりだ。
こうして、この二つの陣営がぶつかり合い、水面下で熾烈な戦いを繰り広げながらせめぎ合う。そしてその結果として歴史の表面にあらわれたものが、私たちが表面上「家康のやったこと」として知っている史実だ、というのがこの小説の骨格である。家康が死んだと知れると大名のほとんどは若輩者の秀忠に従うわけがないため、本来の家康の後継者である秀忠は表面上二郎三郎に服従しなければならず、また秀忠は実のところ徳川家の側近からも「こいつに任せておくと徳川家はどうなってしまうか分からない」と心配されるようなダメ人間なので、二郎三郎はそこにつけこんでうまく状況を操る。しばらくすると、影武者を使って家康が生きているように大名たちを騙していた、ということ自体が秀忠の弱みとなるので、二郎三郎はそれをしたためた書面を作って秀忠への抑止力とする。
まあそんなこんなで、影武者・二郎三郎一派と秀忠一派の権謀術数の争いは熾烈さを増していく。では、大奥の女たちはどうやって騙すのか。まさかエッチしているのにニセモノであることがバレないはずはない、という疑問はその通りで、従って家康と肌を合わせていた女には真実を告げて協力させる。その代表格がお梶だが、この気が強い蠱惑的なお梶と二郎三郎との不思議な男女の絆、そして歳月とともに真の伴侶となっていく過程はとても感動的だ。物語の終盤では読者に深い感慨をもたらす要素となっていく。
ストーリーの構成についていうと、この物語は関ヶ原の戦いからスタートする。従って本物の家康は開巻早々死んでしまうし、二郎三郎はすでに家康の影武者になっているが、その後二郎三郎の回想場面となり、それまでの二郎三郎の人生が読者の前にフラッシュバックする。この部分もかなりボリュームがあり、しかもえらく面白い。二郎三郎は野武士であり、つまり主人を持たない傭兵であり、自由人である。彼の戦いの主たる戦場は戦国時代末期に頻発した一向一揆だった。つまり宗教をバックグラウンドとした革命であり、持たざるものたちの体制への反逆である。
家康そっくりの短足体形である二郎三郎は最初は嘲笑される存在だったが、鉄砲の技術を身に着け、数多くのいくさをこなすことで練達の「いくさ人」になっていく。彼が率いる少数精鋭の部隊が大軍を次々と破って驚異の的となるところなど、単純に痛快きわまりないストーリー展開でワクワクさせる。また、彼が恋人を殺された悲しさから敵を皆殺しにする場面は、その壮絶さで忘れがたい場面になっている。
そして、そんな二郎三郎に出会った徳川家の本多弥八郎正信は家康に酷似した二郎三郎の体形に驚き、主君の影武者にぴったりだと考え、二郎三郎にくっついてあちこち放浪する。彼は二郎三郎に「いいか、絶対に死ぬんじゃないぞ」と言い、二郎三郎はそれを男の友情のセリフだととって感動するが、実は影武者に死なれては困るという打算だった、というあたりなど笑える。
そして二郎三郎の「いくさ人」としてのピークは、織田信長射殺未遂のシーンである。彼の前半生の生きがいは、一向一揆を徹底的に弾圧した信長を殺すことなのである。しかし彼は戦場で信長を見、間違いなく射殺できる唯一無二のチャンスに遭遇しながら信長の「目力」に負ける。必ず天下を取る、と決意している男だけが持つ圧倒的なオーラに気圧されてしまうのである。これが天才と凡人の違いだ、と彼は痛感し、その時から生きがいを失って落ちていく。彼が再び男としてよみがえるのは、家康が死ぬ時である。こうして二郎三郎の人生の物語は、関ヶ原で家康が死んだ時点へとつながっていく。
それにしても、家康は常人離れした短足体形で、だからどうしても替え玉が見つからなかった、というのは本当だろうか。
(次回へ続く)
隆慶一郎の代表作と言われる『影武者徳川家康』を読了。文庫本にして全三巻、なかなかのボリュームである。
徳川家康は実は関ヶ原の戦いで死に、その後に天下を取ったのは実はニセモノ、つまり家康の影武者だったという物語である。まあ、ぱっと聞いただけだとトンデモ時代劇と言われても当然のアイデアだ。ところがこれが実は単なる荒唐無稽な思いつきではない、というから驚きである。作者の隆慶一郎はもともと家康に興味を持っていたが、特に関ヶ原の戦い以降の人が変わったような家康の言動に矛盾を感じ、その謎めいた人物像に惹かれていたという。それがある時誰かの本で家康の身代わり説というものを読み、これで史実の謎が解ける、とひらめいてこの小説を書いた。つまりこれは作者なりの史実解釈、真実探求の書なのである。
従って、これは単に面白おかしく筋を転がしていくだけの小説ではない。エピソードごとに史実が参照され、当時の記録からの文章が引用され、注釈がつけられ、この「身代わり説」によっていかに合理的に史実の謎が説明されるか、を作者が懇切丁寧に説明していく。いやー驚いた。この小説の主眼はそこにあり、チャンバラでも忍法合戦ではない。なんとも知的なエンターテインメントである。
さて、主人公はもちろん家康の影武者その人なのだが、この影武者・二郎三郎のキャラ造形が非常に魅力的だ。もともと野武士上がりのツワモノで、筋金入りの「いくさ人」、加えて影武者として家康の思考法をほぼ完璧に身に着けたレプリカント。ただの、周囲の傀儡ではない。もちろんそうでなければ話が面白くならないが、といっても何の権力もない影武者がただ天下を思いのままにできるはずはないので、「まだ家康が生きていることにしておかないとまずい」という徳川秀忠や側近や大名たちの思惑が、彼をそういう立場に追いやっていくことになる。が、いったんそうなってからは、傀儡として使われ用済みになったら殺されるのは嫌だ、と考え、二郎三郎は天下統一なったばかりのきわめて微妙なパワーバランスを読み、豊臣家と徳川家の間で巧みに動くことで状況を自分の思う方向へもっていく。
この政治的駆け引きこそが本書の読みどころである。二郎三郎に味方するのは豊臣側の島左近、その配下の忍者・六郎、そして六郎が味方につけた風魔一族。島左近と六郎は、二郎三郎が豊臣家を滅ぼすのではなく延命させようとしていることを知り、皮肉にも家康の身代わりである二郎三郎を支援することになる。
もちろん島左近は史実では関ヶ原の戦いで死んだことになっているが、実は生きていた、という設定である。『赤い影法師』のレビューにも書いたが、歴史上死んだことになっている人物が実は生きていた! という設定は伝奇小説には欠かせない。こういうのが出てくると途端にワクワクしてしまうのは、私の悪い癖である。
そして二郎三郎の敵は、徳川秀忠とその配下の柳生宗矩。秀忠はしばらく家康が生きていることにして徳川家の支配体制を固め、豊臣家も滅ぼし、その後なるべくはやく家康(の身代わり)から征夷大将軍を譲り受けて自分が天下人になろうともくろんでいる。もちろん、用済みになった二郎三郎はすぐ殺すつもりだ。
こうして、この二つの陣営がぶつかり合い、水面下で熾烈な戦いを繰り広げながらせめぎ合う。そしてその結果として歴史の表面にあらわれたものが、私たちが表面上「家康のやったこと」として知っている史実だ、というのがこの小説の骨格である。家康が死んだと知れると大名のほとんどは若輩者の秀忠に従うわけがないため、本来の家康の後継者である秀忠は表面上二郎三郎に服従しなければならず、また秀忠は実のところ徳川家の側近からも「こいつに任せておくと徳川家はどうなってしまうか分からない」と心配されるようなダメ人間なので、二郎三郎はそこにつけこんでうまく状況を操る。しばらくすると、影武者を使って家康が生きているように大名たちを騙していた、ということ自体が秀忠の弱みとなるので、二郎三郎はそれをしたためた書面を作って秀忠への抑止力とする。
まあそんなこんなで、影武者・二郎三郎一派と秀忠一派の権謀術数の争いは熾烈さを増していく。では、大奥の女たちはどうやって騙すのか。まさかエッチしているのにニセモノであることがバレないはずはない、という疑問はその通りで、従って家康と肌を合わせていた女には真実を告げて協力させる。その代表格がお梶だが、この気が強い蠱惑的なお梶と二郎三郎との不思議な男女の絆、そして歳月とともに真の伴侶となっていく過程はとても感動的だ。物語の終盤では読者に深い感慨をもたらす要素となっていく。
ストーリーの構成についていうと、この物語は関ヶ原の戦いからスタートする。従って本物の家康は開巻早々死んでしまうし、二郎三郎はすでに家康の影武者になっているが、その後二郎三郎の回想場面となり、それまでの二郎三郎の人生が読者の前にフラッシュバックする。この部分もかなりボリュームがあり、しかもえらく面白い。二郎三郎は野武士であり、つまり主人を持たない傭兵であり、自由人である。彼の戦いの主たる戦場は戦国時代末期に頻発した一向一揆だった。つまり宗教をバックグラウンドとした革命であり、持たざるものたちの体制への反逆である。
家康そっくりの短足体形である二郎三郎は最初は嘲笑される存在だったが、鉄砲の技術を身に着け、数多くのいくさをこなすことで練達の「いくさ人」になっていく。彼が率いる少数精鋭の部隊が大軍を次々と破って驚異の的となるところなど、単純に痛快きわまりないストーリー展開でワクワクさせる。また、彼が恋人を殺された悲しさから敵を皆殺しにする場面は、その壮絶さで忘れがたい場面になっている。
そして、そんな二郎三郎に出会った徳川家の本多弥八郎正信は家康に酷似した二郎三郎の体形に驚き、主君の影武者にぴったりだと考え、二郎三郎にくっついてあちこち放浪する。彼は二郎三郎に「いいか、絶対に死ぬんじゃないぞ」と言い、二郎三郎はそれを男の友情のセリフだととって感動するが、実は影武者に死なれては困るという打算だった、というあたりなど笑える。
そして二郎三郎の「いくさ人」としてのピークは、織田信長射殺未遂のシーンである。彼の前半生の生きがいは、一向一揆を徹底的に弾圧した信長を殺すことなのである。しかし彼は戦場で信長を見、間違いなく射殺できる唯一無二のチャンスに遭遇しながら信長の「目力」に負ける。必ず天下を取る、と決意している男だけが持つ圧倒的なオーラに気圧されてしまうのである。これが天才と凡人の違いだ、と彼は痛感し、その時から生きがいを失って落ちていく。彼が再び男としてよみがえるのは、家康が死ぬ時である。こうして二郎三郎の人生の物語は、関ヶ原で家康が死んだ時点へとつながっていく。
それにしても、家康は常人離れした短足体形で、だからどうしても替え玉が見つからなかった、というのは本当だろうか。
(次回へ続く)




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます