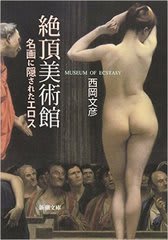
『絶頂美術館―名画に隠されたエロス』 西岡文彦 ☆☆☆☆☆
これがどんな書物なのかは、タイトルと表紙を見れば一目瞭然だろう。名画とエロス。魅惑的なテーマである。私も子供の頃家にあった美術全集を眺めながら、いかにも高尚そうな画題の絵画にエロを感じてどきどきしたものだ。これは芸術を見てエロに反応してしまう自分がいかんのか、それともエロい絵がいかんのか。大体、芸術とエロは別物なのか。これらはとても興味深い、そしてとても奥が深い問いである。ちなみに本書は文庫本なので図版の美麗さに関しては物足りないが、それはしょうがない。本書は画集ではなく、絵とエロティシズムに関するエッセーである。
まあ結論から言ってしまうと、印象派以前の神話やら伝承やらを題材にした絵画でヌードが出てくるものは、裸を見せることが目的だった。神話やら何やらはエクスキューズに過ぎない。写真もビデオもないその時代、異性の裸というものは基本的にナマで見るしかない。恋人がいなければ、あるいは恋人がいても許してくれなければ、裸を見ることはできない。だから人々の裸に対する飢餓感は現在とは比べものにならないわけだが、といってただ裸を描くと不道徳だといって非難される。その非難の厳しさ、スキャンダルもまた今日の比ではない。だから画家は神話や聖書にかこつけて女性のヌードを描き、その実本来の目的であるエロティシズムを十分に盛り込み、人々は芸術賛美の名目に隠れてエロティシズムを満喫した、というわけである。
最初に出てくるカバネルの「ヴィーナスの誕生」からして、その真の意図は明らかだ。波に上に横たわって身をよじらせるヴィーナスはベッドの中の愛人以外のなにものでもなく、その弛緩したポーズ、流し目、反り返った足指まで、すべてが性行為を暗示している。非常にエロティックだ。しかしこれは生まれたてのヴィーナスを描いた絵であるからして、美術館に堂々と展示して紳士淑女の鑑賞に供することができるのである。クレサンジェの彫刻「蛇に噛まれた女」も同じで、これは作者が自分の愛人である高級娼婦の性行為時の姿をそのまま彫刻にしたものだそうだが、タイトルだけ「蛇に噛まれた女」。つまり、これは蛇に噛まれてもだえている女だというのだ。これなど相当見え透いた、バレバレの例だと思うが、これでオッケーだったらしい。とにかくエクスキューズがあればいいのである。
つまりこれらの絵は芸術とポルノを兼ねていたというか、ポルノと芸術が一体だったといってもいいだろう。それは表紙になっているジェローム作「ローマの奴隷市場」でもはっきりしている。このシチュエーションはまるでAVではないか。ここまで露骨にエロを描くならもう堂々とこれはエロですといって描いても同じじゃないかと思ってしまうが、やはり何かしらのエクスキューズが必要だった、というのが今考えると奇妙な時代だし、ついにそのエクスキューズがない絵が登場した時のスキャンダルの激しさがまた異様である。マネの「草上の昼食」である。
この絵は当時とてつもないスキャンダルを巻き起こし、非難轟々だったというのは有名な話だ。本書によれば、この絵が展示されている部屋は嘲笑と哄笑に満ち、身もだえして笑う男がいるかと思えば、椅子にへたりこんで息をつまらせるご婦人もいたという。昔私はそれを聞いて、一体どんなすごい絵なんだろうと思ってマネの画集で探したが、発見した時は「へ? これ?」と拍子抜けしたものである。森のピクニックで裸の女性が座っている絵だが、まずタッチがリアルではないので全然エロくなく、言っちゃ悪いがそんなにきれいな女性でもないし、ポーズもただ冷静に座っているだけである。私の目からするとカバネル「ヴィーナスの誕生」やアングル「泉」のリアルで官能的なヌードの方がよほどエロいと思うが、これらが芸術として賞賛されたのに対し、「草上の昼食」はスキャンダルまみれになってしまった。
その理由は、まず神話や伝承の一場面というエクスキューズがなく同時代の女性の裸だったこと、ピクニックエリアという公共の場(つまり本来服を着ていなければならない場所)で裸でいること、同席している他の男性は服を着ていること、そして裸婦が絵の鑑賞者を平然と見返していること、などだったようだ。まあ、そうしたシチュエーションがエロティックなのは分からないでもない。しかし神話を題材にしたヌード絵画と比べた時にこれがそこまでスキャンダラスだったということを、おそらく現代に生きる我々は理解できない。エロとはコンテキストなのだなとつくづく思う。またこれを描いたマネにはそんな挑発的な意図はなかったというのがまた皮肉である。これですっかりスキャンダラスな画家の烙印を押されたマネは不運だっただろうが、ある意味、絵がそこまでのインパクトを人々に与えることができた時代というのはアーティストにとって幸福な時代でもあったんじゃないだろうか。今の時代、どんなとんでもない絵を描いてもそこまでの社会的反響を引き起こすことは難しいだろう。
マネの絵はまたエロとは無関係の他の理由によっても貶されたらしく、それは黒を使ったからだそうだ。確かにマネの黒は有名である。が、それがなぜいかんのか。私は本書を読むまでマネが黒を巧みに使ったので有名と思っていたのだが、実はそうじゃなく、当時黒はタブーの色だったらしい。なぜなら、当時の絵は色調によってどれだけ奥行きを表現できるかが即ち絵の芸術性と考えられていたため、距離感がなくなってしまう黒はダメだったのである。同じ理由で白もダメだったらしい。意図的に白を多用したホイッスラー「白い服の少女」も当時の展示会で嘲笑されたそうだ。いやー芸術を見る目というか価値観というものは、時代によってこうまで変化するものなのだなあ。後にマチスやピカソが繰り広げた芸術など、この時代の絵画の概念とまったく相いれないものだったことが分かる。
そういう話の他にも、たとえばヴィーナスの足指の表現に絡めて絵は時間の経過を表現できると説明した章や、ギリシャ・ローマ時代の絵では全裸がいわば「正装」とみなされること、史上初めて醜い裸をリアリズムで描いたクールベの衝撃、同性愛絵画のあれこれ、絵画の価値が手間や労力では計れないことを正当化したホイッスラー裁判など、面白い話が盛りだくさんだ。ホイッスラー裁判では、あなたはこの絵を描くのにたった二日しかかかっていないのになぜ二百ギニーも請求するのかと詰問する弁護士に、その前の人生すべてを費やして得た知識と経験に対する対価だ、とホイッスラーは答えたそうな。今日、殴り書きのような単純な絵に莫大な値がつけられる根拠はすべてこのホイッスラー裁判にある。アーティストは皆ホイッスラーに感謝しなければならない。
単に名画の中のエロティシズムを鑑賞するというだけでなく、人間の本音とタテマエというもの、芸術に対する意識というもの、そして絵画が人間に及ぼす不思議な支配力というものにまで思索は深まっていく。絵画好きにはこたえられない本だ。
これがどんな書物なのかは、タイトルと表紙を見れば一目瞭然だろう。名画とエロス。魅惑的なテーマである。私も子供の頃家にあった美術全集を眺めながら、いかにも高尚そうな画題の絵画にエロを感じてどきどきしたものだ。これは芸術を見てエロに反応してしまう自分がいかんのか、それともエロい絵がいかんのか。大体、芸術とエロは別物なのか。これらはとても興味深い、そしてとても奥が深い問いである。ちなみに本書は文庫本なので図版の美麗さに関しては物足りないが、それはしょうがない。本書は画集ではなく、絵とエロティシズムに関するエッセーである。
まあ結論から言ってしまうと、印象派以前の神話やら伝承やらを題材にした絵画でヌードが出てくるものは、裸を見せることが目的だった。神話やら何やらはエクスキューズに過ぎない。写真もビデオもないその時代、異性の裸というものは基本的にナマで見るしかない。恋人がいなければ、あるいは恋人がいても許してくれなければ、裸を見ることはできない。だから人々の裸に対する飢餓感は現在とは比べものにならないわけだが、といってただ裸を描くと不道徳だといって非難される。その非難の厳しさ、スキャンダルもまた今日の比ではない。だから画家は神話や聖書にかこつけて女性のヌードを描き、その実本来の目的であるエロティシズムを十分に盛り込み、人々は芸術賛美の名目に隠れてエロティシズムを満喫した、というわけである。
最初に出てくるカバネルの「ヴィーナスの誕生」からして、その真の意図は明らかだ。波に上に横たわって身をよじらせるヴィーナスはベッドの中の愛人以外のなにものでもなく、その弛緩したポーズ、流し目、反り返った足指まで、すべてが性行為を暗示している。非常にエロティックだ。しかしこれは生まれたてのヴィーナスを描いた絵であるからして、美術館に堂々と展示して紳士淑女の鑑賞に供することができるのである。クレサンジェの彫刻「蛇に噛まれた女」も同じで、これは作者が自分の愛人である高級娼婦の性行為時の姿をそのまま彫刻にしたものだそうだが、タイトルだけ「蛇に噛まれた女」。つまり、これは蛇に噛まれてもだえている女だというのだ。これなど相当見え透いた、バレバレの例だと思うが、これでオッケーだったらしい。とにかくエクスキューズがあればいいのである。
つまりこれらの絵は芸術とポルノを兼ねていたというか、ポルノと芸術が一体だったといってもいいだろう。それは表紙になっているジェローム作「ローマの奴隷市場」でもはっきりしている。このシチュエーションはまるでAVではないか。ここまで露骨にエロを描くならもう堂々とこれはエロですといって描いても同じじゃないかと思ってしまうが、やはり何かしらのエクスキューズが必要だった、というのが今考えると奇妙な時代だし、ついにそのエクスキューズがない絵が登場した時のスキャンダルの激しさがまた異様である。マネの「草上の昼食」である。
この絵は当時とてつもないスキャンダルを巻き起こし、非難轟々だったというのは有名な話だ。本書によれば、この絵が展示されている部屋は嘲笑と哄笑に満ち、身もだえして笑う男がいるかと思えば、椅子にへたりこんで息をつまらせるご婦人もいたという。昔私はそれを聞いて、一体どんなすごい絵なんだろうと思ってマネの画集で探したが、発見した時は「へ? これ?」と拍子抜けしたものである。森のピクニックで裸の女性が座っている絵だが、まずタッチがリアルではないので全然エロくなく、言っちゃ悪いがそんなにきれいな女性でもないし、ポーズもただ冷静に座っているだけである。私の目からするとカバネル「ヴィーナスの誕生」やアングル「泉」のリアルで官能的なヌードの方がよほどエロいと思うが、これらが芸術として賞賛されたのに対し、「草上の昼食」はスキャンダルまみれになってしまった。
その理由は、まず神話や伝承の一場面というエクスキューズがなく同時代の女性の裸だったこと、ピクニックエリアという公共の場(つまり本来服を着ていなければならない場所)で裸でいること、同席している他の男性は服を着ていること、そして裸婦が絵の鑑賞者を平然と見返していること、などだったようだ。まあ、そうしたシチュエーションがエロティックなのは分からないでもない。しかし神話を題材にしたヌード絵画と比べた時にこれがそこまでスキャンダラスだったということを、おそらく現代に生きる我々は理解できない。エロとはコンテキストなのだなとつくづく思う。またこれを描いたマネにはそんな挑発的な意図はなかったというのがまた皮肉である。これですっかりスキャンダラスな画家の烙印を押されたマネは不運だっただろうが、ある意味、絵がそこまでのインパクトを人々に与えることができた時代というのはアーティストにとって幸福な時代でもあったんじゃないだろうか。今の時代、どんなとんでもない絵を描いてもそこまでの社会的反響を引き起こすことは難しいだろう。
マネの絵はまたエロとは無関係の他の理由によっても貶されたらしく、それは黒を使ったからだそうだ。確かにマネの黒は有名である。が、それがなぜいかんのか。私は本書を読むまでマネが黒を巧みに使ったので有名と思っていたのだが、実はそうじゃなく、当時黒はタブーの色だったらしい。なぜなら、当時の絵は色調によってどれだけ奥行きを表現できるかが即ち絵の芸術性と考えられていたため、距離感がなくなってしまう黒はダメだったのである。同じ理由で白もダメだったらしい。意図的に白を多用したホイッスラー「白い服の少女」も当時の展示会で嘲笑されたそうだ。いやー芸術を見る目というか価値観というものは、時代によってこうまで変化するものなのだなあ。後にマチスやピカソが繰り広げた芸術など、この時代の絵画の概念とまったく相いれないものだったことが分かる。
そういう話の他にも、たとえばヴィーナスの足指の表現に絡めて絵は時間の経過を表現できると説明した章や、ギリシャ・ローマ時代の絵では全裸がいわば「正装」とみなされること、史上初めて醜い裸をリアリズムで描いたクールベの衝撃、同性愛絵画のあれこれ、絵画の価値が手間や労力では計れないことを正当化したホイッスラー裁判など、面白い話が盛りだくさんだ。ホイッスラー裁判では、あなたはこの絵を描くのにたった二日しかかかっていないのになぜ二百ギニーも請求するのかと詰問する弁護士に、その前の人生すべてを費やして得た知識と経験に対する対価だ、とホイッスラーは答えたそうな。今日、殴り書きのような単純な絵に莫大な値がつけられる根拠はすべてこのホイッスラー裁判にある。アーティストは皆ホイッスラーに感謝しなければならない。
単に名画の中のエロティシズムを鑑賞するというだけでなく、人間の本音とタテマエというもの、芸術に対する意識というもの、そして絵画が人間に及ぼす不思議な支配力というものにまで思索は深まっていく。絵画好きにはこたえられない本だ。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます