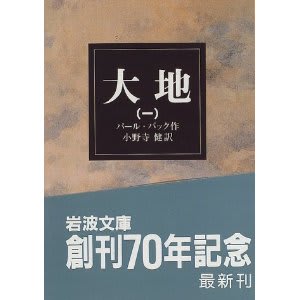
『大地(一、二、三、四)』 パール・バック ☆☆☆☆☆
岩波文庫の全四巻を再読。
一大叙事詩、という言葉がある。言うまでもなく叙事詩とはもともと神話とか英雄譚を韻文形式で綴った詩のことで、厳密には小説を意味しない。だから大河ドラマ的な長編を一大叙事詩、と呼ぶのはいい加減な使い方なのかも知れないが、ある種の小説、長大で、読み終えた時に他では得られない深い感慨を与えてくれる大長編の中には、これぞまさに一大叙事詩だ、そうとしか呼びようがない、と思わせられるものが確かにある。そうした作品はおそらく文学史上色々とあって、どれを思い浮かべるかは人それぞれだろうが、私の場合は『戦争と平和』『怒りの葡萄』そしてこの『大地』が決定版である。リョサの『世界終末戦争』なんかももちろん一大叙事詩には違いないが、やはり普遍性においてはこの三作が一歩抜きん出ている気がする。
では「一大叙事詩」的長編小説とは何だろうか。完全に個人的な感覚で言わせてもらえば、もちろんただ長いだけではダメで、人生における普遍的な感慨が広範に盛り込まれていること、歴史のうねりを感じさせること、この二点が重要である。逆にこの二点をクリアしていればそれほど長くなくてもいい。
で、『戦争と平和』『怒りの葡萄』と並ぶ一大叙事詩であるこの『大地』、大傑作であることは言うまでもない。ピュリッツァー賞受賞作だ。作者は欧米人のパール・バックだが、中国の話である。ちなみに私はパール・バックというのは男性の名前だとばかり思っていたが、女性である。
豊穣な物語、とはまさにこれだ。三部構成で、第一部が貧しい農夫から身を起こして富豪となる王龍の物語、第二部が土地から離れた王龍の三人の息子の物語、そして第三部が王龍の孫・王元が近代化の波の中で自らのアイデンティティを探し求める物語、となっている。第一部は古い時代の中国を舞台にしていることもあってより神話的、寓話的だ。第二部、第三部と進むに従って近代小説的になっていく。たとえば第一部には奴隷や貴族が登場し、飢饉、イナゴの大群の襲来、革命など神話的イベントが多発する。主人公である王龍はこうした歴史的事件、外界からやってくる危機に翻弄される。しかし第三部においてはそういう大事件はほとんど起きず、王元の心理描写、彼の心の中の葛藤が主要なテーマとなる。
三部全体の核となるのが第一部「大地」であることは間違いない。ここに人生のあらゆる要素、あらゆる感慨が描き尽くされている、と感じるのである。第一部を読み終えた読者はみな、自分は今まさに一つの人生を生きたのだ、と実感するに違いない。物語は王龍の結婚の朝から始まる。といっても王龍は老いた父と二人で暮らす一介の農夫、湯にお茶の葉っぱを入れるのさえ「金を飲むようなもんだ」と非難される貧乏百姓である。彼は大金持ちの屋敷に入っていって、そこで働いている女の奴隷をもらってくる。これが彼の結婚だ。女は美しくない。しかし我慢と努力を知っている。この妻・阿蘭とともに王龍は懸命に大地を耕し、銀を貯め、子供を増やし、土地を増やしていく。人間の力ではどうしようもない天災に見舞われ、餓死寸前になっても、決して諦めない。そんな時、彼の心の支えになるのはいつも土地である。「しかしおれにはあの土地がある。あの土地があるんだ」こうして彼は数々の苦難を乗り越え、のしあがっていく。
裕福になった王龍はやがて贅沢の味を知り、美しい女に溺れる。このまま駄目になってしまうのかと思われた時、彼を救うのもやはり土地である。鍬を持って土地を耕し、汗を流して労働する、この行為が王龍を常に真人間に立ち返らせる。こうして第一部「大地」は王龍の努力、苦難、喜び、成功、堕落、立ち直り、悩み、そして静謐で淡い老年の恋までを劇的に、エネルギッシュに描いていく。文体がその力強さを失うことは一度たりともない。
しかしこの第一部を読んで思うのは、王龍が一番幸せだったのは結局、まだ金持ちではなかった時代、阿蘭と二人で懸命に農業をしていたあの時代ではなかったか、ということである。後に金持ちになって人から羨まれるようになるが、たかってくる親戚、息子たちとの確執、愛人騒動など色んなわずらわしい悩みだらけで、とても幸福とは思えない。実際の人の人生もそんなものかもなあ、と思う。皆さん、金持ちが幸せとは限りませんよ。
この第一部では特に、パール・バックの明快な思想が物語を貫いているのを感じとることができる。その思想とは即ち、怠惰な生活、金を使うだけの生活は人間を腐らせる、ということだ。働く人間、ものを生み出す人間こそ尊い。この原則に例外はない。金を持ち、それに慣れると人間は必ず腐っていく。拝金主義者はこの本を読むべきだ。何事も相対化してしまい、「人間の生き方に正解なんてない」が常識となった現代、この物語の力強い確信は爽快だ。そして面白いのは、私たち読者はこの物語を読んでいる時、何が正しくて何が間違っているかが手に取るように分かる。王龍があやまった道に踏み込もうとする時、たとえば贅沢を覚え、妻の阿蘭で満足できなくなり美人の蓮華のところへ通い始める時、あるいは蓮華を家に入れようとする時、なんと愚かな、と慨嘆する。不幸が起きるのは目に見えているじゃないか。正しい道を選択するにはいかにも簡単に思える。ところが自分の実人生の中では、易々と同じ過ちをおかしてしまうのである。
ところでここまで読んで一番心に残るキャラクターは、個人的には王龍の妻・阿蘭である。無口で、不細工だけど従順で、常に王龍に付き従う女。愚鈍なように見えて、実は充分に賢い。おとなしく見えて、自分の望むものはしっかり分かっている。そして控え目に、卑屈に見えて、女としての思いを持ち続けている。単純なようで複雑な、実に深いキャラクターだ。彼女の面影は読者の心の中から決して消えていかないだろう。これこそ生きているキャラクター、芸術家の至芸である。
阿蘭はけなげに王龍を支え、王龍に尽くす。しかし王龍は金持ちになると彼女の醜さに嫌気がさし、蓮華を愛人にする。物語の中で阿蘭が何度か涙をこぼす場面があるが、普段は感情を表に出さない彼女だからこそ、これらの場面は悲痛だ。王龍が蓮華へのプレゼントにしようと阿蘭が大事にしまっていた真珠を奪った時、そして王龍が蓮華を囲い者にするために家に入れた時。大金をかけて作った離れに夫の愛人がやって来ると、彼女は部屋に閉じこもって出てこない。そして王龍に涙をこぼしながら言うのである。「私はあなたの子供を産んだのに…」ああ、心が痛い。
パール・バックの描写は簡潔で飾り気がないが、とても力強い。短い文章の中に驚くほど多くの意味を込めることができる。たとえば飢饉のさなか、王龍の一家が飢えに苦しむ場面。わずかな食べ物を手に入れた王龍は、自分も餓死寸前でありながら、それを幼い娘に与える。そして娘が食べるのを見つめる。ここでパール・バックはただシンプルに、こう書く。「(王龍は)自分が食べたような気がした」これだけだ。が、どれほどお涙頂戴の美辞麗句を連ねようとも、王龍の娘への愛情をこの一文以上に雄弁に表現することはできないだろう。
(次回へ続く)
岩波文庫の全四巻を再読。
一大叙事詩、という言葉がある。言うまでもなく叙事詩とはもともと神話とか英雄譚を韻文形式で綴った詩のことで、厳密には小説を意味しない。だから大河ドラマ的な長編を一大叙事詩、と呼ぶのはいい加減な使い方なのかも知れないが、ある種の小説、長大で、読み終えた時に他では得られない深い感慨を与えてくれる大長編の中には、これぞまさに一大叙事詩だ、そうとしか呼びようがない、と思わせられるものが確かにある。そうした作品はおそらく文学史上色々とあって、どれを思い浮かべるかは人それぞれだろうが、私の場合は『戦争と平和』『怒りの葡萄』そしてこの『大地』が決定版である。リョサの『世界終末戦争』なんかももちろん一大叙事詩には違いないが、やはり普遍性においてはこの三作が一歩抜きん出ている気がする。
では「一大叙事詩」的長編小説とは何だろうか。完全に個人的な感覚で言わせてもらえば、もちろんただ長いだけではダメで、人生における普遍的な感慨が広範に盛り込まれていること、歴史のうねりを感じさせること、この二点が重要である。逆にこの二点をクリアしていればそれほど長くなくてもいい。
で、『戦争と平和』『怒りの葡萄』と並ぶ一大叙事詩であるこの『大地』、大傑作であることは言うまでもない。ピュリッツァー賞受賞作だ。作者は欧米人のパール・バックだが、中国の話である。ちなみに私はパール・バックというのは男性の名前だとばかり思っていたが、女性である。
豊穣な物語、とはまさにこれだ。三部構成で、第一部が貧しい農夫から身を起こして富豪となる王龍の物語、第二部が土地から離れた王龍の三人の息子の物語、そして第三部が王龍の孫・王元が近代化の波の中で自らのアイデンティティを探し求める物語、となっている。第一部は古い時代の中国を舞台にしていることもあってより神話的、寓話的だ。第二部、第三部と進むに従って近代小説的になっていく。たとえば第一部には奴隷や貴族が登場し、飢饉、イナゴの大群の襲来、革命など神話的イベントが多発する。主人公である王龍はこうした歴史的事件、外界からやってくる危機に翻弄される。しかし第三部においてはそういう大事件はほとんど起きず、王元の心理描写、彼の心の中の葛藤が主要なテーマとなる。
三部全体の核となるのが第一部「大地」であることは間違いない。ここに人生のあらゆる要素、あらゆる感慨が描き尽くされている、と感じるのである。第一部を読み終えた読者はみな、自分は今まさに一つの人生を生きたのだ、と実感するに違いない。物語は王龍の結婚の朝から始まる。といっても王龍は老いた父と二人で暮らす一介の農夫、湯にお茶の葉っぱを入れるのさえ「金を飲むようなもんだ」と非難される貧乏百姓である。彼は大金持ちの屋敷に入っていって、そこで働いている女の奴隷をもらってくる。これが彼の結婚だ。女は美しくない。しかし我慢と努力を知っている。この妻・阿蘭とともに王龍は懸命に大地を耕し、銀を貯め、子供を増やし、土地を増やしていく。人間の力ではどうしようもない天災に見舞われ、餓死寸前になっても、決して諦めない。そんな時、彼の心の支えになるのはいつも土地である。「しかしおれにはあの土地がある。あの土地があるんだ」こうして彼は数々の苦難を乗り越え、のしあがっていく。
裕福になった王龍はやがて贅沢の味を知り、美しい女に溺れる。このまま駄目になってしまうのかと思われた時、彼を救うのもやはり土地である。鍬を持って土地を耕し、汗を流して労働する、この行為が王龍を常に真人間に立ち返らせる。こうして第一部「大地」は王龍の努力、苦難、喜び、成功、堕落、立ち直り、悩み、そして静謐で淡い老年の恋までを劇的に、エネルギッシュに描いていく。文体がその力強さを失うことは一度たりともない。
しかしこの第一部を読んで思うのは、王龍が一番幸せだったのは結局、まだ金持ちではなかった時代、阿蘭と二人で懸命に農業をしていたあの時代ではなかったか、ということである。後に金持ちになって人から羨まれるようになるが、たかってくる親戚、息子たちとの確執、愛人騒動など色んなわずらわしい悩みだらけで、とても幸福とは思えない。実際の人の人生もそんなものかもなあ、と思う。皆さん、金持ちが幸せとは限りませんよ。
この第一部では特に、パール・バックの明快な思想が物語を貫いているのを感じとることができる。その思想とは即ち、怠惰な生活、金を使うだけの生活は人間を腐らせる、ということだ。働く人間、ものを生み出す人間こそ尊い。この原則に例外はない。金を持ち、それに慣れると人間は必ず腐っていく。拝金主義者はこの本を読むべきだ。何事も相対化してしまい、「人間の生き方に正解なんてない」が常識となった現代、この物語の力強い確信は爽快だ。そして面白いのは、私たち読者はこの物語を読んでいる時、何が正しくて何が間違っているかが手に取るように分かる。王龍があやまった道に踏み込もうとする時、たとえば贅沢を覚え、妻の阿蘭で満足できなくなり美人の蓮華のところへ通い始める時、あるいは蓮華を家に入れようとする時、なんと愚かな、と慨嘆する。不幸が起きるのは目に見えているじゃないか。正しい道を選択するにはいかにも簡単に思える。ところが自分の実人生の中では、易々と同じ過ちをおかしてしまうのである。
ところでここまで読んで一番心に残るキャラクターは、個人的には王龍の妻・阿蘭である。無口で、不細工だけど従順で、常に王龍に付き従う女。愚鈍なように見えて、実は充分に賢い。おとなしく見えて、自分の望むものはしっかり分かっている。そして控え目に、卑屈に見えて、女としての思いを持ち続けている。単純なようで複雑な、実に深いキャラクターだ。彼女の面影は読者の心の中から決して消えていかないだろう。これこそ生きているキャラクター、芸術家の至芸である。
阿蘭はけなげに王龍を支え、王龍に尽くす。しかし王龍は金持ちになると彼女の醜さに嫌気がさし、蓮華を愛人にする。物語の中で阿蘭が何度か涙をこぼす場面があるが、普段は感情を表に出さない彼女だからこそ、これらの場面は悲痛だ。王龍が蓮華へのプレゼントにしようと阿蘭が大事にしまっていた真珠を奪った時、そして王龍が蓮華を囲い者にするために家に入れた時。大金をかけて作った離れに夫の愛人がやって来ると、彼女は部屋に閉じこもって出てこない。そして王龍に涙をこぼしながら言うのである。「私はあなたの子供を産んだのに…」ああ、心が痛い。
パール・バックの描写は簡潔で飾り気がないが、とても力強い。短い文章の中に驚くほど多くの意味を込めることができる。たとえば飢饉のさなか、王龍の一家が飢えに苦しむ場面。わずかな食べ物を手に入れた王龍は、自分も餓死寸前でありながら、それを幼い娘に与える。そして娘が食べるのを見つめる。ここでパール・バックはただシンプルに、こう書く。「(王龍は)自分が食べたような気がした」これだけだ。が、どれほどお涙頂戴の美辞麗句を連ねようとも、王龍の娘への愛情をこの一文以上に雄弁に表現することはできないだろう。
(次回へ続く)




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます