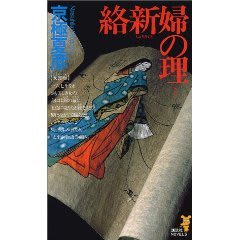
『絡新婦の理』 京極夏彦 ☆☆☆☆
『姑獲鳥の夏』に続いて『絡新婦の理』を再読。やはり京極堂シリーズには中毒性がある。
さて、このタイトルは「じょろうぐものことわり」と読む。なめてんのかと言いたくなるが、これは京極夏彦の勝手な創作ではなく、いわゆる女郎蜘蛛が中国では「絡新婦」と表記する事実に因っているらしい。ちゃんと裏づけがあるのだから文句も言えない。しかしこの人の漢字に対する偏愛ぶりはすごい。タイトルもそうだが、この本を取ってどこでもいいからページを開いてみればいい。漢字フェチである。例によってのけぞりそうな分厚さの本だが、非常に読みやすく、高性能なページターナーである。
このシリーズは単に妖怪をモチーフとして持ってきて殺人事件とくっつけたというだけでなく、妖怪の民俗学的背景が事件のテーマとして織り込まれているところがまたよく出来ているのだが、本書ではその点がとりわけ見事だ。詳しい説明は本文中の怒涛のような京極堂の解説に譲るとして、さわりだけ言うと、機を織って神に仕える巫女が一方では羽衣伝説や七夕になり、一方では水にもぐって女郎蜘蛛という妖怪になった、という考察を下敷きに、近代社会における女性、というか女性性の変遷に色んな角度から光を当てていく。そして実際に事件そのものや関係者に女系家族、フェミニズム、売春などというキーワードがきっちり埋め込まれている。よく考えられていると思うが、それに加えて犯罪の構成や経緯もやたらに複雑である。この作家は一体どうやって、どれぐらいの時間をかけてプロットを練っているのだろうか。非常に興味がある。それからまた、この人の宗教や神話、民俗学についての知識量は一体どうなっているのか。本書ではキリスト教やユダヤ教まで網羅されている。
ストーリーの構成は大雑把にいうと、娼婦が殺された連続目潰し魔事件と、ミッション系女学校での「闇の聖母」による殺人が平行して進み、やがて融合する。レギュラー陣の分担はというと、目潰し魔事件の方を刑事の木場が担当し、「闇の聖母」事件を探偵の榎木津が担当する(榎木津はもちろん捜査などしないが、かわいい女学生がいると言われて出かけていく)。そして当然ながら、佳境に入ったところで京極堂こと中禅寺秋彦が登場する。
面白いのはこの目潰し魔事件、女学校事件の二つがコインの裏表のように同じ事件を構成していて、被害者が共通、しかし「なぜ殺されたか」という経緯の部分がまったく違うという趣向である。視点を変えることで「被害者の共通点」が複数浮かび上がってくる。そしてどちらも目くらましの偽装ではない。おまけに、この事件は外部から干渉しても進行を早めるだけで決して阻止できない仕掛けになっている、というのだからすごい。京極堂の動きすら折り込み済みという、まさに神の如き犯人である。
という風に大風呂敷が広がり、これでもかと盛り上がっていくが、しかし謎解きは例によっていささか肩透かし気味である。要するに「すべて折り込み済み」というのは色んな手を打ってなりゆきにまかせるというだけだし、とても不思議な同一事件の二つの相貌も、結局細かい嘘と計略の積み重ねによっている。大体なんでそんな二重の事件にしなければならないのかという根本的な部分の解明がない。というか、動機が判明してから振り返ると、すべてにおいてなぜにあんな遠回りなことをしなければならないのかが分からない。それにすべてを計算していたというが、さすがに展開が犯人に都合よすぎる。最後の最後、関係者全員の目の前でぽんぽんと起きる殺人などはあまりに安易だと思う。
というわけで、京極堂シリーズ最高傑作とも言われる本書だが、クライマックスの盛り上がりと美しさは『姑獲鳥』の方が上だと思う。ただし、謎の錯綜ぶりは確かにシリーズ最高かも知れない。
『姑獲鳥の夏』に続いて『絡新婦の理』を再読。やはり京極堂シリーズには中毒性がある。
さて、このタイトルは「じょろうぐものことわり」と読む。なめてんのかと言いたくなるが、これは京極夏彦の勝手な創作ではなく、いわゆる女郎蜘蛛が中国では「絡新婦」と表記する事実に因っているらしい。ちゃんと裏づけがあるのだから文句も言えない。しかしこの人の漢字に対する偏愛ぶりはすごい。タイトルもそうだが、この本を取ってどこでもいいからページを開いてみればいい。漢字フェチである。例によってのけぞりそうな分厚さの本だが、非常に読みやすく、高性能なページターナーである。
このシリーズは単に妖怪をモチーフとして持ってきて殺人事件とくっつけたというだけでなく、妖怪の民俗学的背景が事件のテーマとして織り込まれているところがまたよく出来ているのだが、本書ではその点がとりわけ見事だ。詳しい説明は本文中の怒涛のような京極堂の解説に譲るとして、さわりだけ言うと、機を織って神に仕える巫女が一方では羽衣伝説や七夕になり、一方では水にもぐって女郎蜘蛛という妖怪になった、という考察を下敷きに、近代社会における女性、というか女性性の変遷に色んな角度から光を当てていく。そして実際に事件そのものや関係者に女系家族、フェミニズム、売春などというキーワードがきっちり埋め込まれている。よく考えられていると思うが、それに加えて犯罪の構成や経緯もやたらに複雑である。この作家は一体どうやって、どれぐらいの時間をかけてプロットを練っているのだろうか。非常に興味がある。それからまた、この人の宗教や神話、民俗学についての知識量は一体どうなっているのか。本書ではキリスト教やユダヤ教まで網羅されている。
ストーリーの構成は大雑把にいうと、娼婦が殺された連続目潰し魔事件と、ミッション系女学校での「闇の聖母」による殺人が平行して進み、やがて融合する。レギュラー陣の分担はというと、目潰し魔事件の方を刑事の木場が担当し、「闇の聖母」事件を探偵の榎木津が担当する(榎木津はもちろん捜査などしないが、かわいい女学生がいると言われて出かけていく)。そして当然ながら、佳境に入ったところで京極堂こと中禅寺秋彦が登場する。
面白いのはこの目潰し魔事件、女学校事件の二つがコインの裏表のように同じ事件を構成していて、被害者が共通、しかし「なぜ殺されたか」という経緯の部分がまったく違うという趣向である。視点を変えることで「被害者の共通点」が複数浮かび上がってくる。そしてどちらも目くらましの偽装ではない。おまけに、この事件は外部から干渉しても進行を早めるだけで決して阻止できない仕掛けになっている、というのだからすごい。京極堂の動きすら折り込み済みという、まさに神の如き犯人である。
という風に大風呂敷が広がり、これでもかと盛り上がっていくが、しかし謎解きは例によっていささか肩透かし気味である。要するに「すべて折り込み済み」というのは色んな手を打ってなりゆきにまかせるというだけだし、とても不思議な同一事件の二つの相貌も、結局細かい嘘と計略の積み重ねによっている。大体なんでそんな二重の事件にしなければならないのかという根本的な部分の解明がない。というか、動機が判明してから振り返ると、すべてにおいてなぜにあんな遠回りなことをしなければならないのかが分からない。それにすべてを計算していたというが、さすがに展開が犯人に都合よすぎる。最後の最後、関係者全員の目の前でぽんぽんと起きる殺人などはあまりに安易だと思う。
というわけで、京極堂シリーズ最高傑作とも言われる本書だが、クライマックスの盛り上がりと美しさは『姑獲鳥』の方が上だと思う。ただし、謎の錯綜ぶりは確かにシリーズ最高かも知れない。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます