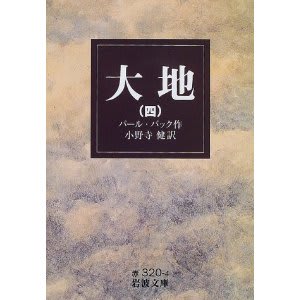
(前回の続き)
さて、第一部「大地」は王龍が死の床について、息子たちに「決して土地を売らないでくれ、土地を売ってしまったら終わりだ」と頼んでいる象徴的な場面で終わる。そして第二部「息子たち」は、王龍の死から始まる。第一部では「長男」「次男」などと書かれ、名前がなかった息子たちだが、第二部から王一、王ニ、王三と名前が与えられる(といっても番号が振られただけだが…)。
長男はぐうたらな貴族になり、次男ははしっこい商売人になる。そして第一部で一番影が薄かった無口な三男はなんと、軍人になる。そしてこの王三、通称王虎が、この第二部「息子たち」の主人公である。
王虎は自分を百姓にしようとした父・王龍を憎み、土地を憎んでいる。だから遺産相続後ただちに自分の土地を兄に売り、金に換え、これを軍資金にして天下を取ろうと野望に燃える。それから自分の軍隊を率いて戦を繰り返し、のし上がっていく。というわけで、第二部は第一部と違ってアクションに富んだ波乱万丈篇だ。ちょっと「水滸伝」とかああいう英雄譚の雰囲気がある。狡猾な敵との戦いや、裏切りなどのエピソードが出てくる。
第二部での大きなテーマの一つに、女との愛がある。王虎は女嫌いである。というか、猛々しい軍人とは思えないほどおくて、と言った方が正確かも知れない。もともと王虎は第一部で梨花という名の女奴隷に心を寄せるが、梨花が父子ほど歳の離れた王龍を愛していることを知り、ショックで家を飛び出してしまう。王虎の父への憎しみと女性不信はここに端を発しているのだが、彼はそれを呪いのように生涯引きずり続ける。第二部中とりわけ印象的なエピソードによって王虎はある女と出会い、ついに生涯の伴侶とめぐり合ったと信じるが、その愛は無残な結末を迎える。
それから息子との関係。王虎は自分の跡を継いでくれる息子を熱望し、ようやく生まれた息子に自分の軍隊、権力のすべてを残そうとする。彼は自分を農夫にしようとした父を憎んでいるので、自分は息子を百姓などにはしない、自分が築く帝国の王にする、と誇らしく夢見る。ところが何たることか、息子の王元は戦争が嫌いで銃にも剣にも興味がなく、農夫になりたいと思っていたのだった。自分の土地を耕して暮らせたらどんな幸せか、と少年は考える。王元には祖父・王龍の血が流れているのだ。王虎は理解できず、怒り、王元を無理矢理軍人にしようとする。こうして因果は巡り、自分を農夫にしようとした王龍を憎んだ王虎のように、自分を軍人にしようとする父を王元は憎むようになる。
父は息子を心から愛し、彼に自分のすべてを継がせたいと願い、それゆえに子もまた一個の独立した人格であることを理解しようとせず、息子から憎まれることになる。親子の確執が世代を超えて繰り返される。
それから王虎はもっと大きなことを成し遂げようと常に思いながら、息子が生まれてからは現状に流されるようになってしまう。いつも何かしら先延ばしにするための理由があるのである。軍隊の準備がまだできていない、今年は税収が少ない、今は情勢が不利だ、などなど。こうしてあっという間に歳月は流れていってしまう、若き日の望みは何一つ実現できないうちに。気がつけば、自分は年老いている。この王虎の姿に身につまされる思いになるのは私だけではないだろう。
王虎は猛々しく、強く、公正なリーダーで、荒くれ者達を威圧するカリスマの持ち主でもあり、二人の兄と比べてもはるかに読者を魅了するキャラクターでありながら、その一方で王龍にはなかった哀れさを強く感じさせるのは、こうした数々の「幻滅」のテーマを体現しているからである。第二部の冒頭部分で王虎が若さと野望に輝き、力に満ち溢れているから余計に、後半の彼に哀愁を感じてしまう。
第三部「崩壊した家」の主人公は王虎の息子、王元である。彼が背負ったテーマは伝統と近代の相克、と言っていいと思う。彼は軍隊が嫌いで農作業が好きだが、だから単純に農夫になることはもうできない。彼は思想を学び、自分の祖国がどうあるべきか、自分は何をするべきかを考える。彼は纏足を野蛮な風習と考え、結婚相手を親が決めるのを古いと考える。海外留学し、そこで西洋社会を見て祖国と比較する。彼の家はすでに名門で、裕福である。従って王龍や王虎のように成功しようとしゃかりきになることもない。そのかわり、祖国の貧富の差は何によるものか、社会はどうあるべきかを考える。
彼は思想の人であり、彼が対決するのは人生そのものよりむしろイデオロギーである。第三部が第一部、第二部よりも印象が薄いのはそのためだろう。彼自身の人生ももちろん描かれるが、その主体は恋愛模様である。
パール・バックは王元の分裂した自我として、いとこを二人登場させる。これは王一の息子たちなのだが、一人は洗練された文化人、享楽主義者でいわば近代文明の申し子でありながら、最後は「誰と結婚しても同じことだから親が決めて下さい」と一種のニヒリズムに至る。もう一人は革命家で、人民のための政府を作るといいながら人民そのものを軽蔑し、嫌悪している。これらの姿を見ながら王元は、伝統と近代の折衷の道を探ろうとする。
王元のイデオロギー遍歴もなかなか興味深くはあるが、やはり読んでいてはっとさせられるのは、もはや百姓の子孫とは思えない近代人・王元の中に、もうこの世にいない王龍の、あるいは阿蘭の血を感じる時である。彼にはやはり同じ血が流れているのだ。アメリカの大学に通ってダンス・パーティーに興じる王元の中に、奴隷の女を嫁にもらい、飢饉に苦しみ、ひたすら土を耕して家族を養った王龍の血が、すなわちその精神と人格が滅びることなく息づいているのである。私たちはそこに、家が続いていくとは、祖先と子孫とはどういうことなのか、それをおぼろげながら垣間見ることができる。
これは小説の中だけの話ではない。私たち全員が間違いなくその絆の中に、古代から現代まで連綿と続く血の絆の中にいるのである。『大地』三部作を読んで私をもっとも感動させるのはそれだ。私の実家には父方の祖父、祖母の白黒写真が飾ってあるが、以前はそれを自分と関係が深い人たちと思ったことはなかった(私が物心つく頃にはもう二人ともこの世にいなかった)。赤の他人と変わりないと思っていたのである。が、この小説を読んだ後ではもうそうは思えない。それは不思議に安らぐような、畏敬の念をかき立てるような、それでいてどこか切ない感覚だ。
『大地』を読めば、おそらくあなたもそれを感じることができるはずだ。
さて、第一部「大地」は王龍が死の床について、息子たちに「決して土地を売らないでくれ、土地を売ってしまったら終わりだ」と頼んでいる象徴的な場面で終わる。そして第二部「息子たち」は、王龍の死から始まる。第一部では「長男」「次男」などと書かれ、名前がなかった息子たちだが、第二部から王一、王ニ、王三と名前が与えられる(といっても番号が振られただけだが…)。
長男はぐうたらな貴族になり、次男ははしっこい商売人になる。そして第一部で一番影が薄かった無口な三男はなんと、軍人になる。そしてこの王三、通称王虎が、この第二部「息子たち」の主人公である。
王虎は自分を百姓にしようとした父・王龍を憎み、土地を憎んでいる。だから遺産相続後ただちに自分の土地を兄に売り、金に換え、これを軍資金にして天下を取ろうと野望に燃える。それから自分の軍隊を率いて戦を繰り返し、のし上がっていく。というわけで、第二部は第一部と違ってアクションに富んだ波乱万丈篇だ。ちょっと「水滸伝」とかああいう英雄譚の雰囲気がある。狡猾な敵との戦いや、裏切りなどのエピソードが出てくる。
第二部での大きなテーマの一つに、女との愛がある。王虎は女嫌いである。というか、猛々しい軍人とは思えないほどおくて、と言った方が正確かも知れない。もともと王虎は第一部で梨花という名の女奴隷に心を寄せるが、梨花が父子ほど歳の離れた王龍を愛していることを知り、ショックで家を飛び出してしまう。王虎の父への憎しみと女性不信はここに端を発しているのだが、彼はそれを呪いのように生涯引きずり続ける。第二部中とりわけ印象的なエピソードによって王虎はある女と出会い、ついに生涯の伴侶とめぐり合ったと信じるが、その愛は無残な結末を迎える。
それから息子との関係。王虎は自分の跡を継いでくれる息子を熱望し、ようやく生まれた息子に自分の軍隊、権力のすべてを残そうとする。彼は自分を農夫にしようとした父を憎んでいるので、自分は息子を百姓などにはしない、自分が築く帝国の王にする、と誇らしく夢見る。ところが何たることか、息子の王元は戦争が嫌いで銃にも剣にも興味がなく、農夫になりたいと思っていたのだった。自分の土地を耕して暮らせたらどんな幸せか、と少年は考える。王元には祖父・王龍の血が流れているのだ。王虎は理解できず、怒り、王元を無理矢理軍人にしようとする。こうして因果は巡り、自分を農夫にしようとした王龍を憎んだ王虎のように、自分を軍人にしようとする父を王元は憎むようになる。
父は息子を心から愛し、彼に自分のすべてを継がせたいと願い、それゆえに子もまた一個の独立した人格であることを理解しようとせず、息子から憎まれることになる。親子の確執が世代を超えて繰り返される。
それから王虎はもっと大きなことを成し遂げようと常に思いながら、息子が生まれてからは現状に流されるようになってしまう。いつも何かしら先延ばしにするための理由があるのである。軍隊の準備がまだできていない、今年は税収が少ない、今は情勢が不利だ、などなど。こうしてあっという間に歳月は流れていってしまう、若き日の望みは何一つ実現できないうちに。気がつけば、自分は年老いている。この王虎の姿に身につまされる思いになるのは私だけではないだろう。
王虎は猛々しく、強く、公正なリーダーで、荒くれ者達を威圧するカリスマの持ち主でもあり、二人の兄と比べてもはるかに読者を魅了するキャラクターでありながら、その一方で王龍にはなかった哀れさを強く感じさせるのは、こうした数々の「幻滅」のテーマを体現しているからである。第二部の冒頭部分で王虎が若さと野望に輝き、力に満ち溢れているから余計に、後半の彼に哀愁を感じてしまう。
第三部「崩壊した家」の主人公は王虎の息子、王元である。彼が背負ったテーマは伝統と近代の相克、と言っていいと思う。彼は軍隊が嫌いで農作業が好きだが、だから単純に農夫になることはもうできない。彼は思想を学び、自分の祖国がどうあるべきか、自分は何をするべきかを考える。彼は纏足を野蛮な風習と考え、結婚相手を親が決めるのを古いと考える。海外留学し、そこで西洋社会を見て祖国と比較する。彼の家はすでに名門で、裕福である。従って王龍や王虎のように成功しようとしゃかりきになることもない。そのかわり、祖国の貧富の差は何によるものか、社会はどうあるべきかを考える。
彼は思想の人であり、彼が対決するのは人生そのものよりむしろイデオロギーである。第三部が第一部、第二部よりも印象が薄いのはそのためだろう。彼自身の人生ももちろん描かれるが、その主体は恋愛模様である。
パール・バックは王元の分裂した自我として、いとこを二人登場させる。これは王一の息子たちなのだが、一人は洗練された文化人、享楽主義者でいわば近代文明の申し子でありながら、最後は「誰と結婚しても同じことだから親が決めて下さい」と一種のニヒリズムに至る。もう一人は革命家で、人民のための政府を作るといいながら人民そのものを軽蔑し、嫌悪している。これらの姿を見ながら王元は、伝統と近代の折衷の道を探ろうとする。
王元のイデオロギー遍歴もなかなか興味深くはあるが、やはり読んでいてはっとさせられるのは、もはや百姓の子孫とは思えない近代人・王元の中に、もうこの世にいない王龍の、あるいは阿蘭の血を感じる時である。彼にはやはり同じ血が流れているのだ。アメリカの大学に通ってダンス・パーティーに興じる王元の中に、奴隷の女を嫁にもらい、飢饉に苦しみ、ひたすら土を耕して家族を養った王龍の血が、すなわちその精神と人格が滅びることなく息づいているのである。私たちはそこに、家が続いていくとは、祖先と子孫とはどういうことなのか、それをおぼろげながら垣間見ることができる。
これは小説の中だけの話ではない。私たち全員が間違いなくその絆の中に、古代から現代まで連綿と続く血の絆の中にいるのである。『大地』三部作を読んで私をもっとも感動させるのはそれだ。私の実家には父方の祖父、祖母の白黒写真が飾ってあるが、以前はそれを自分と関係が深い人たちと思ったことはなかった(私が物心つく頃にはもう二人ともこの世にいなかった)。赤の他人と変わりないと思っていたのである。が、この小説を読んだ後ではもうそうは思えない。それは不思議に安らぐような、畏敬の念をかき立てるような、それでいてどこか切ない感覚だ。
『大地』を読めば、おそらくあなたもそれを感じることができるはずだ。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます