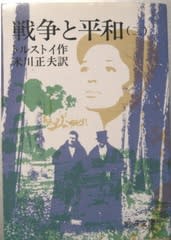
『戦争と平和』 トルストイ ☆☆☆☆☆
岩波文庫版で再読。最近の岩波版『戦争と平和』は改訳され、字が大きくなり、コラムなんかがついているらしいが、私のは古いやつである。全四巻に小さい字がみっちり詰まっている。大長編だ。読み通すのは相当時間がかかる。が、文句なく面白い。そして深い。世紀の文豪トルストイの代表作と言われるだけのことはある。これはやはり大傑作と言わなければならない。
話が複雑すぎて要約は不可能だが、要するに19世紀初頭ナポレオンのロシア侵攻という歴史的大事件を背景にした一大ロマンである。中心となる人物はアンドレイ公爵、ピエール、そしてナターシャの三人だが、それ以外にもナターシャの兄ニコライ、いとこのボリース、同居人ソーニャ、アンドレイの妹マリア、その父、ピエールの淫蕩な美人妻エレン、美貌の遊蕩児アナトーリ、無頼漢ドーロホフ、そしてもちろんナポレオンやロシアの将軍クトゥーゾフなど、無数の登場人物が絡み合いせめぎあいながら華麗なドラマを繰り広げる。
アンドレイ公爵とピエールは親友同士だがキャラ的には正反対で、沈着冷静、懐疑的、ちょっとニヒリスティックでかっこいいアンドレイ公爵に対し、ピエールは夢想家で情熱家、子供のように純真な肥満漢である。アンドレイは社交界に嫌気がさして戦争に行き、負傷して戦争にも嫌気がさして田舎にこもるが、本能のままに生きる太陽のようなナターシャと出会い、再び生きる気力を取り戻す。ところがアンドレイと離れているうちにナターシャは遊蕩児アナトーリに誘惑され、婚約を破棄してしまう。失意のアンドレイは再び戦場に赴き、後にナターシャは負傷した彼と再会し、その最期を看取ることになる。このアンドレイとナターシャの恋愛が本書の一大ハイライトであることは間違いなく、アンドレイとの結婚を控えたナターシャをアナトーリが誘惑するところや、負傷したアンドレイとモスクワから逃げのびるナターシャが再会するあたりはページを繰る手が止まらなくなる。
一方、私生児のピエールは財産を相続して大金持ちになり、一躍社交界の寵児となる。美人のエレンと結婚するがこれがとんでもない女で、ピエールは逃げ出す。彼はフリーメイソンに入ったり戦争に行ったり変装してナポレオンを暗殺しようとしたり、フランス軍の捕虜になって銃殺されそうになったりとさまざまな遍歴をしたあげく、親友アンドレイの恋人だったナターシャと結ばれる。ピエールは本書において常に迷い、思想を求めて彷徨するという役割を与えられており、その成長ぶりは色々な感慨をもたらしてくれる。特に捕虜になって銃殺されそうになるエピソードは圧巻だ。
さて、あらすじだけ見ると普通の大河メロドラマみたいだが、本書はなぜそれほどの大傑作なのか。それを話しはじめるとまたキリがないのだが、まず膨大な登場人物が一人残らず個性的かつ立体的、一人としてステレオタイプがいない。悪役であるドーロホフやアナトーリでさえ、ある種魅力的な奥深さを持っている。例えばアナトーリは愚かで美しいだけの放蕩息子だが、良心の呵責など微塵もなく常に昂然と頭をもたげており、ピエールが「これこそ賢人だ」と感心するような心の平和を保っている。このような「生きた」登場人物が繰り広げるドラマは切実で安易さがなく、現実と同じように非論理的で予想を裏切る、つかみどころのないがゆえにリアルで説得力に満ちた展開をする。ストーリーテリングにおいては、何を書いて何を書かないかが絶妙。トルストイは劇的なドラマの前ふりを入念に描いておいて、もっとも肝心な部分を描かない、またはあっさり数行で書き流すというようなことをする。そしてこれが見事なリリシズムをかもし出す。名人芸である。
それから人間の心理の不可解なメカニズムが見事に描き出されている。現実の人間の心は非論理的で、悲惨な状況の中で喜びを感じたり、幸福の中に悲しみを感じたりするし、さまざまな矛盾や唐突な変心を起こすものだが、本書の登場人物はまさにそういう不可思議な存在だ。そしてそれが、物語になんともいえない奥行きとポエジーを与えている。このポエジーはトルストイのあらゆるページから立ち上ってくるが、ミラン・クンデラはその一例としてアンドレイ公爵の負傷の場面を挙げている。アンドレイは重症を負うのだが彼の心はその時不思議な幸福感に満たされ、世界中のすべてへの愛を感じるのである。そして彼はそのめくるめく感動のうちに自分を裏切ったナターシャを赦す。
それにしてもトルストイの人間描写にはホントに感心する。その引き出しは無限である。たとえばベルグという「子供っぽいエゴイズム」を持った調子のいい男(ナターシャの姉と結婚する)について、いい家具を安く買う話をしながら立ち上がって優雅に妻にキスし、ついでに絨毯のめくれを直す、というさりげない描写がある。笑ってしまうが、これでもう見事にベルグがどんな奴か分かってしまう。あらゆる登場人物について、こういう描写が続出なのである。
この長大な物語の中では恋愛物語以外にも、遺産相続の争い、親子の確執、社交界の醜悪さ、復讐、決闘、戦争など、ありとあらゆるドラマが網羅されているが、これだけ複雑なプロットにもかかわらず全体がまるで優美なシンフォニーのように均整が取れている、これがまた驚異的だ。絶対に物語が破綻していかない。読者はトルストイが無数の腕を持つ人形使いのように、すべてのプロットラインと登場人物を自在に操っているのを感じることができる。さらにいうと、これだけ多くのエピソードがありながら焼き直しが全然ないというのもすごい。
こういう人間ドラマの一方で、トルストイはナポレオン侵攻という歴史的事件を描いていく。本編の中やエピローグで繰り返し語られているが、トルストイは歴史的事件が特定の偉人(ナポレオンやアレクサンドル三世など)によって引き起こされるのではなく、むしろ偉人達は歴史的必然の道具に過ぎないという視点を取っている。だから連戦連勝だったナポレオンがモスクワを占拠し、その後ロシア軍の反撃がなかったにもかかわらず敗走したという不可解な事件を、軍事的駆け引きの結果ではなく歴史の必然として描いている。トルストイによれば、それはナポレオンの戦術の失敗でもロシア軍の戦略の成功でもなく、ただ押しとどめようのない集団力学の結果なのである。そういうわけで、本書ではナポレオンはあまり大した人間には描かれていない。むしろ一般には評価が低い、ロシアの将軍クトゥーゾフの方が賢人として描かれている。
ところでロシアの文豪といえばトルストイとドストエフスキーだが、一般にはドストエフスキーの方が高く評価される場合が多いような気がする。おそらく均整のとれたトルストイに比べてあのバロック的な異形性が評価されるのだと思うが、私はトルストイの方が好きだ。ミラン・クンデラもどうやらトルストイの方が好きなようで、『存在の耐えられない軽さ』のトマーシュとテレザは『アンナ・カレーニナ』をきっかけに知り合うし、二人の犬はカレーニンと名づけられる。エッセーでもあちこちでトルストイの良さについて書いている。トルストイ好きの私としてはとっても嬉しい。
岩波文庫版で再読。最近の岩波版『戦争と平和』は改訳され、字が大きくなり、コラムなんかがついているらしいが、私のは古いやつである。全四巻に小さい字がみっちり詰まっている。大長編だ。読み通すのは相当時間がかかる。が、文句なく面白い。そして深い。世紀の文豪トルストイの代表作と言われるだけのことはある。これはやはり大傑作と言わなければならない。
話が複雑すぎて要約は不可能だが、要するに19世紀初頭ナポレオンのロシア侵攻という歴史的大事件を背景にした一大ロマンである。中心となる人物はアンドレイ公爵、ピエール、そしてナターシャの三人だが、それ以外にもナターシャの兄ニコライ、いとこのボリース、同居人ソーニャ、アンドレイの妹マリア、その父、ピエールの淫蕩な美人妻エレン、美貌の遊蕩児アナトーリ、無頼漢ドーロホフ、そしてもちろんナポレオンやロシアの将軍クトゥーゾフなど、無数の登場人物が絡み合いせめぎあいながら華麗なドラマを繰り広げる。
アンドレイ公爵とピエールは親友同士だがキャラ的には正反対で、沈着冷静、懐疑的、ちょっとニヒリスティックでかっこいいアンドレイ公爵に対し、ピエールは夢想家で情熱家、子供のように純真な肥満漢である。アンドレイは社交界に嫌気がさして戦争に行き、負傷して戦争にも嫌気がさして田舎にこもるが、本能のままに生きる太陽のようなナターシャと出会い、再び生きる気力を取り戻す。ところがアンドレイと離れているうちにナターシャは遊蕩児アナトーリに誘惑され、婚約を破棄してしまう。失意のアンドレイは再び戦場に赴き、後にナターシャは負傷した彼と再会し、その最期を看取ることになる。このアンドレイとナターシャの恋愛が本書の一大ハイライトであることは間違いなく、アンドレイとの結婚を控えたナターシャをアナトーリが誘惑するところや、負傷したアンドレイとモスクワから逃げのびるナターシャが再会するあたりはページを繰る手が止まらなくなる。
一方、私生児のピエールは財産を相続して大金持ちになり、一躍社交界の寵児となる。美人のエレンと結婚するがこれがとんでもない女で、ピエールは逃げ出す。彼はフリーメイソンに入ったり戦争に行ったり変装してナポレオンを暗殺しようとしたり、フランス軍の捕虜になって銃殺されそうになったりとさまざまな遍歴をしたあげく、親友アンドレイの恋人だったナターシャと結ばれる。ピエールは本書において常に迷い、思想を求めて彷徨するという役割を与えられており、その成長ぶりは色々な感慨をもたらしてくれる。特に捕虜になって銃殺されそうになるエピソードは圧巻だ。
さて、あらすじだけ見ると普通の大河メロドラマみたいだが、本書はなぜそれほどの大傑作なのか。それを話しはじめるとまたキリがないのだが、まず膨大な登場人物が一人残らず個性的かつ立体的、一人としてステレオタイプがいない。悪役であるドーロホフやアナトーリでさえ、ある種魅力的な奥深さを持っている。例えばアナトーリは愚かで美しいだけの放蕩息子だが、良心の呵責など微塵もなく常に昂然と頭をもたげており、ピエールが「これこそ賢人だ」と感心するような心の平和を保っている。このような「生きた」登場人物が繰り広げるドラマは切実で安易さがなく、現実と同じように非論理的で予想を裏切る、つかみどころのないがゆえにリアルで説得力に満ちた展開をする。ストーリーテリングにおいては、何を書いて何を書かないかが絶妙。トルストイは劇的なドラマの前ふりを入念に描いておいて、もっとも肝心な部分を描かない、またはあっさり数行で書き流すというようなことをする。そしてこれが見事なリリシズムをかもし出す。名人芸である。
それから人間の心理の不可解なメカニズムが見事に描き出されている。現実の人間の心は非論理的で、悲惨な状況の中で喜びを感じたり、幸福の中に悲しみを感じたりするし、さまざまな矛盾や唐突な変心を起こすものだが、本書の登場人物はまさにそういう不可思議な存在だ。そしてそれが、物語になんともいえない奥行きとポエジーを与えている。このポエジーはトルストイのあらゆるページから立ち上ってくるが、ミラン・クンデラはその一例としてアンドレイ公爵の負傷の場面を挙げている。アンドレイは重症を負うのだが彼の心はその時不思議な幸福感に満たされ、世界中のすべてへの愛を感じるのである。そして彼はそのめくるめく感動のうちに自分を裏切ったナターシャを赦す。
それにしてもトルストイの人間描写にはホントに感心する。その引き出しは無限である。たとえばベルグという「子供っぽいエゴイズム」を持った調子のいい男(ナターシャの姉と結婚する)について、いい家具を安く買う話をしながら立ち上がって優雅に妻にキスし、ついでに絨毯のめくれを直す、というさりげない描写がある。笑ってしまうが、これでもう見事にベルグがどんな奴か分かってしまう。あらゆる登場人物について、こういう描写が続出なのである。
この長大な物語の中では恋愛物語以外にも、遺産相続の争い、親子の確執、社交界の醜悪さ、復讐、決闘、戦争など、ありとあらゆるドラマが網羅されているが、これだけ複雑なプロットにもかかわらず全体がまるで優美なシンフォニーのように均整が取れている、これがまた驚異的だ。絶対に物語が破綻していかない。読者はトルストイが無数の腕を持つ人形使いのように、すべてのプロットラインと登場人物を自在に操っているのを感じることができる。さらにいうと、これだけ多くのエピソードがありながら焼き直しが全然ないというのもすごい。
こういう人間ドラマの一方で、トルストイはナポレオン侵攻という歴史的事件を描いていく。本編の中やエピローグで繰り返し語られているが、トルストイは歴史的事件が特定の偉人(ナポレオンやアレクサンドル三世など)によって引き起こされるのではなく、むしろ偉人達は歴史的必然の道具に過ぎないという視点を取っている。だから連戦連勝だったナポレオンがモスクワを占拠し、その後ロシア軍の反撃がなかったにもかかわらず敗走したという不可解な事件を、軍事的駆け引きの結果ではなく歴史の必然として描いている。トルストイによれば、それはナポレオンの戦術の失敗でもロシア軍の戦略の成功でもなく、ただ押しとどめようのない集団力学の結果なのである。そういうわけで、本書ではナポレオンはあまり大した人間には描かれていない。むしろ一般には評価が低い、ロシアの将軍クトゥーゾフの方が賢人として描かれている。
ところでロシアの文豪といえばトルストイとドストエフスキーだが、一般にはドストエフスキーの方が高く評価される場合が多いような気がする。おそらく均整のとれたトルストイに比べてあのバロック的な異形性が評価されるのだと思うが、私はトルストイの方が好きだ。ミラン・クンデラもどうやらトルストイの方が好きなようで、『存在の耐えられない軽さ』のトマーシュとテレザは『アンナ・カレーニナ』をきっかけに知り合うし、二人の犬はカレーニンと名づけられる。エッセーでもあちこちでトルストイの良さについて書いている。トルストイ好きの私としてはとっても嬉しい。




















文章うまいですねー。はっきり言って、そこいらの大学教授や作家よりも上手ですよ。ひょっとしたらどこかの大学の先生かな、とプロフィールを見てみたら、システム・エンジニアでいらっしゃるんですね。ぼくはばりばりの文系人間ですが、こんな文章は書けません。羨ましい限りです。
『戦争と平和』は何年か前に読みました。一般的には『アンナ・カレーニナ』の方が評価は高いようですが、単純なおもしろさは『戦争と平和』の勝ちかもしれませんね。
過分なお褒めにあずかり恐縮です。でもあちこち読まれるとだんだんボロが出てくると思います…
『アンナ・カレーニナ』も良いですね。ただあまりに可哀想な話なので読んだあとちょっとへこみましたが。個人的には『戦争と平和』と甲乙つけがたいです。
ネットでは「長い!挫折した!」って声がやたら多いですがトルストイは一節の区切りが短いので実は凄く読みやすいです。(ドストエフスキーはやたらめったら一節が長い!)一日四~五節ゆっくり読み進めて、続きを読むときは前に起こったことを思い出すって感じです。エンタメ系の小説を一気読みする感覚で読もうとすると気が遠くなりますが。
「アンナ・カレーニナ」も大好きでこれも二回読んでます。三回目も読みたい。作家の池澤夏樹が「単なるメロドラマ」とか評してたのでこいつの文章は二度と読むまい!と思いましたよ…
ego_danceさんはとんでもなく沢山本を読んでますね。おかげで特にラテンアメリカ系の作家に興味が湧きました。今の所ガルシア・マルケスの「予告された殺人の記録」しか読んだ事がありません。
ジョージ・オーウェルの「1984年」は読まれましたか?載ってなかったような。五十音順の索引とかあると便利なんですが。
オーウェルの「1984年」は読んでません。面白いですか? 五十音順の索引とかも、付けた方がいいかなとは思うんですが、整理するのがどうも面倒で……。
ドストは「カラマーゾフ」や「罪と罰」は確かに面白い・凄い場面は部分部分であるけど全体のまとまりは結構バラバラ、という印象です。(個人的には「地下室の手記」「虐げられた人々」の方が好き。こっちは登場人物が限定されてて読みやすい)
特に「カラマーゾフ」は少々持ち上げられすぎじゃないかなあ?確かに大審問官とかキリスト教のニーチェ的解釈のエッセンスみたいな凄い章はあるけど。
なによりドストは必殺の「登場人物のあり得ない長広舌(笑)」と読みにくさ爆発(そこが良いんだけど)なのに何故かやたらとドスト、ドストと言われてトルストイは無きが如しなのが悲しいです…読みやすいのに…
オーウェルの「1984年」もキャンペーンの一環。これも名前だけは良く知られていていろいろ引用されるけど中身を読まないで吹聴するのは恥ずかしい、という時代錯誤的教養主義から読み始めましたが、あにはからんや。普通に面白い!
今ではこういうネタそのものは様々なバリエーションが作られて「別に…」みたいな沢尻エリカ的冷笑を受けるかもしれませんが、単なる反ファシズム思想小説としてだけでなく、恋愛小説、拷問・洗脳小説(!)としてもぐいぐい読ませます。
これは翻訳版を二回読んで英語原文の本も買っていつか読もうと待機中です。ハヤカワの新訳など時間があったらどうでしょうか。
「1984年」は面白そうなので、ハヤカワ版を入手して読んでみたいと思います。ご推薦ありがとうございました。
こういう「名前だけ知られてる作品」はあらすじだけで読んだ気になってると実際は全然印象が違うことがあるんですよね。
分野が違うけど小津安二郎の「東京物語」も先入観では「古き良き日本人達の失われた美徳」が描かれてる善良かつ退屈な映画だと思い込んで嫌々観始めたんですが…
…なんだ、すっげえ現代的で面白いじゃん。やたら殺伐としてるところがイイ。「名作」というのは=つまらない映画という概念を打ち壊してくれました。(でも世の中的にはこういう意味で「名作」と呼ばれてるわけじゃないような…)もう観たかもしれませんがおススメです。
勢いに乗って小津の他の作品を観たけど…あれ…なんか同工異曲の「娘がなかなか結婚しなくて周囲がやきもき話」がやたら多いな…残念ながらこういうモチーフに時代性の限界を感じる。「晩秋」とかきつかったなー(でも小津作品は出る女優が全員当時のミス日本みたいな美人ばっかでそういう意味では眼福)
人(作品)は見た目(あらすじ)で判断してはいけません、ということで。