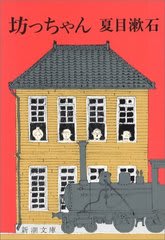
『坊っちゃん』 夏目漱石 ☆☆☆☆
夏目漱石はあまりちゃんと読んだことがないが、『坊っちゃん』だけは子供の頃に読んだ。最近は知らないが、昔の子供はみんな『坊っちゃん』を読んだものである(<本当か?)。『車輪の下』と『坊っちゃん』と『蜘蛛の糸』は子供の必読書だった。で、『坊っちゃん』をおとなになって読み返したのは今回が初めてである。
もちろん夏目漱石は押しも押されぬ大文豪だが、『坊っちゃん』は文学的にはあまり高く評価されていないようだ。内容的にも大衆小説的だし、勧善懲悪、子供向け、といった印象が強いからだろう。その分TVドラマや映画やアニメにはなりやすいし、子供が読んでも面白い。けれども今回読んでみて、やはりそこは夏目漱石、なかなか侮れないものがあると感じた。
まず勧善懲悪という点についてだけれども、確かに主人公の坊っちゃんは曲がったことが嫌いな正義漢で、やはり人情に篤い山嵐と一緒に腹黒い赤シャツと野だいこをこらしめる。しかし解説にもある通り、被害者であるうらなりは結局僻地へ飛ばされてしまい、婚約者だったマドンナとは復縁できないし、おそらくこのまま赤シャツに取られてしまうと思われる。また坊っちゃんと山嵐が学校を辞めてしまう一方で、赤シャツと野だいこは現在の地位を維持、というよりますますのさばっていくことが予想される。決して悪が滅びて正義が栄えたわけではないのである。坊っちゃんと山嵐は、いってみれば暴力でケチな憂さ晴らしをしたに過ぎない(解説では坊っちゃんと山嵐を敗北者と呼んでいる)。本当に勧善懲悪ならば、赤シャツと野だいこは失脚し、うらなりとマドンナは最終的に結ばれなければ嘘だろう。そういう意味では、この小説は実は勧善懲悪になっていないのである。
にもかかわらず、読者はこの結末で確かに爽快感を覚える。というより、この物語全体から爽快感を得る。これは勧善懲悪というより、やはり坊っちゃんのキャラクターによるものだ。現実に卑劣な権力者を敗北させるのは難しい、気性がまっすぐなだけの若輩者にとっては尚更である。この小説が呈示するのはそういう絵空事の勧善懲悪ではなく、坊っちゃんというキャラクターそのものが持つ「救い」である。
また、今回『坊っちゃん』を再読して感じたことが大きく二つある。一つは、「坊っちゃん」の一人称小説である本書には驚くほど近代の理知主義とイデオロギー偏重への罵倒が満ち満ちているということ。もう一つは、坊っちゃんと清の関係である。
前者は一読して明らかな本書の特徴で、坊っちゃんはとにかく怒ってばかりいる。生徒にいたずらされては怒り、校長の遠まわしな注意の仕方に怒り、赤シャツの姦計に怒り、野だいこの卑屈に怒り、山嵐の頑固に怒る。その度に江戸っ子の啖呵にも似た罵倒が迸る。彼の罵倒の対象となるのは卑怯であり男らしくない振る舞いであり、インテリの保身であり、打算であり、そうしたすべてを都合よく正当化する理屈である。そこには根本に、イデオロギーや論理そのものに対する不信感、あるいは嫌悪がある。近代そのものへの嫌悪と言い換えてもいい。もちろん嫌悪するだけでなく、近代合理主義を超える価値観を坊っちゃんはすでに体得している。解説に「坊っちゃんは山嵐を従えて、近代の向こう側へ疾走していく」との記述があるが、そういう意味でこれはまったく正しい。
ではイデオロギーや論理の代わりに坊っちゃんを支えるものとは何か。人と人との情の中から生まれてくる倫理である。ここで二つ目の、清との関係性がクローズアップされてくる。清は小説の冒頭部分と最後の部分、いわばプロローグとエピローグ部分に登場するだけで、坊っちゃんが学校の教員を勤めるメイン・プロット部分には登場しない。だから昔読んだ時はちょっとした脇役ぐらいにしか思わなかったが、大人になって読んでみると、山嵐や赤シャツよりはるかに重要なキャラクターであることが分かる。彼女こそが坊っちゃんの倫理、そして小説全体の倫理を創り出し、支えるキーパーソンなのである。
坊っちゃんが「悪いことをしなければいいんでしょう」と素朴に言う時、その世間知らずを赤シャツは嘲笑する。しかし清だったら感心する、と坊っちゃんは独白する。清は坊っちゃんがいくらいたずらをして周りから迷惑がられても、彼をまっすぐないい気性だと言って褒める。そして両親以上に彼を愛する。彼が四国に赴任する時には、もう会えないかも知れませんと言って涙を流す。彼女は決して頭がいい女性ではないが、人間の装飾には目もくれず本質を直視する能力を持っている。それは打算と功利を旨とする近代的合理主義者や、詭弁によってあらゆる価値を相対化するイデオローグからは愚直と馬鹿にされつつも、実はそれらを超えている。坊っちゃんはそれを知っているから、自信に満ちた一人称でそれらをぶった切っていくのだ。清は本書の屋台骨であり、作者が本当に親近感をおぼえているのは坊っちゃんよりむしろ清の方かも知れない。タイトルの『坊っちゃん』が清視点の呼称であることも、そのことを裏付けているように思える。
ところで、うらなりのいいなずけであり赤シャツの横恋慕の対象であるマドンナは、『坊っちゃん』が映像化される時には必ずヒロイン扱いとなる重要な役柄であるにもかかわらず、この原作ではいやにぞんざいに扱われている、というか、まったく重きが置かれていない。そもそも一言もセリフがなく、従ってその本心も分からない。彼女はうらなりを愛しつつもいやいや赤シャツとつきあったのか、それとも嬉々として赤シャツに乗り換えたのか、全然分からない。これも、いわゆる勧善懲悪の娯楽読み物として本書を見た時、妙に違和感を覚える部分である。
夏目漱石はあまりちゃんと読んだことがないが、『坊っちゃん』だけは子供の頃に読んだ。最近は知らないが、昔の子供はみんな『坊っちゃん』を読んだものである(<本当か?)。『車輪の下』と『坊っちゃん』と『蜘蛛の糸』は子供の必読書だった。で、『坊っちゃん』をおとなになって読み返したのは今回が初めてである。
もちろん夏目漱石は押しも押されぬ大文豪だが、『坊っちゃん』は文学的にはあまり高く評価されていないようだ。内容的にも大衆小説的だし、勧善懲悪、子供向け、といった印象が強いからだろう。その分TVドラマや映画やアニメにはなりやすいし、子供が読んでも面白い。けれども今回読んでみて、やはりそこは夏目漱石、なかなか侮れないものがあると感じた。
まず勧善懲悪という点についてだけれども、確かに主人公の坊っちゃんは曲がったことが嫌いな正義漢で、やはり人情に篤い山嵐と一緒に腹黒い赤シャツと野だいこをこらしめる。しかし解説にもある通り、被害者であるうらなりは結局僻地へ飛ばされてしまい、婚約者だったマドンナとは復縁できないし、おそらくこのまま赤シャツに取られてしまうと思われる。また坊っちゃんと山嵐が学校を辞めてしまう一方で、赤シャツと野だいこは現在の地位を維持、というよりますますのさばっていくことが予想される。決して悪が滅びて正義が栄えたわけではないのである。坊っちゃんと山嵐は、いってみれば暴力でケチな憂さ晴らしをしたに過ぎない(解説では坊っちゃんと山嵐を敗北者と呼んでいる)。本当に勧善懲悪ならば、赤シャツと野だいこは失脚し、うらなりとマドンナは最終的に結ばれなければ嘘だろう。そういう意味では、この小説は実は勧善懲悪になっていないのである。
にもかかわらず、読者はこの結末で確かに爽快感を覚える。というより、この物語全体から爽快感を得る。これは勧善懲悪というより、やはり坊っちゃんのキャラクターによるものだ。現実に卑劣な権力者を敗北させるのは難しい、気性がまっすぐなだけの若輩者にとっては尚更である。この小説が呈示するのはそういう絵空事の勧善懲悪ではなく、坊っちゃんというキャラクターそのものが持つ「救い」である。
また、今回『坊っちゃん』を再読して感じたことが大きく二つある。一つは、「坊っちゃん」の一人称小説である本書には驚くほど近代の理知主義とイデオロギー偏重への罵倒が満ち満ちているということ。もう一つは、坊っちゃんと清の関係である。
前者は一読して明らかな本書の特徴で、坊っちゃんはとにかく怒ってばかりいる。生徒にいたずらされては怒り、校長の遠まわしな注意の仕方に怒り、赤シャツの姦計に怒り、野だいこの卑屈に怒り、山嵐の頑固に怒る。その度に江戸っ子の啖呵にも似た罵倒が迸る。彼の罵倒の対象となるのは卑怯であり男らしくない振る舞いであり、インテリの保身であり、打算であり、そうしたすべてを都合よく正当化する理屈である。そこには根本に、イデオロギーや論理そのものに対する不信感、あるいは嫌悪がある。近代そのものへの嫌悪と言い換えてもいい。もちろん嫌悪するだけでなく、近代合理主義を超える価値観を坊っちゃんはすでに体得している。解説に「坊っちゃんは山嵐を従えて、近代の向こう側へ疾走していく」との記述があるが、そういう意味でこれはまったく正しい。
ではイデオロギーや論理の代わりに坊っちゃんを支えるものとは何か。人と人との情の中から生まれてくる倫理である。ここで二つ目の、清との関係性がクローズアップされてくる。清は小説の冒頭部分と最後の部分、いわばプロローグとエピローグ部分に登場するだけで、坊っちゃんが学校の教員を勤めるメイン・プロット部分には登場しない。だから昔読んだ時はちょっとした脇役ぐらいにしか思わなかったが、大人になって読んでみると、山嵐や赤シャツよりはるかに重要なキャラクターであることが分かる。彼女こそが坊っちゃんの倫理、そして小説全体の倫理を創り出し、支えるキーパーソンなのである。
坊っちゃんが「悪いことをしなければいいんでしょう」と素朴に言う時、その世間知らずを赤シャツは嘲笑する。しかし清だったら感心する、と坊っちゃんは独白する。清は坊っちゃんがいくらいたずらをして周りから迷惑がられても、彼をまっすぐないい気性だと言って褒める。そして両親以上に彼を愛する。彼が四国に赴任する時には、もう会えないかも知れませんと言って涙を流す。彼女は決して頭がいい女性ではないが、人間の装飾には目もくれず本質を直視する能力を持っている。それは打算と功利を旨とする近代的合理主義者や、詭弁によってあらゆる価値を相対化するイデオローグからは愚直と馬鹿にされつつも、実はそれらを超えている。坊っちゃんはそれを知っているから、自信に満ちた一人称でそれらをぶった切っていくのだ。清は本書の屋台骨であり、作者が本当に親近感をおぼえているのは坊っちゃんよりむしろ清の方かも知れない。タイトルの『坊っちゃん』が清視点の呼称であることも、そのことを裏付けているように思える。
ところで、うらなりのいいなずけであり赤シャツの横恋慕の対象であるマドンナは、『坊っちゃん』が映像化される時には必ずヒロイン扱いとなる重要な役柄であるにもかかわらず、この原作ではいやにぞんざいに扱われている、というか、まったく重きが置かれていない。そもそも一言もセリフがなく、従ってその本心も分からない。彼女はうらなりを愛しつつもいやいや赤シャツとつきあったのか、それとも嬉々として赤シャツに乗り換えたのか、全然分からない。これも、いわゆる勧善懲悪の娯楽読み物として本書を見た時、妙に違和感を覚える部分である。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます