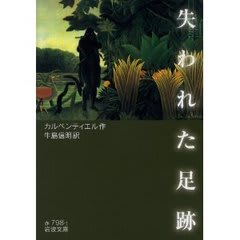
『失われた足跡』 カルペンティエル ☆☆☆☆☆
昔ハードカバーで所有していた『失われた足跡/時との戦い』が人に貸したまま行方不明になった時、どれだけ貸したことを悔やんだか知れない。その時すでに絶版になっていたのだ。しかも、私はまだ斜め読みしただけでちゃんと読んでいなかった。借りた本を返さない人間が世の中にはいるので、すでに絶版になっている本を他人に貸してはいけないということを学んだのだった。
その『失われた足跡』がようやく文庫で出たので、すかさず購入。一応再読のはずだが、まったく内容を覚えていなかった。カルペンティエルといえば『この世の王国』が大好きで何度も読んでいるけれども、あれよりこっちの方が読みづらく、噛み砕くのに手間がかかる感じだ。理由は文体がより抽象的であること、そして『この世の王国』では顕著だった物語性とロマネスクが後退していること。ただしあくまで比較すればの話で、ラテンアメリカ文学独特のアクションの豊富さと奔放な想像力は充分に盛り込まれている。
あるいは、幻想の種類がロマネスク志向ではなく、より形而上学志向になっていると言い換えてもいい。その分、小説としての凄みは増している。本書は、楽器を探す目的で南米のとある国を訪れた音楽家が主人公。妻は女優で公演旅行に出ている。音楽家はガールフレンドを伴って南米を訪れ、最初はバケーション気分に浸っているが、やがてさまざまな異常な、原型的な事件に遭遇する。まずはクーデター発生、ホテルのそばで銃撃戦となり、ホテル客が実際に死亡する。楽器探索の旅に出た後はさまざまな廃墟、宗教的な儀式、あるいは途方もない自然現象などを目の当たりにする。途方もない自然現象とは、たとえば蝶の大群が空を覆ったせいで夜が明けなくなる、などである。ラテンアメリカ文学のマジックリアリズム全開だ。伴っていたガールフレンドは文明人の脆さゆえにみるみる衰弱し、旅から脱落する。
更に旅を続けるうちに、主人公は次第に歴史を遡っていく感覚に捉われる。音楽の誕生をも目撃した彼は、ついに始原の村へと到着する。そこは天地創造直後の世界で、現代では絶滅してしまったはずの原始の動物が生息していた。もはや現実と幻想が渾然一体である。主人公はその始原の村である女と幸福な生活を送るが、創作意欲に駆られて作曲に打ち込んでいると、すぐに楽譜を書き付ける紙がなくなる。文明から離れられない自分と原始世界への憧れのギャップに苦しむ彼は、同時に村における原始的な宗教や刑罰の形成を見て、疑念と不安にとりつかれる。その時ちょうど救援隊が出現し、彼は一旦文明社会へ戻ることを決意する。
が、文明社会に戻った彼を待っていたのは、あらゆる種類の虚妄とスキャンダルだった。最初は生還した冒険者として有名になった彼は妻から告訴され、たちまちスキャンダルと裁判沙汰でぼろぼろになる。当初の予定通り、彼はなんとかあの始原の村へ戻ろうとするが、どうしても帰り道を発見することができない。やがて彼は、一度失われた楽園は二度と取り戻せないことを知るのだった。
異様な物語である。夢のようだが秩序があり、幻想のようだが厳しいほどに歴史的で、それでいてどんな幻想譚よりも幻覚的だ。さっき文体が抽象的と書いたが、正確には抽象的なレトリックとデフォルメされた具象的なレトリックが入り乱れ、読者の現実認識をじわじわ解体していくような奇怪さがある。妙に晦渋だと思っていると、ホテルのクーデター場面ではコメディかと思うほどデフォルメされたアクションが頻発する。今思うとこうやって作者は、現実でも幻想でもない、その境界線すら存在しない、別の次元の虚構空間を読者のために準備しつつあったのである。
こうして読者はカルペンティエルの魔術的文体によって、文明と現代社会の上っ面が徹底的に剥ぎ取られた原初の世界へと連れ去られる。それは生きることの神秘が剥き出しのまま存在する世界、生きるということの意味が完全に再定義されなければならない世界である。魔術的であり神秘的であり、そして多分、きわめて宗教的な読書体験だ。ここで宗教的というのはキリスト教的とか仏教的ということではなく、原初の、剥き出しの世界への畏れを呼び覚ますという意味の「宗教的」である。
自分の世界観に強烈な揺さぶりをかけられているような不安感とともに読み進めていくと、主人公は一旦その世界に足を踏み入れ、そこに留まる決心をし、しかるのちにそれを失ってしまう。楽園は発見され、そしてあらためて失われる。根源的な人間のトラウマがここにはある。しかしその楽園も完全に平和で牧歌的な世界ではなく、宗教や刑罰などの人間社会の萌芽が不穏にうごめき、ざわついている世界だ。何事も定かではない。そしてまた、楽譜を書く紙がなければいてもたってもいられなくなる文明人がそこで生きていくためには、自らが何か別のものに変化しなければならないのではないか、という深甚な不安もある。
めまいを誘うような読書体験。カルペンティエルが作り出したのはそれだ。始原の世界に向かって歴史を遡るとともに、人間の深層心理の奥底へと降りていくような体験である。薄っぺらい意味ではなく真に神話的であり、魔術的文学と呼ぶにふさわしい、驚異の物語である。
昔ハードカバーで所有していた『失われた足跡/時との戦い』が人に貸したまま行方不明になった時、どれだけ貸したことを悔やんだか知れない。その時すでに絶版になっていたのだ。しかも、私はまだ斜め読みしただけでちゃんと読んでいなかった。借りた本を返さない人間が世の中にはいるので、すでに絶版になっている本を他人に貸してはいけないということを学んだのだった。
その『失われた足跡』がようやく文庫で出たので、すかさず購入。一応再読のはずだが、まったく内容を覚えていなかった。カルペンティエルといえば『この世の王国』が大好きで何度も読んでいるけれども、あれよりこっちの方が読みづらく、噛み砕くのに手間がかかる感じだ。理由は文体がより抽象的であること、そして『この世の王国』では顕著だった物語性とロマネスクが後退していること。ただしあくまで比較すればの話で、ラテンアメリカ文学独特のアクションの豊富さと奔放な想像力は充分に盛り込まれている。
あるいは、幻想の種類がロマネスク志向ではなく、より形而上学志向になっていると言い換えてもいい。その分、小説としての凄みは増している。本書は、楽器を探す目的で南米のとある国を訪れた音楽家が主人公。妻は女優で公演旅行に出ている。音楽家はガールフレンドを伴って南米を訪れ、最初はバケーション気分に浸っているが、やがてさまざまな異常な、原型的な事件に遭遇する。まずはクーデター発生、ホテルのそばで銃撃戦となり、ホテル客が実際に死亡する。楽器探索の旅に出た後はさまざまな廃墟、宗教的な儀式、あるいは途方もない自然現象などを目の当たりにする。途方もない自然現象とは、たとえば蝶の大群が空を覆ったせいで夜が明けなくなる、などである。ラテンアメリカ文学のマジックリアリズム全開だ。伴っていたガールフレンドは文明人の脆さゆえにみるみる衰弱し、旅から脱落する。
更に旅を続けるうちに、主人公は次第に歴史を遡っていく感覚に捉われる。音楽の誕生をも目撃した彼は、ついに始原の村へと到着する。そこは天地創造直後の世界で、現代では絶滅してしまったはずの原始の動物が生息していた。もはや現実と幻想が渾然一体である。主人公はその始原の村である女と幸福な生活を送るが、創作意欲に駆られて作曲に打ち込んでいると、すぐに楽譜を書き付ける紙がなくなる。文明から離れられない自分と原始世界への憧れのギャップに苦しむ彼は、同時に村における原始的な宗教や刑罰の形成を見て、疑念と不安にとりつかれる。その時ちょうど救援隊が出現し、彼は一旦文明社会へ戻ることを決意する。
が、文明社会に戻った彼を待っていたのは、あらゆる種類の虚妄とスキャンダルだった。最初は生還した冒険者として有名になった彼は妻から告訴され、たちまちスキャンダルと裁判沙汰でぼろぼろになる。当初の予定通り、彼はなんとかあの始原の村へ戻ろうとするが、どうしても帰り道を発見することができない。やがて彼は、一度失われた楽園は二度と取り戻せないことを知るのだった。
異様な物語である。夢のようだが秩序があり、幻想のようだが厳しいほどに歴史的で、それでいてどんな幻想譚よりも幻覚的だ。さっき文体が抽象的と書いたが、正確には抽象的なレトリックとデフォルメされた具象的なレトリックが入り乱れ、読者の現実認識をじわじわ解体していくような奇怪さがある。妙に晦渋だと思っていると、ホテルのクーデター場面ではコメディかと思うほどデフォルメされたアクションが頻発する。今思うとこうやって作者は、現実でも幻想でもない、その境界線すら存在しない、別の次元の虚構空間を読者のために準備しつつあったのである。
こうして読者はカルペンティエルの魔術的文体によって、文明と現代社会の上っ面が徹底的に剥ぎ取られた原初の世界へと連れ去られる。それは生きることの神秘が剥き出しのまま存在する世界、生きるということの意味が完全に再定義されなければならない世界である。魔術的であり神秘的であり、そして多分、きわめて宗教的な読書体験だ。ここで宗教的というのはキリスト教的とか仏教的ということではなく、原初の、剥き出しの世界への畏れを呼び覚ますという意味の「宗教的」である。
自分の世界観に強烈な揺さぶりをかけられているような不安感とともに読み進めていくと、主人公は一旦その世界に足を踏み入れ、そこに留まる決心をし、しかるのちにそれを失ってしまう。楽園は発見され、そしてあらためて失われる。根源的な人間のトラウマがここにはある。しかしその楽園も完全に平和で牧歌的な世界ではなく、宗教や刑罰などの人間社会の萌芽が不穏にうごめき、ざわついている世界だ。何事も定かではない。そしてまた、楽譜を書く紙がなければいてもたってもいられなくなる文明人がそこで生きていくためには、自らが何か別のものに変化しなければならないのではないか、という深甚な不安もある。
めまいを誘うような読書体験。カルペンティエルが作り出したのはそれだ。始原の世界に向かって歴史を遡るとともに、人間の深層心理の奥底へと降りていくような体験である。薄っぺらい意味ではなく真に神話的であり、魔術的文学と呼ぶにふさわしい、驚異の物語である。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます