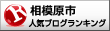今年もやってきました!きのこ観察。
いや〜、麻溝公園であじさい見物し、相模原公園で花しょうぶ鑑賞し、例年ならば訪問したら合わせて相模原公園を散策していたのに、今年4月末に左足指を骨折したため、行動に制限かかりまして。せいぜい1時間ちょいしか歩けなかったんですよ。先日6月23日に鎌倉散策をした夜、ギブス代わりに足指に巻いていたサージカルテープやファイテンのチタンテープを剥がしまして。お試し散策してみよう!と出かけましたらば。あじさいも花しょうぶも今年は去年より早めに見頃となってたから、予想はしてたけど。案の定、きのこも出現してました。
トップ画像は形状からして判別が簡単なノウタケです。ホコリタケ科のきのこで、若い時は食用できます。林内の草地に出ます。この日は2本見つけました。トップ画像は2本のうち傘の直径10センチ超えの大きいきのこです。

続きましてはたぶんカイガラタケ。普通は朽ちつつある木からにょきっと群生して出てて、上の画像のように丸い形になることはほとんどないきのこです。
サルノコシカケ科のきのこで、残念ながら食べられません。こいつは林を歩いてるとよく見かけます。広葉樹、針葉樹の朽木や倒木に夏〜秋に生えます。

既に老菌になってます。きのこ図鑑を見ながら記事を書いてますが、判別しづらいなあ。傘の裏がひだになってないからイグチ系だと思うけども?
もしかしたらアワタケかも?アワタケは夏から秋に雑木林や路傍の林地に発生します。けどきのこの色がイマイチ違うんだよね。アワタケはもっと黄色です。しかし老化してこの色に変わった場合もあるのですよ。きのこはどんどん色や形が変わっていくので、図鑑とにらめっこしても簡単に同定できないんだよ。

ピンボケ画像ですみません。きのこは薄暗い場所に生えてるので、シャッタースピードが遅くなりがちでピンボケしやすく、この日もピンボケ画像を増産してしまいました。上の画像は中ではきのこの種類がまだわかる画像です。これはハリガネオチバタケ。キシメジ科のきのこです。食べられません。夏〜秋に広葉樹林の落ち葉の上に群生する性質があるのですが、発見したのは単独で出てました。これから仲間が出てくるのでしょうか?

よくあるきのこ。そのくせ種類が多いので特定するのは面倒臭い奴。たぶんクヌギタケだと思うけども?クヌギタケもキシメジ科。こいつはたべれるきのこです。私は観察のみで採取はしないので是が非でもきのこの特定はできませんが。何しろきのこは毒持ちの種類もあるのですよ。万一を回避するには取らないのが一番なのだ。あ。どこかから総ツッコミが聞こえてきたけども空耳です。
ちなみにクヌギタケの名前の通り、ナラ・クヌギの切り株や枯れ木の上に多数束になって生えます。そして、夏〜秋に発生するのできのこ観察に出かけて昆虫採集愛好家に観察場所を壊されてる場面に出会うきのこでもあります。何しろきのこ観察と昆虫採集の狩場が同じなので早い者勝ちなのだよ。

さて、相模原公園の東の高い散策路から降りてメタセコイア並木に到着。例年7月の初めに上の画像左に写ってるツガかな?生垣の根元にチャナメツムタケが顔を出すのですが??
期待して歩いてみたけど見当たりませんでした。

噴水を眺める。

そして反対側の斜面の上の散策路へ。ここの散策路沿いに額アジサイが植栽してあるのだ。

背後の林の中の散策路へ移動。

あ!?でかい!軽くピンボケになってしまいましたが、たぶんチシオハツです。画像をよく見ると奥に向かって転々と5個出てますね。きのこは地下で菌糸が繋がってるので、1個見つけると次々見つかることが多いのです。ベニタケ科のきのこで、夏〜秋、マツ林かマツの混じる雑木林に発生します。食べられる。ちなみに、相模原公園でこの日一番よく観察出来たきのこです。林の中のあちこちに混じる赤はとても目立ってました。

これはよくわからん!木の幹から小さいのがにょきにょき出てたので撮影。

さて、私が一番観察を楽しみにしてるポイントへやってきました。思ったより草むらが長く伸びてるのがちょっと心配だ。きのこより草の方が高いと見つけにくくなるんだよね。(続く)
今年5月よりgoo blogの有料会員になって、あれこれ縛りが減りました。なのでカテゴリーを増設。新しく【きのこ観察】を設置しました。以前のきのこの記事も順次こちらのカテゴリーに移動させます。