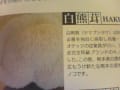熊本では、阿蘇バイオテエックが中心となり四社が役割分担する農商工連携が認定されている。
その内容は、写真の希少品種「ヤマブシタケ」の安定栽培方法を確立すると共に、加工販売方法の確立、販路の開拓を目指すものであるが、農商工連携はそのための「開発費用の獲得+多様な販促+商材開発」を支える仕組みとなる。
ただブランディングについては、しっかりとした戦略のもと挑まなければならないと開発室の室長は説く。ブランディング戦略は・健康増進戦略・エビデンス戦略・一貫生産戦略からなり、トータルで底上げして盛り上げるスキームを構築されている。
その内容は、写真の希少品種「ヤマブシタケ」の安定栽培方法を確立すると共に、加工販売方法の確立、販路の開拓を目指すものであるが、農商工連携はそのための「開発費用の獲得+多様な販促+商材開発」を支える仕組みとなる。
ただブランディングについては、しっかりとした戦略のもと挑まなければならないと開発室の室長は説く。ブランディング戦略は・健康増進戦略・エビデンス戦略・一貫生産戦略からなり、トータルで底上げして盛り上げるスキームを構築されている。