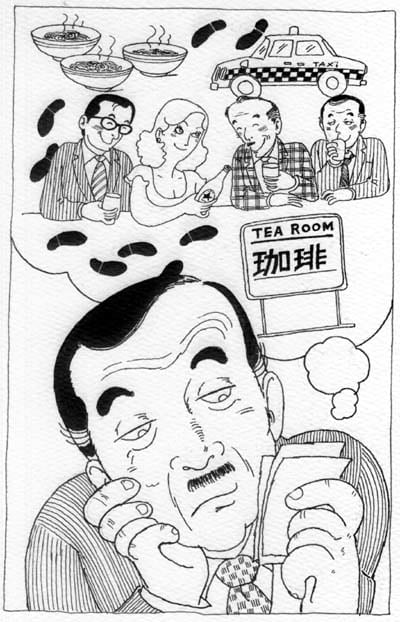時代物の絵を描くようになったのは、1976年頃に都筑道夫さんの「なめくじ長屋捕物帳」の挿し絵を頼まれたのがきっかけだったが、もともと古典落語の世界に興味があって、江戸の資料を集めてはいた。、
江戸のことを知りたくていろいろ本を買ったが、私には致命的な欠陥があった。
それは名古屋から出て来た私には広すぎる東京の地理は不案内で、それゆえに出無精(デブ症ではない)になって、仕事の用のないところには出かけたことがなく、東京の地名は点でしか把握出来ず、江戸の勉強をしていても江戸の全体像を描くことが出来ていなかった。
*例えば古典落語の「百川」という噺でも百川と言う料亭のあった日本橋に当時魚河岸があったこと、噺の中に出てくる長谷川町などの位置関係が把握出来ていればもっと江戸の理解も早かっただろうが、あいにく仕事では日本橋にも長谷川町にも行ったことがなかった。







挿し絵などを描くにあたってさほどの資料を必要とはしなかったが、江戸時代には何故か惹かれるものがあって、老後はこれらの資料を読んで過ごそうと思い、仕事には必要以上の資料を持っていた。
しかしよく考えてみると、私はすでに一般的には<老後>といわれる年代になったが、まだまだ仕事に追われて本を読んで暮らすと言うわけにもいかず、そのうえ昨今は女性と活字を追う気力に欠けて来た。
昨年仕事場の移転に伴い、これらの資料はこのまま死蔵させるより必要とする人の手に渡った方がいいのだろうという判断でちょっと切ない思いをしたが、文庫本だけをを残してあとは古書店に引き取ってもらった。
江戸のことを知りたくていろいろ本を買ったが、私には致命的な欠陥があった。
それは名古屋から出て来た私には広すぎる東京の地理は不案内で、それゆえに出無精(デブ症ではない)になって、仕事の用のないところには出かけたことがなく、東京の地名は点でしか把握出来ず、江戸の勉強をしていても江戸の全体像を描くことが出来ていなかった。
*例えば古典落語の「百川」という噺でも百川と言う料亭のあった日本橋に当時魚河岸があったこと、噺の中に出てくる長谷川町などの位置関係が把握出来ていればもっと江戸の理解も早かっただろうが、あいにく仕事では日本橋にも長谷川町にも行ったことがなかった。







挿し絵などを描くにあたってさほどの資料を必要とはしなかったが、江戸時代には何故か惹かれるものがあって、老後はこれらの資料を読んで過ごそうと思い、仕事には必要以上の資料を持っていた。
しかしよく考えてみると、私はすでに一般的には<老後>といわれる年代になったが、まだまだ仕事に追われて本を読んで暮らすと言うわけにもいかず、そのうえ昨今は女性と活字を追う気力に欠けて来た。
昨年仕事場の移転に伴い、これらの資料はこのまま死蔵させるより必要とする人の手に渡った方がいいのだろうという判断でちょっと切ない思いをしたが、文庫本だけをを残してあとは古書店に引き取ってもらった。