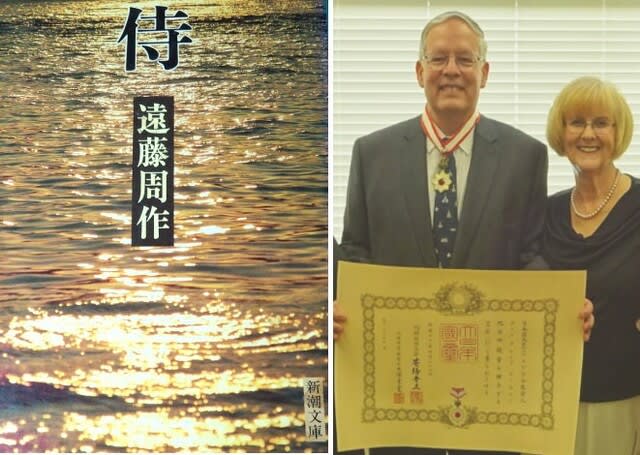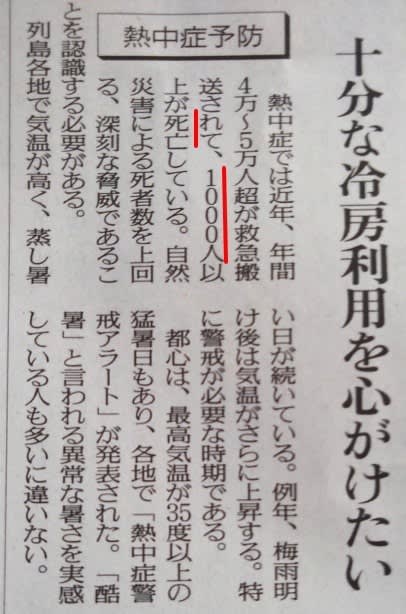きのうは、
30℃の夏日だったが、
熱中症予防に
厳重なクーリング対策をして
朝食に教え子から頂いた
菓子類を頂いてから
劇場に出かけた。

コロナ禍の間は
全く行ってないので、
何年ぶりかである。
宮崎作品は、
『風立ちぬ』来
10年ぶりだという。
前作は、
つまらなかった。
今回は、
監督の集大成というが、
評価が分かれてるとのことで、
これまで宮崎作品を全て観て
2冊ほど分析本も上梓したので、
久石 譲とタッグを組んだ
本作の出来栄えは気になった。
結論から言えば、
あまり面白くなかった。
いささか唐突感のある
エンディングに
“おいてけぼり”感を抱いた
観客も少なくなかったかもしれない。
いちおうは「ファンタジー」系の
作品だが、宮崎タッチが
鼻につき過ぎて
食傷気味になった。
それでも、
深層心理学的に分析してみると、
少年が「死者の世界」を訪れ
現実界に戻ってくると
内的な変容(魂の成長)を得る、
という典型的な『冥界往還』物語の
仕立てになっている。
最近、コミック界では
『異世界』物がトレンドになってるが、
その二番煎じ・亜流に乗じた感もある。
物語の出だしは、
病院の大火のシーンから始まり、
それにより少年(中2くらい?)の
「眞人(マヒト)」は、
助けに走って向かうも
無残にも母を失ってしまう。
愛着対象の喪失と
己れが助けられなかった
自責と悔恨の念は
哀しみと共に苦しみをも
彼にもたらす。
ここに思春期の
「癒されるべき魂」
「救われるべき魂」
が提示される。
夢分析で「火事」は
激しい変化の象意でもあり、
彼の尋常ではない形での
内的な変化・成長・発達が
「母の死」から始まるという事が
のっけからシンボライズされている。
時代は戦中で、
父子は母の実家に疎開し、
父は母似の妹と再婚するが、
すでに胎児を宿している。
マヒトにとっては、
「実母の死」「母似の継母の登場」
「母以外の女性を愛する父」
「田舎への転居」「転校」
「やがて生まれる異母同胞」
・・・という、多くの葛藤が
多変数的なストレス因子として
一挙にのしかかる。
実母の急死だけとっても、
ストレス指数は「100/100」点だが、
更なる環境ストレスも加えれば、
思春期の未熟な自我強度では
何らかの心身症が発症しても
まったく不思議ではない。
そう考えれば、
転校直後の「いじめ」ケンカ後に、
自分の頭を石で殴って
大出血するほどの自傷行為も
衝動的・短絡的な病的心理の
アクトアウト(行動化)とも
考えられないでもない。
物語の王道を辿るなら、
翌日に正々堂々と再戦を挑み、
やがて、少年たちのコミュニティに
受け入れられ、めでたしめでたし、
となるものだが、
マヒトは自傷行為という歪んだ
病的な解決により、それを忌避した。
ここには、愛する母に死なれての
自暴自棄心もあるかもしれないが、
無意識下では、虚栄心の強い父や
胎児に関心の強かろう母似の継母への
「承認欲求」が働いての
退行的な自傷行為とも考えられる。
タイトルの
『君たちはどう生きるか』というのは、
思春期の多感で複雑な思いを抱く
一人びとりへの
「あるべきようわ」を問うている。
主人公の「眞人」は、
「まことの人」になる、
「しんの人」になる、
という意味で、
ユング的に言えば
「自己実現」
「個性化の過程」
の物語に相応しい名ではある。
元型的な解釈で見れば、
『英雄の夜の航海』であり、
『死と再生』が
コンステレート(布置)されている。

物語のキーパースンとして
「アオサギ」が登場するが、
その善悪両方を有する
両義的存在は、まさしく、
二つの顔を持つヤヌス神のような
トリックスター的存在である。
思春期クライシスにあるマヒトの
異界への仲介者として相応しいのが、
狂言廻し的なトリックスターなのである。
「サギ」は『象徴事典』では、
「次世代の礎」(代変わり)
「喪」(象徴的な死と再生)
「司祭」(聖なる仲介者)
という多義性がある。
また、群れで登場するペリカンと
同様に、水辺に棲み、
地上・水面・上空を移動でき、
魚を捕食する。
水も魚も
「無意識」の象徴である。
マヒトが体験した異世界は、
大出血するほどの自傷行為で、
側頭葉に外傷性の硬膜外血種が生じ、
圧迫された脳が意識障害を起こして
コーマ(昏睡)時の長い夢か
白昼夢か、妄想を体験した…と、
解釈することもできるが、
そう言っては身も蓋もないだろう(笑)。
マヒトの辿った「こころの旅」は、
『英雄の旅』という元型そのものである。
ここでの「夜の航海」という
異界・冥界の旅は、
無意識世界と同様に
時空が混沌としており、
「A boy meets a girl」
の物語元型は
「母恋い」として変形され
少女(ヒミ)は現世では
マヒトの母「久子」となる。
図らずも若者の「英雄の旅」に
同伴するはめになった
お手伝いで狡猾な老婆のキリは、
異界では雄々しく精悍な漁師
キリコとしてマヒトを救う。
彼女は怪魚を捕獲し、
マヒトにもそれを解体させ
臓物を破裂させる。
このシーンは言語化し難いが、
「妖しい状況を腑分けする」
と解すると、シンボリックな
シーンではあった。

また、マヒトが自ら作った「矢」や
怪魚を解体する「刃物」
そして、終盤でインコ大王が行う
「世界の切断」…といった事物は、
「塔」がファリック(男根)の
シンボルとして描かれているのと合わせて、
「男性性の獲得」という思春期男児の
テーマが見て取れる。
自傷により
いじめっ子との対決を忌避するのは
「女々しい」男の子であり、
いつまでも亡き実母を思慕し
涙で枕を濡らすのも
子どもじみている男の子の姿だが、
異界の旅(英雄の夜の航海)を経て、
「男性性」を獲得し「雄々しくなる」
という小道具(アイテム)としての
「矢」「刃物」「刀」「塔」などが
描かれているように思えた。
少年の英雄譚の切っ掛けとなったのが、
継母ナツコが、何か霊的なものによって
森へ誘われるように
吸いこまれるように
失踪する姿を目撃する事からだった。
そして、自らも、
それを留めようとする老婆キリと共に
木々のトンネルで出来た
長い小道を辿ってゆく。
このシーンでは
『トトロ』のシーンや
その主題歌の歌詞が
彷彿させられた。
小路→森へのパスポート→すてきな冒険
→魔法の扉が開く→不思議な出会い
→幸せがくる…
さて、妊婦の継母ナツコが、
なんでまた、唐突に寝衣姿で
森に迷い込んだのか…。
これには何の説明もない。
外的要因としては、
悪阻(つわり)が酷く、
マタニティ・ブルーの
鬱性の罪業妄想にかられたのではないか…
と察せられた(笑)。
それは、姉の大切な「忘れ形見」に
傷をつけてしまったことへの自責感が、
傷にふれて謝るシーンで描かれている。
その強い罪業意識が
姉に所縁のある森を抜けた塔への
「お詫び参り」へと
身重で病身の彼女を
向かわせたのかもしれない。
そして、マヒトも、いつしか、
母似で血を分けた叔母を
実母と同一視しはじめて、
大火で救えなかった母の
代償行為としてその救済の衝動に
かられたのだろう。
そのメサイア・コンプレックス
(救済者願望)は、
「自らも助かりたい」という
無意識的な欲求も併存している。
また、外的要因として、
ナツコを森へ誘かった
何か霊的なものがあるとすれば、
それは、まさに、この世に
愛児を残して未練を抱いたまま
逝った姉であり、
まだ未熟な少年マヒトの母である
久子(ヒミ)の魂だったのかもしれない。
物語の大団円は、
マヒトは亡き母の少女時代のヒミに会い、
継母ナツコと共に異界・冥界から
無事、帰還する。
そして、戦争は終わり、
マヒトは「ナツコお母さん」と呼び、
一家は新しく生まれた弟と共に
この世の異界的な僻地空間から
日常生活する都市空間へと戻る処で
「めでたしめでたし」
と物語は終幕する。
量子力学的な世界観で記述するなら、
異界はパラレルワールドであって、
「もうひとつの実在する世界」
という解釈もできよう。
量子の世界でも、
夢や無意識界のように
時空は歪んでおり、混沌としている。
あちらの世界の窓から
現世界を覗くシーンは、
『インターステラー』のシーンをも
彷彿させられた。
時系列的には、
戦中から戦後に変わり、
主人公の思春期前期の
アイデンティティ・クライシス
(自我同一性危機)は、
思春期中期に移行して
“かりそめ”ながらも
拡散状態から少しだけ
豆乳にニガリを打ったように
確立へ向かいはじめた。
それは、心・魂の成長、発達であり、
自己実現へと向かっている、
個性化の過程を
着実に雄々しく歩もうとしている
全うな青年男子の
「あるべきようわ」を示している。
本作は、宮崎監督の
戦中へのノスタルジーを描きながらも、
そこには、スマホやゲーム、ネットに
中毒している若者たちや、
腐敗、退廃しきった政財官の
オトナたちへ絶望や危機感を抱く若者へ
「君たちは、どう生きるのか」
という好々爺の老賢者的な
問いかけなのかもしれない。
その意味では、
意義の深い作品とも言えよう。