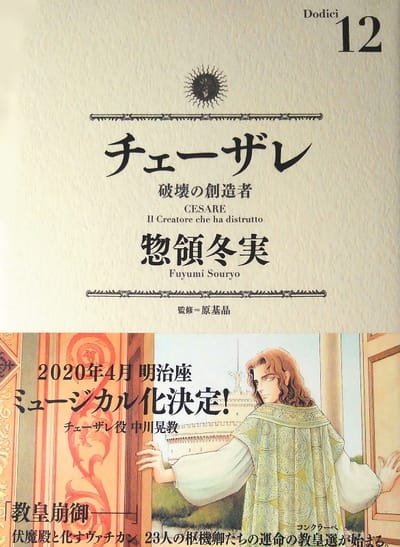録画してあった
『半地下の家族』を観た。
2019のカンヌでの
パルム・ドール受賞作であり、
アカデミー賞も4部門を受賞した。
2.5時間という
長尺物だったが、
前半の詐欺家族の巧妙な
化けぶりに笑わされ、
一転、後半からエンディングまでは
大ドンデン返し・・・と、
ジェットコースター的な
面白さがあった。
韓流ドラマは
『冬ソナ』を皮切りに
歴史物なども
諸々を観てきたので、
登場人物名や
その演技ぶりには馴染みがあり、
達者な演技も十分に楽しめた。

凄惨な結末ではあったが、
途中の若い二人の
仄かなラブストーリーは
なかなか韓流ならではの
胸キュン演出だった。
それを演じたのが、
『奇皇后』(2013)で
主人公の少女時代を
演じていたのは気付かなかった。
吹き替えの山路和弘は
『刑事フォイル』の声で、
好きな神木隆之介も
声優として主役を演じていたのも
よかった。
***
物語を分析的に見るのは
いささか野暮でもあるが、
この「マーダー・ケース」の
異常性、深層心理は奈辺にあるのか
ついつい探ってみたくなる。
富裕層の象徴としての
豪奢なサイドボードと、
その真ん中にポッカリ空いた
虚空のような地下室への入り口は、
見事に象徴的な配置であった。
そこは、我々の
ダークサイドへの通路でもあり、
そこからは少年が目撃したような
「オバケ」が現われもするのである(笑)。
三家族の「愛」が描かれていたが、
それぞれの家族が有する
真善美聖に反する
偽悪醜邪に拠る「綻び」が、
減衰振動の反対現象の
増幅振動し、やがて共振を起こし、
カタストロフィを招来する。
詐欺家族では
長女が犠牲となり、
富裕層家族では
家長が犠牲になり、
元家政婦と秘密の地下暮らしの夫は
両方とも死んでしまう。
悲劇を招いたケースの
「偽悪醜邪」は、
「嘘」「隠匿」「秘密」
「格差」「蔑み」「憎しみ」
「シンプル」
などがキーワードに上がりそうだ。
そして、
なぜか『サクリファイス』という英語が
「犠牲」と「生贄」という
両方の意味で思い浮かんだ。
そう。
亡くなった者たちは、
偽悪醜邪の果ての犠牲者であり、
それらを司(つかさど)る
「魔物」の生贄のように
見えたのである。
悲劇の直接の発端は、
詐欺家族一家が
主人家の留守をいいことに
酒盛りで乱痴気騒ぎをしていた時に
策略で追い出した元家政婦が
尋ねてくることに始まる。
この時、
大雨でずぶ濡れだったことが
なんともシンボリックで
印象的なシーンであった。
それは、
単に嵐の前兆というだけでなく、
「水」や「雨」に象徴される
「無意識」の恐ろしい力が
「意識」による現実世界を
圧倒し、破壊する、ということである。
これからしばらく後には
詐欺家族たちの半地下の住居が
大洪水で呑み込まれる
というシーンが描かれる。
いくらかの酩酊と
エゴ・インフレーションにより、
元家政婦を家に入れてしまったのは、
「その時」の判断や行動を誤った、
いわゆる、「魔がさした」のである。
それは、
心の「間」「隙」に
文字通り「魔」が
侵入することでもある。
そして、
「命運」「運命」が狂うというように
「命」は濁流に「運ばれ」て、
意識の世界は翻弄され、
「死」へと陥落する
観血的悲劇を迎えるのである。
元家政婦の哀願するセリフの
「同業者じゃないですか・・・。
後生ですから…家に入れて下さい・・・」
というのは、
まるで、瓜子姫をさらう
天邪鬼の甘言のようにも聞こえた。
むかし、狐狸庵先生のテキストで
さんざん悪魔について勉強したが、
その折、『エクソシスト』のような
脅かす悪魔は低級で、
ほんとの悪魔は「いないように振る舞い」
なおかつ「人の心地よさに付けこむ」
とあった。
家の施錠を解き、
「境界」の一線を
超えさせたことが、
すべての悲劇の始まりであった。
これが夢分析ならば、
「家」=「自我」「意識の世界」
「超えて侵入するもの」=「シャドウ」
(不幸をもたらす破壊的な無意識の元型)
とセラピストは解釈する。
なので、
「境界を越えないのが大事」
というセリフが、度々
犠牲者の社長が言っていたのは
後になって了解できる。
しかし、
人間関係の境界は守られても、
「臭い」というものは
致し方なく、その境界を
侵襲的に超えてくる。
この物語では、
「臭い」が「格差」「憎しみ」の
メタファーにもなっていた。
そして、それは、
そのまま衝動的な
殺人の動機にさえなったのである。
原題の『寄生虫/Parasite』と
邦題の『半地下の家族』という言葉から、
我われの意識的な自我を
時に操り翻弄し、破滅へと導くこともある
無意識下の元型である「影(シャドウ)」は
誰もが抱えており、
それに対して無自覚すぎると、
かの物語のような悲劇を体験する
・・・という、
現代の箴言のような作品のようにも
心理臨床家には思えた。
衝動殺人をした父に
「寄生」していた「影」とは、
世の不条理や理不尽に翻弄され
なにを商売しても上手くいかない人生と、
一方で、とんとん拍子で事業を成功させている
富裕層社長に対する、また、運命の神に対する、
筆舌に尽くせない葛藤・不満・憤りが
最後に「鬼化」して刃を向けてしまう。
これは、モヤモヤを言語化できず、
自傷他害の行動化(アクト・アウト)する
典型でもある。
流行りの『鬼滅の刃』に倣えば、
我われは、「鬼化」して
人に刃を向けるのではなく、
こころの「鬼」を滅するための
刃を己れ自身に向けねばならないのである。
トランプが煽って
死者まで出した
議事堂占拠事件なぞを観るにつけても
その思いを強くしている。
映画『パラサイト』では、
4人もの殺戮が行われた
凄惨な物語の結末は、
再度、地下に潜入し
息をひそめて生息する父(殺人犯)と
その父の存在の秘密に気付いた
息子(執行猶予中)との
「希望」の灯かりだった。
それは、まるで、
「パンドラの箱」が開いて、
世界に大いなる悲劇と不幸が
飛び出た後、
最後に残ったのが「希望」である、
という神話的元型に酷似していた。
とすれば、
現コロナ禍も
人類の偽悪醜邪に拠るものが
招来したものとすれば、
塗炭の苦しみを味わった後、
「希望」は失われず
其処に在る、ということを
信ずることが、其れもまた、
"希望"なのであろうか。
自らも
ナチの強制収容所の虜囚で、
終戦解放後に
名著『夜と霧』を著した
ヴィクトール・フランクルは、
独自の「実存分析」を唱え、
「希望」や「生き甲斐」こそが、
人を人たらしめて
生かしているものである、
と言っている。


皆川達夫先生の
古いテキストに基づいて、
そのご推薦のルネッサンス期のCDを
ヤフオクやアマゾンで
こつこつと蒐集している。
ルネッサンス初期の
声楽アンサンブルは、
グレゴリオ聖歌を基にしたものが多く、
女性合唱での清澄で深淵な響きは
修道士たちの斉唱とは違った
天国的なスピリチュアリティが感じられ、
こころの中に暗雲が垂れ込みがちな
コロナ禍の今、
一服の清涼剤や安定剤のような
癒しを与えてくれている。

R先生から頂いたお菓子籠に
「牛さん」マシュマロがあり、
可愛いので、よっぽど、
飾りものにしようか迷ったが、
でも食べ物なので、
エーイ! と、
干支を口中に放り込んだ(笑)。
なぜだか、
子どもたちが
幼い頃に流行った
♩『モウモウ・フラダンス』♩
のメロディーと画面が
脳裏に浮かんだ(笑)。

今朝のアサちんに、
すこしばかり
妖艶な表情を視た(笑)。
彼女は、
創作モチベーションを与えくれる
「美」のモチーフでもあり、
アニマであり、女神であり、
スピリチュアル・マドンナでもある。
『半地下の家族』を観た。
2019のカンヌでの
パルム・ドール受賞作であり、
アカデミー賞も4部門を受賞した。
2.5時間という
長尺物だったが、
前半の詐欺家族の巧妙な
化けぶりに笑わされ、
一転、後半からエンディングまでは
大ドンデン返し・・・と、
ジェットコースター的な
面白さがあった。
韓流ドラマは
『冬ソナ』を皮切りに
歴史物なども
諸々を観てきたので、
登場人物名や
その演技ぶりには馴染みがあり、
達者な演技も十分に楽しめた。

凄惨な結末ではあったが、
途中の若い二人の
仄かなラブストーリーは
なかなか韓流ならではの
胸キュン演出だった。
それを演じたのが、
『奇皇后』(2013)で
主人公の少女時代を
演じていたのは気付かなかった。
吹き替えの山路和弘は
『刑事フォイル』の声で、
好きな神木隆之介も
声優として主役を演じていたのも
よかった。
***
物語を分析的に見るのは
いささか野暮でもあるが、
この「マーダー・ケース」の
異常性、深層心理は奈辺にあるのか
ついつい探ってみたくなる。
富裕層の象徴としての
豪奢なサイドボードと、
その真ん中にポッカリ空いた
虚空のような地下室への入り口は、
見事に象徴的な配置であった。
そこは、我々の
ダークサイドへの通路でもあり、
そこからは少年が目撃したような
「オバケ」が現われもするのである(笑)。
三家族の「愛」が描かれていたが、
それぞれの家族が有する
真善美聖に反する
偽悪醜邪に拠る「綻び」が、
減衰振動の反対現象の
増幅振動し、やがて共振を起こし、
カタストロフィを招来する。
詐欺家族では
長女が犠牲となり、
富裕層家族では
家長が犠牲になり、
元家政婦と秘密の地下暮らしの夫は
両方とも死んでしまう。
悲劇を招いたケースの
「偽悪醜邪」は、
「嘘」「隠匿」「秘密」
「格差」「蔑み」「憎しみ」
「シンプル」
などがキーワードに上がりそうだ。
そして、
なぜか『サクリファイス』という英語が
「犠牲」と「生贄」という
両方の意味で思い浮かんだ。
そう。
亡くなった者たちは、
偽悪醜邪の果ての犠牲者であり、
それらを司(つかさど)る
「魔物」の生贄のように
見えたのである。
悲劇の直接の発端は、
詐欺家族一家が
主人家の留守をいいことに
酒盛りで乱痴気騒ぎをしていた時に
策略で追い出した元家政婦が
尋ねてくることに始まる。
この時、
大雨でずぶ濡れだったことが
なんともシンボリックで
印象的なシーンであった。
それは、
単に嵐の前兆というだけでなく、
「水」や「雨」に象徴される
「無意識」の恐ろしい力が
「意識」による現実世界を
圧倒し、破壊する、ということである。
これからしばらく後には
詐欺家族たちの半地下の住居が
大洪水で呑み込まれる
というシーンが描かれる。
いくらかの酩酊と
エゴ・インフレーションにより、
元家政婦を家に入れてしまったのは、
「その時」の判断や行動を誤った、
いわゆる、「魔がさした」のである。
それは、
心の「間」「隙」に
文字通り「魔」が
侵入することでもある。
そして、
「命運」「運命」が狂うというように
「命」は濁流に「運ばれ」て、
意識の世界は翻弄され、
「死」へと陥落する
観血的悲劇を迎えるのである。
元家政婦の哀願するセリフの
「同業者じゃないですか・・・。
後生ですから…家に入れて下さい・・・」
というのは、
まるで、瓜子姫をさらう
天邪鬼の甘言のようにも聞こえた。
むかし、狐狸庵先生のテキストで
さんざん悪魔について勉強したが、
その折、『エクソシスト』のような
脅かす悪魔は低級で、
ほんとの悪魔は「いないように振る舞い」
なおかつ「人の心地よさに付けこむ」
とあった。
家の施錠を解き、
「境界」の一線を
超えさせたことが、
すべての悲劇の始まりであった。
これが夢分析ならば、
「家」=「自我」「意識の世界」
「超えて侵入するもの」=「シャドウ」
(不幸をもたらす破壊的な無意識の元型)
とセラピストは解釈する。
なので、
「境界を越えないのが大事」
というセリフが、度々
犠牲者の社長が言っていたのは
後になって了解できる。
しかし、
人間関係の境界は守られても、
「臭い」というものは
致し方なく、その境界を
侵襲的に超えてくる。
この物語では、
「臭い」が「格差」「憎しみ」の
メタファーにもなっていた。
そして、それは、
そのまま衝動的な
殺人の動機にさえなったのである。
原題の『寄生虫/Parasite』と
邦題の『半地下の家族』という言葉から、
我われの意識的な自我を
時に操り翻弄し、破滅へと導くこともある
無意識下の元型である「影(シャドウ)」は
誰もが抱えており、
それに対して無自覚すぎると、
かの物語のような悲劇を体験する
・・・という、
現代の箴言のような作品のようにも
心理臨床家には思えた。
衝動殺人をした父に
「寄生」していた「影」とは、
世の不条理や理不尽に翻弄され
なにを商売しても上手くいかない人生と、
一方で、とんとん拍子で事業を成功させている
富裕層社長に対する、また、運命の神に対する、
筆舌に尽くせない葛藤・不満・憤りが
最後に「鬼化」して刃を向けてしまう。
これは、モヤモヤを言語化できず、
自傷他害の行動化(アクト・アウト)する
典型でもある。
流行りの『鬼滅の刃』に倣えば、
我われは、「鬼化」して
人に刃を向けるのではなく、
こころの「鬼」を滅するための
刃を己れ自身に向けねばならないのである。
トランプが煽って
死者まで出した
議事堂占拠事件なぞを観るにつけても
その思いを強くしている。
映画『パラサイト』では、
4人もの殺戮が行われた
凄惨な物語の結末は、
再度、地下に潜入し
息をひそめて生息する父(殺人犯)と
その父の存在の秘密に気付いた
息子(執行猶予中)との
「希望」の灯かりだった。
それは、まるで、
「パンドラの箱」が開いて、
世界に大いなる悲劇と不幸が
飛び出た後、
最後に残ったのが「希望」である、
という神話的元型に酷似していた。
とすれば、
現コロナ禍も
人類の偽悪醜邪に拠るものが
招来したものとすれば、
塗炭の苦しみを味わった後、
「希望」は失われず
其処に在る、ということを
信ずることが、其れもまた、
"希望"なのであろうか。
自らも
ナチの強制収容所の虜囚で、
終戦解放後に
名著『夜と霧』を著した
ヴィクトール・フランクルは、
独自の「実存分析」を唱え、
「希望」や「生き甲斐」こそが、
人を人たらしめて
生かしているものである、
と言っている。


皆川達夫先生の
古いテキストに基づいて、
そのご推薦のルネッサンス期のCDを
ヤフオクやアマゾンで
こつこつと蒐集している。
ルネッサンス初期の
声楽アンサンブルは、
グレゴリオ聖歌を基にしたものが多く、
女性合唱での清澄で深淵な響きは
修道士たちの斉唱とは違った
天国的なスピリチュアリティが感じられ、
こころの中に暗雲が垂れ込みがちな
コロナ禍の今、
一服の清涼剤や安定剤のような
癒しを与えてくれている。

R先生から頂いたお菓子籠に
「牛さん」マシュマロがあり、
可愛いので、よっぽど、
飾りものにしようか迷ったが、
でも食べ物なので、
エーイ! と、
干支を口中に放り込んだ(笑)。
なぜだか、
子どもたちが
幼い頃に流行った
♩『モウモウ・フラダンス』♩
のメロディーと画面が
脳裏に浮かんだ(笑)。

今朝のアサちんに、
すこしばかり
妖艶な表情を視た(笑)。
彼女は、
創作モチベーションを与えくれる
「美」のモチーフでもあり、
アニマであり、女神であり、
スピリチュアル・マドンナでもある。