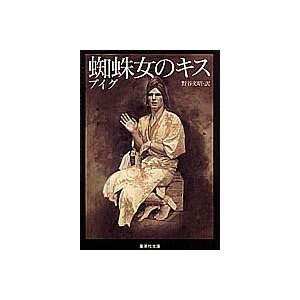
『蜘蛛女のキス』 マヌエル・プイグ ☆☆☆★
プイグの『蜘蛛女のキス』を読了。昔映画を観たが、ウィリアム・ハートがゲイのモリーナを演じていてとても印象的だった。いい映画だったと記憶している。それなのになぜ今まで原作を読まなかったのかというと、この小説は普通の小説と違って叙述法に凝っており、色んな異なる形式のテキストの混合体になっているが、それがどうも億劫だったからだ。地の文というものがなく、会話体、報告書、注釈文、などのパートが入れ替わり立ちかわり現れてくる。こういうのは基本的に苦手である。なんだか作者の声が聞こえてこないというか、隔靴掻痒な感じで、また時に小ざかしい印象もあり、どうも敬遠しがちになってしまう。まあうまく使えば効果的だということは分かる。リョサ『パンタレオン大尉と女たち』やキング『デッド・ゾーン』などでも使われていた。
しかしこれらの作品ではそれがすべてじゃなく、作者の文体がどこかに顔を出していたが、本書では違う。全部このスタイルなのである。主人公のバレンタインとモリーナは牢の中で色々とやりとりするが、会話以外の文章はがんとして出てこない。同性愛を論じた注釈の部分では普通の文体ともいえるが、あれはやはり一種のパスティーシュであって、プイグの小説文体とはいえないだろう。
そんなわけで抵抗があった本書だが、名作という評判が気になって読み始めた。最初はやはり違和感があり、なんでバレンタインとモリーナのやりとりやモリーナが語る映画の内容まで全部会話体オンリーでなければいけないのか分からなかったが、後半になってだんだん分かってきた。まず、モリーナとバレンタインが愛を交わす場面をスマートに処理できる。普通の地の文であれをやるのは結構大変だろう。どうしても生臭くなってしまう。それともう一つ、より重要なのは、センチメンタリズムを抑制するのに有効だということ。本書のストーリー、特に終盤の展開は結構メロドラマティックなのだが、この手法のおかげでうまく感傷性を回避できている。普通の叙述法ではどうしても通俗的になってしまっていただろう。そういう意味ではさすがに巧妙で、感心した。
ところでプイグはアルゼンチンの作家で、この小説もラテンアメリカ文学なのだが、訳者もあとがきで書いている通りちっともそんな感じがしない。随分と都会的な小説だ。ラテンアメリカ文学らしい匂いを求めている人には肩透かしかも知れない。
それからプイグという人はもともと映画志望だったようで、本書にもモリーナが語る形式で色んな映画の話が出てくる。ゾンビの話だったり恋愛ものだったりして、それらのいわば劇中劇がウリの一つらしいが、個人的には今ひとつ物足りなかった。モリーナの話し言葉があまり魅力的には思えないし、女言葉で語られる映画のあらすじもどうもごちゃごちゃしていてのめりこめない。カート・ヴォネガットは「SFはあらすじが一番面白い」といって自作の中でキルゴア・トラウトなる架空のSF作家に小説のあらすじを語らせ、その簡潔さがかえって面白さを引き立てる効果を上げていたが、それに比べるとモリーナの「映画」はだいぶ落ちる、というのが正直な感想だ。それにしてもこの作家、B級映画が好きなんだなあ。
プイグの『蜘蛛女のキス』を読了。昔映画を観たが、ウィリアム・ハートがゲイのモリーナを演じていてとても印象的だった。いい映画だったと記憶している。それなのになぜ今まで原作を読まなかったのかというと、この小説は普通の小説と違って叙述法に凝っており、色んな異なる形式のテキストの混合体になっているが、それがどうも億劫だったからだ。地の文というものがなく、会話体、報告書、注釈文、などのパートが入れ替わり立ちかわり現れてくる。こういうのは基本的に苦手である。なんだか作者の声が聞こえてこないというか、隔靴掻痒な感じで、また時に小ざかしい印象もあり、どうも敬遠しがちになってしまう。まあうまく使えば効果的だということは分かる。リョサ『パンタレオン大尉と女たち』やキング『デッド・ゾーン』などでも使われていた。
しかしこれらの作品ではそれがすべてじゃなく、作者の文体がどこかに顔を出していたが、本書では違う。全部このスタイルなのである。主人公のバレンタインとモリーナは牢の中で色々とやりとりするが、会話以外の文章はがんとして出てこない。同性愛を論じた注釈の部分では普通の文体ともいえるが、あれはやはり一種のパスティーシュであって、プイグの小説文体とはいえないだろう。
そんなわけで抵抗があった本書だが、名作という評判が気になって読み始めた。最初はやはり違和感があり、なんでバレンタインとモリーナのやりとりやモリーナが語る映画の内容まで全部会話体オンリーでなければいけないのか分からなかったが、後半になってだんだん分かってきた。まず、モリーナとバレンタインが愛を交わす場面をスマートに処理できる。普通の地の文であれをやるのは結構大変だろう。どうしても生臭くなってしまう。それともう一つ、より重要なのは、センチメンタリズムを抑制するのに有効だということ。本書のストーリー、特に終盤の展開は結構メロドラマティックなのだが、この手法のおかげでうまく感傷性を回避できている。普通の叙述法ではどうしても通俗的になってしまっていただろう。そういう意味ではさすがに巧妙で、感心した。
ところでプイグはアルゼンチンの作家で、この小説もラテンアメリカ文学なのだが、訳者もあとがきで書いている通りちっともそんな感じがしない。随分と都会的な小説だ。ラテンアメリカ文学らしい匂いを求めている人には肩透かしかも知れない。
それからプイグという人はもともと映画志望だったようで、本書にもモリーナが語る形式で色んな映画の話が出てくる。ゾンビの話だったり恋愛ものだったりして、それらのいわば劇中劇がウリの一つらしいが、個人的には今ひとつ物足りなかった。モリーナの話し言葉があまり魅力的には思えないし、女言葉で語られる映画のあらすじもどうもごちゃごちゃしていてのめりこめない。カート・ヴォネガットは「SFはあらすじが一番面白い」といって自作の中でキルゴア・トラウトなる架空のSF作家に小説のあらすじを語らせ、その簡潔さがかえって面白さを引き立てる効果を上げていたが、それに比べるとモリーナの「映画」はだいぶ落ちる、というのが正直な感想だ。それにしてもこの作家、B級映画が好きなんだなあ。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます