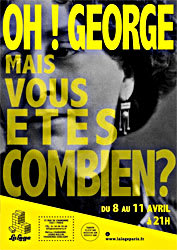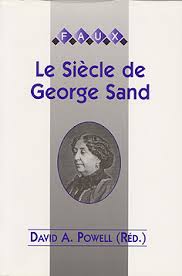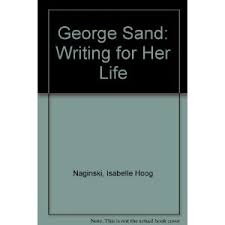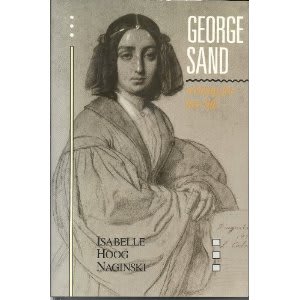Les voyageurs ont été accueillis en musique, mercredi. En prélude au Festival de Nohant, qui débute dans quatre semaines.
Surprise, mercredi après-midi, pour les voyageurs, en gare de Châteauroux, où un piano trônait en bonne place dans le hall. Entre deux trains, Frédéric Chopin les attendait au travers de morceaux choisis.
Cette rencontre impromptue avait été mise sur pieds par le pianiste virtuose Yves Henry, président du Festival Chopin de Nohant : « Cette animation, organisée en partenariat avec le conservatoire de Châteauroux, est un avant-goût de la 47e édition du festival, qui se déroulera du 7 juin au 23 juillet. »
L'idée était d'évoquer un Chopin qui prend le train et s'arrête en gare de Châteauroux, en référence aux voyages de George Sand entre Nohant et la capitale. « Aujourd'hui, notre voyage a débuté à la gare d'Austerlitz où une vingtaine de musiciens participaient à l'évènement. Il s'achève en gare de Châteauroux, à la manière des étapes en diligence qu'effectuait George Sand, en son temps. »
« Jouer Chopin dans une gare est une formidable expérience, s'enthousiasmait Yves Henry. C'est offrir la musique à tous ! » Le public pouvait apprécier mazurka, polonaise et autres nocturnes, brillamment interprétés par le maître et quelques élèves du Conservatoire, en préambule aux festivités. Elles débuteront en avant-première, le 5 juin, par un concert pour les enfants. Placé sous le thème de L'Italie de Chopin et George Sand, l'édition 2014 du Festival de Nohant réunira, une fois encore, de prestigieux interprètes : Aldo Ciccolini, Anne Queffélec, Nikolaï Lugansky, Jean-Philippe Collard, Jean-Bernard Pommier, Gautier Capuçon. Et Yves Henry, bien sûr.
Réservations : office de tourisme de La Châtre, tél. 02 54.48.46.40.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Loisirs/Fetes-festivals/n/Contenus/Articles/2014/05/09/Chopin-a-fait-escale-a-la-gare-1900801
Surprise, mercredi après-midi, pour les voyageurs, en gare de Châteauroux, où un piano trônait en bonne place dans le hall. Entre deux trains, Frédéric Chopin les attendait au travers de morceaux choisis.
Cette rencontre impromptue avait été mise sur pieds par le pianiste virtuose Yves Henry, président du Festival Chopin de Nohant : « Cette animation, organisée en partenariat avec le conservatoire de Châteauroux, est un avant-goût de la 47e édition du festival, qui se déroulera du 7 juin au 23 juillet. »
L'idée était d'évoquer un Chopin qui prend le train et s'arrête en gare de Châteauroux, en référence aux voyages de George Sand entre Nohant et la capitale. « Aujourd'hui, notre voyage a débuté à la gare d'Austerlitz où une vingtaine de musiciens participaient à l'évènement. Il s'achève en gare de Châteauroux, à la manière des étapes en diligence qu'effectuait George Sand, en son temps. »
« Jouer Chopin dans une gare est une formidable expérience, s'enthousiasmait Yves Henry. C'est offrir la musique à tous ! » Le public pouvait apprécier mazurka, polonaise et autres nocturnes, brillamment interprétés par le maître et quelques élèves du Conservatoire, en préambule aux festivités. Elles débuteront en avant-première, le 5 juin, par un concert pour les enfants. Placé sous le thème de L'Italie de Chopin et George Sand, l'édition 2014 du Festival de Nohant réunira, une fois encore, de prestigieux interprètes : Aldo Ciccolini, Anne Queffélec, Nikolaï Lugansky, Jean-Philippe Collard, Jean-Bernard Pommier, Gautier Capuçon. Et Yves Henry, bien sûr.
Réservations : office de tourisme de La Châtre, tél. 02 54.48.46.40.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Loisirs/Fetes-festivals/n/Contenus/Articles/2014/05/09/Chopin-a-fait-escale-a-la-gare-1900801