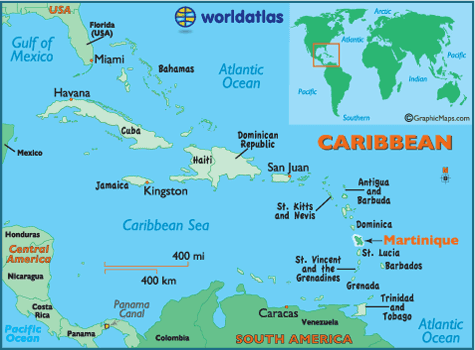ジャン・ルクレール氏講演会
アンリ哲学の展開
開催日時 2013年3月29日(水)立命館大学 衣笠キャンパス 末川記念会館第3会議室
テーマ 肉と身体―現象学的人間学の諸パラダイム―
La chair et le corps. Les paradigmes d'une anthropologie phenomenologique.
報告者 ジャン・ルクレール(Jean Leclercq)
<略歴> ルーヴァン・カトリック大学(ベルギー)哲学科教授。19世紀から20世紀のフランス哲学、宗教哲学を専門とする。ミシェル・アンリ文庫 (2010 年にルーヴァン・カトリック大学内に開設)所長。ASPLF 事務局長。編著書として、Phenomenologies litteraires de l’ecriture de soi, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2009など。
司 会 川瀬 雅也(佐世保工業高等専門学校)
通 訳 服部 敬弘氏(同志社大学、パリ西部大学)
聴講無料・事前申し込み不要
※発表はフランス語で行い、当日、原文と日本語訳のテキストを配布します。また、質疑には通訳がつきます。
※シンポジウム終了後、懇親会を予定しております。