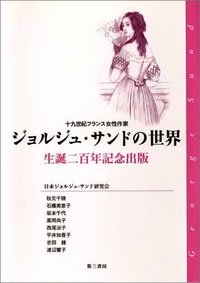https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g187120-d4959485-Reviews-Au_rendez_vous_de_George_Sand-Bourges_Cher_Berry_Centre_Val_de_Loire.html
https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g187120-d4959485-Reviews-Au_rendez_vous_de_George_Sand-Bourges_Cher_Berry_Centre_Val_de_Loire.html
L'histoire d'amour entre Chopin et George Sand
reprend vie au Centre musical En sol mineur
PUBLIÉ LE DIMANCHE 14 AOÛT 2016 À 5 H 42
C'est un bijou digne d'un travail d'orfèvre que nous offrent les musiciennes
prodiges que sont les soeurs Céline et Jacynthe Riverin avec Plume et pantalon,
un mélange de compositions de Frédéric Chopin et des textes de la romancière
George Sand présenté jusqu'à samedi soir au Salon Vert du Centre musical
En sol mineur.
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/08/13/006-theatre-musique-classique-george-sand-frederic-chopin-jacynthe-celine-riverin.shtml
reprend vie au Centre musical En sol mineur
PUBLIÉ LE DIMANCHE 14 AOÛT 2016 À 5 H 42
C'est un bijou digne d'un travail d'orfèvre que nous offrent les musiciennes
prodiges que sont les soeurs Céline et Jacynthe Riverin avec Plume et pantalon,
un mélange de compositions de Frédéric Chopin et des textes de la romancière
George Sand présenté jusqu'à samedi soir au Salon Vert du Centre musical
En sol mineur.
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/08/13/006-theatre-musique-classique-george-sand-frederic-chopin-jacynthe-celine-riverin.shtml
フランスでは14日の夜、テレビでサンドの番組が放映されます。
お見逃しなく!
une émission qui sera diffusée ce soir sur France 5, à 22h15,
dans la série Une maison, un artiste, consacrée à George Sand,
la rebelle de Nohant.
次のレジュメには、ちょっとした間違いがありました。
サンドが亡くなったのは、1871年ではなく1876年です!
RÉSUMÉ
George Sand, née Aurore Dupin, passe une partie de son enfance et
de son adolescence à Nohant, dans le Berry, dans la maison que sa
grand-mère paternelle (et tutrice) a acquise en 1793. En 1821, au décès
de son aïeule, George Sand hérite du domaine, mais elle ne s'y installera
que bien plus tard, continuant à se partager entre Paris, Nohant et d'autres l
ieux de vie. Au gré des années, elle y reçoit ses amis ou amants artistes,
Chopin, Liszt, Balzac, Delacroix ou Flaubert. C'est également à Nohant
qu'elle écrit plusieurs de ses oeuvres majeures, «La Mare au diable» ou
«La Petite Fadette», s'adonne au jardinage et à la botanique. Aujourd'hui
encore, l'intérieur de la maison a conservé les traces du passage de
«la bonne dame de Nohant», qui s'y est éteinte le 8 juin 1871.
http://www.france5.fr/emission/une-maison-un-artiste/diffusion-du-14-08-2016-22h15
Je remercie Laura Colombo de cette information bien palpitante.
LE MYTHE DE L'ATLANTIDE
RÉSUMÉ
La cité de l'Atlantide, citée par le philosophe grec Platon vers 360
avant l'ère chrétienne, a-t-elle réellement existé ? Depuis quelques
décennies, des experts ont mis au jour les ruines d'une ville enfouie
au sud de l'île grecque de Santorin. Découverte en 1967, à 18 mètres
sous le niveau de la mer, Akrotiri présente de troublantes similitudes
avec l'Atlantide décrite par Platon. Akrotiri a été détruite par une
violente éruption volcanique qui a entraîné sa disparition sous vingt
mètres de cendres, il y a 3600 ans. L'explosion fut si puissante
qu'elle provoqua un gigantesque tsunami. Un terrible cataclysme
qui a signé la fin de la civilisation minoenne et a peut-être inspiré
Platon.
http://www.france5.fr/emission/une-maison-un-artiste/diffusion-du-14-08-2016-22h15
お見逃しなく!
une émission qui sera diffusée ce soir sur France 5, à 22h15,
dans la série Une maison, un artiste, consacrée à George Sand,
la rebelle de Nohant.
次のレジュメには、ちょっとした間違いがありました。
サンドが亡くなったのは、1871年ではなく1876年です!
RÉSUMÉ
George Sand, née Aurore Dupin, passe une partie de son enfance et
de son adolescence à Nohant, dans le Berry, dans la maison que sa
grand-mère paternelle (et tutrice) a acquise en 1793. En 1821, au décès
de son aïeule, George Sand hérite du domaine, mais elle ne s'y installera
que bien plus tard, continuant à se partager entre Paris, Nohant et d'autres l
ieux de vie. Au gré des années, elle y reçoit ses amis ou amants artistes,
Chopin, Liszt, Balzac, Delacroix ou Flaubert. C'est également à Nohant
qu'elle écrit plusieurs de ses oeuvres majeures, «La Mare au diable» ou
«La Petite Fadette», s'adonne au jardinage et à la botanique. Aujourd'hui
encore, l'intérieur de la maison a conservé les traces du passage de
«la bonne dame de Nohant», qui s'y est éteinte le 8 juin 1871.
http://www.france5.fr/emission/une-maison-un-artiste/diffusion-du-14-08-2016-22h15
Je remercie Laura Colombo de cette information bien palpitante.
LE MYTHE DE L'ATLANTIDE
RÉSUMÉ
La cité de l'Atlantide, citée par le philosophe grec Platon vers 360
avant l'ère chrétienne, a-t-elle réellement existé ? Depuis quelques
décennies, des experts ont mis au jour les ruines d'une ville enfouie
au sud de l'île grecque de Santorin. Découverte en 1967, à 18 mètres
sous le niveau de la mer, Akrotiri présente de troublantes similitudes
avec l'Atlantide décrite par Platon. Akrotiri a été détruite par une
violente éruption volcanique qui a entraîné sa disparition sous vingt
mètres de cendres, il y a 3600 ans. L'explosion fut si puissante
qu'elle provoqua un gigantesque tsunami. Un terrible cataclysme
qui a signé la fin de la civilisation minoenne et a peut-être inspiré
Platon.
http://www.france5.fr/emission/une-maison-un-artiste/diffusion-du-14-08-2016-22h15
皆さま
猛暑お見舞い申し上げます。
この酷暑の中をお墓参りに里帰りされておられる方も多いことと思います。
お盆の13日はご先祖の霊が家に戻ってくる日ですね。
新盆の家では大切な人が道に迷わず戻ってくることができるようにと
玄関の前で目印の迎え火を焚き、小さな砂山を作ってたくさんの蝋燭を
灯して先祖の霊を家にお迎えします。真夏の夕闇が迫る頃におこなわれる
この儀式は幻想的で、子供心にも敬虔な心持ちにさせられたものでした。
地域によっても違うようですが、家の中に祭壇をつくり、そこに天ぷらや
おはぎなどお盆のご馳走を供え、きゅうりやなすと割り箸で拵えた馬や牛を
置き、その背中には茹でたそうめんを飾ります。
はすの花やほおずきなどもお供えします。
ご先祖様が天国に戻るとき、ほおずきを提灯にし、野菜の馬やはなびらの
船に乗って、お腹を空かすことなく、無事にあの世に戻っていけるように
という願いが、これらの物には籠められているのです。
16日には、家の前で送り火を焚き、天国に戻ってゆくご先祖様をお見送り
します。
この幻想的で奥ゆかしい習わしは、古くから人々が守り続けてきた貴重な
文化の遺産ゆえ、いつまでも続きますようにと祈らずにはいられません。
ところで、
本日、8月13日は、サンドやショパンと親交のあった画家ドラクロワの命日です。
ウジェーヌ・ドラクロワは、フランスの19世紀ロマン主義を代表する画家として
知られています。
1798年4月26日 の生まれで、1863年8月13日にパリで没しています。
出生に関しては、政治家タレイランが父であったとする説が強いようです。
タレイランは、仏大革命の時代から七月王政まで、フランスの政界で活躍しました。
おもに外交官、外相を務めましたが、一時は首相の任にさえ就いた大物政治家でした。
ドラクロワは今でこそ大画家として有名ですが、古典主義全盛の当時は、彼の作風は
線も色も不安定で過激だとされ、サロンに応募しても選出されず、失意のうちに日々を
過ごすこともあったようです。サンドは、そんな彼に花を贈ったり、手紙を書いて慰め
たりしたのでした。
ドラクロワの父親タレイラン説が有力なのは、ドラクロワが絶対絶命ともいえるような
人生の危機に見舞われるたびに、どこからともなく援助の手が差し伸べられ、必ず窮地
から救われるという不可解な事実が何度もあったことに起因しているようです。
ルーブル美術館所蔵の「民衆を導く自由の女神」は、1830年の作品です。
"La Liberté guidant le peuple" Musée du Louvre
皆さま、どうぞよいお盆休みをお過ごし下さいますよう。
Ferdinand Victor Eugène Delacroix ;
Le 13 août 1863 s'éteignait le peintre Eugène Delacroix,
considéré comme le chef de file du romantisme
de la peinture française du XIXe siècle.

森本淳生(編)『〈生表象〉の近代―自伝・フィクション・学知』
判型:A5判上製
頁数:496頁
水声社
定価:7500円+税
ISBN:978-4-8010-0133-6 C 0090 好評発売中!
<生>の無秩序な増殖に対峙する近代の諸制度――
文学・思想・芸術を構成する様々なジャンルやメディア、学知、学校教育といった
近代固有の制度のなかで、人間の〈生〉はいかに媒介され表象されるのか?
自伝的エクリチュールと主体の問題から、権力を内包する社会制度と個人の交錯、
そしてフィクションをも用いて表現される不定形な〈生〉を分析することにより、
〈近代=モデルニテ〉を横断的に再考する壮大な試み。
「近代における〈生表象〉とは、さまざまな記録媒体が発達するなかでアナーキーに
増殖してきた断片的な生の痕跡と、それをさまざまに理解し、規制し、管理しようと
する諸制度とが交錯する場である。こうした生表象システムを、文学・思想・芸術の
様々なジャンル、作文・日記教育、種々の学問制度についての考察を通して横断的に
分析するとき、われわれを現在なお規定している〈近代〉=モデルニテの内実につい
ての新しい視野が得られるのではないだろうか。」(「序」より)
[目次]
序 〈生表象〉とは何か?(森本淳生)
第一部 近代における〈生表象〉の変容
Ⅰ西洋
第一章 戯れ言をまじめに読む―エラスムス『痴愚神礼讃』と古代模擬弁論の伝統(堀尾耕一)
第二章 自伝誕生をめぐる神話―ルソー『告白』受容の一側面(桑瀬章二郎)
第三章 表象の失調へと注がれる眼差し―スタンダールと鏡の経験(片岡大右)
第四章 自伝と過去の現前―レチフ・ド・ラ・ブルトンヌからネルヴァルへ(辻川慶子)
第五章 ジェラール・ド・ネルヴァルの『オーレリア』あるいは書物と人生―
「ロマン主義の百足」(ジャン=ニコラ・イルーズ/辻川慶子訳)
Ⅱ日本
第六章 「師」の表象――本居宣長の場合(田中康二)
第七章 歌舞伎役者五代目市川団十郎の引退(廣瀬千紗子)
第二部 教育・額値・帰属性
Ⅰ〈生表象〉と教育制度―日記、作文、手記
第八章 書かされる「私」――作文・日記、そして自伝(安田敏朗)
第九章 「花咲く乙女たち」の作文教育(中野知律)
第十章 「証言の時代」の幕開け―第一次世界大戦戦争文学をめぐって(久保昭博)
Ⅱ〈生表象〉と近代的学知の生成
第十一章 オートフィクションとしての理論――フロイトのケース(立木康介)
第十二章 ライフヒストリー・レポートの無謀と野望―柳田民俗学を「追体験」する(菊地暁)
Ⅲ〈生表象〉の主体と帰属性
第十三章 「戦争詩」から「自伝/オートフィクション」へ―
〈生表象〉の帰属と文学性の問題について(吉澤英樹)
第十四章 植民地において〈私〉を語ること、〈私たち〉を語ること
―エメ・セゼールからマリーズ・コンデへ(尾崎文太)
第十五章 「女」の自己表象―応答性・被読性と田村俊子「女作者」(飯田祐子)
第十六章 「文学」の拒絶、あるいは不可視の「文学」(坂井洋史)
第三部 自伝とフィクション
第十七章 『わが秘密の生涯』を読む――性をめぐる自伝とフィクション(大浦康介)
第十八章 トーマス・マンの自己表象とモデルネ―『魔の山』を中心に(尾方一郎)
第十九章 ジャン=ポール・サルトル―生とフィクション(ジル・フィリップ/森本淳生訳)
第二十章 「追憶の計画」―谷崎潤一郎とジョルジュ・ペレックの〈自己〉構築における記憶とフィクション(エステル・フィゴン)
第二十一章 オートフィクションと写真―〈本物〉とは異なる価値観の形成に向けて(塚本昌則)
第二十二章 北京の日曜日―クリス・マルケルからミシェル・レリスに(千葉文夫)
終章 〈文人〉の集合的(自)伝記を書くとはいかなることか?
(ウィリアム・マルクス/森本淳生訳)
人名索引
編者あとがき
[編者について]
森本淳生(もりもとあつお)1970年、東京都生まれ。一橋大学大学院准教授(フランス文学)。著書に、Paul Valéry. L’imaginaire et la genèse du sujet. De la psychologie à la poétique(Lettres Modernes Minard, 2009)『小林秀雄の論理――美と戦争』(人文書院、2002年)。訳書にJ・ランシエール『マラルメ セイレーンの政治学』(共訳、水声社、2014年)などがある。
『知のミクロコスモス 中世・ルネサンスのインテレクチュアル・ヒストリー』
ヒロ・ヒライ、小澤実編
中央公論新社
2014年3月
398ページ
ISBN 978-4120045950
定価3,700円+税。
紹介記事
http://newclassic.jp/9606
マルティン・ルターは、教皇の文書を火にくべるとともに、聖書の俗語訳を生みだした。
神と人間を媒介する教会の役割の多くが否定され、ただ聖書のみに依拠して信仰を立ち
あげる必要性が説かれた。伝統的な聖遺物崇拝は攻撃され、日々の信仰生活を彩っていた
多くの儀礼が廃棄された。廃棄こそされなかったものの、その解釈が変更され、それゆえ
大きな論争を呼んだ儀式に、聖餐式(せいさんしき)がある。
解釈の次元のみならず、現実の世界においてもじつにグロテスクな帰結を招いた聖餐を
めぐる論争の源流はどこにあるのか。ここで平野が着目するのがフランソワ・ラブレーの
『ガルガンチュアとパンタグリュエル』である。そこでラブレーがカトリックの聖餐式を
嘲笑してみせているというのだ。
ラブレーの聖餐式にたいする隠された笑い
聖餐式におけるパンとワインを神の血肉として崇拝する者たちは、全能の神ならぬ腹全能
の神のとりまきと同型なのではないか。この秘めた笑いがのちにプロテスタントの論争家
たちの手で表面化させられることになる・・・
中世の聖職者たちが葛藤のなかで懸命に維持しようとしていた「教会の平和という絆」は
断ち切られた。スコラ哲学が解体され、情報量が指数関数的に増大し、新たな伝統が捏造
され、地理的地平が拡大し、宗教宗派の分裂が進むなかで、聖書の言葉を中心に聖職者たち
がたばねようとした世界は砕け散った。そうしてあらわれたのがスピノザである。
スピノザは超越神の観念を否定し、神を世界そのものと同一視した。それにより世界から
人間理性が理解できない領域は消去される。
わたくしは、自然学上の問題を議論するにあたって、聖書の文章の権威から出発するのでは
なく、感覚でとらえられる実験と必然的な証明から出発すべきであろうと思います。…しかし、
こういったからといって、わたくしは、聖書の章句に最高の尊敬を払うべきではないという
つもりはありません。むしろ、自然学のなんらかの結論に確実に達したならば、それをわたくし
たちは、聖書そのものの真の解釈と聖書に必ず含まれている真の意味(これはまったく真理で
あって証明された真実と合致するのですから)を探究するための手段として役立てねばなりません
3。
(3. ガリレオ「クリスティーナ大公妃宛手紙」、青木靖三編訳『世界の思想家 6 ガリレオ』
平凡社、1976 年、209 ページより引用。 )
古代のある時点においてキリスト教は正典のうえに築かれた信仰となった。正典たる聖書を
読む能力を独占し、その解釈権を専有し、釈義を伝える方策を統制することによって、中世
の教会は「万事につけ、われわれは、可能なかぎり統一を守るべき」という目標を達成しよう
と試みた。たしかにガリレオにいたるまでに、その試みは挫折し、キリスト教世界は分裂して
いた。だがカトリックが聖書の解釈権を手放そうとしていたわけではなかった。むしろプロテ
スタントへの対抗のなかで、禁書目録をはじめとする新たな手段をもちいて、教会は勢力圏内
での正統性の独占を強化しようとしていた。そのなかでガリレオは聖書解釈の権利を聖職者から
奪いとろうとしたのである。しかもそれをローマにまで出向いてとなえたのだった。
であればこそ、ガリレオが異端誓絶の判決を受けたのは当然であった。その判決をくだす聖邪
検庁で大きな勢力を占めていたのはドミニコ会士、すなわち中世において葛藤の中心にいた
聖職者たちの末裔であった。それにより彼らは信仰と科学の分断といういっそう深刻な葛藤の
種をまき、後継者たちを苦しめつづけることになる。
ガリレオの反逆のうちには、恐るべき知性の冴えと愚劣なほどの傲慢さが混じりあっていた。
たいする教会権力は懸命に秩序を維持しようとしながら、しかし決定的に硬直し、抑圧的な
ものとなっていた。
ヒロ・ヒライ、小澤実編
中央公論新社
2014年3月
398ページ
ISBN 978-4120045950
定価3,700円+税。
紹介記事
http://newclassic.jp/9606
マルティン・ルターは、教皇の文書を火にくべるとともに、聖書の俗語訳を生みだした。
神と人間を媒介する教会の役割の多くが否定され、ただ聖書のみに依拠して信仰を立ち
あげる必要性が説かれた。伝統的な聖遺物崇拝は攻撃され、日々の信仰生活を彩っていた
多くの儀礼が廃棄された。廃棄こそされなかったものの、その解釈が変更され、それゆえ
大きな論争を呼んだ儀式に、聖餐式(せいさんしき)がある。
解釈の次元のみならず、現実の世界においてもじつにグロテスクな帰結を招いた聖餐を
めぐる論争の源流はどこにあるのか。ここで平野が着目するのがフランソワ・ラブレーの
『ガルガンチュアとパンタグリュエル』である。そこでラブレーがカトリックの聖餐式を
嘲笑してみせているというのだ。
ラブレーの聖餐式にたいする隠された笑い
聖餐式におけるパンとワインを神の血肉として崇拝する者たちは、全能の神ならぬ腹全能
の神のとりまきと同型なのではないか。この秘めた笑いがのちにプロテスタントの論争家
たちの手で表面化させられることになる・・・
中世の聖職者たちが葛藤のなかで懸命に維持しようとしていた「教会の平和という絆」は
断ち切られた。スコラ哲学が解体され、情報量が指数関数的に増大し、新たな伝統が捏造
され、地理的地平が拡大し、宗教宗派の分裂が進むなかで、聖書の言葉を中心に聖職者たち
がたばねようとした世界は砕け散った。そうしてあらわれたのがスピノザである。
スピノザは超越神の観念を否定し、神を世界そのものと同一視した。それにより世界から
人間理性が理解できない領域は消去される。
わたくしは、自然学上の問題を議論するにあたって、聖書の文章の権威から出発するのでは
なく、感覚でとらえられる実験と必然的な証明から出発すべきであろうと思います。…しかし、
こういったからといって、わたくしは、聖書の章句に最高の尊敬を払うべきではないという
つもりはありません。むしろ、自然学のなんらかの結論に確実に達したならば、それをわたくし
たちは、聖書そのものの真の解釈と聖書に必ず含まれている真の意味(これはまったく真理で
あって証明された真実と合致するのですから)を探究するための手段として役立てねばなりません
3。
(3. ガリレオ「クリスティーナ大公妃宛手紙」、青木靖三編訳『世界の思想家 6 ガリレオ』
平凡社、1976 年、209 ページより引用。 )
古代のある時点においてキリスト教は正典のうえに築かれた信仰となった。正典たる聖書を
読む能力を独占し、その解釈権を専有し、釈義を伝える方策を統制することによって、中世
の教会は「万事につけ、われわれは、可能なかぎり統一を守るべき」という目標を達成しよう
と試みた。たしかにガリレオにいたるまでに、その試みは挫折し、キリスト教世界は分裂して
いた。だがカトリックが聖書の解釈権を手放そうとしていたわけではなかった。むしろプロテ
スタントへの対抗のなかで、禁書目録をはじめとする新たな手段をもちいて、教会は勢力圏内
での正統性の独占を強化しようとしていた。そのなかでガリレオは聖書解釈の権利を聖職者から
奪いとろうとしたのである。しかもそれをローマにまで出向いてとなえたのだった。
であればこそ、ガリレオが異端誓絶の判決を受けたのは当然であった。その判決をくだす聖邪
検庁で大きな勢力を占めていたのはドミニコ会士、すなわち中世において葛藤の中心にいた
聖職者たちの末裔であった。それにより彼らは信仰と科学の分断といういっそう深刻な葛藤の
種をまき、後継者たちを苦しめつづけることになる。
ガリレオの反逆のうちには、恐るべき知性の冴えと愚劣なほどの傲慢さが混じりあっていた。
たいする教会権力は懸命に秩序を維持しようとしながら、しかし決定的に硬直し、抑圧的な
ものとなっていた。
読みたいと思いつつ、なかなか時間が取れなかった書を手にできて
ちょっとだけうれしい夏季休暇です。
以下は、『作家の聖別―フランス・ロマン主義〈1〉一七五〇‐一八三〇年―
近代フランスにおける世俗の精神的権力到来をめぐる試論』』からの抜き書きです。
サンドのことも正しく言及されていました。
ーーー
ロマン主義革命の核心は、文学の変容というよりもむしろ、
文学の地位が驚くべき向上を果たしたことにある。
復古王政初期にフランスを旅したレディ・モーガンは、ルソーに
呪詛を投げつけている過激王党派の人々が、それにもかかわらず
「ルソーの感情的修辞法を模倣しており、この階級の人々はいまだ
かつてない程にそれを仲間うちで使いこなしている」と驚きとともに
報告している。
スタンダールが食ってかかっているのは、サン=シモン主義の新聞
『生産者』に集まった人々であるが、彼らは彼が考えていたより柔軟で
あって、現代的な言葉遣いをするなら、産業と知識人について多くの
考察をしていた。
ベニシューの議論のフュマロリによる説明には、「フランスの例外」を
特権的色彩のもとに論じる『精神の外交』や『ヨーロッパがフランス語を
話していた頃』著者自身の傾向が色濃く反映している。しかし、十八世紀
フランスにおける著作家の状況をめぐるトクヴィルとサルトルの分析の
共通性を指摘し(・・・)、政治的スペクトルを横断して共有される
フランス的近代の独自性の認識を踏まえつつその継承と補完を企てる
『作家の聖別』の分析が、態勢の内部と外部に同時に立ってその支持者と
批判者を兼務する知的同業集団の存在を「ブルジョワ社会」の一般的
特徴として提示する一方で、その形成をフランス固有の歴世的過程に
即して綿密に跡付けているのは紛れもない事実だ。
文学者たちのこの共同体は、二月革命によって実現した「ロマン派
の共和国」(・・・)ーラマルチーヌが首班を務め、ジョルジュ・サンドが
公報を執筆し、ユゴーが憲法制定議会議員であったーにおいて体制それ自体と
ひととき一体化した後、直ちに経験された幻滅を経て、信者も神も欠いた
「対象無き祭司職」(・・・)のうちに沈潜していく。
『作家の聖別―フランス・ロマン主義〈1〉一七五〇‐一八三〇年―
近代フランスにおける世俗の精神的権力到来をめぐる試論』』より
ポール ベニシュー (著), Paul B´enichou (原著),
片岡 大右 (翻訳), 原 大地 (翻訳), 辻川 慶子 (翻訳), 古城 毅 (翻訳)
単行本: 687ページ
出版社: 水声社 (2015/01)
言語: 日本語
ISBN-10: 4801000282
ISBN-13: 978-4801000285
発売日: 2015/01
内容(「BOOK」データベースより)
十九世紀前半、宗教的権力に代わり、世俗的な聖職者たらんとした詩人、文学者たちの
「聖別」の過程を克明に追いながら、いかにして文学が高い精神的職務を担うよう求め
られるに至ったのかを論じる。フランス・ロマン主義を徹底的に解明する渾身の長大評論、
第一巻。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
ベニシュー,ポール
1908年、トレムセン(アルジェリア)生まれ。2001年パリに没した。ユルム街の高等師範学校
(フランス、パリ)に学ぶ。第二次大戦中のアルゼンチン亡命を挟み、戦前・戦後にかけて長く
フランスで中等教育に携わった後、1958年にハーヴァード大学(アメリカ合衆国)に招かれて、
以後79年までフランス文学およびスペイン口承文学を講じた
片岡/大右
1974年北海道生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科にて博士号取得。現在、同研究科研究員。フランス文学・思想史
原/大地
1973年東京都生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科単位取得退学。パリ第四大学にて博士号取得。現在、慶應義塾大学商学部准教授。フランス語・フランス文学
辻川/慶子
1973年大阪府生まれ。京都大学大学院文学研究科単位取得退学。パリ第八大学にて博士号取得。現在、白百合女子大学准教授。十九世紀フランス文学
古城/毅
1975年東京都生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科にて博士号取得。現在、学習院大学法学部教授。政治学史
(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


sur les pas de George Sand
à Nohant
sur les pas de George Sand
à la Châtre
http://bonheurdelire.over-blog.com/article-sur-les-pas-de-george-sand-a-la-chatre-75622807.html
La Seyne Animations
Festival Sand et Chopin en Seyne: un festival international d'art pluriel
Tamaris et George Sand: une belle histoire d'amour entre un lieu d'exception et une artiste anticonformiste, amoureuse, libre et visionnaire...
Pour Chrystelle Di Marco et Gabriel Boz, créateurs de ce festival musico-littéraire, choisir ce couple de légende comme inspiration était une évidence.
Tout ces arts seront réunis au fort Napoléon pour un festival unique en son genre du 25 au 27 août!
A partir de 15€ par soirée
Renseignements et réservations: http://www.festivalsandetchopinenseyne.com/#!le-festival/cee5
et offices de tourisme
https://www.ouest-var.net/actualite/la-seyne-festival-sand-et-chopin-en-seyne-un-festival-international-d-art-pluriel-12148.html
Festival Sand et Chopin en Seyne: un festival international d'art pluriel
Tamaris et George Sand: une belle histoire d'amour entre un lieu d'exception et une artiste anticonformiste, amoureuse, libre et visionnaire...
Pour Chrystelle Di Marco et Gabriel Boz, créateurs de ce festival musico-littéraire, choisir ce couple de légende comme inspiration était une évidence.
Tout ces arts seront réunis au fort Napoléon pour un festival unique en son genre du 25 au 27 août!
A partir de 15€ par soirée
Renseignements et réservations: http://www.festivalsandetchopinenseyne.com/#!le-festival/cee5
et offices de tourisme
https://www.ouest-var.net/actualite/la-seyne-festival-sand-et-chopin-en-seyne-un-festival-international-d-art-pluriel-12148.html