
引き続き座間・さくら百華の道に咲く桜の紹介です。
まずはトップ画像。普賢象:花は大輪。八重咲きで淡紅色。開花期は4月下旬。
もと、東京の荒川堤で栽培されていた品種です。
室町時代から知られる品種で、2本の葉化した雌しべの状態を、普賢菩薩が乗っている象の鼻に見立てて、この名がつけられたといわれています。

わさ〜とボリュームたっぷりな八重桜。


蘭々(らんらん):花は大輪。八重咲きで白色。開花期は4月下旬。
松前固有品種の白蘭(はくらん)に雨宿を交配して、浅利政俊によって作出された品種です。上野動物園のパンダ蘭々の死を悼み1980年5月5日の子供の日に命名されました。


須磨浦普賢象(すまうらふげんぞう):花は大輪。八重咲きで黄緑色。開花期は4月下旬。
1990年に神戸市須磨浦公園内に植えられている、普賢象の枝変わりとして発見された品種です。発見場所と、元の品種名に因んで名付けられました。

これまたボリュームたっぷりの桜です。あえて上の画像を選んだのは、中央左にピンク色の花がありますよね?実は須磨浦普賢象は時間が経つにつれ花色が変化するのですよ。咲き進むのが楽しみな桜です。咲き始めの黄緑色も風情がありますが、また見に来よう。


御衣黄(ぎょいこう):花は中輪。八重咲きで黄緑色。開花期は4月下旬。
もと、東京の荒川堤で栽培されていた品種です。黄緑色の花色が特異なため、古くから栽培されていたものといわれています。

桜にしては珍しいけども。雑木にはよくある花だよな。見てる人もほとんどいない。

駿河台匂(するがだいにおい):花は大輪。一重咲きで白色。開花期は4月下旬。
もと、東京の荒川堤で栽培されていた品種です。江戸駿河台の一庭園にあったため、この名がつけられたといわれます。芳香が非常に強い品種です。


紅華(こうか):花は大輪。八重咲きで紅色。開花期は4月下旬。
1965年に浅利政俊によって作出された品種で、大山桜と里桜の雑種と推定されています。開花期間が長く美しい八重桜です。


福禄寿:花は大輪。八重咲きで淡紅色。開花期は4月下旬。
もと、東京の荒川堤で栽培されていた品種です。
花弁は厚い質感があり、大きくねじれたように波打つのが特徴です。

松月(しょうげつ):花は大輪。八重咲きで淡紅色。開花期は4月中旬。
もと、東京の荒川堤で栽培されていた品種です。外側の花弁ほど淡紅色が濃くなるグラデーションが美しく、桜愛好家の中でも人気がある品種です。

大輪で八重咲きなのでたっぷり花がついた枝は重そうですね。まだ木が細いからなおさら。これくらいだとよく観察できます。
ところで、説明プレートにちょくちょく登場する浅利政俊氏ってどういう人?気になったので検索してみた。
浅利政俊:桜研究家・桜守。
2005年、財団法人「日本さくらの会」(会長・河野洋平衆議院議長)から桜の研究に長年貢献したとして「桜守」の称号・賞を受ける。
1931年北海道生まれ。北海道学芸大学(現北海道教育大)在学中同校講師植物分類学者菅原繁蔵先生より桜研究の資料文献を引き継ぎ、師の紹介で日本植物学会に所属した。
元小学校教諭、元北海道教育大学非常勤講師。
主な著書「北国の桜」「サクラの品種に関する調査研究報告」など。
さて、今日はここまで明日に続きます。










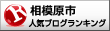


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます