3.渡辺一夫『寛容について』
渡辺一夫『寛容について』は1942年から1970年に書かれた雑文をまとめたものです。
16世紀ヨーロッパ、特にフランスルネサンス期の血で血を洗うような宗教戦争について書くことをとおして、戦争、そして敗戦後の日本、あるいは戦後の世界がどのようにあるべきかを問うています。
新旧両派の不寛容は恐るべきものだった。
自分の教義と異なる教義を寛容することは指導的な改革者たちの思いも及ばぬところであり、宗教改革は指導者たちも戦慄するような結果を招いた。
中世の理想が世界から異端者を一掃することであったとすれば、新教徒の目的は反対者全部を国土から排斥することだった。
神の名によって殺戮し、正義の名の下で果たし合いをする人間に対して、非人間的で愚劣な行為であり、解決は他に求めねばならぬと説くこと、またそうした考えを抱き通すことこそが「精神の真の特権」である。
渡辺一夫はユマニスト(人文主義者)、なかでも中心人物であるエラスムスを高く評価します。
エラスムスの晩年には、ヨーロッパ各地で宗教戦乱が拡大し、不寛容が「歴史を作って」いた。
カトリックもカルヴァン派もそれぞれが火刑台を用意し、キリストの名によって殺戮することを常習とするにいたった。
ユマニストたちはキリスト教本来への復帰を熱望していた。
エラスムスは容赦なくキリスト教会の制度の欠陥や聖職者たちの行動を批判した。
批判をするだけで、現実を変える力を持ち合わせないユマニストは、所詮無力なものだと言われる。
キリストの名のもとでキリスト教徒がお互いを殺し合うことがいかに愚劣であるか、こうした自覚を与えてくれたものは、ユマニスムの隠れた地味な働きである。
ユマニストが現代も生き続けているなら、経済問題や思想問題のために争うことも愚劣だと観じ、それらは人間が正しく幸福に生きられるようにするためにあるという根本義を必ず人々は悟るだろう。
ルネサンス期のフランスにおいて、旧教会側が不寛容で狂信的な圧力を振った。
そのために、宗教改革運動に身を投ずるにいたって人々がたくさんいる。
その一人であるカルヴァンは宗教改革運動の一方の頭領となり、自分が正しいと思った「神」に仕えねばならぬという「使命観」を抱かざるを得なくなり、その結果、旧い狂信に新しい狂信を対立せしめざるを得なくなった。
ジュネーブに拠点を置いて活動するカルヴァンは神政政治を敷き、厳格な統制と絶対権力を実践し、自由は完全に粉砕された。
誤った教理を持つ者、自分を批判する者を追放、斬首、そして火刑までして弾圧した。
カステリヨンは『異端者について』でカルヴァンを批判し、次のように言っています。
「異端者」と同じ呼び名の例として、渡辺一夫は「アカ」「非国民」をあげていますが、現在だったら「反日」「売国奴」でしょうか。
さらにカステリヨンは、異端者というものは「我々及び我々の意見と一致しない」人々にすぎず、党派宗門がたくさんあれば、当然、異端者と呼ばれる人々の数も増すわけであり、一つの村で善良な信者だと言われていた人でも、宗派の違う隣村へ行けば、異端者と見なされることもあり得ると述べているそうです。
ルネサンス期のユマニストは「これはキリストと何の関係があるか」と問うた。
キリスト教徒同士でありながら、キリストの名を掲げてお互いに殺し合うような愚劣さに対しても、自分の名声と利益とのためにキリストの言葉を歪める人々の暴状に対しても、瑣末な論議に耽って根幹となる精神を見失っている神学者に対しても、この言葉は投げかけられた。
渡辺一夫は「これは人間であることと何の関係があるか」と言い換えて問います。
そして、「寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか?」という問いを立て、「不寛容たるべきではない」と論じます。
しかしながら、ヘイトスピーチに対しても言論の自由を認めるべきかどうか、難しい問題です。
暴力を用いてもよい最悪の場合とはどんな場合を渡辺一夫は考えていたのでしょうか。














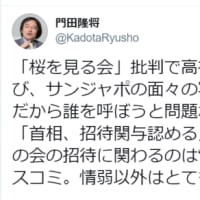
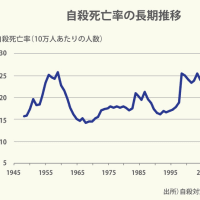
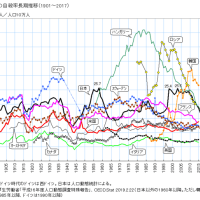

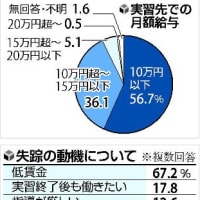







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます