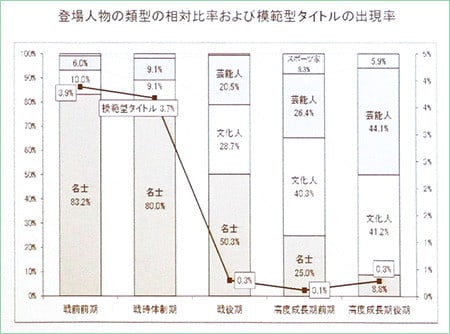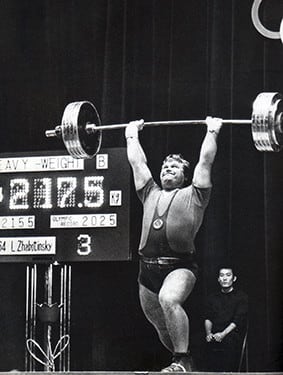「皆さんの親・兄弟・配偶者、すべての人に伝わるよう叫び続けます。日本中に言います。三重大学を倒そうとしている人たちは、この人たちだと」(汚職やパワハラに耐えかね18人中14人が退職し手術に支障が出ている三重大学病院の臨床麻酔部を率いていた60代・男性医師の音声)
新型コロナウイルスのクラスター(感染集団)が発生した静岡城北高校に対してインターネット上で「アホなのか! 全員PCR(検査)受けろ」「城北高、コロナ怖い」など同校を中傷する書き込みが10件以上確認されたことがわかった。また高校に「感染者を教えろ」「受診させろ」など対応を非難するような電話もかかるなど新型コロナの「二次被害」が起きている。県教育委員会は「教職員らが懸命に対応しているところで、高校は被害者ということを理解してほしい」と強く呼びかけている。

「なんと清らかな素朴さだろう!」初めて公衆浴場の前を通り、30~40人の全裸の男女を目にしたとき、私はこう叫んだものである。私の時計の鎖についている大きな、奇妙な形の紅珊瑚の飾りを間近に見ようと、彼らが浴場を飛び出してきた。誰かにとやかく言われる心配もせず、しかもどんな礼儀作法にもふれることなく、彼らは衣服を身につけていないことに何の羞(は)じらいも感じていない。その清らかな素朴さよ!
(中略)国家安泰には、女性の社会道徳が一役かっている。女性が一人で復讐することはありうるが、世界史を見渡してみても、女性どうし、または女性が男性と共謀して暴力沙汰や政治的混乱を引き起こしたという事例はない。
この点について、日本の権力者たちは、長い経験と人間性についての洞察によって、ある完全な答を得ていたにちがいない。彼らは、公衆浴場で民衆が自由にしゃべりたいことをしゃべっても、国家安泰にはいっこうに差し支えがないと、判断したのである。
日本政府は、売春を是認し奨励するいっぽうで、結婚も保護している。正妻は一人しか許されず、その子供が唯一の相続人となる。ただし妾を自宅に何人囲おうと自由である。 —(Hシュリーマン/シュリーマン旅行記 清国・日本/講談社学術文庫1998・原著1865)
このシュリーマンはドイツ出身で移住したロシアで商売に成功、40代で世界旅行をして清国、次いで開国直後・明治維新直前の日本を訪れた感想を著したもので、男女問わず賭け事を好み、鉄道など西欧文明を拒否する清国を「不潔で退廃的」とするいっぽう日本を「人びとは素朴で質素、世界一清潔、われわれの文明が正しいのか疑いたくなるほど」と絶賛。日本スゴイ・ホルホル。
もちろんこの素朴で清潔な異文明は維新後急速に変貌し、近代国家として列強の一角に加わるわけですが、シュリーマンが心惹かれた点の一つに彼を世話した人夫や下級役人が決して賄賂を受け取らなかったということがあり、これはいまだに警察の賄賂やタクシーのぼったくりが後を絶たない諸外国に比べ独特な美質ではないかと思う。自立した個人が形成する「社会」がない代わり、人間関係と利害関係が不可分に連なる「世間」の目が人の言動を律する。
明文化された法治でない、相対的に移り変わる人治。なので世間とインターネットはものすごく相性が悪い。ウシジマくん・フーゾク編の女たちは杏奈の前ではその場にいない瑞樹の悪口を言ったり情報交換で盛り上がるが、杏奈が去ると杏奈の悪口を言う。媚びるとか裏切るとかの自覚もないその場限りの社交。のためにも酒が必要。コロナの緊急事態宣言、再び出せばGoToの失敗を認めることになるとか東京など3人の知事から求められて出すのは面子がとか政治家も売春婦レベル。子どものころからスマホ(バカホ)にさらされ刹那的な生き方を強いられる若者層もそういう悪事に長じる自民党に共感。阿片と賭博が蔓延する、モラルの荒廃した末期清朝、そうならないために頭を下げて西欧文明を取り入れたわーくにが150年遅れで似た末路を辿ることになったのは皮肉な歴史といえよう。





















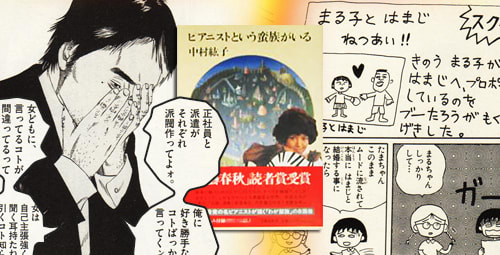





 の男女同権レベルの順位はこれからも下げ止まったままではないか。
の男女同権レベルの順位はこれからも下げ止まったままではないか。