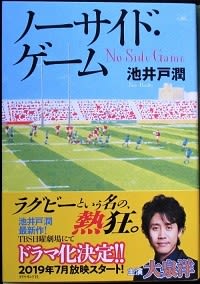
「第四章 セカンドシーズン」 ―1、2―――
(満員のホームでリーグ戦開幕された。若いハーフ団だ)
9月第1週の土曜日。リーグ戦の開幕を迎えた。
キックオフは午後7時。トキワスタジアムは、1時間前の会場と同時に客席が埋まり始め、試合開始10分前には自由席までほぼ満員の状態にまで膨れ上がっていた。
「こんなに大勢のお客さんに来ていただけるなんて」
多英は万感胸に迫る表情で、ピッチサイドからスタンドを見上げている。
君嶋は言った。「このお客様の平均単価は約2千円だ」
通常のプラチナリーグのチケット平均単価は1千円ちょっとで、その倍近い価格で販売していることになる。
この1万5千人分のチケットの殆どをアストロズが協会から安く買い取り、自前のルートで売りさばいたのだ。
新たに開催したアストロズ・ホームページからのチケット販売、いまや会員数2万5千人を誇るアストロズ・ファンクラブーーーこの二つの販売チャンネルは、どちらも君嶋が立ちあげたのだ。
肝心なことは、どこの誰が、どんなチケットを購入したかを把握できることだ。性別や年齢、職業まで把握しており、君嶋は、この日の観客の男女比が6対4で、購入者の平均年齢が32歳であることも知っている。
日本蹴球協会からチケットを安く卸して高く売ることで、アストロズはこの試合で約1千万円のチケット収入を得た。さらに、アストロズのファン層が特定できたことで、ホームページやスタジアムの広告主を絞り込み、チケット収入を上回る広告収入の獲得にも成功している。
それはどれも日本蹴球協会の運営に依存していては、絶対に実現しなかったものばかりであった。
君嶋がメインスタンドの関係者席につくと同時に選手たちが入場してきた。
開幕戦の相手であるサクラ製鋼インパルズは強豪で油断ならない相手だが、満員のファンで埋まったホームで迎え撃てるのはアストロズにとって大きなアドバンテージに違いない。
電光掲示板と場内アナウンスが出場選手を発表して盛り上げていく。
背番号3のプロップ友部が紹介されると、スタジアムに一段と大きな拍手が沸き上がった。友部は休みになると、お土産にラグビーボールを持って市内の小児科病院に入院している子供たちを励まし続けているのだ。
どよめきが起きた。
ハーフ団――つまりスクラムを組むフォワードと、トライゲッターのバックスとのつなぎ役である、スクラムハーフとスタンドオフの二人が発表されたからだ。
背番号9、スクラムハーフは佐々である。昨年のサイクロンズ戦で後半投入されていい働きをしたから目の肥えたファンは知っている。
本当のどよめきを生んだのは、スタンドオフ七尾圭太がコールされたときであった。
―――浜畑じゃないのか。誰もがそう思ったに違いない。
ここにいる客の殆どが、七尾についてほとんど何の知識もない。しかも、驚くべはその若さだ。
ハーフ団は、いわば攻撃のしきり役である。なのに、佐々が2年目で七尾は1年目だ。
この重要な開幕戦に、ベテランの浜畑を最初から出さないのは何ゆえだ。こんなハーフ団で本当に戦えるのか。
だが、それが単なる杞憂であることを、誰でも気づくそのときが近づいている。
やがて、試合開始を告げるキックオフの笛が鳴った。
最初のラインアウトだ。スクラムハーフの佐々が素早く捌き、ボールが七尾に渡る。
密集に走り込み、あとわずかで抜けようというところで惜しくもタックルされたが、その瞬間、ボールは逆サイドからスピードに乗って走り込んできたバックスの選手にパスされていた。
完璧なオフロードパス—ータックスされながらのパスだ。虚を突かれた相手ディフェンスの対応が遅れ、小さな穴ができた。それを見逃すことなくアストロズのバックスがゴールポスト横へと走り込んでいく。
あっけないほどの先制トライが生まれたのは、開始わずか5分のことであった。
「第四章 セカンドシーズン」 ―3―――
(本当の悪人・脇坂の姿が見えてきた)
ノーサイドの笛が鳴ったとき、君嶋は安堵のため息と共に立ち上がると、新堂工場長そして多英と握手した。スコアは36対10の大差だ。
前半に三っつ、後半に二つトライを奪い、逆に強豪インパルスのトライを一つだけに抑え込んだ完勝だ。
脳裏に焼き付いているのは、七尾を中心とする華麗な攻撃の数々だ。意表を突くオフロードパス、いったいどうやって投げたか分からないほどのショートパス、大胆な一人飛ばしパス、佐々やバックス陣との多彩なサインプレー。さらに特に印象的なのは、時に効果的に繰り出される正確なキックパスであった。
「君嶋くん」
思いかけず声をかけられた。そこに立っていたのは、滝川桂一郎その人であった。
かって常務取締役として権勢を誇った滝川が、本社役員を外れ、業績の悪化した金融子会社の社長に転じたのは3月のことであった。その滝川がアストロズの試合の観戦すること自体、ありえないことのように思えた。
「座らないか」、滝川に言われ、並んでシートにかけた。
「滝川さんには、アストロズの運営について非常に有意義な指摘をいただいたと思っています」
「ここまでよくやったな。しかし、今シーズンしかないかも知れないな。脇坂が潰しにかかっていることは聞いたよ」
「一つ申しあげておきたいんですが」
君嶋は言った。「あのカザマ商事の隠蔽工作を暴露した報告書ですが、あれはーー」
「君が調べたんだってな」
滝川は知っていたが、君嶋が言わんとすることはそこではない。
「そうです。ただ私は、あの報告書を取締役会の一週間前に脇坂さんに上げていたんです。それは、取締役会であんなふうに使われるためではありません。もっと前の段階で、営業部に事実を知らせることだってできたし、そうすべきだったと思います」
「だが脇坂は、それを私を追い落とすために使った」
淡々と語る滝川は、澄み渡った瞳に硬質な性格を映していた。
「私には滝川さんを追い詰める意図はありませんでした。それだけはお伝えしておきます」
「だが、君もよく調べたな。正直、あの報告書には感服した」
ぽんと膝を打って立ち上がりながら、滝川は言った。
「自分の目がいかに節穴か、頭から冷や水を浴びせられたような気分だった。脇坂がどうやって調べたのかと思ったが、あとで実は君の仕事だと聞いて納得したよ。資金が引き出された銀行口座の明細まで調べ上げるとはね。私の負けだ」
立ち去ろうとした滝川は、ふと怪訝な眼差しを君嶋に向けた。「どうかしたか」
「いえ」
君嶋は小さく首を振ってから、「今、資金が引き出された銀行口座の明細まで調べ上げたとおっしゃいましたか」、そうあらためて問うた。
「それがどうかしたか」
「私の報告書に、その項目はありませんでした。確かに現金を渡したという青野氏の証言と森下教授の受領書のコピーがあっただけです」
疑問を浮かべた滝川の目が、君嶋に向けられる。
「どういうことかね、それは」
「わかりません」
君嶋が答えると、滝川は数歩歩きかけたところで足を止めた。そして、
「君を、横浜工場に飛ばしたのは、私じゃないからな」
意外なことを口にした。「私は、そんなケチなことはしない。いつも論理的ではあったが、お前のような奴は経営戦略室には必要だと私は思っていた。いまそうだ」
滝川はひょいと右手を挙げて去って行った。
「第四章 セカンドシーズン」-4-- に続く














