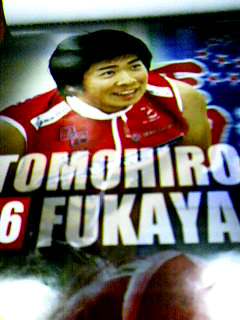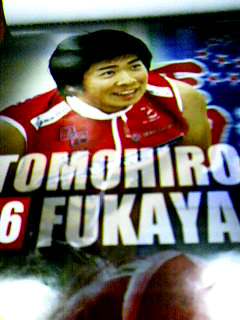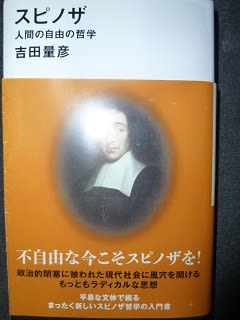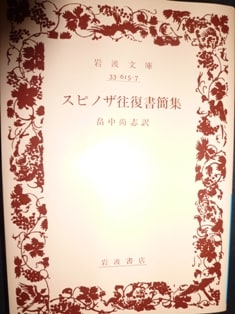スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。
静岡記念の決勝 。並びは新山に浅井,真杉‐坂井の栃木,深谷‐岩本の南関東,嘉永‐荒井の九州で河端は単騎。熊本記念 以来の優勝で記念競輪22勝目。静岡記念は初優勝。このレースはだれが先行するのかを予想するのも難しいメンバー構成で,展開次第でだれにでもチャンスがありそうなレースだと思っていました。新山の先行は最も考えられる展開だったのですが,真杉が早い段階で発進したので先行争いになり,後方で足を溜めた深谷が有利になりました。河端もこのラインを追っていたと考えればラインでの上位独占ですから,前にいた選手に厳しいレースだったということがよく分かると思います。第一部定義六 により,神Deumは絶対に無限absolute infinitumです。神が絶対に無限であるためには,ある属性attributisは備えていても別の属性は備えていないというわけにはいきません。そうではなく,無限に多くのinfinitis属性を備えていなければならないのです。第一部定義六の前半部分と後半部分は,こうした条件によって接続されていることになります。第一部定理二五系 はこの観点から記述されていると解しておくのがよいでしょう。もちろんこの系Corollariumは,僕たちにとって未知の属性の個物Res particularesに対しても妥当するのは間違いないと僕は考えますが,僕たちが延長と思惟のふたつの属性しか認識することができない以上,僕たちが認識できる個物は延長の属性Extensionis attributumの個物である物体corpusか,思惟の属性Cogitationis attributumの個物である物体の観念ideaのどちらかであることになるからです。よって再びこの系に注目すれば,物体は延長の属性によってみられる神を一定の仕方で表現するexprimuntur様態modiであることになりますし,物体の観念は,思惟の属性によってみられる神を一定の仕方で表現する様態であるということになります。
奈良記念の決勝 。並びは佐々木に山崎,道場‐松井‐郡司の南関東,古性‐三谷‐山本の近畿で皿屋は単騎。小田原記念 以来となる3勝目。奈良記念は初優勝。このレースは南関東勢の二段駆けが有力で,すんなりそうした展開になってしまえば松井と郡司の優勝争いになるでしょうから,古性がそうはさせまいと分断策に出るだろうと予想していました。僕は古性が前受けして道場が押さえにきたところで松井のところに飛びつくような展開を想定していたのですが,スタートを郡司に譲るような形で南関東の前受けになりましたので,松井は競られにくくなりました。郡司と古性の競りになったのは展開によるものですが,競りは競輪の醍醐味のひとつではあり,郡司と古性のように力がある選手同士だとなおさらなので,車体故障であっさりと決着がついてしまったのは残念な気がします。直線が短いとはいえ楽に古性にマークされることになりましたので,それを振り切った松井は称えてもよいでしょう。共通概念 notiones communesを通しての認識 cognitioについての場合にも当て嵌まると僕は考えています。第二部定理三八系 でいわれているように,僕たちの精神 mensのうちにはいくつかの共通概念があるのですが,この系Corollariumの証明Demonstratioの様式からすれば,僕たちの精神のうちには,少なくとも延長の属性Extensionis attributumの十全な観念idea adaequataがあるということが帰結しなければならないと僕は考えています。このことについてはかつて検討しましたので,ここでは詳細は省きます。そしてこの延長の属性は神Deusの本性essentiaを構成する属性なのですから,これは神を十全に認識するcognoscereということと同じことであると僕は考えています。したがってこの観点からも,現実的に存在する人間の精神mens humanaのうちには,神の十全な観念が必然的にnecessarioあるということが出てくるという見解opinioを僕は有しているのです。第一部定義六 でいわれている神の観念を余すところなく表現しているかといえば,ぼくはそのようには考えません。これもまた延長の属性によって説明される限りでの神の十全な観念が僕たちの知性 intellectusのうちにあるということを意味するのであって,絶対に無限な実体substantiaとしての神,無限に多くのinfinita属性によってその本性を構成される限りでの神の十全な観念が僕たちの精神のうちにあるという意味にはならないと僕は考えるconcipereのです。
高松記念の決勝 。並びは郡司‐松谷‐福田の神奈川,田中に成田,犬伏‐島川‐香川の四国に坂本。松阪記念 からの連続優勝で記念競輪22勝目。高松記念は初優勝ですが,2017年のウィナーズカップ を当地で制しています。このレースは郡司の脚力が上なので,逃げなければならないような展開にならない限りは勝てるのではないかと思っていました。田中の前受けというのは意外な展開だったと思うのですが,後方から動いて無理なく3番手に入れたのが大きかったです。それでも犬伏には一旦は出られてしまったわけで,完勝といえるような内容ではなったのも事実ではないでしょうか。第一部定義三 でいわれているように,実体というのはそれ自身のうちにあり,かつそれ自身によって概念されなければならないのであって,ネコとかイヌとかいったものは,その定義 Definitioからは外れることになるからです。そしてここが重要なところですが,このことが意味するのは,第一部定義三のような仕方で実体を定義するのであれば,一般に実体として考えられているようなものはすべて,すべてがいいすぎならほとんどは,実体ではないということになるということです。といのも,もしそれがそれ自身のうちにあってそれ自身によって考えられるなら,そのものは存在するために自分以外のものは不要ですし,それを概念するために別の概念notioを必要としないでしょう。いい換えれば一切の外部を必要としないことになるでしょう。
松坂記念の決勝 。並びは深谷‐郡司‐岩本の南関東,古性‐岩津の西日本,山田‐小川の九州で佐藤と浅井は単騎。小田原記念 以来の優勝で記念競輪21勝目。松阪記念 は連覇で2勝目。2019年の共同通信社杯 も当地で勝っています。このレースの注目点はふたつで,ひとつは深谷‐郡司という強力な並びを分断しにいく選手がいるかということで,もうひとつは仮に南関東勢がすんなり先行となった場合に古性が捲れるのかといううこと。だれも分断策には出ず,古性の位置取りが悪くなりましたので,郡司には最高の展開になりました。引きつけずに発進すれば岩本とのワンツーになったと思われますが,これは先行した深谷をなるべく上位に残すための走り方で,基本的に郡司はこのような走行をします。古性は深谷が突っ張ることを見越して,動かずに岩本の後ろを回っていた方がよかったでしょう。これは作戦の失敗だと思いますが,山田がよく頑張ったともいえると思います。第二部定理七系 でいわれているように,神が思惟する力Dei cogitandi potentiaは神が行動する力agendi potentiaと等しいので,ある形相的有esse formaleが何らかの属性attributumのうちに存在するなら,その観念ideaが思惟の属性Cogitationis attributumのうちにあることになります。このとき,書簡六十四 および書簡六十六 でスピノザがいっていることは,Aの属性のある個物res singularisの観念と,それとは別のBの属性の個物の観念は,同じように観念という思惟の属性の個物であるのだけれど,それらは様態的にmodaliter区別されるのではなく実在的にrealiter区別されなければならないということであると僕は解しました。もしもそれらが様態的に区別されるのであれば,たとえばAの属性の個物はAの属性の様態modusだけを認識するcognoscereのではなく,Bの属性の様態も認識することになるでしょうし,そればかりではなく無限に多くのinfinitaすべての属性の様態も認識されることになります。しかしそれらの書簡でスピノザは明確にそれを否定しています。ということは,各々の属性の観念の区別distinguereは様態的区別ではなく実在的区別でなければならないのです。チルンハウス Ehrenfried Walther von Tschirnhausはこの路線でスピノザの主張を解していたのです。そしてこの場合は,僕たちは僕たちの世界と別の様態によって構成される別の世界を認識することができるようになりますから,僕たちの世界の外部に別の世界があるというように認識することになります。いい換えれば僕たちの世界には外部があると認識します。ところが実際にはこのチルンハウスの解釈は誤りerrorで,物体corpusの観念と未知の属性の個物の観念は実在的に区別されるのですから,僕たちの精神mensがそうしたものを認識することはありません。よって僕たちは僕たちの世界以外の世界を認識することがないので,僕たちの世界の外部には別の世界はないと結論することになります。つまり僕たちの世界には外部はないという結論に至るのです。このように,この区別も内在と関連するのです。
昨年の競輪の表彰選手 は22日に発表されました。当ブログに関連する選手を紹介していきます。オールスター ,寛仁親王牌 ,グランプリ とビッグを3勝。和歌山記念 ,松山記念 ,函館記念 ,富山記念 と記念競輪は4勝。グランプリを勝ってGⅠも2勝ですから当然でしょう。2021年 ,2023年 に続き2年連続3度目のMVP。ウィナーズカップ ,競輪祭 とビッグは2勝。福井記念 ,向日町記念 と記念競輪は2勝。2018年 と2019年 に続き優秀選手賞は5年ぶり3度目の受賞。全日本選抜 を優勝。川崎記念 と小田原記念 を制覇。優勝以外の安定した成績でふたり目に滑り込んだ感です。2020年 と2021年に続く3度目の優秀選手賞。ヤンググランプリ を優勝。脚力的にはヤンググランプリ出走選手の中にはもっと上の選手がいましたが,実績を得たことでの受賞でした。高松宮記念杯 を優勝。北井は選手歴は浅いですが若いわけではないので,これからの数年が本当の勝負どころだと思います。第一部定理五 から内在の哲学が必然的にnecessario帰結することになっているとはいえ,この定理Propositioは僕がいうところの名目的定理であって,複数の実体substantiaが存在することが否定されているわけではありません。実際は第一部定理一四 にあるように,実在する実体は神 Deusが唯一なのですから,このこと自体に大きな意味がないように感じられるかもしれませんし,このような論理的帰結に何か意味があるようにも思えないかもしれません。なので実在的な意味からも説明を加えておくことにします。本性 essentiaは第一部定義六 から分かるように,無限に多くの属性infinitis attributisから構成されています。僕たちが認識するcognoscereことができるのは延長の属性Extensionis attributumと思惟の属性Cogitationis attributumですから,僕たちが認識することができない無限に多くの属性があるわけです。これを神からみれば,それらの属性のどれを抽出したとしても,それが神の外部にあるということはできません。たとえばその属性のうちでどのようなことが生じたとしても,やはり第一部定理一八 にあるように神は内在的原因 causa immanensとしてその事象に対して働くagereのですから,神には外部がないということは明白でしょう。第一部定理二一と第一部定理二二 から,どのような属性にも直接無限様態と間接無限様態があると解さなければなりませんから,僕たちが認識しているような世界は,すべての属性のうちにあるでしょう。
大宮記念の決勝 。並びは佐々木悠葵‐武藤の関東,寺崎‐脇本‐村上の近畿の番手に佐々木真也の競り,嘉永‐徳永‐嶋田の九州。高松記念 以来の2勝目。このレースは佐々木真也が事前から競りのコメントを出し,実際にそのようなレースに。脇本は引くような形で3番手になったので,脚は残っているかと思ったのですが,意外なほどスピードが上がりませんでした。車体に何か問題が生じたのかと思うほどでした。佐々木悠葵の捲りはマークの武藤が離れてしまったほど素晴らしいもので,このレースは展開が向いたという感じはありますが,この開催の調子のよさを十分に生かしきったと思います。第二部定理一三系 では,人間の身体Corpus humanumは僕たちがそれを感じている通りに存在するということが証明されています。デカルト René Descartesは,自分の身体が存在するということは確実視できなかったので,神Deusを通してこのことを論証するに至りました。それに対していえば,スピノザはそのような論証過程を経ずとも,人間の身体が現実的に存在するということを論証したことになります。ただ一方で,このことは,定理Propositioとして論証されているわけですから,僕たちが思惟しているということ,したがって思惟している僕たちの精神mensが現実的に存在するということが公理Axiomaとして,すなわちそれ自体で明らかなこととして示されているのとは異なり,それは自明ではなく,論証されなければならないことであったことも確かです。自分の身体が存在するということについては論証Demonstratioによって確実視されることであるけれど,自分の精神が存在するということについては論証を経ずともそれ自体で確実視できることであるという相違がスピノザの哲学には確かにあるのであって,そのことを僕たちに教えてくれるというだけで,吉田が第二部公理二を援用していることは意味のあることだと僕は考えるのです。
和歌山記念の決勝 。並びは菅田‐大槻の宮城,古性‐山口の近畿中部,石塚‐東口‐椎木尾の和歌山,松本‐山田の西国。グランプリ から連続優勝。記念競輪は富山記念 以来の13勝目。和歌山記念は昨年 からの連覇で2勝目。このレースは脚力で古性が断然の上位。ただ和歌山勢の邪魔はできないでしょうから,そこがどう出るかといったところ。松本が地元勢に競り込んで,番手を奪っての発進でしたから,届くかどうか心配なところもありましたが,問題ありませんでした。結果的には隊列が短くなった分よかったのかもしれません。菅田を叩いた後で菅田がインから巻き返そうとしたのですが,その巻き返しを許さなかったのがとても大きかったと思います。神 Deusが世界を創造するcreareというときには,まず神が存在して,その後に創造された世界が存在するようになるということが必要とされます。したがってこの場合は,単に原因causaである神が世界に対して本性naturaの上で先立っているだけでは十分ではないのであって,存在existentiaの上でも神が世界に先立っていなければなりません。しかしすでにみたように,スピノザの哲学では,原因である神が結果effectusである直接無限様態に対して本性の上では先立ちますが,存在の上で先立つわけではありません。同様に,原因である直接無限様態は本性の上では結果である間接無限様態に先立ちますが,存在の上では先立つわけではありません。純粋に存在だけに目を向けた場合には,神も神の本性essentiaを構成する属性attributumも,直接無限様態も間接無限様態も,同じ意味で永遠aeternumであるといわれるのであり,永遠から永遠にわたって存在するという意味においては,区別はないからです。なのでスピノザの哲学では,僕たちが普通に解するような意味においては,神が世界を創造するということが否定されていると解さなければなりません。他面からいえば,神がある事柄を意志するからそのような世界が創造されるというわけではないだけでなく,神がある事柄を認識するcognoscereから,そう認識された世界が創造されるというわけでもないのです。第二部定理七系 でいわれているように,神が思惟する力potentiaは神が現実的に行動する力と等しいのであって,それを上回っているわけではありません。神がある事柄を思惟したらその事柄は現実的に生じているのですが,それは前者が原因で後者が結果であるという関係にあるわけではなく,ある事柄が神の力によって現実的に生じたら,そのことの観念ideaも神のうちにあるという以上でも以下でもないのです。
立川記念の決勝 。並びは郡司‐岡村の南関東,藤井‐山口‐清水の中部近畿,取鳥‐園田の西国で平原と高橋は単騎。名古屋記念 以来の記念競輪2勝目。GⅢは3勝目。一昨年は日本選手権を優勝したので昨年はS班でしたが優勝はありませんでした。このレースは藤井の先行が有力で,その番手から発進するであろう山口を,郡司が捲れるかというのが最大の焦点。山口の番手捲りがあるとはいえ,郡司はそのラインの4番手追走と,作戦面は悪かったわけではありません。藤井の後ろから山口に番手捲りをされると,郡司の力ではやや及ばないということなのでしょう。デカルト René Descartesのこの考え方は,スピノザによって否定されるいくつかのデカルトの考え方のうちのひとつであって,そういってよければその代表的なもののひとつです。つまりこれはあくまでもデカルトの考え方の説明なのであって,スピノザがそれに同意しているわけではありません。確実性certitudoの問題は真理veritasのしるしsignumの問題に還元されることになるのですが,スピノザにとって真理のしるしとは真理それ自身にほかなりません。スピノザの哲学における真理というのは,真の観念idea veraの総体を意味しますから,思惟の様態cogitandi modiであって,かつ個々の真の観念が個々の真理のしるしである,あるいは同じことですが真の観念が個々の真理の確実性を保証するのです。このために神Deusが存在している必要はありませんし,神を十全に認識している必要もありません。ただ現実的に存在するある人間の精神mens humanaのうちにXの真の観念があるのであれば,それ以外の何も必要とせず,その人間はXについて確実であることができます。これは,Xの真の観念が現実的に存在するある人間の精神のうちにあるのであれば,その同じ人間の精神のうちにXの真の観念の観念idea ideaeもあるとスピノザは主張するからです。よって現実的に存在するある人間の精神のうちにXの真の観念があれば,その人間はXの真の観念を知っているということを知ることができるので,Xについて確実であることができるということです。スピノザはこのような考え方を,デカルトの哲学の解説書である筈の『デカルトの哲学原理 Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae 』の中ですでに仄めかしているということは,かつて検討した通りです。
12月30日に静岡競輪場 で行われたKEIRINグランプリ2024 。並びは真杉‐平原の関東,北井‐郡司‐岩本の南関東,脇本‐古性の近畿で新山と清水は単騎。寛仁親王牌 以来の優勝でビッグ10勝目。グランプリはやはり静岡で開催された2021年 に優勝していて3年ぶりの2勝目。ほかに静岡では2018年 と2019年 に記念競輪を制しています。このレースは北井が楽に先行して無風で番手を回れた郡司が番手捲りに出るというような展開にでもならない限りは近畿勢が優勢で,番手の古性が最有力候補だろうとみていました。真杉を叩いた後で北井があまりスピードを上げなかったのがどういう理由だったのかは分かりませんが,このために脇本の先行となり,僕が予想していたような結果となりました。単騎のふたりのうち,新山は単騎戦が不得手ですが清水は得意としているタイプなので,こういう結果も十分に予測でき,配当は意外なほどついたという印象です。我思うゆえにわれあり cogito, ergo sum」は,デカルト René Descartesが確実なものを求めた結果effectusとして得ることができた結論ですが,吉田がいっているようにあくまでもこれは第一の結論です。哲学を開始するためには確実なことが必要であるから確実なものが求められたのですから,この結論は最終的なものというより,哲学を開始するための出発点であったという方が正しいのです。
12月28日に静岡競輪場 で行われたヤンググランプリ 。並びは中野‐大川の北日本,村田‐纐纈の中部,太田‐真鍋の瀬戸内,後藤‐東矢の九州で山口は単騎。誤謬 errorを犯したり夢を見たりすることはあるとしても,そのことを考えているのが自身であることは変わりありません。したがって,自身が何かを考えているということは確かに成立しているとデカルト René Descartesは気付きました。ということは,その考えている主体subjectumである自分自身が存在しているということもまた成立しているとデカルトは結論しました。したがって,自身が向き合っている世界は不確実で頼りないものとデカルトは疑い得たとしても,その不確実で頼りない世界と向き合っている自分自身が存在しているということは確実である,つまり疑い得ないとデカルトは結論したことになります。これが「我思うゆえに我ありcogito, ergo sum」といわれるデカルトの第一の結論です。
昨日の佐世保記念の決勝 。並びは佐々木‐末木の上甲,深谷‐渡辺の静岡,窓場‐稲川‐村田の近畿,松浦‐荒井の西国。ステノ Nicola Stenoは,上申書を書いている間,バチカン写本 が含んでいる毒に,たとえ偶然にでもだれかが触れてしまうことがないように,バチカン写本を肌身離さず持ち歩いていたと語っているそうです。もしステノのこのことばが,上申書を提出してからバチカン写本を提出するまでのおよそ3週間の期間を含んでいるのであれば,辻褄は合うことになります。しかしそうであるなら,ステノがどこでそのように語っているかということを問題としなければなりません。発見されたバチカン写本は発刊され,それに解説とステノの上申書が付せられているのですから,普通に考えればこれは上申書の中でステノが語っていることばだと思われます。実際にこの文章は,上申書を提出するまでの間はバチカン写本を肌身離さず持っていたというように読解できますから,上申書に書かれている内容であると解する方が自然でしょう。とすると,上申書を提出してからバチカン写本を提出するまでの3週間の期間のことはここには含まれていないということになるでしょう。もちろんその3週間の間も,ステノがバチカン写本を肌身離さず所持していたということは間違いないと僕は思いますが,なぜ上申書とバチカン写本の提出の間に3週間の期間があったのかということは謎として残ります。上申書はバチカン写本に関する説明なのですから,上申書の内容を審査するためには,資料としてバチカン写本が必要だったと僕には思えるからです。Opera Posthuma は同年の暮れになってからオランダで発刊されました。ローマカトリックはその遺稿集に対して異例の早さで禁書指定に動き,実際に禁書となりました。これはステノのカトリックに対する大きな功績といえるでしょう。もちろんそれはカトリックに対するという前提なのであって,自由思想家にとってはステノの動きは迷惑なものでしかなかったことは間違いありません。
玉野競輪場 で行われた昨日の広島記念の決勝 。並びは新山‐菅田‐渡部の北日本,太田‐松浦‐池田の山陽で鈴木と佐々木と山田は単騎。岐阜記念 以来の優勝で記念競輪22勝目。広島記念は2018年 ,2021年 ,2022年 と優勝していて2年ぶりの4勝目。玉野では2022年のサマーナイトフェスティバル と今年 の記念競輪も優勝しています。このレースは太田と新山の先行争いがあるかどうかがひとつの焦点。太田がすんなりと先行することができましたので,番手の松浦にとってとても有利になりました。近年に比べると苦労した1年でしたが,脚力は戻ってきているようですので,来年は期待できるのではないでしょうか。神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』は,匿名で出版されたのですが,著者がスピノザであるということは公然の事実でした。だから書簡四十二 はフェルトホイゼン Lambert van Velthuysenの論考を求めたオーステンスJacob Ostensがスピノザに送ったのですし,スピノザは自身が著者であることを隠そうとせずオーステンスに宛てて書簡四十三 という返信を書いています。またライプニッツ Gottfried Wilhelm Leibnizに宛てた書簡四十六 ではスピノザは私の『神学・政治論』といういい方をしていますし,書簡七十 によればスピノザは自著として『神学・政治論』をホイヘンス Christiaan Huygensに献本しています。もちろんこうしたことは書簡の中のことであって,書簡を交わし合うような仲の人物に対しては『神学・政治論』が自著であるということを隠す必要はないとスピノザが考えていたがゆえであったかもしれません。しかしそこでそのことを否定する必要がないほど,『神学・政治論』の著者がスピノザであるということは公然の秘密であったからだという見方もできると思います。ステノ Nicola Steno自身も書簡六十七の二 の中で,『神学・政治論』という名前こそ出していませんが,それと理解できるような文章において,その本がスピノザの手によるものだと多くの人がいっているし,自分もそう思っているといっています。もしもスピノザがステノに対して『神学・政治論』を献本していれば,はっきりとそういいきれた筈ですから,スピノザはおそらくステノには『神学・政治論』を献本しなかったのでしょう。書簡七十六 の内容によって,スピノザはステノがカトリックに改宗したことは間違いなく知っていました。研究活動よりも宗教活動に中心を移行したということももしかしたら知っていたのかもしれません。それはおそらく,書簡六十七の二の中でステノがいっているように,ステノがイタリアに移ってからもスピノザとステノは疎遠ではなかったため,ステノがスピノザにそれを知らせたからでしょう。すでに指摘しておいたように,遅くとも『神学・政治論』が出版された時点では,ステノはカトリックに改宗していましたから,そのことが影響したと思われます。
8日の松山記念の決勝 。並びは山崎‐大槻の北日本,深谷‐松谷‐山賀の南関東,犬伏‐松本‐橋本の四国で浅井は単騎。防府記念 以来の優勝で記念競輪3勝目。松山記念は2021年 にも優勝していて2勝目。このレースは犬伏の先行が有力で,松本の二段駆けが見込めるところ。それを脚力で上位の深谷が捲れるかが焦点。この焦点通りのレースになりました。松本がただ番手から捲っていくのではなく,深谷を牽制するように発進していったのがうまく,最後まで抜かせないことに成功。純粋な脚力勝負になっていれば少なくとももっと差は詰まっていたでしょうし,あるいは深谷の逆転まであったかもしれません。書簡六十七の二 は,スピノザに宛てられたわけではなく,パンフレットのような公開書簡であったとしてみましょう。この場合は考慮しておかなければならない点があります。書簡六十七 と書簡六十七の二の大きな差異は,何度もいっているようにその内容にあります。アルベルト Albert Burghはスピノザに対して憎悪のような感情affectusを抱いていて,それを剝き出しにしています。しかしステノ Nicola Stenoの書簡からスピノザに対する憎悪のような感情はみられません。むしろ感情としていえば,憐れみcommiseratioに近いものが感じ取れるのであって,誤った道に進んでいるスピノザを,カトリックという正しい道に誘導しようという,一種の心遣いが感じられます。
大垣記念の決勝 。並びは中野に瓜生,森田‐坂井‐白岩の関東,山口‐不破の岐阜,松浦‐中本の西国。四日市記念 以来となる記念競輪2勝目。このレースは熊本勢がふたりいたのですが,中本は松浦,瓜生が中野の後ろを選択したので,それぞれにラインのある4分戦になりました。マーク選手よりも自力の選手の方が力量は上だったので,並びが出た時点で自力型の力勝負になると予想。坂井は自力があってかつ森田をマークできるのでチャンスはあるとみていました。森田が飛びつきを狙うレースになったので,マークを外すような形で山口の外を並走になったのですが,かえってそれが幸いしました。マークを守って山口と内と外が逆になっていたら,優勝は山口だったかもしれません。書簡六十七の二 でステノ Nicola Stenoがスピノザのことを今でも疎遠ではないというとき,この今というのいうのが当然ながらステノがこの書簡を書いている時点の今であるということは明白です。この書簡は1675年にフィレンツェで書かれたものと推定されますから,その時点でもステノはスピノザを疎遠ではないと思っていたことになるでしょう。なお,この書簡にはスピノザの名前は出ておらず,宛先は新哲学の改革者となっていますし,書簡の文中ではあなたといわれていますが,それがスピノザを意味することは間違いありません。また,この書簡の冒頭に,あなたの著作であると他人がいい,ステノ自身もいろいろな理由からそのように思っている本,という表現がありますが,この本が『神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』を意味することも間違いないでしょう。マイエル Lodewijk Meyerとかシモン・ド・フリース Simon Josten de Vriesといったような,スピノザの親友たちとの交わりに比較したならそれほど親密ではなかったといえるでしょうが,スピノザと面会したことがある人物のうちブレイエンベルフ Willem van Blyenburgとかライプニッツ Gottfried Wilhelm Leibnizと比べたら,少なくとも遜色なく,あるいはそれ以上に親密であったと考えてよいように思います。Opera Posthuma に掲載されなかったのは不自然であるということをあげています。これは説得力があります。
小倉競輪場 で争われた昨晩の第66回競輪祭の決勝 。並びは菅田‐松谷の東日本,寺崎‐脇本‐村上の近畿,犬伏‐松浦‐荒井の西国で浅井は単騎。向日町記念 以来の優勝。ビッグは3月のウィナーズカップ 以来の11勝目。GⅠは2022年のオールスター競輪 以来の8勝目。競輪祭は初勝利。このレースは寺崎が後ろからの周回になったので,前受けの犬伏を叩きにいくことになりました。そのときに犬伏が飛びつくのではなく,引いて巻き返すという戦法を採ったので,脇本が無風で番手を回れることに。犬伏の発進に合わせて番手から発進し,後ろに犬伏に入られてしまったのですが,小倉で1周くらいの先行であれば,自力型の犬伏に番手に入られてしまっても,余裕で振り切るだけの脚力があるということでしょう。犬伏は自分が勝つための戦法ですから,これはこれで悪くないと思いますが,脇本との差をほとんど詰められなかったのは課題といえそうです。Opera Posthuma が発刊される以前に遡ることができる『エチカ』の手書きの原稿が発見されたというものでした。それは,スピノザ本人の自筆の草稿ではないものの,おそらく自筆の原稿から丁寧に写し取られた写本であるということまでそこでは伝えられていました。ホイヘンス Christiaan Huygensに宛てた自筆の書簡が現存していて,その筆跡によって鑑定された結果ですから,歴史的事実であると解して大丈夫です。実際に写本が書かれたのは,こちらは想定で,1674年末か1675年初めとされています。かなり短い期間に特定されていますので,これも想定とはいえ,ほぼ歴史的事実と解して大丈夫でしょう。このあたりのことは『スピノザー読む人の肖像 』に書かれていて,それを検討したときに書いていますので,より詳しいことはその部分を読み直してください。