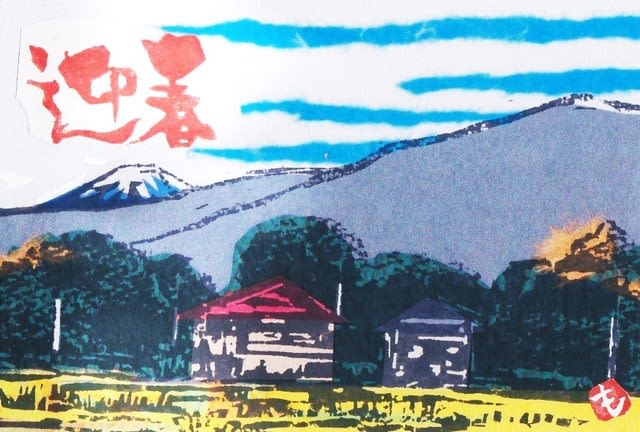(^^♪ ジャーン!!
上の写真は合成による妄想(孟想というべきかも)写真です。
野菜の栽培教科書によると・・・
スイカの苗は植え付け後、本葉が5~6枚のところで蔓の先端をカットし、子蔓を4本のばし・・・中略・・・1株で大玉スイカなら2個、小玉スイカなら4~5個を収穫・・・それ以上に実を着けると甘さが落ちると書いてあったが・・・

数年前に野良友から放任栽培(別名無摘芯栽培)によって1株の苗から20個以上ものスイカが収穫でき、甘さも変わらない・・・と言う話を聞き及び、ものは試しに・・・と4年前から小玉スイカの放任栽培をしてみたところ、毎年18個・15個・16個、最後の一個まで甘くておいしいスイカが収穫できた。
*大玉スイカは1個でも冷蔵庫に入らないから・・・と女房に栽培を禁じられています。

しかし、放任栽培4年目の昨年の夏は、蔓枯れ病に犯され、たった3個の収穫をしただけで、あえなくダウン⤵
そんな経緯があっての今年のスイカ栽培だから、力も入ろうというもの・・・。

スイカ栽培予定地は、畑というより土木作業現場という感じになっています。
スイカの苗の植え付け時期は5月上旬というのに、もう1ケ月も前から土の入れ替え・相模川の河川敷から篠竹を伐り出して運ぶなどをはじめ、頭の中はすっかりスイカの収穫期にすっ飛んで、スイカの畝の準備はもう90%完了しました。
今年のスイカ栽培は、2株を植えることにして、1株はこれまでと同じ放任栽培。
もう1株は支柱で作った棚に蔓を這わせる放任栽培+空中栽培(宙づり栽培)。
この写真はネットから拝借した空中栽培の例です。


このカラスの害を防ぐ効果と同時に蔓を棚の上に這わせることで、夏の農作業のグリーンカーテンともなります。
しかし、野菜ドロボウの票的にはなりやすそうなので、この点の対策も考えなくては・・・。