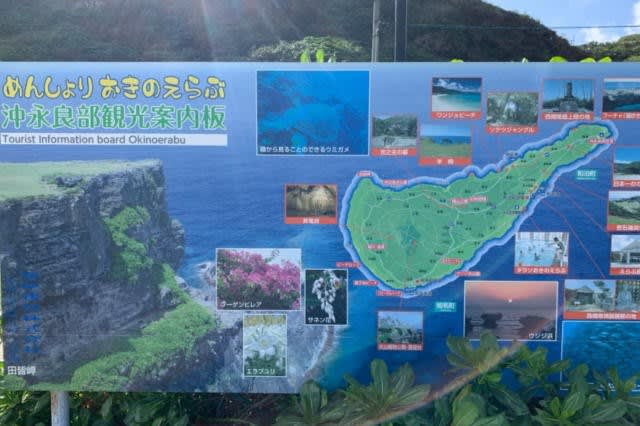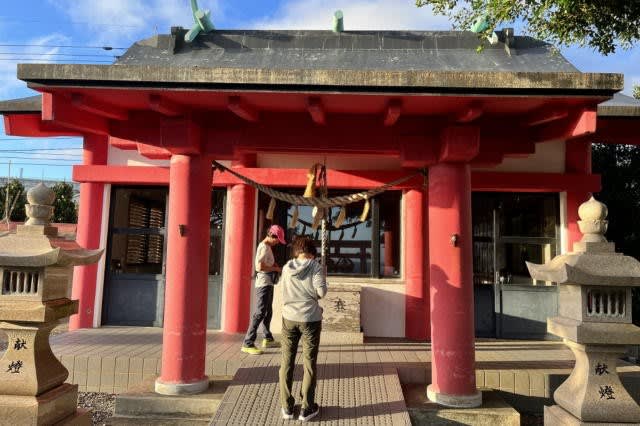先週、長崎県の五島列島に出かけてきた。福江島で行われた五島つばきマラソンに参加するためだが、最近五島の話題を多く聞くこともあり、せっかくなので観光も楽しもうと言うことで9人の仲間たちと長めの日程で楽しんできた。
五島に行くには、長崎空港からバスで長崎港まで移動し、フェリー又はジェットホイルで五島最大の島、福江島に行くことができる。今回は、長崎港からはジェットホイルで福江島に向かう。高速船なので乗船時間は1時間25分だ。午後1時前には、福江島に到着する。
福江島では早速、レンタカー2台を借りて観光に向かう。午後からの観光なのでたくさんは行けないが、まず向かったのが堂崎天主堂だ。駐車場から、海岸沿いを歩いていくと興味を引くものが見えてきた。

面白い形の岩が姿を見せている。形がりんごに似ていることからりんご岩と呼ばれるようになったという。ただし、引き潮の時にしか見られないので、ちょうど運が良かった。

そしてその先にあるのが、天主堂を伴う堂崎教会だ。禁教令が解かれたあと、五島キリシタン復興の任を帯びて、フランス人宣教師フレノー、マルマン両神父が五島を訪れ布教にあたり、1879年にマルマン神父によって、五島における最初の天主堂(木造)が建てられた。その後着任した、ペルー神父によって1908年に、現在のレンガ造りの教会堂が完成したという。現在は、長崎県の有形文化財(建造物)の指定を受けている。

建築の際には資材の一部がイタリアから運ばれ、内部は木造で色ガラス窓、コーモリ天井などの教会堂建築となっていて、弾圧の歴史や資料を展示する資料館として、一般公開されている。

外の庭園にはアルメイダ神父が五島に布教したときの様子を描いたレリーフがある。

堂崎教会の敷地に建てられたヨハネ五島殉教碑。日本二十六聖人の一人、聖ヨハネ五島は、五島のキリシタンの家に生まれた。豊臣秀吉の迫害が強まり、神父の逮捕命令が出た際、自ら申し出て神父の身代わりとなった。1597年、長崎・西坂の丘で処刑されたときは19歳の若さだったという。西坂で殉教した26人の遺骨は宣教師によって集められ、そのほとんどがマカオに送られたが、現在は分骨されたものが堂崎天主堂に納められている。

教会の裏山斜面にある聖母マリア像。真っ白く美しい像だ。

教会内部は、堂崎天主堂キリシタン資料館として、布教時代から迫害を経て復活にいたる信仰の歴史が展示されている。写真撮影はできないので、見るだけにして堂崎天主堂を後にした。
次に向かったのが、水ノ浦教会。1880年に最初の教会が建築されたが、老朽化にともない、奥の土手を削って広げ、1938年、鉄川与助設計施工の木造の優美な現教会に改築された。

ロマネスク、ゴシック、和風建築が混合した白亜の美しい教会で、木造教会堂としては最大の規模を誇り、青空に尖塔がそびえる光景は絵になる美しさだというが、この日は曇っていて青空ではなかった。

教会の入り口には、「私は門である」、「私を通って入る人は救われる」とある。我々も救われたのであろうか。残念ながら、教会内部は、感染症対策の一環で堂内の拝観はできなかった。

水ノ浦教会のルルド。「1858年にフランスのルルドで聖母がベルナデッタという少女の前に姿を現し、そこに数々の難病を治す奇跡の泉が湧き出た」というのがキリスト教徒には有名なルルドの泉の話で、ここにも、奇跡の泉と洞窟のマリア像でルルドが作られている。巡礼者の聖地となっているのだ。

裏山の斜面には、十字架をあしらった墓地が並んでいる。本土とは違い、キリスト教信者の多い島らしい風景だ。

ホテルのチェックインの時間までには、まだ十分時間が有ったので、鬼岳(おんたけ)に向かう。朝ドラ「舞い上がれ」では、子供の舞が凧揚げをするシーンのロケが行われたのは島北部、岐宿町の魚津ケ崎公園(マラソンのコースで通る)だが、本来、凧揚げ大会が行われるのは島の南東部、上大津町にある標高315mの鬼岳山頂付近であるということで立ち寄ってみることにした。駐車場から階段を上り、山を登っていく。

この時期は、緑がなく一面茶色の斜面が広がっている。

鬼岳は、その勇壮な名称とは反対に、丸みを帯びたやわらかな形状で古くから市民に親しまれているそうだ。こんな景色を見ると、ランナーは走りたくなるようだ。


後ろを振り返れば、海も見え、小さな島がいくつも見える。

鬼岳山頂315mに到着。

この穏やかな姿からは、かつて噴火した火山とは想像しにくいが、火口の尾根伝いを歩くことができ、眼下には福江の市街地や海を望める。体力が有り余っているメンバーばかりなので、火口をぐるっと一周して駐車場に戻った。

この日の観光はこれでお終いとし、福江港近くのホテルにチェックインした。
「2023五島つばきマラソンツアー:2日目」に続く。
五島に行くには、長崎空港からバスで長崎港まで移動し、フェリー又はジェットホイルで五島最大の島、福江島に行くことができる。今回は、長崎港からはジェットホイルで福江島に向かう。高速船なので乗船時間は1時間25分だ。午後1時前には、福江島に到着する。
福江島では早速、レンタカー2台を借りて観光に向かう。午後からの観光なのでたくさんは行けないが、まず向かったのが堂崎天主堂だ。駐車場から、海岸沿いを歩いていくと興味を引くものが見えてきた。

面白い形の岩が姿を見せている。形がりんごに似ていることからりんご岩と呼ばれるようになったという。ただし、引き潮の時にしか見られないので、ちょうど運が良かった。

そしてその先にあるのが、天主堂を伴う堂崎教会だ。禁教令が解かれたあと、五島キリシタン復興の任を帯びて、フランス人宣教師フレノー、マルマン両神父が五島を訪れ布教にあたり、1879年にマルマン神父によって、五島における最初の天主堂(木造)が建てられた。その後着任した、ペルー神父によって1908年に、現在のレンガ造りの教会堂が完成したという。現在は、長崎県の有形文化財(建造物)の指定を受けている。

建築の際には資材の一部がイタリアから運ばれ、内部は木造で色ガラス窓、コーモリ天井などの教会堂建築となっていて、弾圧の歴史や資料を展示する資料館として、一般公開されている。

外の庭園にはアルメイダ神父が五島に布教したときの様子を描いたレリーフがある。

堂崎教会の敷地に建てられたヨハネ五島殉教碑。日本二十六聖人の一人、聖ヨハネ五島は、五島のキリシタンの家に生まれた。豊臣秀吉の迫害が強まり、神父の逮捕命令が出た際、自ら申し出て神父の身代わりとなった。1597年、長崎・西坂の丘で処刑されたときは19歳の若さだったという。西坂で殉教した26人の遺骨は宣教師によって集められ、そのほとんどがマカオに送られたが、現在は分骨されたものが堂崎天主堂に納められている。

教会の裏山斜面にある聖母マリア像。真っ白く美しい像だ。

教会内部は、堂崎天主堂キリシタン資料館として、布教時代から迫害を経て復活にいたる信仰の歴史が展示されている。写真撮影はできないので、見るだけにして堂崎天主堂を後にした。
次に向かったのが、水ノ浦教会。1880年に最初の教会が建築されたが、老朽化にともない、奥の土手を削って広げ、1938年、鉄川与助設計施工の木造の優美な現教会に改築された。

ロマネスク、ゴシック、和風建築が混合した白亜の美しい教会で、木造教会堂としては最大の規模を誇り、青空に尖塔がそびえる光景は絵になる美しさだというが、この日は曇っていて青空ではなかった。

教会の入り口には、「私は門である」、「私を通って入る人は救われる」とある。我々も救われたのであろうか。残念ながら、教会内部は、感染症対策の一環で堂内の拝観はできなかった。

水ノ浦教会のルルド。「1858年にフランスのルルドで聖母がベルナデッタという少女の前に姿を現し、そこに数々の難病を治す奇跡の泉が湧き出た」というのがキリスト教徒には有名なルルドの泉の話で、ここにも、奇跡の泉と洞窟のマリア像でルルドが作られている。巡礼者の聖地となっているのだ。

裏山の斜面には、十字架をあしらった墓地が並んでいる。本土とは違い、キリスト教信者の多い島らしい風景だ。

ホテルのチェックインの時間までには、まだ十分時間が有ったので、鬼岳(おんたけ)に向かう。朝ドラ「舞い上がれ」では、子供の舞が凧揚げをするシーンのロケが行われたのは島北部、岐宿町の魚津ケ崎公園(マラソンのコースで通る)だが、本来、凧揚げ大会が行われるのは島の南東部、上大津町にある標高315mの鬼岳山頂付近であるということで立ち寄ってみることにした。駐車場から階段を上り、山を登っていく。

この時期は、緑がなく一面茶色の斜面が広がっている。

鬼岳は、その勇壮な名称とは反対に、丸みを帯びたやわらかな形状で古くから市民に親しまれているそうだ。こんな景色を見ると、ランナーは走りたくなるようだ。


後ろを振り返れば、海も見え、小さな島がいくつも見える。

鬼岳山頂315mに到着。

この穏やかな姿からは、かつて噴火した火山とは想像しにくいが、火口の尾根伝いを歩くことができ、眼下には福江の市街地や海を望める。体力が有り余っているメンバーばかりなので、火口をぐるっと一周して駐車場に戻った。

この日の観光はこれでお終いとし、福江港近くのホテルにチェックインした。
「2023五島つばきマラソンツアー:2日目」に続く。