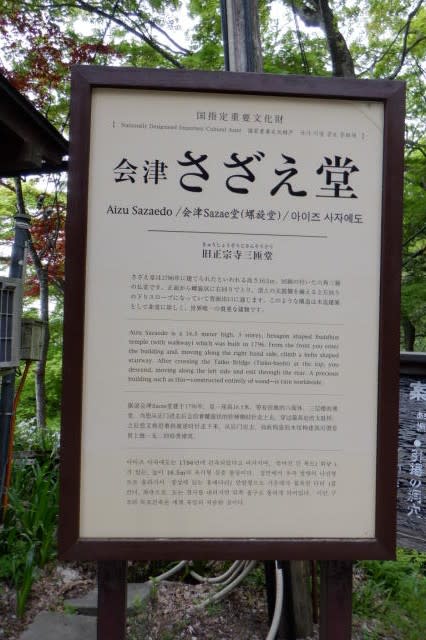ここ数年、9月から10月にかけて東北の紅葉の山に登りに行っている。今年は、昨年天候不順であきらめた焼石岳のリベンジで計画を立てていた。1日目は、焼石岳の登山口に近い宿までの移動だけだが、前回行ってない岩手県一関市の猊鼻渓(げいびけい)に立ち寄って行くことにした。
猊鼻渓は、日本百景の一つにも数えられている。砂鉄川の浸食でできた高さ100メートルの絶壁に奇岩、洞窟、滝など迫力のある絶景が広がる渓谷で、船頭が棹一本で操る「舟下り」が有名だ。
折しも、台風15号の接近の影響で、岩手県は小雨模様だが、舟下りは問題なく運行するということで早速、舟に乗り込む。

舟には動力がなく、全て船頭一人が操る棹だけが頼りだ。さいわい激しい流れがある場所ではないので、軽妙な船頭のトークを聞きながらゆっくりと船は進んで行く。

舟が動き出すと、餌を貰う事を期待してか、カモが早速舟に寄ってくる。

岩壁の下にある洞窟には毘沙門様が祀られているそうだ。

折り返してきた舟とすれ違う。

船着き場で下船して、散策道を歩く。

船頭さんは、我々が戻ってくるまで、休憩ができると喜んでいた。

橋を渡り反対岸に向かう。

終点には、ここの地名の由来となった大猊鼻岩がそそり立っている。侵食された鍾乳石が獅子の鼻に似ているという事だ(猊とは獅子のこと)。

大猊鼻岩の近くまで行ってみるが、どこが獅子の鼻なのかよくわからなかった。

近くには、売店もある。

売店では、うん玉という石が売られている。

「福」「縁」「寿」「愛」「願」「運」「恋」「絆」「禄」「財」と書かれたうん玉を岩壁の穴めがけて投げて、穴に入れば願い事がかなうという。好きなうん玉を選んで、早速穴めがけて投げるが、意外と遠くて穴はおろか、岩壁に当たることも難しい。

集合時間が近づき、舟に戻っていく。

次の舟がやってきて、我々の舟と入れ替わる。

一部のカモは、我々の舟に急いで追いついてくる。

慣れているカモは、人間の手から直接餌をとっていく。

舟下りのクライマックスでは、船頭が唄う「げいび追分」が、そそりたつ岩肌に響き渡り、旅情をより一層高めてくれる。ここの舟下りの一番の名物らしい。
猊鼻渓は、春の新緑に始まり、5月の藤の花、10月には紅葉、そして雪景色と、四季折々の景色は壮観だという。時期が合えば、茶席舟、舟上十六夜コンサートなど季節限定のイベントも多彩で、冬はアツアツの木流し鍋をいただく「こたつ舟」が運行されるなど、一年を通じて幅広い世代に愛される観光地だという。天気が今一だったが、なかなか楽しい観光地だった。

「2022東北紅葉登山ツアー:2日目中尊寺、石ノ森萬画館等観光」に続く。
猊鼻渓は、日本百景の一つにも数えられている。砂鉄川の浸食でできた高さ100メートルの絶壁に奇岩、洞窟、滝など迫力のある絶景が広がる渓谷で、船頭が棹一本で操る「舟下り」が有名だ。
折しも、台風15号の接近の影響で、岩手県は小雨模様だが、舟下りは問題なく運行するということで早速、舟に乗り込む。

舟には動力がなく、全て船頭一人が操る棹だけが頼りだ。さいわい激しい流れがある場所ではないので、軽妙な船頭のトークを聞きながらゆっくりと船は進んで行く。

舟が動き出すと、餌を貰う事を期待してか、カモが早速舟に寄ってくる。

岩壁の下にある洞窟には毘沙門様が祀られているそうだ。

折り返してきた舟とすれ違う。

船着き場で下船して、散策道を歩く。

船頭さんは、我々が戻ってくるまで、休憩ができると喜んでいた。

橋を渡り反対岸に向かう。

終点には、ここの地名の由来となった大猊鼻岩がそそり立っている。侵食された鍾乳石が獅子の鼻に似ているという事だ(猊とは獅子のこと)。

大猊鼻岩の近くまで行ってみるが、どこが獅子の鼻なのかよくわからなかった。

近くには、売店もある。

売店では、うん玉という石が売られている。

「福」「縁」「寿」「愛」「願」「運」「恋」「絆」「禄」「財」と書かれたうん玉を岩壁の穴めがけて投げて、穴に入れば願い事がかなうという。好きなうん玉を選んで、早速穴めがけて投げるが、意外と遠くて穴はおろか、岩壁に当たることも難しい。

集合時間が近づき、舟に戻っていく。

次の舟がやってきて、我々の舟と入れ替わる。

一部のカモは、我々の舟に急いで追いついてくる。

慣れているカモは、人間の手から直接餌をとっていく。

舟下りのクライマックスでは、船頭が唄う「げいび追分」が、そそりたつ岩肌に響き渡り、旅情をより一層高めてくれる。ここの舟下りの一番の名物らしい。
猊鼻渓は、春の新緑に始まり、5月の藤の花、10月には紅葉、そして雪景色と、四季折々の景色は壮観だという。時期が合えば、茶席舟、舟上十六夜コンサートなど季節限定のイベントも多彩で、冬はアツアツの木流し鍋をいただく「こたつ舟」が運行されるなど、一年を通じて幅広い世代に愛される観光地だという。天気が今一だったが、なかなか楽しい観光地だった。

「2022東北紅葉登山ツアー:2日目中尊寺、石ノ森萬画館等観光」に続く。