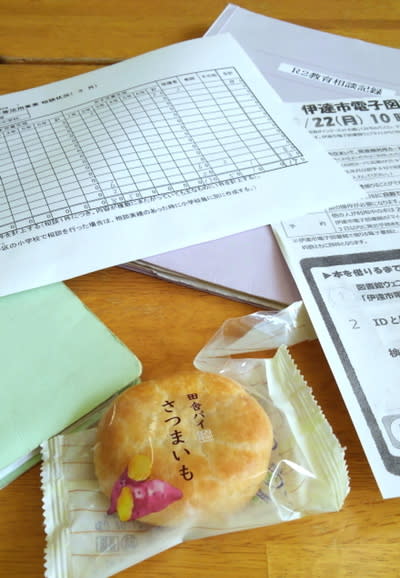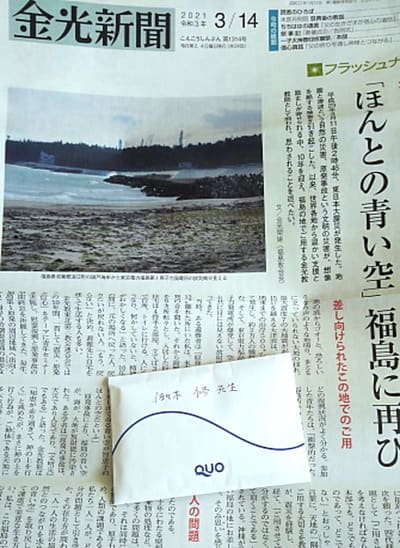久方ぶりに
棚倉の三ツ星鮨店
『小判寿司』を
美女ふたり連れで訪れた。
おふた方とは、
Y中で一年間、
担任、養護として
ケース・カンファレンスで
関ってきて、
それぞれの立場で
生徒たちにセラピュウティックな
コミットをしてきたので、
心通い合う「治療・支援チーム」
と思っている。
そのうちのおひとりが、
今年度で離任されるので、
その「解散式食事会」をも兼ねた
棚倉グルメ旅行でもあった。

昨年、近所の近津幼稚園で
講演に招聘された折、
講演料で懐を膨らませて(笑)
『小判』に寄ったのだが、
あいにくの臨時休業で
落胆した帰った。
なので、
あの時の心残りを
今こそ解消しようとばかり、
事前に予約して
意気揚々と訪問した。
親方、女将さん、ヨシ君とも
みなお変わりなく、
"いつもの"小判の雰囲気が
嬉しかった。

今回は、
いつものような
"お好み"ではなく、
"おまかせ"であった。
連れのお二方とも、
この日を楽しみにしておられたが、
カウンター正面に座るなり
銀座のジュエリーショップの
ショーウインドーのような
ネタケースの美しさに
心奪われていた。
R先生は、
親方の魚を下ろし
握る姿にじっと見入っていて、
「お仕事姿が綺麗ですね…」
と感心しておられた。
⁂
まずは、
春日子(かすご)から。
鯛の幼魚を酢〆したもので
鮨では"光もの"と言われるが、
この時季、
まさに文字通りに
その桜色は「春の日」を
彷彿させる淡い味である。
芝海老を炒って造った
"おぼろ"が
鋳込んである。
鹿の子目の飾り包丁に
煮切りが滲みて、
皮ぎしのグラデーションを
美しく見せていた。
続いては、
淡いオレンジ色の
閖上(ゆりあげ)の赤貝。
3.11以降は
海底が荒れて、
何年も水揚げがなかったが、
ようやく食せるようになり
"復興の証し"のような
銘品である。
親方が俎板に叩きつけると
身がキュンと縮み、
活物ならではなの
豊かな香りに
シャクリとした食感、
清涼感のある澄んだ味だった。
ルビーやガーネットを思わす
鮮紅色の"漬け"(鮪)は、
赤身の爽やかさと
深みを兼ね備えた
逸品だった。
「魚偏」に「春」と書くと
「鰆(さわら)」となる。
藁火で皮目を燻され部分が
フッと鼻腔を抜けると
得も言われぬ高貴さが
醸し出され、さながら、
極上フレンチの
『フュメ』(スモーク料理)に
匹敵するものだった。
鮨の代名詞、
「ザ・スシ」でもある
小鰭(こはだ)は
四日も熟成されたもので、
二枚付けで供された。
その光る黒点の皮目に
サッと引かれた煮切りにより、
さながら一服の銀屏風を
愛でるかの如き
雅びな気分が感じられた。
金目鯛も
軽く〆られ、
皮目をほんのり炙られていた。
極上の味もさることながら、
その江戸前仕事には
目を見張る。
即ち、
「姿・香り・味」と
視覚・嗅覚・味覚が
「美しく、芳しく、旨く」
三拍子が揃い踏みなのである。
加えて、親方の握りは、
酢飯の間に空気を存分に含み、
漬け台に置かれた瞬間に
スッと沈み込む。
表現は甚だ宜しくないが
"エアー握り"(笑)
なのである。
したがって、
その手取りは軽く
口中でハラリとほどける。
これもまた
江戸前仕事を極めた
至高の職人技巧なのである。
なので、
これを味わってしまうと、
カッチリ握り〆た
よその店のスシは、
江戸前の「握り」ではなく
"おにぎり"なのである(笑)。

本鮪の
"すなずり"と言われる
腹身の大トロは、
見るからに
脂がのった"ジャバラ"で、
食べる前から
「激ウマッ!!」もの
であった(笑)。
もう、
美女おふたかたも
陶然として
眼がトロンと潤んでいた。
まさに、
「おィひィ~ ・・・」
「もぅ、らめぇ~ ・・・」
ってな
感じである(笑)。

そして、
ミョウバンに晒されていない
無添加のバフンウニは、
クリーミーで
トロントロン・・・。
後から、
フンワリと風味が
鼻から抜ける。
モゥ…ヾ(_ _。) ノ ㇻメ~♡ ガクッ
それから、
"釣り鯵"を
満喫する。
"網獲り鯵"は
身が潰れたりして
どうしても味が
落ちるのである。
昔の人は、
【味がいいのでアジ】
と付けたという。
活けの才巻海老は、
半生のティエド(ほのかな温み)で。
頭のミソが
鋳込んであり
海老の甘みと旨みが
一身に詰まっている。

請戸の白魚には
黄身醤油がかけられ、
群青の小皿に映える
目にも艶冶な逸品である。
仄かな苦みが
和食に於いて
【春は苦みを盛れ】
という料理訓を
彷彿した。
・・・フィナーレも近づき、
親方から
中落ちの手巻きを
手渡される。
"手渡し"は、
近年、都会でも
カウンター席で
よくあるスタイルである。

甘めに炊かれた干瓢の
サビ入り海苔巻きを頬張り、
女将さんのこしらえた
逸品のギョク(玉子焼)で
フルコースの仕舞いとなった。
♪ (´¬`) = 3 フィ~
あぁ、存分に
極上の江戸前鮨を
堪能させて頂きやした。
(人'∀'*)☆*:.。

ヨシ君が創られた
見事なガラス工芸品をも
見せて頂き、
その美しさにも
魅せられました。
棚倉の三ツ星鮨店
『小判寿司』を
美女ふたり連れで訪れた。
おふた方とは、
Y中で一年間、
担任、養護として
ケース・カンファレンスで
関ってきて、
それぞれの立場で
生徒たちにセラピュウティックな
コミットをしてきたので、
心通い合う「治療・支援チーム」
と思っている。
そのうちのおひとりが、
今年度で離任されるので、
その「解散式食事会」をも兼ねた
棚倉グルメ旅行でもあった。

昨年、近所の近津幼稚園で
講演に招聘された折、
講演料で懐を膨らませて(笑)
『小判』に寄ったのだが、
あいにくの臨時休業で
落胆した帰った。
なので、
あの時の心残りを
今こそ解消しようとばかり、
事前に予約して
意気揚々と訪問した。
親方、女将さん、ヨシ君とも
みなお変わりなく、
"いつもの"小判の雰囲気が
嬉しかった。

今回は、
いつものような
"お好み"ではなく、
"おまかせ"であった。
連れのお二方とも、
この日を楽しみにしておられたが、
カウンター正面に座るなり
銀座のジュエリーショップの
ショーウインドーのような
ネタケースの美しさに
心奪われていた。
R先生は、
親方の魚を下ろし
握る姿にじっと見入っていて、
「お仕事姿が綺麗ですね…」
と感心しておられた。
⁂
まずは、
春日子(かすご)から。
鯛の幼魚を酢〆したもので
鮨では"光もの"と言われるが、
この時季、
まさに文字通りに
その桜色は「春の日」を
彷彿させる淡い味である。
芝海老を炒って造った
"おぼろ"が
鋳込んである。
鹿の子目の飾り包丁に
煮切りが滲みて、
皮ぎしのグラデーションを
美しく見せていた。
続いては、
淡いオレンジ色の
閖上(ゆりあげ)の赤貝。
3.11以降は
海底が荒れて、
何年も水揚げがなかったが、
ようやく食せるようになり
"復興の証し"のような
銘品である。
親方が俎板に叩きつけると
身がキュンと縮み、
活物ならではなの
豊かな香りに
シャクリとした食感、
清涼感のある澄んだ味だった。
ルビーやガーネットを思わす
鮮紅色の"漬け"(鮪)は、
赤身の爽やかさと
深みを兼ね備えた
逸品だった。
「魚偏」に「春」と書くと
「鰆(さわら)」となる。
藁火で皮目を燻され部分が
フッと鼻腔を抜けると
得も言われぬ高貴さが
醸し出され、さながら、
極上フレンチの
『フュメ』(スモーク料理)に
匹敵するものだった。
鮨の代名詞、
「ザ・スシ」でもある
小鰭(こはだ)は
四日も熟成されたもので、
二枚付けで供された。
その光る黒点の皮目に
サッと引かれた煮切りにより、
さながら一服の銀屏風を
愛でるかの如き
雅びな気分が感じられた。
金目鯛も
軽く〆られ、
皮目をほんのり炙られていた。
極上の味もさることながら、
その江戸前仕事には
目を見張る。
即ち、
「姿・香り・味」と
視覚・嗅覚・味覚が
「美しく、芳しく、旨く」
三拍子が揃い踏みなのである。
加えて、親方の握りは、
酢飯の間に空気を存分に含み、
漬け台に置かれた瞬間に
スッと沈み込む。
表現は甚だ宜しくないが
"エアー握り"(笑)
なのである。
したがって、
その手取りは軽く
口中でハラリとほどける。
これもまた
江戸前仕事を極めた
至高の職人技巧なのである。
なので、
これを味わってしまうと、
カッチリ握り〆た
よその店のスシは、
江戸前の「握り」ではなく
"おにぎり"なのである(笑)。

本鮪の
"すなずり"と言われる
腹身の大トロは、
見るからに
脂がのった"ジャバラ"で、
食べる前から
「激ウマッ!!」もの
であった(笑)。
もう、
美女おふたかたも
陶然として
眼がトロンと潤んでいた。
まさに、
「おィひィ~ ・・・」
「もぅ、らめぇ~ ・・・」
ってな
感じである(笑)。

そして、
ミョウバンに晒されていない
無添加のバフンウニは、
クリーミーで
トロントロン・・・。
後から、
フンワリと風味が
鼻から抜ける。
モゥ…ヾ(_ _。) ノ ㇻメ~♡ ガクッ
それから、
"釣り鯵"を
満喫する。
"網獲り鯵"は
身が潰れたりして
どうしても味が
落ちるのである。
昔の人は、
【味がいいのでアジ】
と付けたという。
活けの才巻海老は、
半生のティエド(ほのかな温み)で。
頭のミソが
鋳込んであり
海老の甘みと旨みが
一身に詰まっている。

請戸の白魚には
黄身醤油がかけられ、
群青の小皿に映える
目にも艶冶な逸品である。
仄かな苦みが
和食に於いて
【春は苦みを盛れ】
という料理訓を
彷彿した。
・・・フィナーレも近づき、
親方から
中落ちの手巻きを
手渡される。
"手渡し"は、
近年、都会でも
カウンター席で
よくあるスタイルである。

甘めに炊かれた干瓢の
サビ入り海苔巻きを頬張り、
女将さんのこしらえた
逸品のギョク(玉子焼)で
フルコースの仕舞いとなった。
♪ (´¬`) = 3 フィ~
あぁ、存分に
極上の江戸前鮨を
堪能させて頂きやした。
(人'∀'*)☆*:.。

ヨシ君が創られた
見事なガラス工芸品をも
見せて頂き、
その美しさにも
魅せられました。