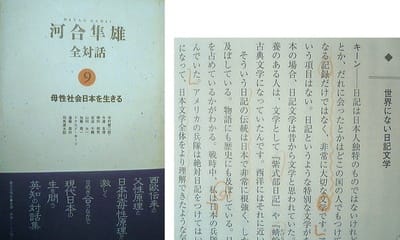きのうは、午後から、
お祝いしたいお客様が
いらっしゃる予定だったので、
午前中から
プチケーキを焼いたり
ドラ焼きを作って、
“パティシエごっこ”
“和菓子職人ごっこ”
を楽しんでいた。
幸い、
卒業生から頂いた花束が
まだ生き生きとしていたので、
卓上に飾り、
菓子類はティースタンドに
ドレッセした。

「アフタヌーン・ティー」について
ウィキってみたら、
1840年頃に、某公爵夫人によって
始められたとされる
イギリス発祥の喫茶習慣という。
紅茶と共に
軽食や菓子を摂る習慣で、
英国の上流階級文化の
精髄の一つらしい。
単に飲食を楽しむだけでなく、
会話の場であり、
食器や花なども愛でるので、
広範な分野のセンスや
知識・教養が要求されるから、
日本の「茶道」と同じである。
ロー・ティー(Low tea)
とも呼ばれ、
客間の低いテーブルで
提供される。
取って付けたような
我が家の“おそ松くん”な
Afternoon tea だったが、
お客様にはお喜びいただき、
趣味の菓子作りも
役に立つもんだと思った。

長らく
教育分析に通って来られている
T先生から
「謝辞」を記載した
論文を献呈して頂き、
光栄に思わせて頂いた。
心理屋・SCとして
いずれやらねば…と、思っていた
『高校生のネット依存の要因』
という研究テーマに着手され、
「自尊感情」がリスク・ファクターでなく
「関与様式」に関連性が有ることを
見出された。
ことに、
「普段の生活の不適応感や
発散できないストレスを
ネット上で吐き出し、
その爽快感が依存の一因になる」
というのは
臨床的経験を裏付ける卓見である。
いわゆる「コミュ障」系や
「メンヘラ」系といわれる
不登校の中高生が
『フォートナイト』や
『荒野行動』といった
バトル物にハマッて
依存になっているケースが
少なくない。
そして、
「攻撃的言動」と
依存の正の関連性は、
ネット上での誹謗中傷事件を
起こす子たちほど、
依存傾向が高いというのも
臨床的実感に即していた。
直近の
厚労省研究班の発表による
「中学生10%、高校生16%が依存症」
というのは、
“亡国の兆し”という
危機感を抱かざるを得ない。
そのような
喫緊の社会問題に
真正面から取り組まれて、
十分に先行研究を行い、
500以上もの母集団からデータを取って
綿密な統計分析を行った当論文は
まさに社会的ニーズに応えたもので、
公益性のある情報をもたらしてくれた。
先行研究の要旨を概観するだけでも
「ネット依存研究」の最先端が伺われた。
今後の検討課題として
「高校生活充実度と依存の関連性」や
「男女差」などが示されたことも
有益であった。
ご縁のある先生が
このような立派な論文を書かれたことは、
望外の喜びでもあり、
今最も関心のあるテーマなので
不思議なシンクロニシティをも感じた。

ファイナル・リサイタルへ
あと1ケ月を切って、
さすがに「お尻に火」モードで
毎日欠かさず筋トレ、
ギター練習、楽譜の再検討、
プログラム印刷、CD作成なぞを
やっている。
昨晩も遅くまで、
フラメンコ・デュオのソロパートを
弾いては書き直し、
弾いては書き直し・・・と、
念入りに検討した。
これを充実した「春休み」
というのだろう(笑)。
今晩も、
フラメンコ・デュオの相方H君と
レッスン方々、合わせの追い込みをやる。
彼は音楽教員だが、
ギターでのステージは
初めてになるので、
念入りな練習を
必死モードでやっている。
音楽に、楽器に、
全人的に没入して
忘我の境地になるのは
「くるたのしい」もので、
ライフ・モットーである
「人生、深生き」の
濃密な実践でもある。
本番の舞台上では、
さらなる凝縮した時間と
生の実感を得ることだろう。
お祝いしたいお客様が
いらっしゃる予定だったので、
午前中から
プチケーキを焼いたり
ドラ焼きを作って、
“パティシエごっこ”
“和菓子職人ごっこ”
を楽しんでいた。
幸い、
卒業生から頂いた花束が
まだ生き生きとしていたので、
卓上に飾り、
菓子類はティースタンドに
ドレッセした。

「アフタヌーン・ティー」について
ウィキってみたら、
1840年頃に、某公爵夫人によって
始められたとされる
イギリス発祥の喫茶習慣という。
紅茶と共に
軽食や菓子を摂る習慣で、
英国の上流階級文化の
精髄の一つらしい。
単に飲食を楽しむだけでなく、
会話の場であり、
食器や花なども愛でるので、
広範な分野のセンスや
知識・教養が要求されるから、
日本の「茶道」と同じである。
ロー・ティー(Low tea)
とも呼ばれ、
客間の低いテーブルで
提供される。
取って付けたような
我が家の“おそ松くん”な
Afternoon tea だったが、
お客様にはお喜びいただき、
趣味の菓子作りも
役に立つもんだと思った。

長らく
教育分析に通って来られている
T先生から
「謝辞」を記載した
論文を献呈して頂き、
光栄に思わせて頂いた。
心理屋・SCとして
いずれやらねば…と、思っていた
『高校生のネット依存の要因』
という研究テーマに着手され、
「自尊感情」がリスク・ファクターでなく
「関与様式」に関連性が有ることを
見出された。
ことに、
「普段の生活の不適応感や
発散できないストレスを
ネット上で吐き出し、
その爽快感が依存の一因になる」
というのは
臨床的経験を裏付ける卓見である。
いわゆる「コミュ障」系や
「メンヘラ」系といわれる
不登校の中高生が
『フォートナイト』や
『荒野行動』といった
バトル物にハマッて
依存になっているケースが
少なくない。
そして、
「攻撃的言動」と
依存の正の関連性は、
ネット上での誹謗中傷事件を
起こす子たちほど、
依存傾向が高いというのも
臨床的実感に即していた。
直近の
厚労省研究班の発表による
「中学生10%、高校生16%が依存症」
というのは、
“亡国の兆し”という
危機感を抱かざるを得ない。
そのような
喫緊の社会問題に
真正面から取り組まれて、
十分に先行研究を行い、
500以上もの母集団からデータを取って
綿密な統計分析を行った当論文は
まさに社会的ニーズに応えたもので、
公益性のある情報をもたらしてくれた。
先行研究の要旨を概観するだけでも
「ネット依存研究」の最先端が伺われた。
今後の検討課題として
「高校生活充実度と依存の関連性」や
「男女差」などが示されたことも
有益であった。
ご縁のある先生が
このような立派な論文を書かれたことは、
望外の喜びでもあり、
今最も関心のあるテーマなので
不思議なシンクロニシティをも感じた。

ファイナル・リサイタルへ
あと1ケ月を切って、
さすがに「お尻に火」モードで
毎日欠かさず筋トレ、
ギター練習、楽譜の再検討、
プログラム印刷、CD作成なぞを
やっている。
昨晩も遅くまで、
フラメンコ・デュオのソロパートを
弾いては書き直し、
弾いては書き直し・・・と、
念入りに検討した。
これを充実した「春休み」
というのだろう(笑)。
今晩も、
フラメンコ・デュオの相方H君と
レッスン方々、合わせの追い込みをやる。
彼は音楽教員だが、
ギターでのステージは
初めてになるので、
念入りな練習を
必死モードでやっている。
音楽に、楽器に、
全人的に没入して
忘我の境地になるのは
「くるたのしい」もので、
ライフ・モットーである
「人生、深生き」の
濃密な実践でもある。
本番の舞台上では、
さらなる凝縮した時間と
生の実感を得ることだろう。