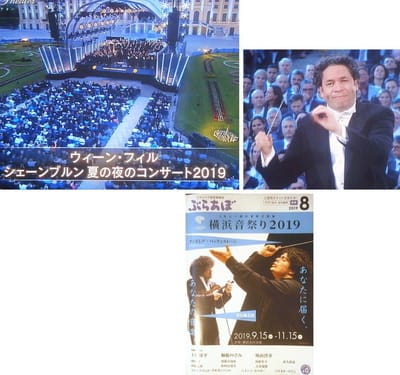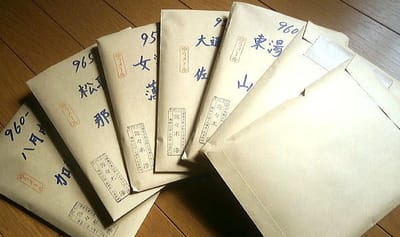きのうは午前中に
老母の退院のために
迎えに行った。
ベッドに伏した姿は、
骨と皮だけになって縮こまり、
点滴やぶつけて出来たアザだらけ
皺だらけの腕を見て
「老い」の悲惨さを見せつけらて
気が滅入りそうだった。
三人部屋の病室から
外の風景を眺めると
子どもの頃、
旧医大の小児病棟に
長いこと入院していた時のことを
思い出した。
その時は、
母親が付き添いで
自分がベッドに伏していた。
年月を経て、
それが逆転の構図になり、
その老母の晩年をどう看取るか
という人生のステージに来た。
ベッドから車椅子に
移そうという時に、
大量の粗相をしていたので
看護婦さんがカーテンを引いて
清拭して下さり、
病棟のパジャマを貸してくれた。
子どもの頃、
ネションベン垂れで
よく母親から叱られていたが、
それも逆転構図になり、
垂れ流しを目の当たりにすると
「悲哀」と「無常」を
感じずにはいられなかった。
「生病老死」の姿を
亡き祖父母・父たちが
それぞれ見せてくれたが、
いずれの姿も
目で見せてくれた「教育」だと
受け止めてきた。
祖母も認知症で
よく垂れ流しては
始末したこともあったが、
25年来同居していた祖母を置いて
大阪に赴任した時に心情を句にした。
フクシマで
死ぬまで生きよ
クソ垂れババア
看護師や介護士たちが
それぞれプロの手馴れた手つきで
声かけをしながら
老母を取り扱うのを見ていると、
なんだかその手間と大変な事を
金で解決しているような
後ろめたさを感じないでもなかった。
でも、
四六時中それに付き切りで、
心身疲弊し、思考停止になって、
しまいには身内が手にかけるという
哀れな事件が少なくないので、
「金で解決」というのは
「次善策」なんだ・・・と、
思うことにしている。
なにより、
その負担金は
老母自らが年金をきっちりと
払ってきてくれたことで
すべて賄われているので、
これは子ども孝行であったと
ありがたく思っている。
2週間の入院の
請求書の実費は77万で、
実質は一割負担の7.7万だったが、
その高額医療を見るにつけても
ビンボー人は老後の治療も
ままならないなぁ・・・と、
ため息が出た。
もっとも、
ナマポ(生活保護)は
医療費がタダにはなるのだろうが・・・。

看護婦さん二人が
エレベーターまで
退院の見送りをしてくだすったが、
「また、近々、
お世話になるかもしれません」
と、挨拶しておいた。
二回目の入院だったが、
微細な脳梗塞と脳溢血を
交互に発症しているので、
Dデイまでは
また度々世話になる予感がしたので、
その時は、子として、
粛々と看取り介助をしようと
覚悟した。

カミさんが買っていた
【本屋大賞】の
『そして、バトンは渡された』を
借りて読んでみた。
【大賞】物は、
おととしの
『蜜蜂と遠雷』以来である。
あれはピアノ・コンクール物で
抜群に面白かった。
『そしバト』は、
ライトノベル風の
軽味のある作品で、
笑わせもし、エンディングでは
泣かせもしてくれた。
例によって、
ワルイ癖で
アマゾンのレヴューで
世間のコンセンサスを
覗いてみた。
星5つ 45% *****
星4つ 20% **+
星3つ 13% *+
星2つ 13% *+
星1つ 9% *
…という、
概ね「良評価」に傾いていた。
〈くさす派〉は
常に一割は居るもので、
これらは〈くさし〉と
呼ぶことにしている(笑)。
曰く・・・
「薄っぺらい、中身のない内容」
「まったく現実的でない夢物語」
「羞恥心のない乞食根性のクソガキに共感できない」
と、クサシは様々。
映画化しやすい
素材のようにも思えたので、
それも近々、現実化するかもである。

明け方に、
久しぶりに、中学時代に
恋焦がれた女の子の夢を見た。
ほとんど
言葉を交わしたことのない子だったが、
夢んなかでは
意識しながらも
けっこうしゃべっており、
しかも、結末は、
その子が性転換していて
男性器まで顔の皮膚を移植して
整形したと聞いて愕然とする。
なんじゃ~、
この夢は~ッ!!
と、起きしなに
驚いた。
ε=ε=ヾ(*。>◇<)ノ
夢分析の専門家なので、
今日一日かけて
ぽつぽつと
分析するつもりではいる。
自由連想法と
ウォッチワード・テストという
ツールを用いて
自己分析してみると、
意外な無意識からのメッセージを
受け取ることがある。
まずは、
現状の意識を列挙して、
それとの関連性や、
世界情勢を俯瞰して
懸念材料との関連性を
探ってみようと思う。
〈あおり事件〉の低脳犯の
劣悪・凶暴な犯行シーンや
卑劣・卑怯な逮捕シーンを
ニュースで何度も見せられて、
不快に感じ、ここ数日、
心穏やかでなかった。
自分も過去、二回も
ヤンキーや暴走族に
胸ぐらをつかまれて脅されたり、
土下座させられた、
という恐怖と屈辱の〈闇史〉があるので、
それで抑圧・忘却していた
「悔しさ」や「殺してやりたい」
というシャドウが
賦活したのかもしれない。
それにしても、
なんで美少女のSちゃんが、
男に性転換して、
しかも、魔術で部屋を猛回転させて、
それをストップさせると
お払い用の「お札」を
撒きちらす…。
【・_・?】ナンデ
老母の退院のために
迎えに行った。
ベッドに伏した姿は、
骨と皮だけになって縮こまり、
点滴やぶつけて出来たアザだらけ
皺だらけの腕を見て
「老い」の悲惨さを見せつけらて
気が滅入りそうだった。
三人部屋の病室から
外の風景を眺めると
子どもの頃、
旧医大の小児病棟に
長いこと入院していた時のことを
思い出した。
その時は、
母親が付き添いで
自分がベッドに伏していた。
年月を経て、
それが逆転の構図になり、
その老母の晩年をどう看取るか
という人生のステージに来た。
ベッドから車椅子に
移そうという時に、
大量の粗相をしていたので
看護婦さんがカーテンを引いて
清拭して下さり、
病棟のパジャマを貸してくれた。
子どもの頃、
ネションベン垂れで
よく母親から叱られていたが、
それも逆転構図になり、
垂れ流しを目の当たりにすると
「悲哀」と「無常」を
感じずにはいられなかった。
「生病老死」の姿を
亡き祖父母・父たちが
それぞれ見せてくれたが、
いずれの姿も
目で見せてくれた「教育」だと
受け止めてきた。
祖母も認知症で
よく垂れ流しては
始末したこともあったが、
25年来同居していた祖母を置いて
大阪に赴任した時に心情を句にした。
フクシマで
死ぬまで生きよ
クソ垂れババア
看護師や介護士たちが
それぞれプロの手馴れた手つきで
声かけをしながら
老母を取り扱うのを見ていると、
なんだかその手間と大変な事を
金で解決しているような
後ろめたさを感じないでもなかった。
でも、
四六時中それに付き切りで、
心身疲弊し、思考停止になって、
しまいには身内が手にかけるという
哀れな事件が少なくないので、
「金で解決」というのは
「次善策」なんだ・・・と、
思うことにしている。
なにより、
その負担金は
老母自らが年金をきっちりと
払ってきてくれたことで
すべて賄われているので、
これは子ども孝行であったと
ありがたく思っている。
2週間の入院の
請求書の実費は77万で、
実質は一割負担の7.7万だったが、
その高額医療を見るにつけても
ビンボー人は老後の治療も
ままならないなぁ・・・と、
ため息が出た。
もっとも、
ナマポ(生活保護)は
医療費がタダにはなるのだろうが・・・。

看護婦さん二人が
エレベーターまで
退院の見送りをしてくだすったが、
「また、近々、
お世話になるかもしれません」
と、挨拶しておいた。
二回目の入院だったが、
微細な脳梗塞と脳溢血を
交互に発症しているので、
Dデイまでは
また度々世話になる予感がしたので、
その時は、子として、
粛々と看取り介助をしようと
覚悟した。

カミさんが買っていた
【本屋大賞】の
『そして、バトンは渡された』を
借りて読んでみた。
【大賞】物は、
おととしの
『蜜蜂と遠雷』以来である。
あれはピアノ・コンクール物で
抜群に面白かった。
『そしバト』は、
ライトノベル風の
軽味のある作品で、
笑わせもし、エンディングでは
泣かせもしてくれた。
例によって、
ワルイ癖で
アマゾンのレヴューで
世間のコンセンサスを
覗いてみた。
星5つ 45% *****
星4つ 20% **+
星3つ 13% *+
星2つ 13% *+
星1つ 9% *
…という、
概ね「良評価」に傾いていた。
〈くさす派〉は
常に一割は居るもので、
これらは〈くさし〉と
呼ぶことにしている(笑)。
曰く・・・
「薄っぺらい、中身のない内容」
「まったく現実的でない夢物語」
「羞恥心のない乞食根性のクソガキに共感できない」
と、クサシは様々。
映画化しやすい
素材のようにも思えたので、
それも近々、現実化するかもである。

明け方に、
久しぶりに、中学時代に
恋焦がれた女の子の夢を見た。
ほとんど
言葉を交わしたことのない子だったが、
夢んなかでは
意識しながらも
けっこうしゃべっており、
しかも、結末は、
その子が性転換していて
男性器まで顔の皮膚を移植して
整形したと聞いて愕然とする。
なんじゃ~、
この夢は~ッ!!
と、起きしなに
驚いた。
ε=ε=ヾ(*。>◇<)ノ
夢分析の専門家なので、
今日一日かけて
ぽつぽつと
分析するつもりではいる。
自由連想法と
ウォッチワード・テストという
ツールを用いて
自己分析してみると、
意外な無意識からのメッセージを
受け取ることがある。
まずは、
現状の意識を列挙して、
それとの関連性や、
世界情勢を俯瞰して
懸念材料との関連性を
探ってみようと思う。
〈あおり事件〉の低脳犯の
劣悪・凶暴な犯行シーンや
卑劣・卑怯な逮捕シーンを
ニュースで何度も見せられて、
不快に感じ、ここ数日、
心穏やかでなかった。
自分も過去、二回も
ヤンキーや暴走族に
胸ぐらをつかまれて脅されたり、
土下座させられた、
という恐怖と屈辱の〈闇史〉があるので、
それで抑圧・忘却していた
「悔しさ」や「殺してやりたい」
というシャドウが
賦活したのかもしれない。
それにしても、
なんで美少女のSちゃんが、
男に性転換して、
しかも、魔術で部屋を猛回転させて、
それをストップさせると
お払い用の「お札」を
撒きちらす…。
【・_・?】ナンデ