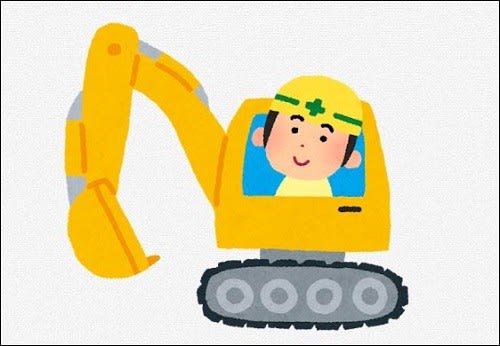
人口減少が進むわが国ですが、特に地方都市では都会よりもそれがより顕著です。
地方都市では出生率が上がらないことに加えて都市への移動という社会的な人口の増減もあって、人口が減ってゆくのです。
そこで生じる課題は、地域の中で求められる仕事をこなしてくれる人=担い手が不足してくるという事。
予算やお金の問題ではなく、お金を用意したところでそれを受け取って仕事をしてくれる人が少なくなるのです。
リクルートワークス研究所が3月に公表した資料では、「2040年に働き手が1100万人ふそくする」という予測が打ち出されました。
このままの予測通りになると、日常生活で必要なゴミ収集やインフラのメンテナンス、などの各種サービスが滞ってしまうことになります。
それへの処方箋としてリクルートの資料ではいくつかの提案が打ち出されています。
①徹底的な機械化・自動化、②ワーキッシュアクトという形で全世代がとにかく皆出来る範囲で働くこと、③シニアの小さな活動で社会の困りごとを片付ける、④ムダな業務の改善、という四つです。
徹底的な機械化、自動化というと、自動運転で人がいなくてもサービスが得られるような印象ですが、それよりも人力でチマチマやっている仕事を少しでも機械化して効率化するという事でも良いのだと思います。
いずれにせよ、誰かがやってくれるのを待つのではなく、もう自らが行動して多能工になり少しでも多くのことをできるようになるという準備が必要なのです。
◆
そういう思いが募った結果、介護の資格を取ったり大型特殊免許を取って建設車両の操作もできるような作業免許も取得した私。
古巣の開発局へ挨拶まわりに行った際にも、後輩の職員たちに「あなたたちが退職して高齢化する時代にはもっと全員参加が求められるから、平時である今のうちに興味ある分野で資格取得やスキルアップをしておくことを勧めます」と言って歩いていました。
私が大特の免許を取ったと言うと「すごいですね」とは言うものの、「皆なんだかんだでできないものですよ」となんだかわからないような"やらない理由"を述べる人がふつうです。
ところが今日ある後輩からメールが来て、「小松さんの話を聞いて、ちょっと探してみたら家の近くに建設車両の特別講習が受けられるところがあると気づきました。ちょうどいいや、と思って、建設系小型特殊車両用の特別講習を受けて小型機械なら運転できるようになりました」という報せが届きました。
これまで何人にもこの手の話をしましたが、実際に行動に移してくれた人は初めてです。
しかも小型特殊機械の作業免許を取ったとのこと。
実際には災害の被災地で重機による技術ボランティアをするにも、大型の機械よりは小型のバックホウやホールローダーで泥の掻きだしをするのが現実的だ、とも聞きました。
そう、無理をして大型特殊の免許を取らなくても自動車普通免許さえあれば、二日間の特別講習で取得できる小型特殊の作業免許があれば十分に実用に足るとも言えるのです。
災害に強い国土というのは、何が何でも壊れない、災害にならないインフラ作りを目指すという事もありますが、そんなとんでもないものを作るよりも、たとえ災害を受けたとしても皆で寄ってたかってそこから少しでも早期に元に戻せる力がある、という国土なのではないでしょうか。
そういう意味で、男性でも女性でも、老いも若きも、職種に限らずに一人でも多くの人が重機を動かせる資格とスキルを持つような社会を目指したいものです。
一人がやれる能力を高めることも労働力不足対策の一つなのですから。
やれることを気がついた今すぐにやってみましょう。
わが道は実践あるのみです。
地方都市では出生率が上がらないことに加えて都市への移動という社会的な人口の増減もあって、人口が減ってゆくのです。
そこで生じる課題は、地域の中で求められる仕事をこなしてくれる人=担い手が不足してくるという事。
予算やお金の問題ではなく、お金を用意したところでそれを受け取って仕事をしてくれる人が少なくなるのです。
リクルートワークス研究所が3月に公表した資料では、「2040年に働き手が1100万人ふそくする」という予測が打ち出されました。
このままの予測通りになると、日常生活で必要なゴミ収集やインフラのメンテナンス、などの各種サービスが滞ってしまうことになります。
それへの処方箋としてリクルートの資料ではいくつかの提案が打ち出されています。
①徹底的な機械化・自動化、②ワーキッシュアクトという形で全世代がとにかく皆出来る範囲で働くこと、③シニアの小さな活動で社会の困りごとを片付ける、④ムダな業務の改善、という四つです。
徹底的な機械化、自動化というと、自動運転で人がいなくてもサービスが得られるような印象ですが、それよりも人力でチマチマやっている仕事を少しでも機械化して効率化するという事でも良いのだと思います。
いずれにせよ、誰かがやってくれるのを待つのではなく、もう自らが行動して多能工になり少しでも多くのことをできるようになるという準備が必要なのです。
◆
そういう思いが募った結果、介護の資格を取ったり大型特殊免許を取って建設車両の操作もできるような作業免許も取得した私。
古巣の開発局へ挨拶まわりに行った際にも、後輩の職員たちに「あなたたちが退職して高齢化する時代にはもっと全員参加が求められるから、平時である今のうちに興味ある分野で資格取得やスキルアップをしておくことを勧めます」と言って歩いていました。
私が大特の免許を取ったと言うと「すごいですね」とは言うものの、「皆なんだかんだでできないものですよ」となんだかわからないような"やらない理由"を述べる人がふつうです。
ところが今日ある後輩からメールが来て、「小松さんの話を聞いて、ちょっと探してみたら家の近くに建設車両の特別講習が受けられるところがあると気づきました。ちょうどいいや、と思って、建設系小型特殊車両用の特別講習を受けて小型機械なら運転できるようになりました」という報せが届きました。
これまで何人にもこの手の話をしましたが、実際に行動に移してくれた人は初めてです。
しかも小型特殊機械の作業免許を取ったとのこと。
実際には災害の被災地で重機による技術ボランティアをするにも、大型の機械よりは小型のバックホウやホールローダーで泥の掻きだしをするのが現実的だ、とも聞きました。
そう、無理をして大型特殊の免許を取らなくても自動車普通免許さえあれば、二日間の特別講習で取得できる小型特殊の作業免許があれば十分に実用に足るとも言えるのです。
災害に強い国土というのは、何が何でも壊れない、災害にならないインフラ作りを目指すという事もありますが、そんなとんでもないものを作るよりも、たとえ災害を受けたとしても皆で寄ってたかってそこから少しでも早期に元に戻せる力がある、という国土なのではないでしょうか。
そういう意味で、男性でも女性でも、老いも若きも、職種に限らずに一人でも多くの人が重機を動かせる資格とスキルを持つような社会を目指したいものです。
一人がやれる能力を高めることも労働力不足対策の一つなのですから。
やれることを気がついた今すぐにやってみましょう。
わが道は実践あるのみです。















